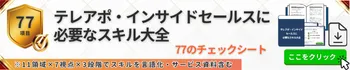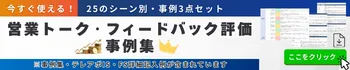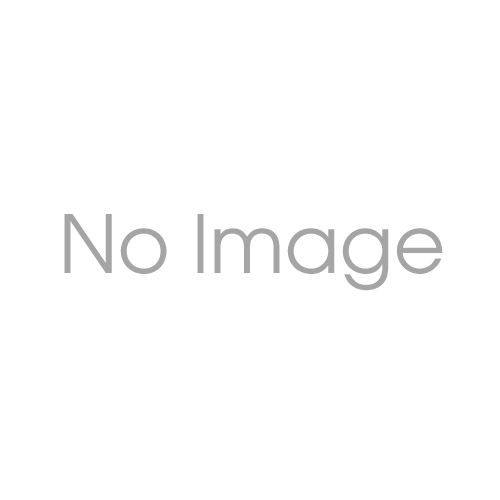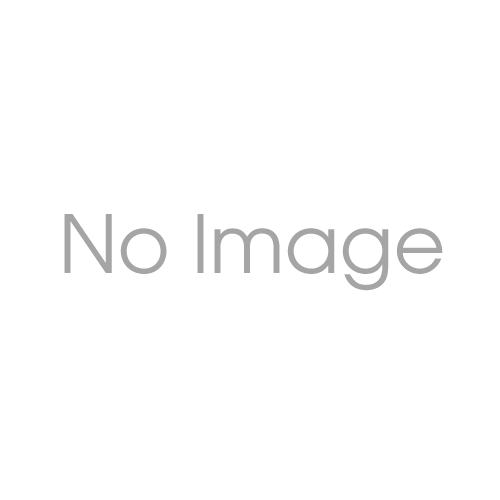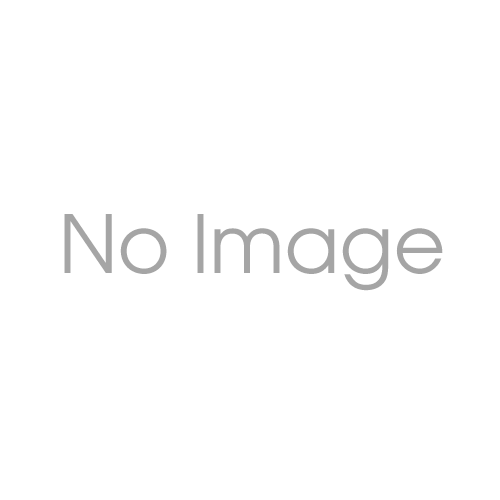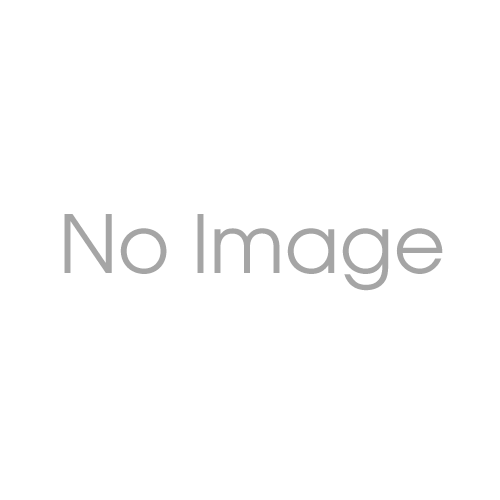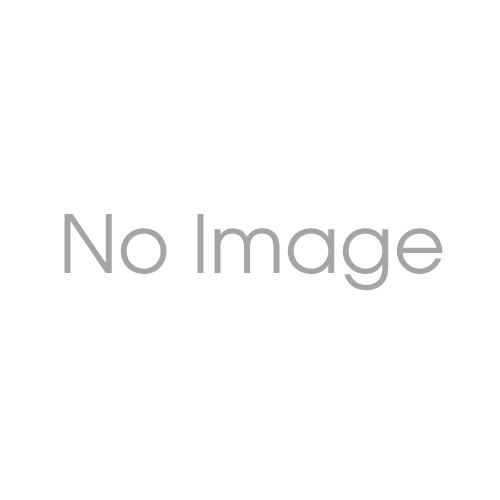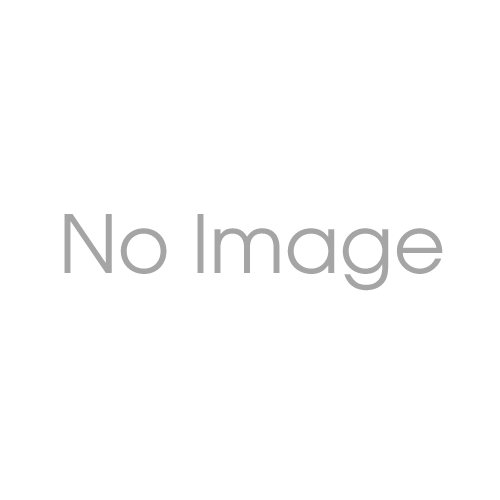テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
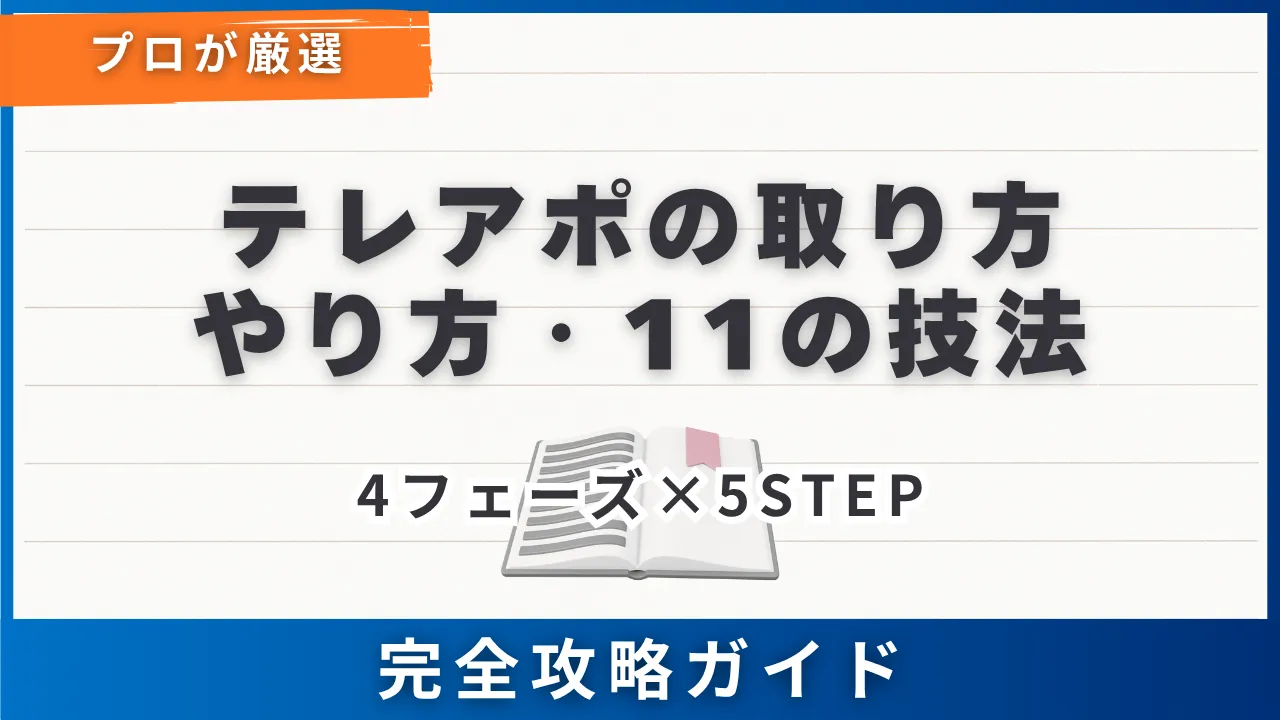
「テレアポをかけても断られてばかり…」
「どう話せばアポイントにつながるのか分からない」
「アポイントを取る自信が持てず、電話をかけるのが怖い」
そんな悩みを抱えていませんか?
BtoB営業の現場では、テレアポの成功率が商談数を左右します。
しかし、準備不足やトークの組み立て方が曖昧なまま架電しても、成果にはつながりません。
本記事では、新規事業の営業担当者が実践できるテレアポの取り方・やり方を、4フェーズ×5STEPの流れと12の技法で徹底解説します。
・テレアポを成功させる9つの手順(ターゲット選定からフォロー体制まで)
・成果を出すための11の技法(声のトーン、共通話題、質問設計など)
・挨拶編・導入編・本題編・クロージング編の4フェーズ別5STEPの実践法
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、
ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
テレアポを取る3つの目的
「リード獲得」で次の商談につなげるため
テレアポの最大の目的は、見込み顧客との接点を作り、次の商談へとつなげることです。
電話という直接的なコミュニケーション手段を使うことで、メールや広告では届かない温度感を持った対話が可能になります。更に直接的に相手の考える課題感を聞き出しつつ提案につなげていくことが可能です。
特に法人営業では、キーマンとの最初の接触がその後の商談化率を左右します。
重要なのは、単にアポイントを取ることではなく、相手のニーズや課題を軽く探りながら、商談の価値を感じてもらうことです。
具体的には、以下のようなポイントを意識すると効果的です。
・相手の業務課題に触れ、自社サービスとの接点を示す
・導入実績や具体的な成果を短く伝え、信頼感を醸成する
・次回の商談で何が得られるかを明確に伝える
このように、テレアポは単なるアポイント獲得の手段ではなく、商談化への第一歩として機能します。
次の商談につなげるためには、相手に「この電話は自分にとって価値がある」と感じてもらうことが重要です。
「顧客理解」を深めて商談の精度を高めるため
テレアポは、顧客の課題や状況を直接ヒアリングできる貴重な機会です。
商談前に顧客の温度感やニーズを把握しておくことで、提案の精度が飛躍的に向上します。
特に新規開拓では、顧客の業務フローや意思決定プロセスを理解しているかが、成約率を左右します。
電話でのヒアリングでは、メールでは得られない「声のトーン」や「反応の速さ」から、相手の関心度や緊急性を読み取りましょう。
顧客理解を深めるために意識したいポイントは以下の通りです。
・現在抱えている課題や困りごとを簡潔に引き出す
・過去の導入経験や検討状況を確認する
・意思決定に関わる人物や部署を把握する
このように、テレアポは情報収集の場としても機能します。
得られた情報をもとに商談を設計することで、提案内容が相手の課題に的確に刺さり、クロージング率が向上します。
「関係構築」で将来のビジネスチャンスを育てるため
テレアポは即座にアポイントを取ることだけが目的ではありません。
長期的な視点で見れば、顧客との信頼関係を築く最初の接点として重要です。
特にBtoB営業では、一度の架電で即決に至ることは稀であり、継続的なコミュニケーションを通じて関係性を深めていくことが求められます。
つまり、認識として中長期的な関係構築のための第一歩と考えて関係構築を意識したテレアポでは、相手に「この営業担当者は信頼できる」と感じてもらうことが第一です。
具体的には、以下のようなアプローチが有効です。
・押し売りせず、相手の状況を尊重した対話を心がける
・業界トレンドや有益な情報を提供し、価値を感じてもらう
・断られた場合でも、次回のフォローアップを自然に提案する
このように、テレアポは短期的な成果だけでなく、中長期的な関係構築の起点となります。
信頼関係が築ければ、将来的な受注や紹介案件につながる可能性が高まり、営業活動全体の効率が向上します。
テレアポの取り方の流れ・9つの手順
1「ターゲット選定」で優先度の高い企業を見極める
テレアポの成功率は、最初のターゲット選定で大きく変わります。
闇雲に架電するのではなく、自社の商材やサービスにマッチする企業を優先的に選ぶことが重要です。
ターゲット選定の精度が高ければ、架電数が少なくても成果につながりやすくなります。
まず、業界や企業規模、事業内容を基準に自社のサービスが課題解決につながる企業をリストアップします。
次に、企業の成長フェーズや最近のニュースをチェックし、ニーズが顕在化している可能性が高い企業を絞り込みます。
具体的には、以下のようなステップで進めると効果的です。
① 業界や事業領域を分析し、自社商材との親和性を確認する
② 企業規模や従業員数を基準に、予算感や意思決定スピードを推測する
③ 直近のニュースやプレスリリースから、ニーズの仮説を立てる
④ 優先順位をつけ、架電リストを整理する
このように、ターゲット選定は「誰に電話をかけるか」を戦略的に決める重要なプロセスです。
優先度の高い企業から架電することで、限られた時間を最大限に活用できます。
2「キーマン特定」で決裁者へ最短ルートを取る
ターゲット企業が決まったら、次に重要なのがキーマンの特定です。
キーマンとは、サービス導入の意思決定に関わる人物を指します。
決裁者に最短でアプローチできるかが、商談化のポイントです。
まず、企業のウェブサイトや組織図を確認し、部門責任者や役職者の名前をリストアップします。
次に、LinkedInや企業の公式SNSを活用して、担当者の役割や関心領域を把握します。
キーマンを特定する具体的な手順は以下の通りです。
① 企業の組織図やメンバー紹介ページを確認する
② 役職や部門名から、決裁権を持つ人物を推測する
③ LinkedInやSNSで担当者のプロフィールを調査する
④ 受付や総務経由でキーマンの名前を確認する方法も検討する
このように、キーマンを事前に特定しておくことで、受付突破率が向上し、商談化までの時間が短縮されます。
最短ルートで決裁者にアプローチすることが、テレアポ成功の鍵です。
3「リスト精査」でムダのない架電計画を立てる
架電リストが整ったら、次はリストの精査です。
リストの精度が低いと、つながらない番号や既に取引終了した企業に時間を奪われてしまいます。
ムダのない架電計画を立てるためには、リストの品質管理が欠かせません。
まず、リスト内の重複を削除し、連絡先の正確性を確認します。
次に、過去の架電履歴やCRMのデータをもとに、優先順位を設定します。
リスト精査の具体的な手順は以下の通りです。
① 重複データをチェックし、リストを整理する
② 電話番号やメールアドレスの正確性を確認する
③ 過去の架電履歴をもとに、再アプローチが有効な企業をピックアップする
④ 架電スケジュールを作成し、時間帯や曜日を考慮して計画を立てる
このように、リストを精査することで、つながる確率が高まり、架電の効率が最大化されます。
質の高いリストが、テレアポの成果を支えます。
4「準備トーク」で想定質問と回答を整理しておく
テレアポでは、相手からの質問に即座に答えられるかどうかが信頼を左右します。
事前に想定質問と回答を整理しておくことで、会話がスムーズになり、自信を持って対応できます。
準備トークは、架電前の「リハーサル」のようなものです。
まず、よくある質問をリストアップし、それぞれに対する回答を準備します。
次に、トークスクリプトを作成し、導入・ヒアリング・クロージングの流れを整理します。
準備トークの具体的な手順は以下の通りです。
① よくある質問(料金・導入期間・サポート体制など)をリスト化する
② 各質問に対する簡潔で分かりやすい回答を準備する
③ トークスクリプトを作成し、会話の流れを可視化する
④ ロールプレイで実際に声に出して練習する
このように、準備トークを徹底することで、想定外の質問にも落ち着いて対応できるようになります。
特に、導入からヒアリング、クロージングの流れも決めておくことが、焦らずに対処できる効果的な方法です。
準備が自信につながり、架電時のパフォーマンスを高めます。
5「初回コール」で信頼感を与える第一声を磨く
初回コールの第一声は、相手の印象を決定づける重要な瞬間です。
声のトーンや名乗り方、挨拶の仕方で、相手が話を聞く姿勢になるかどうかが変わります。
第一声で信頼感を与えることができれば、その後の会話がスムーズに進みます。
声のトーンは、明るく落ち着いた印象を心がけましょう。
名乗り方は、会社名と自分の名前を明確に伝え、相手が安心できるようにします。
以下に、第一声で信頼感を与えるためのポイントを整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
声のトーン |
「お忙しいところ失礼いたします。◯◯株式会社の△△と申します」 |
|
名乗り方 |
「私、◯◯社で営業を担当しております△△と申します」 |
|
挨拶の仕方 |
「本日は、◯◯のご提案でお電話させていただきました」 |
このように、第一声は相手に「この電話は信頼できる」と感じてもらうための入口です。
声のトーンと名乗り方を磨くことで、受付突破率が向上し、商談化の可能性が高まります。
6「課題ヒアリング」で相手の"本音"を引き出す
テレアポの中盤では、相手の課題やニーズを引き出すヒアリングが重要です。
本音を引き出せるかどうかが、商談の質を大きく左右します。
ヒアリングのポイントは「相手が話しやすい質問を投げかける」です。
オープンクエスチョンを使い、相手に自由に話してもらう時間を作ります。
また、共感のフレーズを挟むことで、相手の警戒心を和らげることができます。
以下に、本音を引き出すためのヒアリング例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
オープンクエスチョン |
「現在、どのような課題を感じていらっしゃいますか?」 |
|
共感フレーズ |
「それは大変ですよね。同じようなお声を他社様からもよくお聞きします」 |
|
深掘り質問 |
「具体的には、どのような場面で困ることが多いですか?」 |
このように、ヒアリングは相手の本音を引き出すための対話です。
本音が分かれば、提案の精度が高まり、商談化率が向上します。
7「価値提案」で相手にとっての"得"を具体的に伝える
ヒアリングで課題を把握したら、次は価値提案です。
価値提案とは、自社のサービスが相手にどのようなメリットをもたらすかを具体的に伝えることです。
相手にとっての"得"が明確であれば、商談への関心が一気に高まります。
ポイントは、抽象的な説明ではなく、数字や実績を使って具体的に伝えることです。
また、ベネフィットを短く簡潔に伝えることで、相手の記憶に残りやすくなります。
以下に、価値提案の例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
ベネフィット訴求 |
「導入後3ヶ月で、業務時間を約30%削減できた事例がございます」 |
|
数字での提示 |
「同業他社では、年間120時間の工数削減を実現しています」 |
|
実績の提示 |
「◯◯業界で50社以上の導入実績がございます」 |
このように、価値提案は相手に「自分にも役立ちそう」と感じてもらうための重要なステップです。
具体的に伝えることで、商談への期待感が高まります。
8「アポ設定」で確実に日程を押さえる
価値提案が終わったら、次はアポイント設定です。
アポイント設定は、テレアポの最終ゴールであり、確実に日程を押さえることが重要です。
相手に選択肢を提示し、決断しやすい状況を作りましょう。
具体的には、以下のような手順でアポイントを設定します。
① 候補日を2〜3つ提示し、相手に選んでもらう
② 相手の都合を確認し、柔軟に調整する
③ 日程が決まったら、その場で確認し、メモを取る
④ アポイント後、確認メールをすぐに送付する
このように、アポイント設定は相手の負担を減らし、自然に日程を押さえることがポイントです。
確実に日程を押さえることで、商談化への道が開けます。
9「フォロー体制」を整え、アポ後の成果につなげる
アポイントが取れたら、次はフォロー体制の整備です。
アポイント後のフォローが、商談の成功率を大きく左右します。
フォローを怠ると、せっかく取ったアポイントが無駄になってしまうこともあります。
具体的には、以下のようなフォローを行います。
① アポイント後すぐに、お礼と日程確認のメールを送る
② 商談に必要な資料を事前に送付し、相手の理解を深める
③ 商談前日にリマインドの連絡を入れ、キャンセルを防ぐ
④ 商談後は、次のアクションを明確に伝え、継続的なコミュニケーションを取る
このように、フォロー体制を整えることで、アポイントが確実に商談につながり、成約率が向上します。
フォローは、テレアポの成果を最大化するための最後の仕上げです。
テレアポのやり方11の技法(コツ)
「声のトーン」で印象を操作して聞かれやすくする
電話では、声だけで相手に印象を与えなければなりません。
同じ内容を話していても、声のトーンが違うだけで相手の受け取り方は変わります。
明るく落ち着いたトーンで話すと、相手は安心感を覚え、話を聞く姿勢になりやすくなります。
一方、低く暗いトーンや早口で話すと、相手は警戒心を持ち、電話を早く切りたいと感じてしまうでしょう。
声のトーンをコントロールすることで、相手の心理状態を自然に誘導できます。
以下に、シーン別の声のトーン使い分け例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
挨拶時のトーン |
「お忙しいところ失礼いたします」と、やや高めで明るいトーンで話す |
|
ヒアリング時のトーン |
「現在、どのような課題をお持ちですか?」と、落ち着いた穏やかなトーンで話す |
|
提案時のトーン |
「こちらのサービスで、業務効率が30%向上した事例がございます」と、自信を持った安定したトーンで話す |
このように、声のトーンは相手の印象を左右する重要な要素です。
第一印象を決めるシーン、相手に共感を示すシーン、自信を相手に示すシーン等、それぞれのシーンに応じてトーンを使い分けることで、相手が話を聞きやすくなり、商談化率が向上します。
「共通話題」で警戒を解き、距離を一気に縮める
初対面の相手は、営業電話に対して警戒心を持っています。
その警戒心を解く最も効果的な方法が、共通話題を見つけることです。
共通話題があると、相手は「この人は自分と似た視点を持っている」と感じ、心を開きやすくなります。
具体的には、業界のトレンドや地域の話題、季節ネタなどが入口として有効です。
法人営業では、相手の業界に関する最新ニュースや、共通の取引先の話題を挟むと、一気に距離が縮まります。
以下に、共通話題の例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
業界トレンド |
「最近、◯◯業界では人手不足が深刻化していると聞きますが、御社ではいかがですか?」 |
|
地域ネタ |
「御社のあるエリアは、最近オフィスビルが増えてにぎやかですよね」 |
|
季節ネタ |
「今日は急に冷え込みましたね。体調など崩されていませんか?」 |
このように、共通話題は相手の警戒心を和らげ、会話の入口を作る強力な武器です。
話題を一つ挟むだけで、相手の態度が柔らかくなり、本題に入りやすくなります。
「質問設計」で相手が話しやすい流れをつくる
テレアポでは、こちらが一方的に話すのではなく、相手に話してもらうことが重要です。
そのために必要なのが、質問設計です。
質問の仕方次第で、相手が話しやすくなり、本音を引き出すことができます。
オープンクエスチョンを使うと、相手は自由に話すことができます。
クローズドクエスチョンを使うと、相手は簡単に答えやすくなります。
以下に、質問設計の例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
オープンクエスチョン |
「現在、どのような課題を感じていらっしゃいますか?」 |
|
クローズドクエスチョン |
「◯◯についてご興味はございますか?」 |
|
深掘り質問 |
「具体的には、どのような場面でお困りですか?」 |
このように、質問設計は相手が話しやすい流れを作るための技術です。
質問を工夫することで、相手の本音を引き出し、提案の精度が高まります。
「断られた瞬間の返し方」で再チャンスを作る
テレアポでは、断られることは日常茶飯事です。
しかし、断られた瞬間の返し方次第で、再チャンスを作ることができます。
断られたからといってすぐに諦めるのではなく、相手の断りを受け入れつつ、次の接点を作る工夫が必要です。
ポイントは、共感のフレーズを挟み、相手の気持ちを尊重することです。
その上で、代替案や次回の提案を自然に伝えることで、相手の心理的ハードルを下げることができます。
以下に、断られた時の返しフレーズ例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
共感フレーズ |
「お忙しいところ、ありがとうございました。またタイミングを見てご連絡させていただきます」 |
|
代替提案 |
「では、資料だけでもお送りしてもよろしいでしょうか?」 |
|
次回フォロー |
「また◯ヶ月後にお声がけさせていただいてもよろしいですか?」 |
このように、断られた瞬間の返し方が、次のチャンスにつながります。
諦めずに次の接点を作ることで、将来的な商談化の可能性が残ります。
「数字と実績」で信頼を一瞬で勝ち取る
テレアポでは、短時間で信頼を得る必要があります。
そのために最も効果的なのが、数字と実績を使うことです。
数字は具体的で分かりやすく、相手に「この会社は実績がある」と感じてもらえます。
実績を伝えることで、サービスの信頼性が一気に高まります。
抽象的な説明よりも、「導入社数」「削減時間」「成果率」などの数字を盛り込むことで、説得力を増しましょう。
以下に、数字と実績を使った例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
導入実績 |
「現在、◯◯業界で100社以上の導入実績がございます」 |
|
効果数値 |
「導入後3ヶ月で、業務時間を約30%削減できた事例があります」 |
|
成果率 |
「同業他社では、導入1年で売上が20%向上した実績があります」 |
このように、数字と実績は信頼を短時間で獲得するための強力な武器です。
具体的な数字を示すことで、相手の関心が高まり、商談化率を向上させましょう。
「短く刺さるフレーズ」で相手の興味を引く
テレアポでは、長々と説明するよりも、短く印象的なフレーズで相手の興味を引くことが重要です。
短いフレーズは記憶に残りやすく、相手の関心を一瞬で引きつけることができます。
ポイントは、ベネフィットを一言で表現することです。
キャッチフレーズのように、耳に残る言葉を使うと効果的です。
以下に、短く刺さるフレーズ例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
ベネフィット訴求 |
「初期費用0円で、すぐに始められます」 |
|
課題解決訴求 |
「人手不足でお困りなら、3ヶ月で解決できます」 |
|
差別化訴求 |
「業界特化型だから、提案が深く刺さります」 |
このように、短いフレーズは相手の記憶に残り、興味を引く入口になります。
一言で相手の心をつかむことで、話を聞いてもらえる確率が上がります。
「無音の使い方」で沈黙をチャンスに変える
テレアポでは、沈黙が訪れることがあります。
多くの営業担当者は沈黙を恐れ、焦って話し続けてしまいます。
しかし、沈黙は相手に考える時間を与える重要な瞬間です。
質問を投げかけた後、あえて無音の時間を作ることで、相手が自分の考えを整理し、本音を話しやすくなります。
特に、提案後やクロージングの場面では、無音の使い方が決断を促すことがあります。
以下に、無音を活用するタイミング例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
質問後の沈黙 |
「現在、どのような課題をお持ちですか?」と聞いた後、3秒待つ |
|
提案後の沈黙 |
「こちらのサービスで課題を解決できると思いますが、いかがでしょうか?」と伝えた後、相手の反応を待つ |
|
クロージング時の沈黙 |
「では、◯日と△日、どちらがご都合よろしいですか?」と聞いた後、相手の返答を待つ |
このように、無音は相手の本音を引き出し、決断を促すための技術です。
沈黙を恐れず、相手に考える時間を与え、商談の質を上げましょう。
「目的別トーク」で"売り込み"ではなく"提案"に変える
テレアポでは、売り込みと思われた瞬間に相手の警戒心が強くなります。
そのため、売り込みではなく提案のスタンスで話すことが重要です。
目的別トークとは、相手の課題に応じて提案内容を変える手法です。
目的に対する課題解決型のトークを使うことで、相手は「この電話は自分にとって価値がある」と感じます。
情報提供型のトークを使うことで、相手は「有益な情報をもらえた」と感じ、信頼が生まれます。
以下に、目的別トークの例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
課題解決型 |
「人手不足でお困りとのことでしたが、弊社のサービスで3ヶ月で解決できた事例があります」 |
|
情報提供型 |
「最近、同業他社で導入が進んでいる◯◯について、情報共有させていただけますか?」 |
|
関係構築型 |
「まずは一度、お話だけでも聞かせていただけませんか?」 |
このように、目的別トークは売り込みではなく提案に変える技術です。
相手の課題に寄り添うことで、信頼を築き、商談化率を向上させましょう。
「架電タイミング」を読み、つながる確率を最大化する
テレアポでは、架電するタイミングが成功率を大きく左右します。
たとえば相手が忙しい時間帯に電話をしても、話を聞いてもらえません。
逆に、相手が落ち着いている時間帯に電話をすれば、話を聞いてもらえる確率が高まります。
一般的に、法人営業では午前中の早い時間帯や、昼休み明けの時間帯がつながりやすいと言われています。
また、曜日によっても相手の忙しさが変わるため、タイミングを見極めることが重要です。
以下に、つながりやすい架電タイミング例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
午前中 |
9時〜10時頃は、朝のメールチェック後で比較的落ち着いている |
|
昼休み明け |
13時〜14時頃は、昼休み明けで時間に余裕がある |
|
夕方前 |
15時〜16時頃は、夕方の業務に入る前で対応しやすい |
このように、架電タイミングを工夫することで、つながる確率が最大化されます。
相手の業務リズムを読み、最適なタイミングで架電することが成功の鍵です。
「CRM活用」で通話履歴をナレッジ化する
テレアポでは、1回の架電で成果が出ないことも多くあります。
そのため、通話履歴をCRMに記録し、次回のアプローチに活かすことが重要です。
CRMに記録することで、過去の会話内容や相手の反応を振り返ることができます。
これにより、次回の架電時に「前回お話しした◯◯の件ですが」と自然に会話を再開できます。
また、チーム全体で情報を共有して他のメンバーへ引き継ぐ際にも、スムーズに対応するようにしましょう。
以下に、CRMに記録すべき項目例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
会話内容 |
「人手不足の課題について触れた。特に◯◯部門でのニーズが高い」 |
|
相手の反応 |
「興味はあるが、今期は予算がないとのこと」 |
|
次回アクション |
「来期予算確定後の◯月に再度連絡する」 |
このように、CRM活用は通話履歴をナレッジ化し、次の成果につなげる重要な手段です。
記録を習慣化することで、営業活動全体の効率が向上します。
「アポ後のフォロー」で受注率を2倍に引き上げる
アポイントが取れたら、それで終わりではありません。
アポ後のフォローが、受注率を左右します。
フォローを怠ると、せっかく取ったアポイントがキャンセルされたり、商談が進まなくなるかもしれません。
具体的には、アポイント直後にお礼メールを送り、日程を再確認します。
商談前日にはリマインドの連絡を入れ、当日のキャンセルを防ぎます。
商談後は、次のアクションを明確に伝え、継続的なコミュニケーションを取りましょう。
以下に、アポ後のフォローアクション例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
お礼メール |
「本日はお時間をいただき、ありがとうございました。◯日の◯時にお伺いいたします」 |
|
資料送付 |
「事前に資料をお送りいたしますので、ご確認ください」 |
|
リマインド連絡 |
「明日の◯時にお伺いする予定です。何かご変更があればお知らせください」 |
このように、アポ後のフォローは受注率を高めるための重要なプロセスです。
フォローを徹底することで、アポイントが確実に商談につながり、成約率が向上します。
挨拶編:テレアポの取り方・やり方・5STEPで解説
1「第一声」で印象を左右する"声の入り方"を極める
第一声は、相手がこちらの話を聞くかどうかを決める最重要ポイントです。
電話に出た瞬間の数秒で、相手は「この電話は聞く価値があるか」を無意識に判断しています。
第一声で好印象を与えることができれば、その後の会話が驚くほどスムーズに進みます。
声の入り方で特に意識したいのは、トーンとスピード、そして明瞭さです。
やや高めで明るいトーンを意識すると、相手に安心感と親しみやすさを与えることができます。
また、ゆっくりと明瞭に話すことで、相手が聞き取りやすくなり、丁寧な印象を与えます。
以下に、第一声で印象を良くするための声の入り方例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
明るいトーン |
「お忙しいところ失礼いたします」と、やや高めで明るい声で話す |
|
ゆっくり明瞭に |
「◯◯株式会社の△△と申します」と、一語一語をはっきりと発音する |
|
適度な間を取る |
名乗った後、1秒程度の間を置いてから本題に入る |
このように、第一声の声の入り方を極めることで、相手の警戒心が和らぎ、話を聞いてもらえる確率が高まります。
まずは第一声で好印象を与え、会話の入口を開くことが成功の鍵です。
2「会社名と肩書き」で信頼を感じさせる名乗り方を使う
名乗り方は、相手に「この電話は信頼できる」と感じてもらうための要素です。
会社名と肩書きを明確に伝えることで、相手は「正式な営業電話だ」と認識し、安心して話を聞く姿勢になります。
曖昧な名乗り方をすると、相手は「怪しい電話かもしれない」と警戒してしまいます。
名乗り方で意識したいのは、会社名をフルネームで伝え、自分の役割を明確にすることです。
また、肩書きを添えることで、専門性や責任感が伝わり、信頼度が上がります。
以下に、信頼を感じさせる名乗り方の例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
会社名のフルネーム |
「株式会社◯◯の△△と申します」と、正式な会社名を伝える |
|
肩書きの明示 |
「営業部の△△と申します」と、部署や役割を添える |
|
丁寧な言い回し |
「私、◯◯社で営業を担当しております△△と申します」と、丁寧に名乗る |
このように、会社名と肩書きを明確に伝えることで、相手の信頼を得ることができます。
名乗り方を丁寧にして、その後の会話がスムーズに進むようにしましょう。
3「相手の反応」に合わせてテンポを自然に変える
テレアポでは、相手の反応に応じてテンポを調整することが重要です。
相手がゆっくり話すタイプなら、こちらもゆっくりと話すことで安心感を与えます。
逆に、相手がテキパキと話すタイプなら、こちらも簡潔に要点を伝えることで好印象を与えます。
テンポを相手に合わせることを「ペーシング」と呼び、信頼関係を築くための基本的なテクニックです。
相手のペースに合わせることで、相手は「この人は自分のことを理解してくれている」と感じやすくなります。
以下に、相手の反応に合わせたテンポ調整の例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
ゆっくり話す相手 |
こちらもゆっくりと話し、相手が考える時間を十分に取る |
|
テキパキ話す相手 |
要点を簡潔にまとめ、無駄な説明を省く |
|
沈黙が多い相手 |
焦らず相手の反応を待ち、相手が話し出すまで待つ |
このように、相手の反応に合わせてテンポを変えることで、会話がスムーズに進みます。
相手のペースを尊重することが、信頼関係を築く第一歩です。
4「一言のアイスブレイク」で空気を和らげる
挨拶の後、すぐに本題に入ると相手は身構えてしまいます。
一言のアイスブレイクを挟むことで、相手の警戒心を和らげ、会話を自然に進めることができます。
アイスブレイクとは、相手との距離を縮めるための軽い話題や共感のフレーズです。
季節の話題や天気の話、相手の地域に関する話など、無難で共感しやすい話題が効果的です。
ポイントは、相手が負担なく返答できる内容にすることです。
以下に、一言のアイスブレイク例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
季節の話題 |
「急に寒くなりましたが、体調など崩されていませんか?」 |
|
天気の話 |
「今日は朝から雨が強いですが、御社周辺はいかがですか?」 |
|
地域の話 |
「御社のあるエリアは、最近開発が進んでにぎやかですよね」 |
このように、一言のアイスブレイクを挟むことで、相手の緊張がほぐれます。
軽い会話から入ることで、本題に入りやすくなり、商談化率が向上します。
5「聞く姿勢」を伝えて、安心感を与えるトーンを出す
挨拶の最後には、「聞く姿勢」を相手に伝えることが重要です。
一方的に話すのではなく、相手の話を聞く準備があることを示すことで、相手は安心して話せます。
聞く姿勢を伝えるためには、相づちやリピート、共感のフレーズを使うことが効果的です。
また、声のトーンを柔らかくし、相手が話しやすい雰囲気を作ることも大切です。
以下に、聞く姿勢を伝えるためのフレーズ例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
相づち |
「はい、そうなんですね」と、相手の話に適度に相づちを打つ |
|
リピート |
「◯◯でお困りなのですね」と、相手の言葉を繰り返して共感を示す |
|
共感フレーズ |
「それは大変ですよね。他社様からも同じようなお声をよくお聞きします」 |
このように、聞く姿勢を伝えることで、相手は「この人は自分の話を聞いてくれる」と感じます。
聞く姿勢を示すことが、信頼関係を築く上で大切です。
導入編:テレアポの取り方・やり方・5STEPで解説
1「話す目的」を先に伝えて聞く体制を整える
導入時に大切なのは、なぜ電話をしているのかを明確に伝えることです。
目的が不明確なまま話を進めると、相手は「何の話だろう?」と不安になり、警戒心が高まります。
話す目的を先に伝えて、相手は「この電話はこういう内容なんだ」と理解し、聞く体制を整えましょう。結論から先に述べる意識を持って会話することも重要です。
心理学的にも、理由を添えることで相手の承諾率が上がることが実証されています。
ポイントは、相手にとってのメリットや関連性を含めた目的を伝えることです。
以下に、話す目的を伝えるフレーズ例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
目的の明示 |
「本日は、◯◯業界の業務効率化についてご提案したくお電話いたしました」 |
|
相手へのメリット提示 |
「御社の◯◯課題の解決につながる事例をご紹介できればと思いまして」 |
|
関連性の提示 |
「同業他社様で導入が進んでいる◯◯について、情報共有させていただきたく」 |
このように、話す目的を先に伝えることで、相手は安心して話を聞く姿勢になります。
目的を明確にすることが、導入をスムーズに進める第一歩です。
2「相手の業務課題」に触れて関心を引く導入をする
導入では、相手の業務課題に触れることで関心を引くことができます。
一般的な営業トークではなく、相手の具体的な課題に触れることで、「この電話は自分に関係がある」と感じてもらえます。
業務課題に触れる際は、業界全体のトレンドや他社の事例を引き合いに出すと効果的です。
相手が「自分も同じ課題を抱えている」と共感することで、話を聞く意欲が高まります。
以下に、相手の業務課題に触れる導入例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
業界課題の提示 |
「最近、◯◯業界では人手不足が深刻化していると聞きますが、御社ではいかがですか?」 |
|
他社事例の引用 |
「同じ業界の◯◯社様では、◯◯の課題を抱えていらっしゃいました」 |
|
共感の提示 |
「業務の属人化でお困りの企業様が増えていますが、御社でも同様のお悩みはございますか?」 |
このように、相手の業務課題に触れることで、関心を引くことができます。
課題に共感することが、導入を成功させる鍵です。
3「業界トレンド」を交えて共通理解を築く
導入では、業界トレンドを交えることで共通理解を築くことができます。
業界トレンドに触れることで、「この営業担当者は業界のことをよく理解している」と感じてもらえます。
また、トレンドを共有することで、相手との会話のきっかけを生み、自然に本題へと移行しましょう。
ポイントは、最新の業界ニュースや市場動向を事前にリサーチしておくことです。
以下に、業界トレンドを交えた導入例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
最新ニュース |
「先日、◯◯業界で新しい規制が発表されましたが、御社への影響はいかがですか?」 |
|
市場動向 |
「最近、◯◯市場が拡大していると聞きますが、御社でも注目されていますか?」 |
|
技術トレンド |
「AI活用が◯◯業界で進んでいますが、御社でも導入をご検討されていますか?」 |
このように、業界トレンドを交えることで、共通理解を築くことができます。
トレンドを話題にすることが、信頼関係を深める入口です。
4「相手の時間」を尊重して信頼を積み上げる
導入では、相手の時間を尊重する姿勢を示すことが重要です。
忙しい相手に対して、いきなり長々と話すと「時間を奪われている」と感じさせてしまいます。
相手の時間を尊重する姿勢を示すことで、「この営業担当者は配慮がある」と好印象を与えます。
具体的には、電話の所要時間を伝えたり、相手の都合を確認したりすることが効果的です。
以下に、相手の時間を尊重するフレーズ例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
時間確認 |
「今、2〜3分ほどお時間をいただいてもよろしいでしょうか?」 |
|
都合確認 |
「お忙しいところ恐れ入ります。今、お話しできるタイミングでしょうか?」 |
|
配慮の提示 |
「お時間が厳しい場合は、改めてお電話させていただきますが、いかがでしょうか?」 |
このように、相手の時間を尊重することで、信頼を積み上げることができます。
時間を尊重する姿勢が、相手の安心感につながります。
5「会話の主導権」を自然に握る話し方を使う
導入の最後は、会話の主導権を自然に握ることです。
主導権を握ることで、こちらが意図した流れで会話を進めることができます。
ただし、強引に主導権を握ろうとすると、相手は警戒してしまいます。
自然に主導権を握るためには、質問を使って相手の反応を引き出しながら、会話の流れを作ることが効果的です。
以下に、会話の主導権を握る話し方の例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
誘導質問 |
「現在、◯◯についてどのような取り組みをされていますか?」 |
|
選択肢の提示 |
「◯◯と△△、どちらの課題が優先度高いでしょうか?」 |
|
次の展開への誘導 |
「詳しくお話しできればと思いますが、少しお時間をいただけますか?」 |
このように、会話の主導権を自然に握ることで、こちらのペースで話を進めることができます。
主導権を握ることが、商談化への道を開く鍵です。
本題編:テレアポの取り方・やり方・5STEPで解説
1「課題ヒアリング」で相手の"困りごと"を明確にする
本題に入ったら、まず相手の課題を引き出すことが最優先です。
課題が明確にならないまま提案をしても、相手には刺さりません。
課題ヒアリングの目的は、相手が抱えている具体的な困りごとを言語化し、その解決策として自社サービスを位置づけることです。
ポイントは、オープンクエスチョンで相手に自由に話してもらい、深掘り質問で具体性を高めることです。
相手が話している中で急に質問を挟み込むのではなく、あくまですべて話し終わった後に「〇〇とおっしゃっておりましたが、その点は▲▲ということですか?」等と質問していくことで、深くまでヒアリングすることが可能です。
また、共感のフレーズを挟むことで、相手は「この人は自分の悩みを理解してくれている」と感じやすくなります。
以下に、課題ヒアリングのための質問例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
オープンクエスチョン |
「現在、業務で最も時間がかかっている作業は何でしょうか?」 |
|
深掘り質問 |
「その作業は、具体的にどのような点が負担になっていますか?」 |
|
共感フレーズ |
「それは大変ですね。他社様からも同じようなお声をよくお聞きします」 |
このように、課題ヒアリングで相手の困りごとを明確にすることが、提案の精度を高める第一歩です。
課題を引き出すことができれば、その後の提案が自然に響くようになります。
2「提案価値」を短く伝えて印象を残す
課題を把握したら、次は自社サービスの提案価値を伝えます。
ここで重要なのは、長々と説明するのではなく、短く簡潔に伝えることです。
短いフレーズで提案価値を伝えることで、相手の記憶に残りやすくなります。
ポイントは、相手の課題に対して「どのように解決できるか」を具体的に示すことです。
また、数字や実績を交えることで、説得力が増します。
以下に、提案価値を短く伝える例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
課題解決の提示 |
「その課題は、弊社のサービスで3ヶ月以内に解決できます」 |
|
数字での効果提示 |
「導入後、業務時間を平均30%削減できた実績がございます」 |
|
短いキャッチフレーズ |
「初期費用0円で、すぐに始められるのが特徴です」 |
このように、提案価値を短く伝えることで、相手の印象に残ります。
簡潔に伝えることが、興味を引く鍵です。
3「競合比較」で自社の強みを自然に伝える
提案価値を伝えた後は、競合との違いを明確にすることが重要です。
相手は「他社とどう違うのか」を必ず気にしています。
競合比較を自然に挟むことで、自社の強みを際立たせることができます。
他社を批判するのではなく、自社の独自性や差別化ポイントを伝えましょう。
以下に、競合比較で自社の強みを伝える例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
独自機能の提示 |
「弊社のサービスは、◯◯機能が標準搭載されている点が他社と異なります」 |
|
サポート体制の差別化 |
「導入後3ヶ月間は専任担当者が並走する点が、他社にはない強みです」 |
|
業界特化の強み |
「◯◯業界に特化しているため、業界特有の課題に対応できます」 |
このように、競合比較で自社の強みを自然に伝えることで、相手は「この会社は違う」と感じます。
差別化を明確にすることが、選ばれる理由を作ります。
4「導入実績」を活用して信頼を補強する
提案の説得力を高めるために、導入実績を活用すると効果的です。
実績を伝えることで、「この会社は信頼できる」という安心感を与えることができます。
特に、同業他社や類似規模の企業の実績を伝えると、相手は自社での導入イメージを持ちやすくなります。
ポイントは、具体的な社名や成果を伝えることです。
以下に、導入実績を活用した信頼補強の例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
同業他社の実績 |
「同じ◯◯業界の△△社様にも導入いただいております」 |
|
導入社数の提示 |
「現在、◯◯業界で50社以上の導入実績がございます」 |
|
成果の具体例 |
「◯◯社様では、導入後6ヶ月で売上が20%向上しました」 |
このように、導入実績を活用することで、信頼を補強することができます。
実績が、提案の説得力を高める強力な武器になります。
5「質問でリード」しながら自然にアポへ誘導する
本題の最後は、質問を使ってアポイントへ自然に誘導します。
いきなり「会いませんか?」と言うのではなく、質問で相手の関心を確認しながら進めることが重要です。
質問でリードすることで、相手は自分の意思で「会ってみたい」と思うようになります。
ポイントは、相手に選択肢を与え、決断しやすい状況を作ることです。
以下に、質問でリードしながらアポへ誘導する例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
関心確認の質問 |
「もう少し詳しくお話しできればと思いますが、ご興味はございますか?」 |
|
選択肢の提示 |
「今週と来週、どちらがご都合よろしいでしょうか?」 |
|
次のステップの誘導 |
「一度、お会いして具体的な事例をご紹介させていただけますか?」 |
このように、質問でリードしながら自然にアポへ誘導することで、相手は抵抗なくアポイントを受け入れやすくなります。
質問を使い、スムーズなアポイント設定をしましょう。
クロージング編:テレアポの取り方・やり方・5STEPで解説
1「次のアクション」を明確に提示して迷いをなくす
クロージングでは、次に何をすべきかを明確に伝えることが重要です。
相手が「次に何をすればいいのか分からない」状態では、アポイントは確定しません。
次のアクションを具体的に提示することで、相手は迷わずに決断することができます。
ポイントは、こちらから能動的に提案し、相手が選びやすい形を作ることです。
以下に、次のアクションを明確に提示する例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
具体的な提案 |
「それでは、来週お伺いして詳しくご説明させていただけますか?」 |
|
選択肢の提示 |
「お時間は30分ほどで結構ですが、午前と午後、どちらがご都合よろしいですか?」 |
|
即決を促す提案 |
「今なら◯日の◯時が空いておりますが、いかがでしょうか?」 |
このように、次のアクションを明確に提示することで、相手の迷いをなくすことができます。
明確な提示が、アポイント確定への最短ルートです。
2「相手の都合」を優先して日程調整をスムーズにする
クロージングでは、相手の都合を最優先にすることが信頼につながります。
こちらの都合を押し付けるのではなく、相手が答えやすい選択肢を提示することが重要です。
相手の都合を優先する姿勢を示すことで、「この営業担当者は配慮がある」と感じてもらえます。
ポイントは、複数の候補日を提示し、相手に選んでもらう形を取ることです。
以下に、相手の都合を優先した日程調整の例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
複数候補の提示 |
「◯日の午後、もしくは△日の午前はいかがでしょうか?」 |
|
柔軟な対応の提示 |
「もしご都合が合わない場合は、ご希望の日時をお聞かせください」 |
|
相手主導の調整 |
「来週から再来週で、ご都合のよろしい日はございますか?」 |
このように、相手の都合を優先することで、日程調整がスムーズに進みます。
相手を尊重する姿勢で、信頼関係を深めましょう。
3「一言フォロー」で相手の心理的ハードルを下げる
アポイントを確定する前に、一言フォローを挟むことで相手の心理的ハードルを下げることができます。
「まだ決めかねている」という相手に対して、安心感を与えるフレーズが効果的です。
ポイントは、「まずは話を聞くだけでも大丈夫」という軽い印象を与えることです。
以下に、心理的ハードルを下げる一言フォロー例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
ハードルの低い印象 |
「まずはお話を聞いていただくだけで結構ですので」 |
|
プレッシャーを下げる |
「もちろん、その場でご契約いただく必要はございません」 |
|
安心感 |
「情報提供だけでも喜んでお伺いしますので、お気軽にどうぞ」 |
このように、一言フォローで相手の心理的ハードルを下げることで、アポイントを受け入れやすくなります。
安心感を与えることが、決断を後押しします。
4「確認トーク」でアポを確実に押さえる
アポイントが決まったら、必ず確認トークで日程を押さえることが重要です。
口頭で決めただけでは、後でキャンセルされる可能性があります。
確認トークで日時と場所を明確にし、相手にコミットメントを持ってもらうことが必要です。
ポイントは、復唱して確認し、その場でメモを取ることです。
以下に、確認トークでアポを押さえる例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
日時の復唱 |
「それでは、◯月△日の◯時にお伺いいたします。お間違いございませんか?」 |
|
場所の確認 |
「御社のオフィスに直接お伺いする形でよろしいでしょうか?」 |
|
担当者の確認 |
「当日は、◯◯様にお会いできるという認識で合っていますでしょうか?」 |
このように、確認トークでアポを確実に押さえることで、後でのキャンセルを防ぐことができます。
確認が、アポイントの確実性を高めます。
5「通話後のメモ」で学びを次の架電に活かす
電話が終わったら、すぐに通話後のメモを取ることが重要です。
記憶が鮮明なうちにメモを取ることで、次回のフォローや他の架電に活かします。
通話後のメモは、自分の成長だけでなく、チーム全体のナレッジとしても活用できます。
ポイントは、会話の内容だけでなく、相手の反応や自分の気づきも記録することです。
以下に、通話後のメモで記録すべき項目例を整理しました。
|
項目 |
例文 |
|
会話内容 |
「人手不足の課題について言及。特に◯◯部門でのニーズが高い」 |
|
相手の反応 |
「興味はあるが、予算確保が来期になる可能性がある」 |
|
次回アクション |
「◯月△日にアポイント設定。事前に資料を送付する」 |
このように、通話後のメモで学びを記録することで、次の架電に活かすことができます。
メモを習慣化することが、営業スキルの向上につながります。
テレアポが失敗しやすい3つの理由
「第一声で信頼をつかめない」から相手が話を聞く気にならない
テレアポが失敗する最大の理由は、第一声で信頼をつかめないことです。
電話に出た瞬間の数秒で、相手は「この電話を聞く価値があるか」を無意識に判断しています。
第一声で信頼を得られなければ、その後どれだけ良い提案をしても相手の耳には届きません。
失敗する主なパターンは
・声のトーンが暗い
・名乗り方が曖昧
・話すスピードが速すぎる
などがあげられます。
また、いきなり本題に入ってしまい、相手が心の準備をする時間がないことも失敗の原因です。
信頼をつかむためには、明るく落ち着いたトーンで話し、会社名と名前を明確に伝えることが重要です。
さらに、相手の時間を尊重する姿勢を示すことで、「この電話は信頼できる」と感じてもらえます。
第一声は、テレアポ全体の成否を決める最重要ポイントです。
ここで失敗すると、その後の挽回は非常に困難になります。
まずは第一声を磨き、相手に安心感を与える入り方を習得することが成功への第一歩です。
「相手の立場を理解しないトーク」で一方的な売り込みに聞こえてしまう
テレアポが失敗する二つ目の理由は、相手の立場を理解しないトークをしてしまうことです。
こちらが話したいことを一方的に話すだけでは、相手は「売り込まれている」と感じて警戒します。
相手の立場を理解しないトークとは、相手の課題や状況を無視して、自社サービスの説明だけをすることです。
相手が何に困っているのか、どのような状況なのかを理解せずに提案しても、響くはずがありません。
また、相手の話を聞かずにこちらが話し続けると、相手は「この人は自分の話を聞いてくれない」と感じてしまいます。
相手の立場を理解するためには、まずヒアリングに時間を使い、相手の課題を引き出すことが重要です。
聞く割合を7割にすることで、相手は「この人は自分のことを理解しようとしてくれている」と感じます。
相手の課題を理解した上で提案することで、初めて「売り込み」ではなく「提案」になります。
一方的なトークは、相手との距離を広げるだけです。
相手の立場に立ったコミュニケーションを心がけることが、信頼関係を築く鍵です。
「アポイントが目的化」してしまい、会話の質が下がっている
テレアポが失敗する三つ目の理由は、アポイントを取ることが目的化してしまうことです。
アポイントを取ることだけに集中すると、会話の質が下がり、結果的に商談につながらないアポイントになってしまいます。
相手の課題をしっかりヒアリングせずに、日程を押さえようとしてしまいます。
その結果、アポイントは取れても、商談時に「思っていた内容と違う」と言われてしまうかもしれません。
また、無理やりアポイントを取ろうとすると、相手は「押し売りされている」と感じ、信頼関係が損なわれます。
アポイントは、あくまで次の商談につなげるための手段であり、目的ではありません。
本当の目的は、相手の課題を理解し、信頼関係を築き、最終的に受注につなげることです。
アポイントを取ることよりも、質の高い会話をすることに集中すべきです。
質の高い会話ができれば、アポイントは自然とついてきます。
目的を見失わず、相手との関係構築を第一に考えることが、長期的な成果につながります。
テレアポの3つの効果(メリット)
「即時の反応」が得られ、顧客の温度感をその場で確認できる
テレアポの最大のメリットは、即時に相手の反応を得られることです。メールや資料送付では、相手がどう感じているのかを確認するまでに時間がかかります。
一方、電話では相手の声のトーンや反応のスピードから、興味の度合いや温度感をその場で把握できます。
即時に反応を得たら、次のアクションを素早く実行しましょう。
興味が高い相手にはすぐにアポイントを設定し、興味が薄い相手には情報提供に切り替えるなど、柔軟な対応が可能です。
また、相手の反応を見ながらトークを調整できるため、提案の精度が高まります。
以下に、即時の反応が得られるメリットを整理しました。
|
項目 |
メリット |
ベネフィット |
|
温度感の把握 |
声のトーンや返答のスピードで興味度を判断できる |
次のアクションを即座に決定できる |
|
リアルタイム調整 |
相手の反応に応じてトークを変更できる |
提案の精度が高まり、商談化率が向上する |
|
即座のフォロー |
その場で疑問や不安を解消できる |
相手の納得度が高まり、アポイント確定率が上がる |
このように、即時の反応が得られることで、営業活動のスピードと精度が飛躍的に向上します。
リアルタイムでのコミュニケーションが、テレアポの大きな強みです。
「声のトーン」で信頼関係をつくり、メールでは届かない温度を伝えられる
テレアポのもう一つの大きなメリットは、声のトーンで信頼関係を築けることです。
メールやチャットでは、文字だけでは伝わらない温度感や誠意を伝えることが難しいです。
しかし、電話では声のトーンや話し方で、相手に安心感や親近感を与えることができます。
声のトーンで感情を伝えることができるため、相手は「この人は信頼できる」と感じやすくなります。
また、共感のフレーズを声に乗せることで、相手との心理的な距離が縮まるでしょう。
メールでは届かない温度を伝えて、相手の心を動かしてください。
以下に、声のトーンで信頼関係を築くメリットを整理しました。
|
項目 |
メリット |
ベネフィット |
|
感情の伝達 |
声のトーンで誠意や共感を伝えられる |
相手との心理的距離が縮まり、信頼関係が築ける |
|
安心感の提供 |
落ち着いた声で話すことで安心感を与えられる |
相手が警戒心を解き、話を聞く姿勢になる |
|
パーソナライズ |
相手の反応に応じて声のトーンを調整できる |
相手に合わせたコミュニケーションができ、好印象を与える |
このように、声のトーンで信頼関係を築くことができるのは、テレアポならではの強みです。
人の温度を感じられるコミュニケーションが、メールにはない価値を生み出します。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【有料級】門外不出!誰もがトップセールスになれる、法人営業のコツ
「現場の生の情報」を直接聞き出し、提案精度を高められる
テレアポの三つ目のメリットは、現場の生の情報を直接聞き出せることです。
メールやアンケートでは、相手が書きやすい表面的な情報しか得られないことが多いです。
しかし、電話では会話の中で相手の本音や、言語化されていない課題を引き出すことができます。
現場の生の情報を得ることで、相手の真のニーズを把握し、提案精度を高めることができます。
また、会話の流れの中で自然に深掘りできるため、アンケートでは得られない具体的な情報収集が可能です。
生の情報を基に提案することで、相手に「この会社は自分のことをよく理解している」と感じてもらえます。
以下に、現場の生の情報を聞き出すメリットを整理しました。
|
項目 |
メリット |
ベネフィット |
|
本音の引き出し |
会話の中で相手の本音や悩みを聞き出せる |
真のニーズを把握し、的確な提案ができる |
|
具体的な情報収集 |
数値や事例など具体的な情報を得られる |
提案の説得力が増し、商談化率が向上する |
|
リアルタイム深掘り |
その場で疑問を深掘りし、詳細を確認できる |
提案の精度が高まり、受注率が上がる |
このように、現場の生の情報を直接聞き出せることで、提案の質が飛躍的に向上します。
生の声を聞くことが、最も価値のある営業活動です。
▼編集部のおすすめ動画を見る
法人営業の超具体的なヒアリング方法
テレアポの取り方・やり方で気を付けたい3つのこと
「聞く割合7割」で、相手に話してもらう時間をつくる
テレアポで最も重要なのは、聞く割合を7割にすることです。
多くの営業担当者は、自社のサービスを説明することに時間を使いすぎてしまいます。
しかし、一方的に話すだけでは、相手の課題やニーズを把握することができません。
聞く割合を7割にすることで、相手に話してもらう時間を作ることができます。
相手が話すことで、本音や具体的な課題が見えてきます。
また、相手は「この人は自分の話を聞いてくれる」と感じ、信頼関係が生まれやすくなります。
聞く割合を増やすためには、オープンクエスチョンを使い、相手が自由に話せる環境を作ることが重要です。
以下に、聞く割合を増やすためのやり方例を整理しました。
|
項目 |
やり方の例 |
|
オープンクエスチョンの活用 |
「現在、どのような課題を感じていらっしゃいますか?」と質問する |
|
相づちとリピート |
「なるほど、◯◯でお困りなのですね」と相手の言葉を繰り返す |
|
沈黙を恐れない |
質問の後、3秒待って相手が話し出すまで待つ |
このように、聞く割合を7割にすることで、相手の本音を引き出し、提案の精度が高まります。
話すことよりも、聞くことを優先することが成功の鍵です。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【感覚で営業している人必見】ヒアリングのポイントはこれ一つ!
「一言目の目的」を明確にして、なぜ電話しているのかを端的に伝える
テレアポでは、一言目で電話の目的を明確に伝えることが重要です。
目的が不明確なまま話を進めると、相手は「何の話だろう?」と不安になり、警戒心が高まります。
一言目で目的を伝えることで、相手は安心して話を聞く体制を整えることができます。
目的を明確にするには、「なぜ電話しているのか」を端的に伝えてください。
ポイントは、相手にとってのメリットや関連性を含めた目的を伝えることです。
以下に、一言目で目的を明確にするやり方例を整理しました。
|
項目 |
やり方の例 |
|
目的の明示 |
「本日は、◯◯業界の業務効率化についてご提案したくお電話いたしました」 |
|
相手へのメリット提示 |
「御社の◯◯課題の解決につながる事例をご紹介したくお電話しました」 |
|
簡潔な理由提示 |
「同業他社様で成果が出ている取り組みをお伝えしたく、お電話いたしました」 |
このように、一言目で目的を明確にすることで、相手は話を聞く姿勢になります。
目的を端的に伝えることが、会話をスムーズに進める第一歩です。
▼編集部のおすすめ動画を見る
テレアポで確実に会える技術を体系的に解説!元キーエンスNo.1営業による直伝シリーズ総集編【電話営業】【営業コンサル】
「断られた瞬間」の返し方を準備し、次のチャンスにつなげる
テレアポでは、断られることは避けられません。
しかし、断られた瞬間の返し方を準備しておくことで、次のチャンスにつなげることができます。
断られたからといってすぐに諦めるのではなく、相手の断りを受け入れつつ、次の接点を作る工夫が必要です。
ポイントは、共感のフレーズを挟み、相手の気持ちを尊重することです。
その上で、代替案や次回の提案を自然に伝えることで、相手の心理的ハードルを下げることができます。
以下に、断られた瞬間の返し方を準備するやり方例を整理しました。
|
項目 |
やり方の例 |
|
共感フレーズの準備 |
「お忙しいところ、ありがとうございました。またタイミングを見てご連絡いたします」 |
|
代替案の提示 |
「では、資料だけでもお送りしてもよろしいでしょうか?」 |
|
次回フォローの提案 |
「また◯ヶ月後にお声がけさせていただいてもよろしいですか?」 |
このように、断られた瞬間の返し方を準備しておくことで、次のチャンスを作ることができます。
断られても諦めず、次につなげる姿勢が長期的な成果を生みます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【テレアポ対応術】あるある断り文句5選!トップセールスの返し方を解説!
テレアポの取り方・やり方が上手い人3つの特徴
「声だけで印象をコントロール」し、安心感を与えられる
テレアポが上手い人の第一の特徴は、声だけで印象をコントロールできることです。
電話では顔が見えないため、声のトーンや話し方だけで相手に印象を与えなければなりません。
上手い人は、相手の反応や状況に応じて、声のトーンを自在に変えることができます。
明るく落ち着いたトーンで話すことで、相手に安心感を与え、警戒心を解きましょう。
また、声のスピードや間の取り方を調整することで、相手が聞き取りやすく、理解しやすい話し方を実現しています。
声だけで印象をコントロールできる人は、第一声で相手の心をつかみ、その後の会話を有利に進めるのが特徴です。
上手い人が意識している声のコントロールのポイントは以下の通りです。
・声のトーンを明るく保ち、相手に好印象を与える
・話すスピードを相手に合わせ、聞き取りやすくする
・適度な間を取り、相手が考える時間を与える
このように、声だけで印象をコントロールできることが、テレアポが上手い人の特徴です。
声の使い方を磨くことで、相手との距離を一気に縮めてみましょう。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【テレアポのコツ】明日からアポがとれる営業になる方法
「相手の判断基準」を会話の中で見抜き、提案内容を即座に変えられる
テレアポが上手い人の第二の特徴は、相手の判断基準を会話の中で見抜けることです。
相手がどのような基準で意思決定をしているのかを理解することで、提案内容を最適化することができます。
上手い人は、会話の中で相手が重視しているポイントを素早く見抜き、それに合わせて提案を調整します。
たとえば
「相手がコスト重視なら価格面のメリットを強調」
「相手が品質重視なら実績や信頼性を前面に出す」
などです。
また、相手の言葉の端々から、どのような課題を抱えているのか、何に困っているのかを読み取ることができます。
相手の判断基準を見抜くことで、的確な提案ができ、商談化率が飛躍的に向上します。
上手い人が意識している判断基準の見抜き方は以下の通りです。
・相手が何度も言及するキーワードに注目する
・質問の内容から、相手の関心事を推測する
・相手の反応の強弱から、重視しているポイントを見極める
このように、相手の判断基準を会話の中で見抜き、提案内容を即座に変えれることが上手い人の特徴です。
柔軟な対応力が、成約率を高める鍵になります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
BtoB営業で必ずヒアリングするべきポイントは「BANT」
「数より質」にこだわり、1本1本の電話を商談化につなげられる
テレアポが上手い人の第三の特徴は、数より質にこだわることです。
多くの営業担当者は、とにかく架電数を増やすことに集中してしまいます。
しかし、上手い人は1本1本の電話の質を高めることに注力します。
質の高い電話とは、相手の課題をしっかりヒアリングし、信頼関係を築き、次の商談につなげる電話です。
無理にアポイントを取ろうとせず、相手にとって価値のある会話を優先します。
その結果、1本1本の電話が確実に商談化につながり、最終的な受注率が高くなります。
数より質にこだわることで、時間あたりの成果を向上しましょう。
上手い人が意識している質を高めるためのアクションは以下の通りです。
・事前に相手の企業情報をリサーチし、準備を徹底する
・ヒアリングに時間をかけ、相手の本音を引き出す
・アポイント後のフォローを丁寧に行い、商談の確度を高める
このように、数より質にこだわり、1本1本の電話を商談化につなげられることが上手い人の特徴です。
質を追求する姿勢が、長期的な成果を生み出します。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【アポイントはこう取れ!】受付突破・アポ取得のテクニック全公開!トークスクリプトの作り方も教えます【電話営業のコツ・ポイントをご紹介】
テレアポの取り方やり方で、お困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「テレアポをがんばっているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
結局どうすればアポイントが取れるのかわからない、トークスクリプトを作っても上手く機能しない、そんな不安、よくわかります。
テレアポのノウハウは世の中にたくさんありますが、本当に実践で使えるノウハウを持っている会社はごくわずかです。
だからこそ、ただ情報を集めるのではなく、"現場目線で本当に使えるアドバイス"をもらえるパートナーを見つけることが大切です。
弊社スタジアムでは、営業代行の戦略設計から現場実行までを一気通貫で支援しています。
IT・Web領域に精通した専任担当が、1商材にフルコミットする体制で支援するため、スピードと成果にこだわる方には特にフィットします。
テレアポで成果を出したい、新規開拓営業を強化したい営業担当者・営業責任者の方へ。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
"現場を熟知した営業のプロ"に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き
【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説
営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順
【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版
インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集
営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文
【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全
【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集
【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!
アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説
【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略
【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説
法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略
【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説
深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順
営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善
13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド
営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション
営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順
【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版
【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集
営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド
営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別
【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果
【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順
【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順
【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点
営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順
【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド
【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き
営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順
できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法
売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法
プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順
【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き
営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策
【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説
【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説
なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術
新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順
営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説
なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法
ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP
ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集
飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法
【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド
【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版
セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法
セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド
新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版
新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全
【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説
新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ
新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法
【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版
【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集
アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法
インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順
【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版
【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法
SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法
MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説
BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法
BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略
BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順
【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版
【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ
【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説
営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選
FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド
【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方
14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順
アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ
シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ
これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順
【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集
【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP
【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説
営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ
御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP
【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順
【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集
営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法
営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順
27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場
【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順
営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準
新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル
営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント
クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順
営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説
営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順
営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順
最終更新日