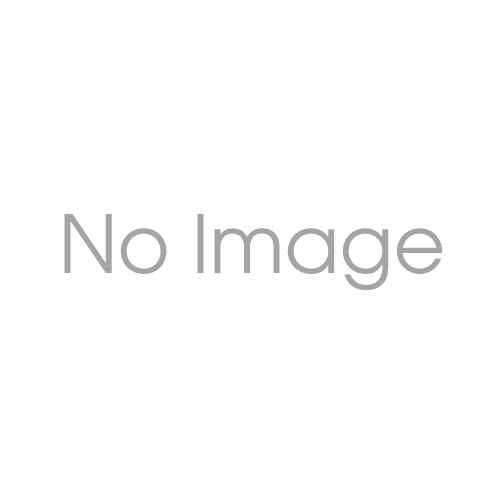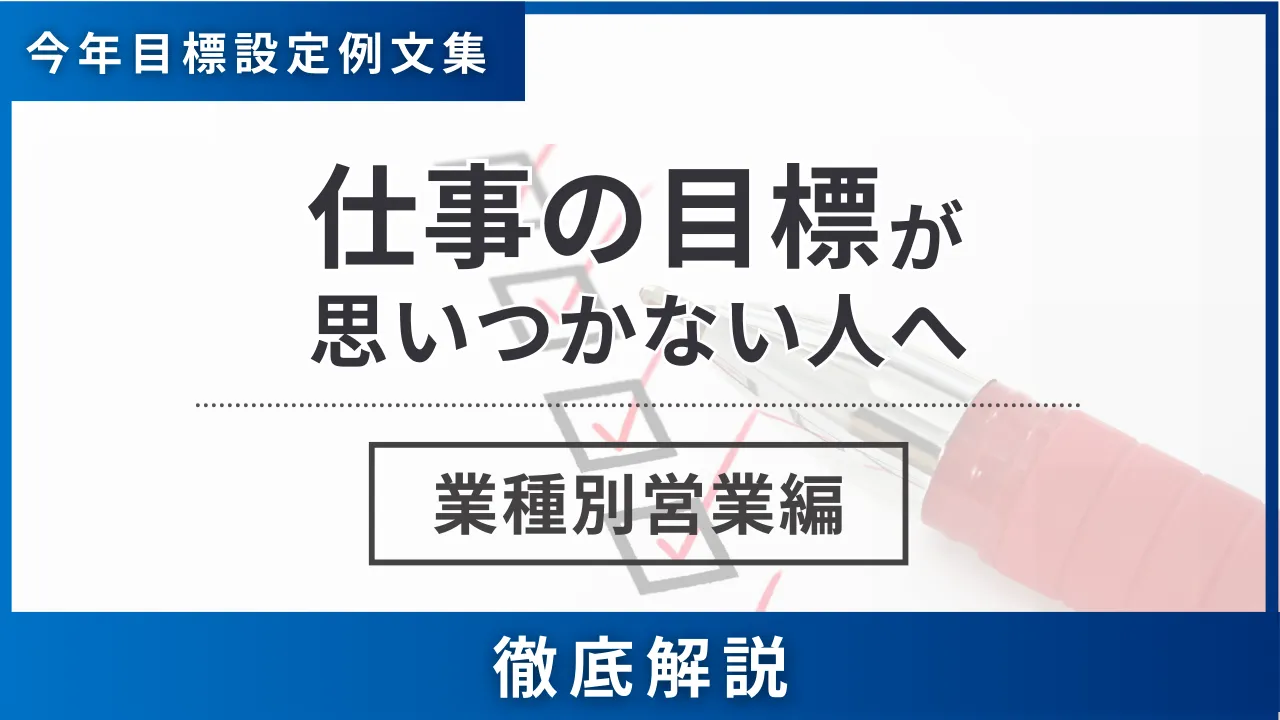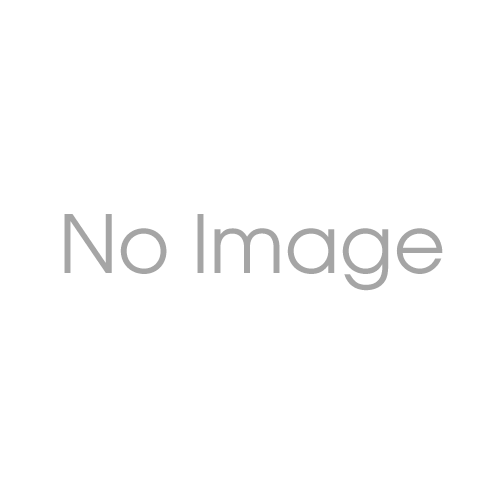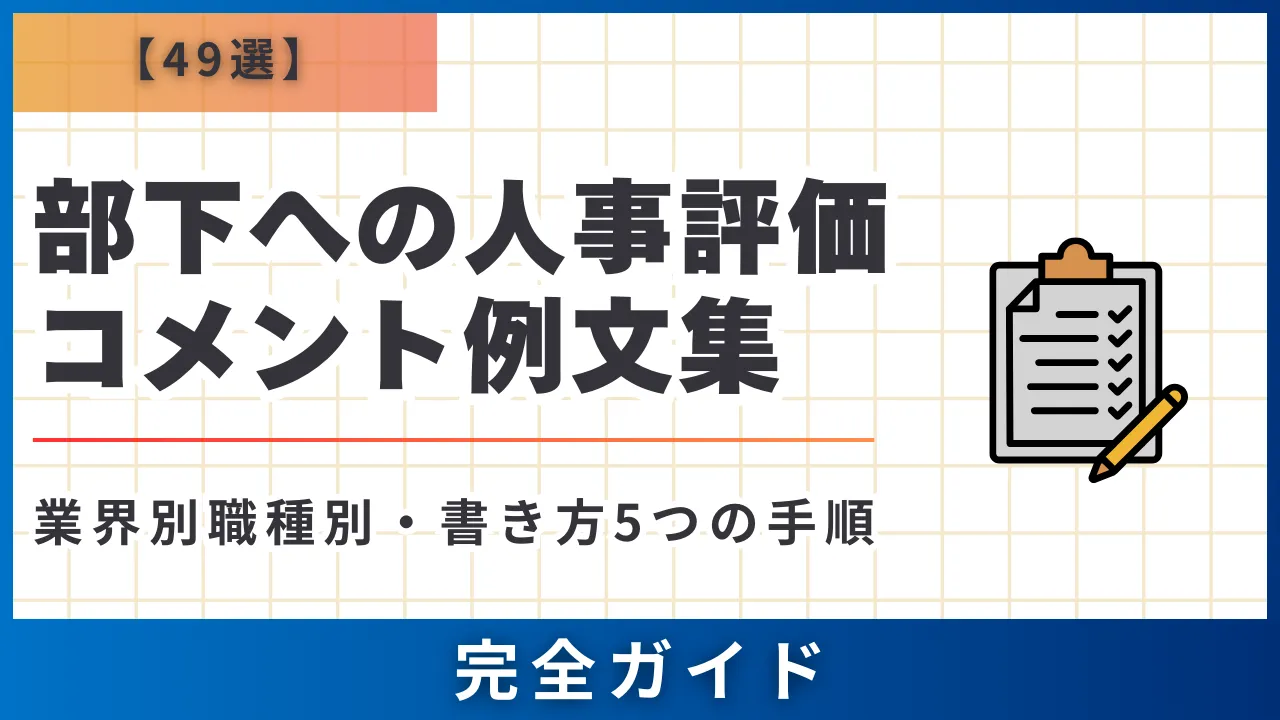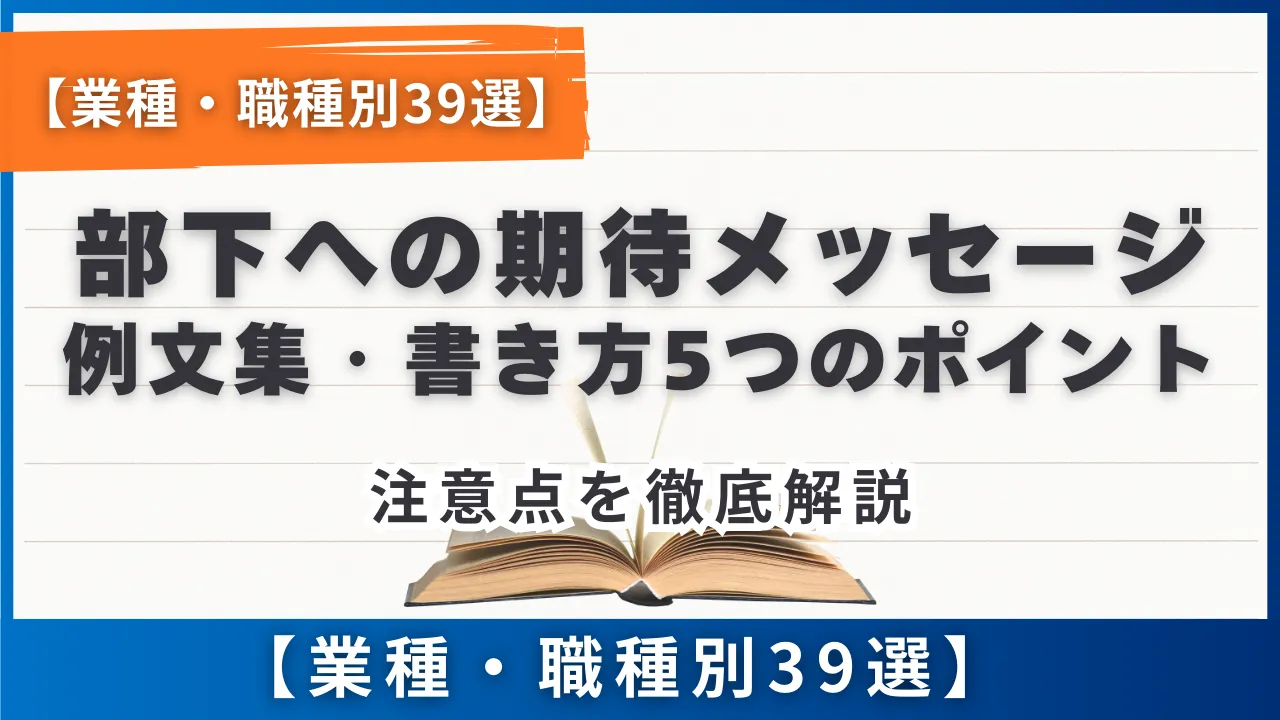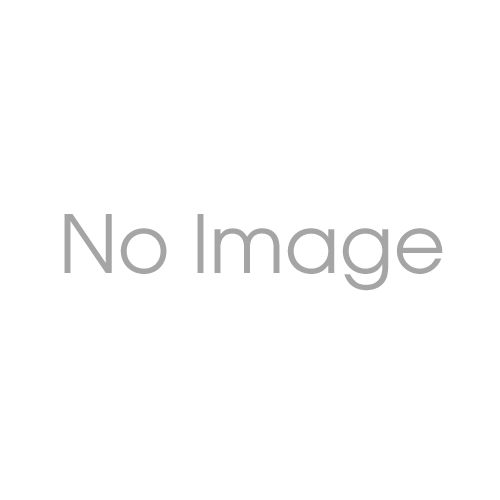営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例

「営業目標の“立て方”次第で、成果は天と地ほど変わる」
「頑張ってるのに数字が出ない…」「チームに目標の温度差がある」──そんな悩み、ありませんか?
営業目標の立て方が曖昧なままでは、いつまで経っても成果は上がりません。
本記事では、“明日から使える目標設計のコツ”を余すことなく解説。
現場で本当に効果のあった方法を、体系的にまとめました。
・目標がブレない!営業目標の立て方4つの基本(KGI・KPI・報告基準)
・チームの動きが変わる!目標を具体化する5つのコツ(逆算・粗利・3秒ルール)
・育成も評価もスムーズに!目標設定3つのメリット(型化・評価軸・納得感)
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
- 「売上が伸びない」「営業組織の強化」「IT商材の営業」なら
- 「営業電話のモニタリング」「自動フィードバック」なら
営業目標の設定方法(立て方・決め方)4つの基本
営業目標1「KGIの決め方」

KGIとは「会社や組織が目指す最終ゴール」のことです。
つまり、売上や契約数など“最終的な成果”を数値で示したものです。
けれど、「KGIは聞いたけど、現場は何をすればいいの?」とよく言われます。
実は、KGIは“動ける指標”になっていなければ、ただの数字で終わってしまいます。
例えば、
・「新規契約数を前年比120%にする」
・「売上1億円を達成する」
より具体的には、
・「月に商談20件を組む」
・「毎週1社以上に提案書を出す」
ポイントは、KGIを“やるべき行動”に言い換えることです。
目標が行動とつながれば、現場が前を向いて走り出せます。
営業目標2「KPIの決め方」
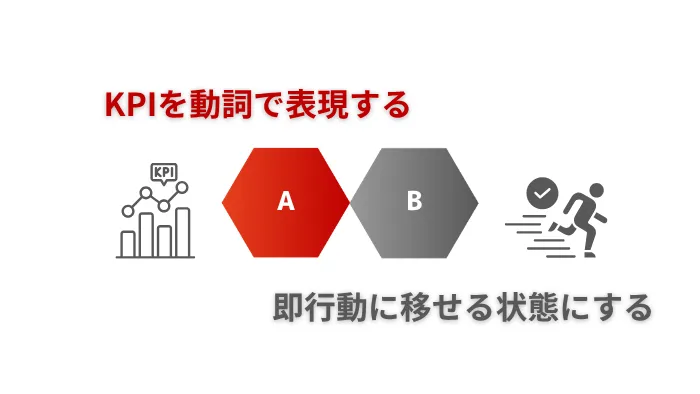
KPIとは「KGIを実現するための中間指標」です。
つまり、成果にたどり着くまでの“進捗の見える化”です。
けれど、「毎週数字は追っているけど、意味がない」と感じている営業は少なくありません。
実は、KPIは“達成できる設計”になっていないと、現場の手が止まります。
例えば、
・「週に5件の初回商談を設定する」
・「月間の訪問件数を100件にする」
より具体的には、
・「月曜にリストを整理し水曜までにテレアポを完了する」
・「商談後24時間以内に要点をチャットで共有する」
ポイントは、KPIを“動詞”で表現し、すぐに行動に移せる状態にすることです。
数字を動かす手応えがあると、現場に前向きな空気が流れはじめます。
※補足:SMARTの法則
Specific (具体的): 曖昧な表現ではなく、明確な目標を設定する。
Measurable (測定可能): 数値で測定できる指標を設定する。
Achievable (達成可能): 現実的に達成可能な目標を設定する。
Relevant (関連性): 目標達成に関連性の高い指標を設定する。
Time-bound (期限を定める): いつまでに達成するか期限を設定する。
このように、SMARTの法則に基づく設定もおすすめです。
営業目標3「週次報告目標の決め方」
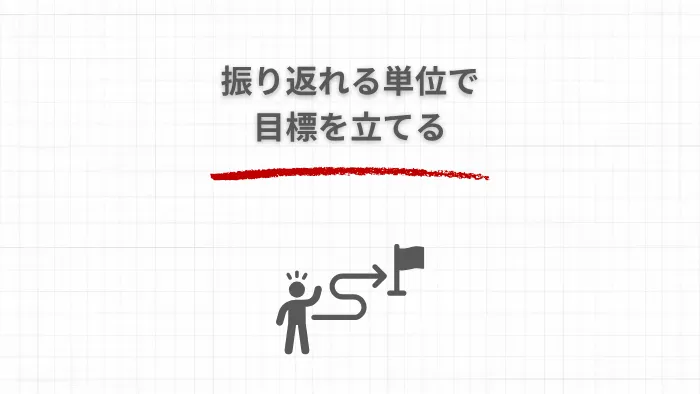
週次報告目標とは、「1週間ごとの進捗を見える化するための行動指標」です。
つまり、目標に向けて“今どこにいるか”を確認するチェックポイントです。
けれど、「報告して終わり」「数字だけ羅列されている」そんな週報になっている現場も多いです。
実は、週次目標が“行動のズレ”を見つけるために設計されていないと、改善が生まれません。
例えば、
・「新規リード接触数を毎週20件にする」
・「提案件数を週5件にする」
より具体的には、
・「水曜時点でリード進捗を棚卸しする」
・「金曜朝に案件ごとの確度(どのくらいの確率で月内に受注に至るか など)をチームで共有する」
ポイントは、“振り返れる単位”で目標を立て、週のどこで確認するかまで決めておくことです。
行動が見える週報があれば、次に打つ手が自然と浮かんできます。
営業目標4「月次報告目標の決め方」

月次報告目標とは、「1ヶ月ごとの成果と課題を整理し、次の打ち手につなげるための目標」です。
つまり、1ヶ月単位で“進んだかどうか”を判断する中間の成果指標です。
けれど、「月末に数字だけ並べて終わる」「振り返りが行動につながらない」そんな悩みもよく聞きます。
実は、月次目標が“行動の質”まで見ていないと、課題が曖昧なまま次の月を迎えてしまいます。
例えば、
・「月間商談数を40件にする」
・「クロージング率を25%に上げる」
より具体的には、
・「受注までの商談回数を全件分ふり返る」
・「失注理由を3分類して来月の対策を立てる」
ポイントは、「結果」だけでなく「要因」に目を向けることです。
数字に“意味”を持たせることで、次のアクションがブレなくなっていきます。
21選【タイプ別詳細】営業の目標設定の具体例
以下に、タイプ別で営業の目標設定の具体例をまとめました。
現場でよくあるものをまとめておきましたので、ぜひお役立て下さい。
【売上・受注】結果にこだわる目標(成果主義)
- 今期中に売上100万円を自分でつくる。
- 毎月新しく2社と契約する。
- 「月50万」の案件を月3本受注する。
【商談・提案】案件を前に進める目標(プロセス管理)
- 1週間で10件は商談に持ち込む。
- 提案書をもたもたせず、商談の翌日までに出す。
- 毎回商談終わったら、その日のうちにフォローメール送る。
【新規開拓】ゼロイチに挑む目標(行動量を担保した仮説検証)
- 毎日70件電話して、最低1件はアポとる。
- 1日20社は飛び込みで挨拶に行く。
- テレアポのアポ率を5%はキープする。
【既存顧客】信頼を積み上げる目標(顧客接点管理)
- 今担当してるお客さん、月1回は必ず顔出す。
- 「もう買わないかも」という会社を毎月3社、もう一度掘り起こす。
- 今ある契約を来月までに1件でもアップセルにつなげる。
【社内・チーム】一緒に勝つ目標(協業設計)
- 今月やった成功事例を、社内に1回はシェアする。
- 新人のロープレに週1回実施する。
- 自分の失敗を1つ、チームMTGで正直に話す。
【効率化】ムダを減らす目標(工数管理)
- CRM入力を「今日中」にやり切る。翌日はNG。
- 商談の録音データを、要点だけSlackに5行で書いて残す。
- 提案書のたたき台はまずAIに作らせて、10分で下書きを出す。
【行動・習慣】継続する目標(習慣化)
- 毎朝9時までに「今日やること」をSlackに投稿する。
- 毎週1回30分、自分の商談を録音してひとりで聴き返す。
- 月末までに「翌月の営業先5件」を先に決めておく。
このように営業目標は「数字」だけでなく、「行動」とセットで、計測可能なものを設定することが大切です。
営業の目標設定をより具体的にする5つのコツ
「商談数」まで落とし込めば目標が動き出す
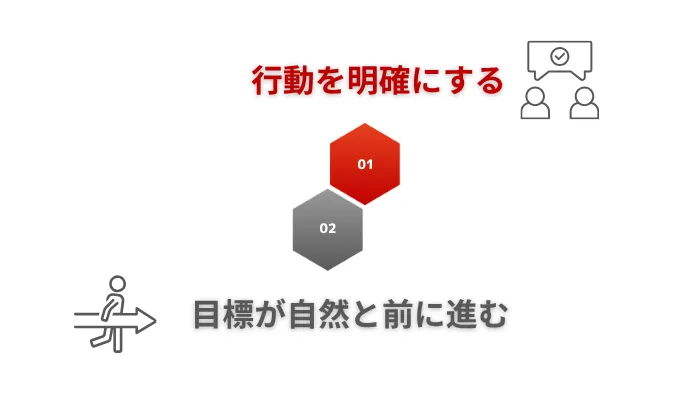
商談数とは、「売上をつくるための打席の数」のことです。
つまり、売上目標を“何件話すか”に変えることです。
でも実際には、「あと何件必要か?」が見えないまま動いている人が多いです。
実は、売れないのではなく、話す量が足りてないだけのこともあります。
たとえば、「商談件数を週ごとに管理する」「1社に複数接点を持つ」など
具体的には、「初回アポを週10件にする」「決裁者と直接会う回数を増やす」などが有効です。
ポイントは、「今月いくら売るか?」ではなく「今週何件話すか?」に変えることです。
行動が明確になると、目標は自然と前に進んでいきます。
「逆算設計」で“いつ・何件”やるかが見えるようにする
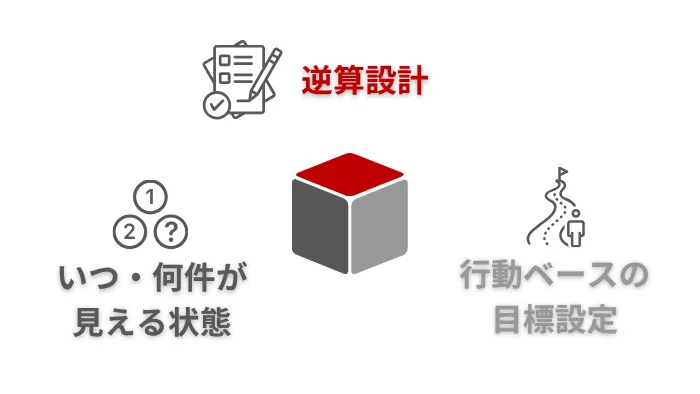
逆算設計とは、「ゴールから逆に辿って、今やることを明確にする方法」です。
つまり、“結果”ではなく“行動”を起点に目標を組み立てるということです。
でも実際は、「今月あと何件必要か?」がざっくりのまま走ってしまうことが多いです。
実は、気合や根性ではなく、逆算の精度が足りていないだけのケースもあります。
たとえば、「月末から逆に週の商談数を割り出す」「成約率を基に必要なアポ数を出す」など
具体的には、「週3件の受注に向けて商談を週15件に設定する」「1日2アポを5日連続で組む」などが効果的です。
ポイントは、「今週どれだけ動けば、数字が間に合うか?」を具体的に言える状態をつくることです。
逆算して数が見えれば、迷わず動けるようになります。
「見込み管理」を基準にすればムダが減るようにする

見込み管理とは、「受注確度ごとに案件を整理し、注力すべき商談を見極めること」です。
つまり、全件を追うのではなく、“勝てる案件”に時間を割くという考え方です。
けれども実際は、「すべての商談を同じ温度感で追ってしまう…」という声もよく聞きます。
実は、動いてるつもりでも、見込みが薄い案件ばかりを追っていることが原因かもしれません。
たとえば、「確度B以上を重点フォローにする」「確度Aは週1でクロージングに動く」など
より具体的には、「温度が高い決裁者に3日以内に再提案する」「社内稟議中の案件は週次で確認する」などが有効です。
ポイントは、「今やるべき案件はどれか?」を数字と温度感で判断できるようにすることです。
そうすることで、ムダな動きが減って、勝ち筋に集中できるようになります。
「1件の粗利」から逆算してKPIを作る
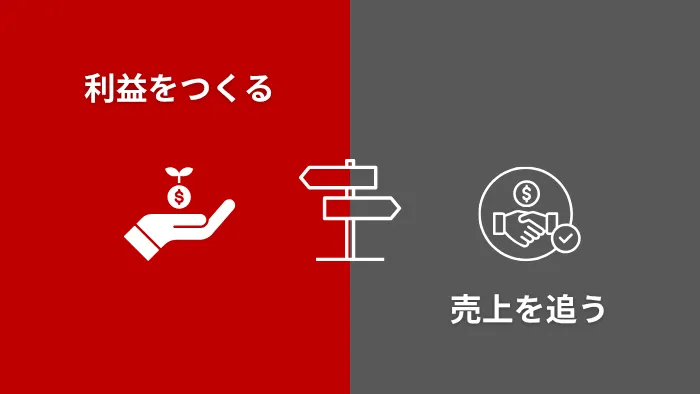
1件の粗利とは、「1商談がどれだけ利益を生んでいるか」を示す数値です。
つまり、売上ではなく“利益”を基準に目標設計をするということです。
けれども実際は、「売上目標はあるけど、粗利は見ていない…」という現場も少なくありません。
実は、売上を積んでも利益が残らないのは、“単価”と“件数”の計算が合っていないだけかもしれません。
たとえば、「粗利5万円の商品なら月20件で100万円に届く」「平均単価が変わったらKPIを再設計する」など
より具体的には、「粗利3万円の商品なら週5件の受注を狙う」「利益率50%なら提案数を倍に増やす」などが有効です。
ポイントは、「売上を追う」から「利益をつくる」への視点を持つことです。
粗利から逆算すれば、動く量も、注力する案件も、すべてが見えてきます。
「数値は3秒で答えられる表現」にする
数値は3秒で答えられる状態とは、「感覚ではなく、具体的な数字で即答できること」です。
つまり、“なんとなく”をやめて、“明確な数値”で目標を話せるようにすることです。
でも現場では、「今月あと何件必要?」と聞かれて、すぐに答えられないケースが多いです。
実は、目標が曖昧なのではなく、“表現”が具体的になっていないだけの場合もあります。
たとえば、「週に何件アポが必要かを言語化する」「残り日数で割って1日単位にする」など
より具体的には、「今月あと12件中、今週5件やる」「1日2アポで残り6日間で達成する」などが効果的です。
ポイントは、「すぐ言える」ことが、「すぐ動ける」ことにつながるという点です。
3秒で言えれば、頭が整理され、動きもブレなくなっていきます。
営業の目標設定をする3つの理由
「動ける目標」があると行動が加速する
「動ける目標」とは、結果ではなく行動に焦点を当てた、すぐに取りかかれる目標のことです。
つまり、「今月1件受注する」ではなく、「今日3件架電する」ような目標の立て方を指します。
けれども実際には、「やるべきことが分かっているつもり」なのに、手が止まる場面も多いのではないでしょうか。
実は、「動けない理由」は気持ちではなく、目標の粒度が粗すぎるからかもしれません。
たとえば、「キーマンとの接点数を1日1件つくる」「見積依頼を3件もらう」など、
・「商談化率を上げたい」→「接触回数を増やす」
・「案件数が足りない」→「紹介依頼を毎日1件送る」
ポイントは、目標を“数字”にすることではなく、“動きに変換”することです。
目の前のTODOが明確になると、行動スピードが自然と上がっていきます。
目標があるから動くのではなく、動けるから目標が近づいてきます。
今日の一歩が見える目標に、置き換えてみるのがコツです。
▼編集部のおすすめ動画を見る
それ、設定の仕方に原因があるかも。多くの人が見落とす目標設定の落とし穴と、すぐ実践できる「OKR」と「SMART」の活用法を1分半で解説します!
「数字が会話になる」からマネジメントが回る
「数字が会話になる」とは、感覚や雰囲気ではなく、数値をもとにコミュニケーションが進む状態のことです。
つまり、「たぶん良さそう」ではなく、「商談化率が前月比20%改善した」と言える状態を指します。
けれども実際は、「頑張ってます」「いけそうです」といった抽象的な報告が、チームの動きを曖昧にしてしまう場面も多いです。
実は、数字を言語に変えることで、行動の振り返りも指示も、すべてがクリアになります。
たとえば、
・「初回架電からの商談化率が15%だった」
・「提案から受注までの平均リードタイムが28日だった」
ポイントは、数字を“評価”に使うのではなく、“会話のきっかけ”に使うことです。
感覚を揃えることで、ズレを最小化し、スピードも精度も上がります。
数字があると、問い方が変わります。
「なぜ動けてない?」ではなく、「どの数字が鈍っている?」と聞けるようになります。
「狙いのズレ」にすぐ気づけるようになる
「狙いのズレに気づける」とは、成果が出ない理由を感覚ではなく、数字や事実から正確に見つけられる状態のことです。
つまり、「頑張ってるのに受注できない」ではなく、「提案フェーズで競合に負けている」と気づける状態を指します。
けれども実際は、「なんとなく案件が止まっている」「たぶん温度感が低かった」など、感覚だけで判断してしまうこともありますよね。
実は、ズレは動きが止まってから探すのではなく、数字から先に察知することができるんです。
たとえば、
・「初回商談から提案までの移行率が大きく落ちている」
・「案件数はあるのに受注単価が下がっている」
ポイントは、“フェーズごとの数字”で狙いを定点チェックすることです。
どこで止まりやすいかを見ておくと、ズレに気づくスピードが一気に上がります。
営業はズレないことより、ズレに早く気づけることの方が大切かもしれません。
数字があると、違和感を見逃さず、すぐに修正できます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業戦略】「もう感覚任せにしない」“戦略的営業”で目標を当たり前に達成する方法
営業の目標設定をする3つのメリット
「何をすれば売れるか」が見えてくる
「営業の目標設定」とは、売上や商談数といった結果指標だけでなく、それを生み出す行動レベルまでを具体化する設計です。
つまり、目標設定は「ゴールを決める作業」ではなく、「売れるプロセスを解像度高く設計する営み」と言い換えることができます。
けれども現場では、「今月あと何をやればいいのか、ピンとこない…」という声をよく耳にします。
実は、その違和感の正体は、“目標が行動にまで落ちていない”ことにあります。
例えば、
・「ヒアリング数を週単位で管理する」
・「初回訪問から次アクションを48時間以内に設定する」
より具体的には、
・「1日1件、決裁者との面談を確保する」
・「面談直後に録音を元に3行で要点メモを送る」
ポイントは、「数字」ではなく「動詞」で捉えることです。
行動にまで言語化されていれば、迷わず手が動くようになります。
「今日は何をすれば“売れる”のか」がひと目でわかる状態が、営業の迷いを減らし、着実に成果を積み上げる土台になります。
「育成の型」ができてチームで勝てる
「育成の型」とは、成果を出すための行動や思考を、誰でも再現できるように言語化・可視化したものです。
つまり、属人的な成功体験を「共有財産」に変えて、チーム全体の勝率を底上げする仕組みとも言えます。
けれども現場では、「できる人のやり方が他の人に伝わらない…」という課題に直面しがちです。
実は、この状態では、育成のたびに個別対応が必要になり、結果としてチームの生産性が伸びにくくなります。
例えば、
・「初回訪問の型を5ステップで統一する」
・「ニーズ深掘りの質問集を共有する」
より具体的には、
・「アイスブレイク→課題仮説→事例提示→共感→次アクション」の流れで話す
・「ペイン確認は“困っていること”ではなく“放置したらどうなるか”を聞く」
ポイントは、「教えること」を減らし、「一緒にやって再現する」環境をつくることです。
メンバーが「何をどうやれば成果につながるか」を自分の言葉で語れるようになると、チーム全体での成果も安定してきます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
営業責任者必見! 成功する営業チーム構築のヒント!【法人営業】Mansuke営業メンター/植野由芙子
「評価の軸」が明確になって揉めない
「評価の軸」とは、個人の成果や行動を正しく測るための基準を、あらかじめチーム内で共有しておく仕組みです。
つまり、上司の“感覚”ではなく、誰が見ても納得できる“共通物差し”をつくることを意味します。
けれども現場では、「なぜ自分だけ評価が低いのか納得できない…」という声が出てしまうことも少なくありません。
実は、こうしたすれ違いの多くは、事前に「何で評価されるのか」が明示されていないことが原因です。
例えば、
・「案件化率」「クロージング率」を数値で開示する
・「初回訪問数」「商談の質」を行動で可視化する
より具体的には、
・「週10件以上の訪問で次回提案につながった数を報告する」
・「失注理由をSlackに3行で記録するルールをつくる」
ポイントは、「評価を後出ししない」ことです。
評価軸を最初に伝えておけば、メンバーは安心して動けるようになります。
評価に関する不満の芽を摘むには、「何を見ているか」をあらかじめ示し、ズレが生まれないようにすることが大切です。
営業の目標設定をする際に気をつけたい3つのポイント
「高すぎる目標」はチームの士気を潰す
高すぎる目標とは、現実のリソースや状況を無視して設定された、達成の見込みが極めて低い目標のことです。
つまり、「頑張れば届く」ではなく「どう頑張っても届かない」と感じるレベルの数値です。
けれども、営業現場では「高い数字を掲げれば行動量も上がるはず」と思い込んでしまう場面もあります。
実はその心理は“目標の不確実性が高すぎると人は動けなくなる”という、心理学でも証明されている現象に直結しています。
たとえば、「半年後に1.5倍の新規開拓を達成する」「提案数を今月だけ3倍に引き上げる」など
ポイントは、数字自体の高さではなく、それが現場の肌感と乖離していないかを確かめることです。
「それ、無理じゃないですか?」と誰もが思ってしまう目標は、そもそも挑戦しようとすら思われません。
メンバーが“やれるかも”と感じられる設計に落とし込めると、自然と行動に火がついてきます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
モチベーションが上がる目標の立て方 (営業の目標設定②)
「数を追うだけ」では受注につながらない
「数を追うだけ」とは、商談件数や電話数などの“活動量”ばかりに意識が向いてしまい、“質”を見失った状態を指します。
つまり、動いた分だけ成果が出ると信じて、とにかく数を稼ぐことが目的化している状況です。
けれども実際は、「なぜ成約しなかったのか?」が見えないまま走り続けているケースも多いです。
実は、“数は足りているのに成果が出ない”とき、真のボトルネックは「誰に」「何を」伝えているかにあります。
たとえば、「課題が曖昧なまま提案してしまう」「キーマンに届く前に商談が終わる」など
ポイントは、「行動量=成果」ではなく「行動の中身が成果を決める」と捉え直すことです。
一見地味な“ターゲットの見直し”や“商談ログの深掘り”こそが、次の受注につながる確かな一手になります。
「回せないPDCA」は意味がない
「回せないPDCA」とは、計画や振り返りだけで止まってしまい、改善や次の行動に結びつかない状態を指します。
つまり、形だけのP(Plan)とD(Do)で満足し、C(Check)やA(Action)が機能していないサイクルです。
けれども実際は、「毎週振り返っているのに成果が伸びない…」と感じている営業チームも少なくありません。
実は、“見直しているつもり”でも、問いが浅ければ改善点が見えてこないことが多いです。
たとえば、「ヒアリングが浅かった理由を5WHYで深掘りする」「受注理由を分解して他商談に転用する」など
ポイントは、「なぜ?」を具体的に掘り下げて、“次の打ち手”に変換していく習慣を持つことです。
PDCAは回すものではなく、“進化させ続けるもの”として活用していくと、着実に成果が積み上がっていきます。
営業の目標設定をして成果に繋げる4つの手順
まず「KGI」を決めてゴールを明確にする
営業活動を始める前に、まず「KGI(最終目標)」を決めておくと、動きに一貫性が出てブレにくくなります。
KGIとは「最終的にどうなったら成功か?」を数値で定義したゴールのことです。
ポイントは、「売上〇〇万円」や「成約数△件」など、誰が見ても同じ結果だとわかる“客観的な指標”にすること。
よくあるのは、「とにかく頑張る」や「商談を増やす」など、成果ではなく行動目標をKGIとしてしまうケースです。これでは効果測定ができません。
具体的には、「今期は新規売上300万円をKGIに設定する」など、数字+期間を明確に決めることが重要です。
まずは「今期のゴールは何か?」を自分に問いかけてみることから始めてみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
営業の方、特に必見! KGI・KPIの設定方法!
次に「KPI」を逆算して行動に落とす
KGIが決まったら、そこに到達するための「KPI(中間目標)」を設定することで、日々の動きに明確な方向が生まれます。
KPIとは「KGIを実現するための途中経過の数値」で、行動レベルにまで落とし込むことがポイントです。
よくあるのは、「KGIだけ決めて日々の動きが感覚頼りになる」パターン。これでは計画と現実がズレやすくなります。
例えば、「新規売上300万円」がKGIなら、「週5件の新規商談」「月20件の提案提出」などがKPIになります。
具体的には、「1件成約に対して必要な商談数」「商談を生むためのアポ数」から逆算し、行動ベースに落とし込む流れです。
まずは、「この売上、何件の商談から逆算できるか?」を紙に書き出してみると整理が進みますよ。
▼編集部のおすすめ動画を見る
9割が知らないKPIの設定方法! 現場が改善されない理由と対策を徹底解説
週1で数字を見て詰まりを潰す
KPIを立てたら、あとは「進捗を週1で振り返る仕組み」を入れることで、ズレを早期に修正しやすくなります。
ここで言うのは、数字を見て「何が詰まっているか?」を特定する作業です。
ポイントは、感覚ではなく「どの数字が止まっているか?」に注目すること。
よくあるのは、数字を見て一喜一憂して終わってしまい、「どこで止まっているのか」まで深掘りしないパターンです。
具体的には、「アポは取れてるが商談化していない」「提案は出せてるがクロージング率が低い」など、KPIの途中にある“滞留箇所”を見つけて対処します。
週1回、5分だけでもいいので、KPIの数字に“引っかかっているところはどこか”を自問してみてください。
月1で振り返って修正する
週ごとに数字を追っていたら、月に一度は「全体の進み具合」を俯瞰して見直す時間をつくると軌道修正が効きやすくなります。
ここでの目的は、「最初に立てたKGI・KPIが現実に合っているか?」を確認し、必要なら修正することです。
ポイントは、「達成できそうか?」ではなく「このやり方でいいのか?」と視点を変えること。
よくあるのは、「思ったより数字が届いていないけど、まぁそのうち…」と根拠なく先延ばしにしてしまうケースです。
例えば、「アポ率が低いならトークスクリプトを見直す」「成約率が下がってきたら提案資料の構成を変えてみる」など、数字を起点に“やり方”を調整していきます。
月初や月末など、カレンダーに“見直しタイミング”を決めておくと、自然と動きが整ってきますよ。
営業の目標設定でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「営業の目標設定をがんばっているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
がんばって設定した目標が、チームを動かす力にならない。数字ばかりが先行して、現場のやる気がついてこない――そんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか。目標設定がうまくいかないと、日々の営業活動に迷いが生まれ、結果にも影響が出てしまいますよね。
でも大丈夫です。営業目標の立て方には“勝ちパターン”があります。
それは、現場感に即した設計と、数字の裏付けに基づいたリアリティのある設定です。
弊社スタジアムは、目標設計から実行体制の構築まで、現場を知り尽くした営業のプロが一貫で伴走します。
「目標設定の壁を超えたい」と思った今が、変化のチャンス。
いま悩んでいるあなたにこそ、この機会を活用してほしい。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
2025年最新トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
なぜ勝てない?「勝てる営業組織」のあるべき姿と9つの改革ポイント
営業組織の強化方法「完全ガイド」属人化を防ぐ8ステップ・11の特徴
【管理職必見】部下の飛び込み営業が怖い10の理由/成果に変える7つの指導法
BtoB営業で「売れる人」になる15のコツ|トップ営業が実践する思考法と手順
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業で「結果を出す」心構え15選|プロが教える思考・習慣・行動原則
営業で結果が出ない5つの理由と13の打開策【考え方が肝】
営業成績が悪い9つの理由|売れない営業の共通点と今日からできる改善策
インサイドセールス15のコツと今すぐ使えるトークフレームワーク3選
営業マンが「化ける」まで【11の共通項】マネージャーのための3つの習慣
【脱ダメ営業マン】特徴13選共通パターンと改善4ステップ
営業は数字が全ては錯覚?9つの理由営業の不振を脱却する実践的方法
2025年 最新アウトバウンド営業で成果を出す15のコツ
【完コピOK】テレアポが上手い人の頭の中話し方と思考法をインストールする15の具体的な方法
テレアポの教科書「13のコツ」と電話営業で避けたい5つのNG行動
【例文7選】営業メールの教科書|返信率を高める13のコツ準備〜書き方まで完全解説
最終更新日