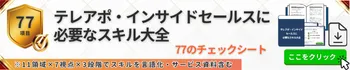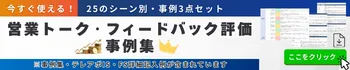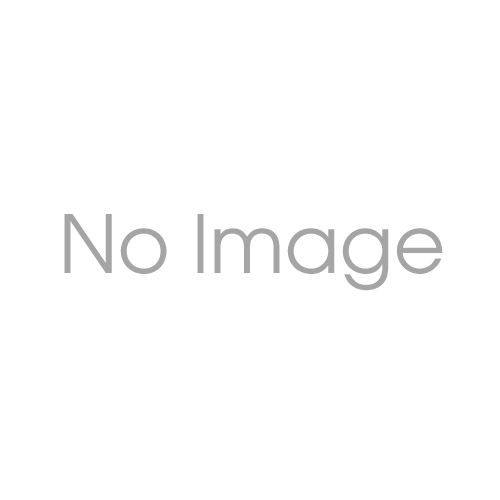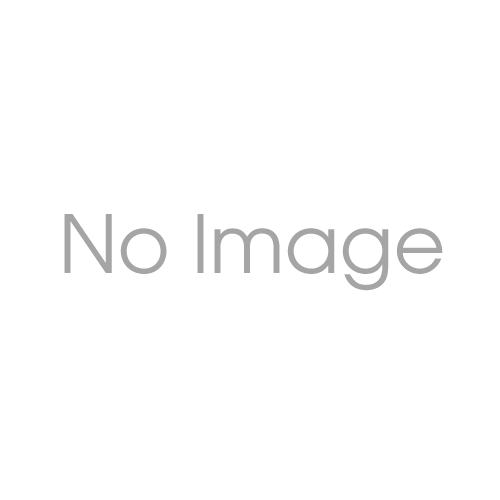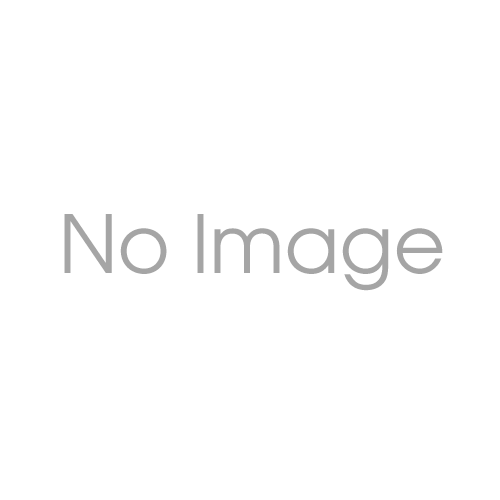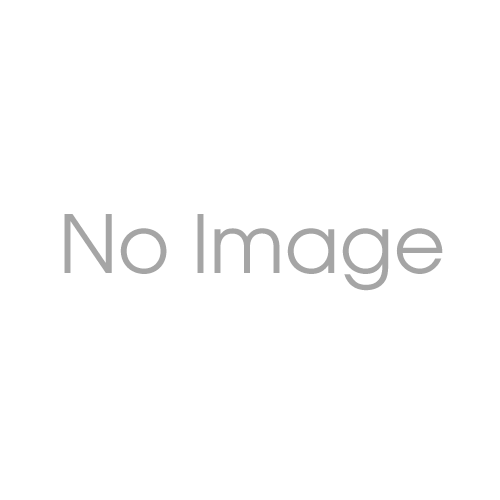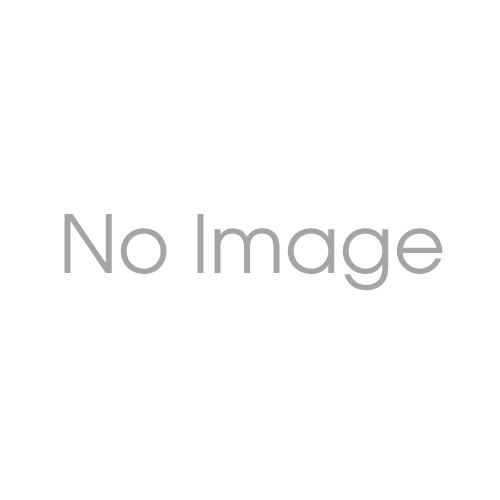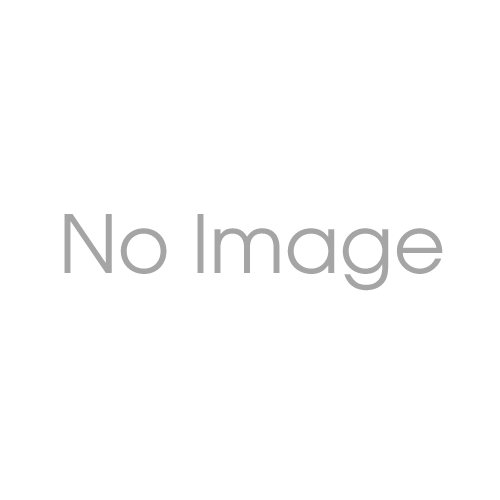営業成績が悪い9つの理由|売れない営業の共通点と今日からできる改善策
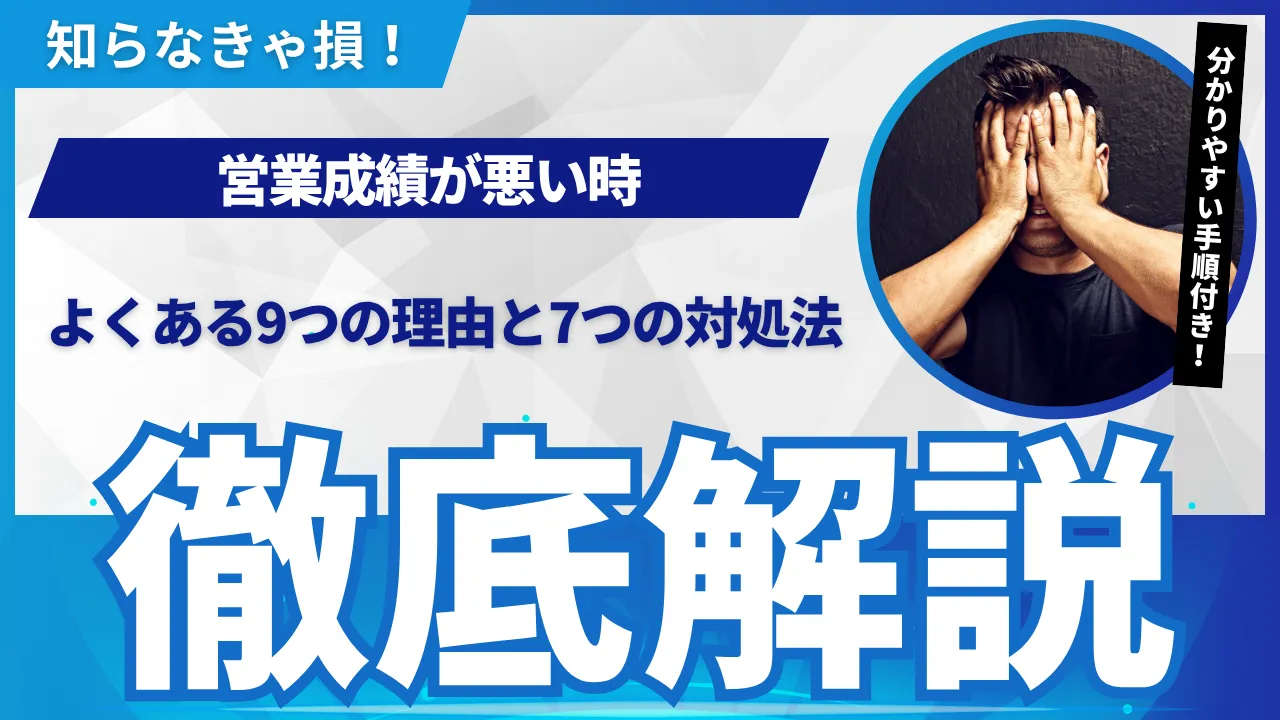
「営業って、こんなに成果出なかったっけ…?」
資料も出して、提案もして、アポも取ってる。なのに数字がついてこない──
そんな“地味にキツい営業不調”、あなたにも心当たりはありませんか?
実はこの状態、がんばり方を間違えているだけかもしれません。
よくある落とし穴を見抜き、明日から変えられる習慣にアップデートすれば、営業成績はちゃんと上向きます。
本記事では、再現性のある“勝てる営業のやり方”を、現場目線で徹底解説します。
・営業成績が悪い時よくある9の理由9つ(キーマン未接触・稟議落ち・感覚営業)
・営業成績の不調から脱出する具体策7選(業種絞り・朝ロープレ・KPI逆算表)
・営業成績を出し続ける人の9つの習慣(初回で決裁確認・提案3パターン・Slackメモの活用)
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
営業成績が悪い時よくある9の理由
「ペルソナ設定」がズレていると、最初から刺さらない
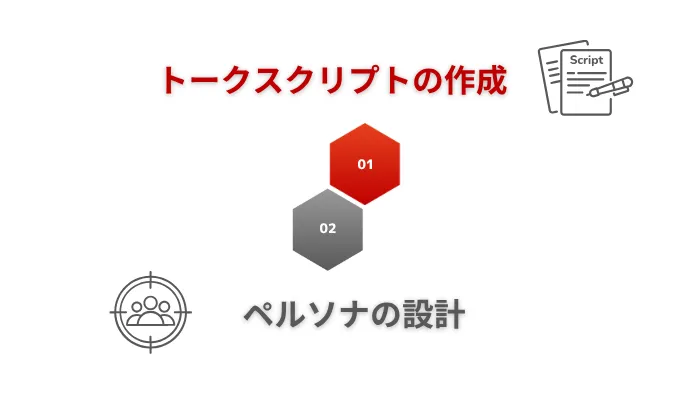
ペルソナとは「最も商談化しやすい決裁者像」を言語化する作業です。
つまり、誰に・何を・どう提案するかの“起点”であり、ここがズレると全営業活動が空回りします。
「商談は入るけど決まらない」「提案資料が刺さらない」そんな営業の違和感を感じたことはありませんか?
実は、見込み顧客の“役職”や“課題の解像度”を見誤ると、そもそもニーズに届かないことが多いんです。
「情シス向けに経営課題を語ってしまう」「係長にCFO向け資料を送ってしまう」などが典型例です。
営業代行会社は、CVR(商談化率)改善に直結する「職位別トークスクリプト」や「ターゲット階層設計」を持っています。
・「決裁者の関心軸」に合わせてトークをリフレーミングする
・「LTVの高い業種」を起点にリストを再設計する
このように、“誰に届けるか”を一点突破で見直すだけで、営業の打ち手はガラッと変わってきます。
「課題ヒアリング」が浅いと、提案が刺さらずスルーされる
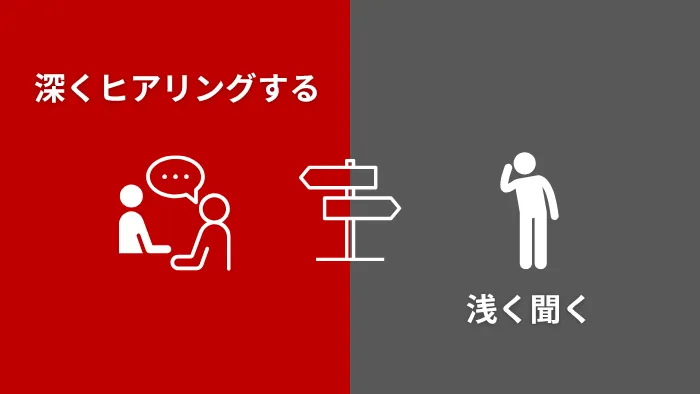
課題ヒアリングとは、「顧客の真のニーズや業務上のボトルネックを言語化するための対話」です。
つまり、聞き出せた情報の“深度”が、その後の提案の刺さり方を決めるわけです。
「提案したのに検討止まりだった」「課題感あると言ってたのに失注した」そんな営業の違和感、ありませんか?
実は、表面の要望(Wants=あると嬉しいもの)だけを拾って、真の課題(Needs=ないといけないもの)を掘れていないケースが多いんです。
「担当者の“業務不満”だけで提案してしまう」「“価格の安さ”に引っ張られた提案をする」などが典型例です。
営業代行会社では、BANT条件に加え「解決インパクト」「現行手段の不満」「KPI未達の背景」などまで深掘りする質問設計を行っています。
・「過去の打ち手」を聞き、なぜ変えたいのかの“理由”を明らかにする
・「意思決定の構造」を把握し、誰の腹落ちが必要かを整理する
このように、“浅く聞く”のではなく“深く潜る”意識でヒアリングを行うと、提案の質が見違えてきます。
「競合対策」が甘いと、資料の時点で負けている

競合対策とは、他社との違いを明確に伝え、顧客に選ばれる理由を論理的に示す営業戦略のことです。
つまり、提案資料の中で「なぜ自社を選ぶべきか」を言語化できなければ、比較された瞬間に埋もれてしまうということです。
「提案資料に差がない」「価格以外の価値が伝わらない」そんな悩み、営業で感じたことはありませんか?
実は、その違和感は“資料作成”時点での競合想定の甘さに起因しているケースが多いです。
たとえば「競合資料を精査して設計する」「営業代行会社と競合比較の壁打ちをする」といった工夫が必要です。
・競合との違いを“顧客の言葉”で説明できるようにする
・失注理由を蓄積し、資料改善のPDCAを回す
このように、“資料の時点で選ばれる”状態をつくることが、営業の底上げに直結します。
「キーマン接触」ができてないと、商談が回らない
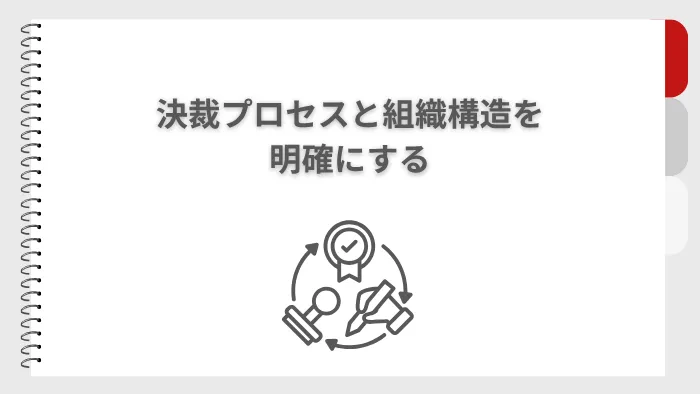
キーマン接触とは、意思決定権を持つ担当者と直接つながることを指します。
つまり、現場担当者との会話だけでは、いくら提案を重ねても前に進まないケースが多いです。
「窓口と3回打ち合わせした」「見積提出後に連絡が来ない」営業でそんな経験ありませんか?
実は、BtoB営業では“決裁者と最初に会えているかどうか”が、案件の成否を左右する大きな分岐点になります。
「キーマンの情報を営業代行会社に確認する」「初回訪問で決裁フローを質問する」などが具体策です。
・初回ヒアリング時に「誰が最終判断をされるか」を確認する
・商談設計時に「決裁プロセス」と「組織構造」を明確にする
このように、“誰と話すか”にこだわることで、商談の質とスピードを劇的に変えてみてください。
「導入するメリット」が数字で語れないと、稟議で落ちる

導入メリットの数値化とは、提案の効果や価値を具体的な数値で示すことを指します。
つまり、定性的な表現だけでは「この提案、本当に必要?」と社内で疑問視されやすくなります。
「コスト削減としか伝えていない」「業務効率化の根拠が曖昧」そんな営業の課題、感じたことはありませんか?
実は、法人営業においては、定量的な裏付けがない提案は、稟議の段階で高確率で止まる傾向があります。
「“年間●時間削減”と明記する」「“導入半年で費用回収”を提示する」などが具体的な対策です。
このように、営業代行会社の知見も借りながら、“数値で語れる提案”に変えていくことが、決裁突破の近道になります。
「ネクストアクション未設定」で、商談が自然消滅する
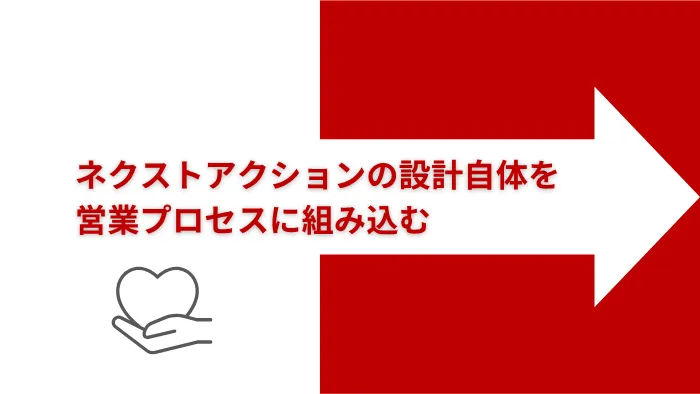
ネクストアクションとは、次に営業担当者が取るべき“具体的な一手”を指します。
つまり、次回アポの日時や資料送付の約束、社内稟議の段取りなどを明確に決めておくことです。
「提案後に音沙汰がない」「決裁者と繋がれない」そんな経験、営業で感じたことはありませんか?
実は、それらの多くは“次にやること”が曖昧なまま終話してしまったことが原因で起きています。
「次回打ち合わせ日を仮押さえする」「検討資料をその場で共有する」などがその具体例です。
営業代行会社では、商談ごとにアクションログを残し、次回動線を必ず設計する仕組みがあります。
・会話の最後に“確認事項とToDo”を口頭で整理する
・カレンダー招待をその場で送信し、記憶ではなく予定に残す
このように、ネクストアクションの設計自体を営業プロセスに組み込んでみてください。
「提案書の型」がないと、毎回アドリブで勝率が落ちる
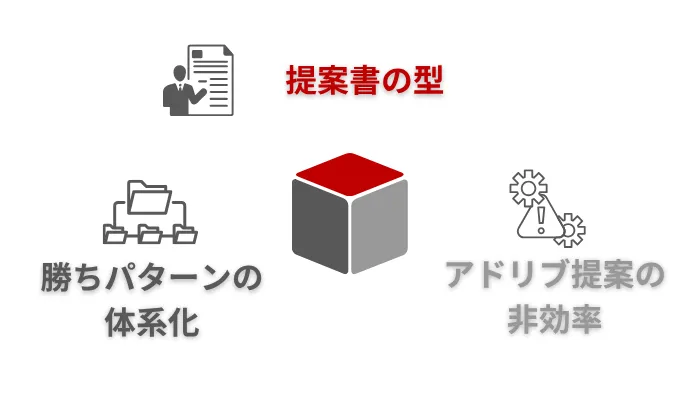
提案書の型とは、営業における「勝ち筋」を再現性ある形で文書化したテンプレートのことです。
つまり、過去に刺さった提案の流れや構成を“型”として持たないと、毎回ゼロから考えるアドリブ提案になり、営業成果にバラつきが出やすくなります。
「案件ごとに資料の構成がバラバラ」「毎回提案に時間がかかる」そんな営業の悩み、感じたことはありませんか?
実は、こうした非効率の背景には“提案書の型”が社内に存在していない、または定着していないケースが非常に多いです。
「決裁者向けの“導入効果に特化した構成”を用意する」「業界別の“汎用テンプレートを営業代行会社と共創する”」などが代表例です。
・決裁者視点の提案導線を構造化する
・過去事例ベースで勝ちパターンを体系化する
このように、型を持つことで、誰が提案しても一定水準を担保できるようにしてみてください。
「CRM入力」が雑だと、振り返れず改善できない
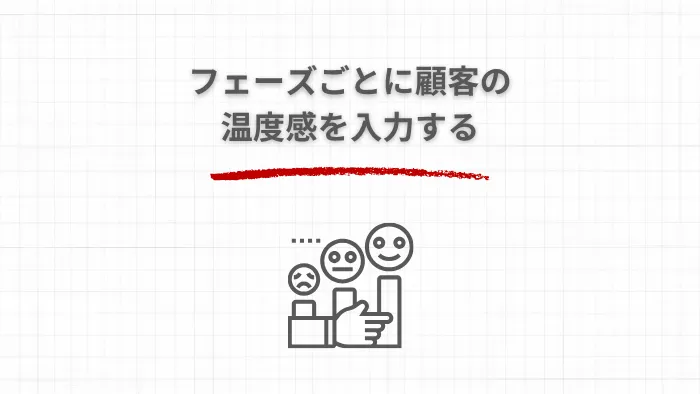
「CRM入力が雑」とは、営業活動の履歴や商談の経緯をシステムに正確かつ詳細に残していない状態を指します。
つまり、どの案件で何が起きていたのか、営業担当者本人さえ思い出せず、次の打ち手を見誤る原因になります。
「前回提案内容を忘れる」「顧客の課題が曖昧なまま進める」そんな営業の悩み、感じたことありませんか?
実はこの問題、忙しさや面倒くささが原因ではなく、CRMを“社内の共通言語”として捉えられていないことが多いです。
「提案理由を具体的に記録する」「受注失注理由を正確に残す」など、営業代行会社の多くが徹底している入力ルールがあります。
・フェーズごとに顧客の温度感を入力する
・次回打ち手を“第三者でもわかる”粒度で記載する
こうした“見える化の習慣”が、営業組織の再現性と改善サイクルを生み出していきます。
今のCRM運用が“日報の延長”で止まっていないか、一度見直してみてください。
「感覚営業」が抜けないと、いつまでも成果が安定しない
感覚営業とは、過去の経験や勘に頼り、体系的なプロセスやデータを用いずに進める営業スタイルを指します。
つまり、営業の再現性や予測性が乏しく、成果の波が大きくなりがちという特徴があります。
「提案内容が毎回異なる」「商談の進め方が属人的」そんな営業、身に覚えはありませんか?
実はこの状態、努力不足ではなく“構造不在”が原因となっていることが非常に多いです。
「案件管理をSFAで一元化する」「トークスクリプトを標準化する」といった方法が、感覚営業からの脱却には有効です。
営業代行会社を活用すると、KPI設計やセールスプロセスの整備まで伴走してもらえるため、再現性の高い営業が構築しやすくなります。
・「受注率を分解し、ボトルネックを可視化する」ようにする
・「ファネルごとに必要な行動量を設計する」ようにする
このように、仕組みで営業を動かす考え方を、今日から少しずつ取り入れてみてください。
営業成績が悪い時7つの対処法
「ターゲットリスト」を捨てて、刺さる業種に絞り込む
数字が伸び悩むときは、「数を打つ」より「刺さる相手に絞る」方が案外うまくいくことが多いです。
リストが広すぎると、誰にも刺さらず、熱量の低い提案になってしまいます。
だからこそ、“この業種にしか言えないこと”を言える準備が、大切になってきます。
実際、「業界あるある」で一笑い取れた瞬間に、ぐっと距離が縮まるケースも珍しくありません。
ポイントは、「自分たちが勝てる場所を見極めること」です。
- 「過去に高確率で商談化した業種」に絞る
- 「担当者の肩書き」が似ている層を優先する
- 「競合導入事例」が刺さりそうな業界を狙う
狙いを定めれば、打ち手も変わります。広げるより、削る勇気が商談の質を高めてくれます。
「ロープレ」を毎朝10分やるだけで、トークが研ぎ澄まされる
営業が伸び悩むとき、頭よりも“口”を動かす方が突破口になることがあります。
朝イチのロープレは、脳より先に身体を営業モードにしてくれる時間です。
とくに決裁者への初回トークは、言い回しひとつで流れが変わるので、大切にしたい時間になります。
毎日10分で、言い淀みや余計な言葉がどんどん削ぎ落とされていきます。
ポイントは、相手役に「気になった一言だけ」フィードバックしてもらうことです。
- 「提案理由」だけを1分で語る練習
- 「反論対応」だけを3パターン録音して聞き返す
- 「初回アポの冒頭トーク」だけを徹底して繰り返す
磨くのは流暢さじゃなく、“伝わる骨組み”です。トークの温度が、朝10分で変わり始めます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業ロープレ完全版#2】法人営業のヒアリングは『コレ』で決まる【ヒアリング編】
「受注確度の高い商談」だけに、時間を全振りしてみる
成果が鈍るときは、薄く広く動くよりも、見込みの高い案件に絞るのが大切です。
「今月まだイケる」相手に、残りの力を集中的に注いでみる。
スプレッドより、ディープなアプローチの方が商談の密度が上がります。
「何社アプローチしたか」ではなく、「誰とどこまで深掘れたか」を見直すのがポイントです。
実際、確度の高い商談は、次のアクションも具体的に決まりやすく、前に進む感覚が違います。
ポイントは、「数を打つ」ではなく「受注確度を意識する」です。
- 「過去に3回以上やり取りがある相手」へ集中的にフォロー
- 「稟議・検討フェーズに入っている案件」だけに打ち手を練る
- 「現場担当と決裁者の両方に接点がある商談」に注力する
商談の密度を攻めた方が、結果的には数字に返ってきやすいです。
「Slackで商談録」を流し、チーム内からアドバイスをもらう
調子が悪いときこそ、一人で抱え込まない工夫が大切です。
Slackに「商談の要点」を流すと、第三者視点のヒントがもらえる場面があります。
自分では気づかない“もったいない言い回し”や“攻め方の選択肢”が見えてくることもあります。
ポイントは、「相談」ではなく「情報共有」です。
具体的には次のような工夫が有効です。
- 「商談メモ」ではなく「話した内容の時系列」を流す
- 「失注理由」を自分なりに仮説化して書く
- 「どう切り返すか?」の問いを添える
“わかる人にだけ伝わる”ではなく、“誰にでも状況が伝わる”共有が、良質なアドバイスを引き出します。
「商談後5分以内フォロー」で記憶が残っているうちに口説く
温度が高いうちに動くと、意思決定のスピードも変わってきます。
特にBtoB商談では「印象の鮮度」が購買意欲を大きく左右します。
大切なのは、“商談内容を覚えているうちに”相手の温度をもう一度引き上げること。
ポイントは、「後日改めて」ではなく「今の熱をつかまえる」タイミングです。
- 「商談直後にサンクスメール」で、要点と温度をそのまま再送
- 「相手の発言を引用」して、“ちゃんと聞いてた感”を届ける
- 「次回アクションの仮日程」を提示して、判断の腰を軽くする
記憶が新しいうちの一通が、検討リストの最上位に引き上げるポイントになります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【小井の5分朝礼「商談後のプロセスがわかりません」にお答えします!】
「上司同行」でトークのクセを一撃で修正してもらう
クロージング直前で失注が続くときは、上司同行が“ズレ”の正体をあぶり出してくれます。
自分では気づきにくい「導入トークの温度」や「ヒアリングの深度」に、成約を左右する差が潜んでいることがあります。
大切なのは、同行後すぐに“刺さらなかった理由”をすり合わせることです。
ポイントは、「話す量」ではなく「相手の表情が変わるタイミング」です。
- 「ヒアリング項目」を事前に共有して、ズレの原因を言語化
- 「初回商談のシナリオ設計」を見直して、逆質問を増やす
- 「提案資料の入り方」を調整して、興味関心の導線を作る
一度のフィードバックで、提案トークの“設計図”が生まれ変わることもあります。
「KPI逆算表」を手元に置いて、動きを数字で可視化する
感覚だけで動くと、どこで滑ってるか見えにくくなります。
受注が止まってきたときは、「商談化率」「提案率」「成約率」を数字で棚卸ししてみるのが大切です。
KPI逆算表があると、ネクストアクションが迷わなくなります。
ポイントは、「アポ数を追う」のではなく「歩留まりを整える」こと。
- 「成約率」から逆算して、必要な「新規架電数」を割り出す
- 「案件化率」が低ければ、ヒアリング項目と初期打診の精度を見直す
- 「日報」に逆算値を落とし込み、現場でズレを即チェック
このように、数字を見える化しておくと、打ち手の優先度が自然と見えてきます。
営業成績を残し続ける人がやっている9つの習慣
「初回商談」で“決裁者の同席可否”を必ず確認している
初回商談における“決裁者確認”とは、提案前の段階で意思決定権を持つ人物の同席可否を見極める行為です。
つまり、誰に提案をぶつけるかによって、商談の成否が決まるといっても過言ではありません。
「現場担当だけと話していた」「提案後に“持ち帰ります”と言われた」そんな営業の悩み、感じたことはありませんか?
実は、これは提案内容の問題ではなく、“決裁フローを把握していなかった”ことが原因のケースが多いです。
「決裁者のスケジュールを確認する」「初回に合意形成者を招くよう促す」などがその一例です。
このように、商談の土台を整えることが、営業成績の底上げにつながっていきます。
「商談冒頭の3分」で信頼を一気に取りにいく
商談の冒頭3分とは、初対面の相手と信頼関係を築くために最も重要な時間です。
つまり、相手が“この人の話を聞こう”と心を開くか否かが決まる分岐点です。
「アイスブレイクが形式的になる」「商品紹介から始めてしまう」そんな営業、無意識にやっていませんか?
実は、営業成績が高い人ほど、冒頭で“共通項の発見”や“相手の背景理解”に時間を使っています。
「事前準備で相手の会社ニュースを調べて話す」「雑談で経営者の価値観を引き出す」などがその具体例です。
このように、冒頭3分で“聞く準備”を整えれば、その後の提案が刺さりやすくなります。
商談は“開始”で9割決まると意識して、ぜひ実践してみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業マン必見】最初の3分で信頼される営業は、何が違うのか?
「Slackに商談メモ」を毎回アップして、改善PDCAを回している
商談メモをSlackに即時アップするとは、営業活動を“情報資産”として積み上げる習慣のことです。
つまり、属人化しがちな「営業トーク」や「キーマン情報」をチームで再現できる状態にする動きです。
「過去商談の熱量が共有できない」「提案理由の言語化が弱い」そんな営業の壁、感じたことありませんか?
実は、メモの蓄積が弱いと“失注理由の解像度”や“勝ちパターンの特定”が曖昧になり、PDCAが回りにくくなります。
・メモに“課題仮説→解決案→次回アクション”を必ず記載する
・チャンネル単位で“商談ログのタグ管理”を行い、検索性を高める。
このように、営業現場の“暗黙知”をSlackで“可視化資産”に変えることで、成績の再現性は自然と高まっていきます。
想定外に備えて「3つの提案パターン」を常に引き出しに持っている
提案パターンとは、商談の転び方に応じて、あらかじめ用意された「刺さる打ち手」のことです。
つまり、軸をズラした複数案を持っておくことで、ひとつが崩れても商談が死なない状態をつくる考え方です。
「キーマン異動で白紙になる」「想定外の値下げ要望が来る」そんな経験、営業でありませんか?
実は、事前に“型”を仕込んでおけば、いざ逆風でも提案の軸を瞬時に切り替えられる強みになります。
たとえば「業務負荷削減に振り切る提案をする」「月額から成果報酬に切り替えて再提示する」などの策が有効です。
こうした“営業設計の引き出し”が、失注を防ぎ、営業成績を底上げしてくれます。
「競合比較表」を生成AIで作成して、迷う余地を潰している
競合比較表とは、顧客の意思決定を“背中押し”するために、機能・価格・サポート体制などを軸に他社との違いを一目で伝える営業資料です。
つまり、ヒアリングで得た課題をもとに「買う理由」を定量で示す“比較ロジック”です。
「競合に流れる理由がわからない」「提案が刺さってるのに決まらない」そんな営業の悩み、ありませんか?
実は、比較表がないと、相手は“なんとなくの安心感”で無難に競合を選んでしまうことが多いんです。
「決裁者向けにROIを強調する」「他社にはない運用支援を目立たせる」などがその一例です。
生成AIを使えば、競合LPやIR情報を元に、自社優位の“ファクト整理”ができます。
このように、“定量×ロジック”の競合比較があるだけで、営業成績は驚くほど変わってきます。
「ヒアリングシート」を使って、聞く項目をルーティン化している
ヒアリングシートとは、営業時に聞くべき項目を事前に整理し、商談の質と再現性を高めるためのツールです。
つまり、担当者ごとの“聞き漏れ”や“話の脱線”を防ぎ、成約率を安定化させる手助けをしてくれる仕組みとも言えます。
「毎回ヒアリングがバラつく」「聞きたいことが聞けずに終わる」そんな経験、営業の現場で感じたことはありませんか?
実は、こうした営業のバラつきは個人スキルの問題ではなく、“準備のフレームがないこと”に原因がある場合が多いです。
「顧客課題を深掘りできる質問を用意する」「導入時期を確実に聞き出す」などがその一例です。
より具体的には
・定量/定性ヒアリングを分けて整理する
・BANT項目をテンプレ化する
このように、ヒアリングを型化することで営業成績を伸ばすきっかけをつくってみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【無料で配布!】ヒアリングシートを大公開【営業マン必持】
「返信は5分以内」でレスポンスの質で信頼を積んでいる
即レスとは、顧客からの連絡に対して5分以内に返す営業行動のことです。
つまり、商談前から「この人、仕事早いな」と思わせる信頼構築の第一歩です。
「営業」で返信のスピードが本当に成績に影響すると思いますか?
実は、初動対応が早いだけで、案件の温度感が下がる前に“商談化率”が一気に跳ね上がる傾向があります。
とくに法人営業では、決裁者が複数のベンダーを比較している中で「反応速度」が無意識に判断軸になっています。
「Web問い合わせに即電話する」「議事録を当日中に送付する」などがその一例です。
より具体的には
・一次返信だけでも“リアクション”を即打ちする
・SFA上で対応ステータスを“即アップデート”する
タイミングを逃すだけで、熱が冷めて案件がフェードしてしまうこともあります。
返信スピードこそ、無形の“提案価値”だと捉えて、営業成績に直結するアクションとして取り組んでみてください。
「商材知識」を業界トレンドと絡めて語れる
商材知識とは、商品のスペックや機能を理解するだけでなく、業界の変化や構造的課題と結びつけて提案できる力のことです。
つまり、顧客の現場課題と“刺さる活用シーン”をセットで語れるかが、営業成績を左右します。
「営業で商材を語るとき、業界のどんなトピックと結びつけていますか?」
実は、機能説明だけでは決裁者の意思決定を動かせず、“業界構造を俯瞰した提案”が信頼を生みます。
「SaaSで“業務工数を40%削減する”」「物流DXで“実車率を改善する”」などがその一例です。
より具体的には
・“ターゲット業界の課題構造”をピラミッド構造で整理する
・“業界内の意思決定パターン”に合わせて導入インパクトを言語化する
このように、「業界変化 × 商材活用」という視点で、商談の突破力を高めてみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【トップセールス集結②】売れる営業になるために今すぐ実践できること
「スケジュール管理」が徹底されており、2割の余裕がある
スケジュール管理とは、目標達成に向けて“営業活動”を逆算しながら時間を設計することです。
つまり、アポ・商談・内勤すべてを“案件進捗”ベースで整理し、ムダな移動や待機を削ぎ落とす考え方です。
「急な商談で提案書が間に合わない」「予実管理の時間が取れない」そんな営業の悩み、感じたことありませんか?
実は、予定が埋まりすぎていると、“リードタイムの確保”ができず、案件の質も成約率も下がりがちです。
「午前中に“架電集中枠”を設ける」「週1で“提案ブラッシュアップ枠”を入れる」などがその一例です。
より具体的には
・クロージング前に“決裁者対策ミーティング”を先に入れておく
・週初めに“数字進捗レビュー”を固定枠として押さえておく
このように、“2割の空白”を戦略的に組み込むことが、営業成績を安定させる動線をつくっていきます。
営業成績が悪い状況を脱却する4つの手順
まず「失注商談10件」を洗い出して失注パターン言語化する
営業成績が落ちてきたとき、最初にやるべきは“自分の負けパターン”の可視化です。
ここでいう可視化とは、感覚や印象ではなく、「具体的な失注理由の言語化」を意味します。
ポイントは、「商談ごとの敗因」を単にメモするのではなく、言語として“共通点”を拾うこと。
よくあるのは、「価格で負けた」「競合に流れた」といった表面的なまとめで終わるパターン。これでは改善のヒントが見えてきません。
具体的には、以下の手順がおすすめです。
①過去30〜60日の失注商談から10件をピックアップ
②商談ごとの「最終接点・相手の言葉・競合名・提案内容」を書き出す
③そこから「共通して現れるキーワードや相手の反応」を抜き出す
④それらを一文で言い表す失注パターンに落とし込む
たとえば、「検討はするが上に通らない」が共通していれば、「決裁者との接点不足型」と命名するだけで、次回からの動きが変わります。
言葉にすると、次の一手が具体的になります。今すぐ10件の商談を振り返ってみましょう。
「決裁者へのフロー」を引き直して提案の順序を整える
いきなりプレゼンせずに、まず「誰に、何を、どう通すか」の全体像を描いてから動くのが第一歩です。
「決裁者へのフローを引き直す」とは、商談相手の社内承認プロセスを把握し、その流れに沿って提案の順番や内容を見直すことです。
ポイントは、「影響力のあるキーマンが誰か」「誰がどこで止める可能性があるか」を事前に整理しておくこと。
よくあるのは、目の前の担当者だけに話して満足してしまい、実際の決裁者に届かずにフェードアウトするケースです。
具体的には、次のように進めます。
①相手に「社内で誰にどう共有される予定か」を自然にヒアリングする
②その流れに沿って「中継者にも刺さる要素」を資料に盛り込む
③先に通す順番を見直し、必要なら段階的な提案に切り分ける
「この話、どう通したら一番スムーズですかね?」と一言添えるだけで、驚くほど展開が変わることがあります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【目指せトップ営業マン!担当者の壁を突破!決裁者に話を …
「案件棚卸しシート」で優先順位をつけ直す
「何から手をつけるべきか分からない…」そんなときは、案件を“見える化”するだけで突破口が見えてきます。
棚卸しとは、全案件の「受注確度」「案件ステージ」「キーマン接触状況」を整理し、“追うべき案件”にリソースを集中させる作業です。
ポイントは、「提案済み」「比較検討中」などの“フェーズ分け”と、「BANT条件」「ネクストアクションの明確さ」で仕分けること。
ありがちなのが、“商談回数が多い案件=ホット”と勘違いしてしまい、実は動かない案件に工数をかけすぎるミスです。
たとえば、スプレッドシートに「商談回数」「決裁者接触の有無」「案件金額」「最終接触日」を列で並べ、色分けすると「動かせる案件」と「寝かせる案件」が一目で判断できます。
一度、冷静に“商談の棚”を並べ替えてみてください。ムダ打ちが減り、歩留まりがグッと改善する感覚があるはずです。
「週次の振り返りMTG」をチームでルーティン化する
数字が伸び悩むときは、「受注率の鈍化」や「商談フェーズの停滞」が起きている可能性があります。
週次MTGは、それを“営業プロセス単位”で解像度高く洗い出す場になります。
ポイントは、「アポ数」や「案件創出数」ではなく、「初回商談の質」や「次回打診率」など“中間KPI”にフォーカスすること。
よくある間違いは、「数値の羅列」で終わってしまい、打ち手が抽象論に寄ってしまうことです。
例えば、「提案資料を送ってから返信が遅い案件が増えてる」と感じたら、「送付タイミング」「補足トーク」「送信後のフォロー」まで掘り下げて共有する。
たったそれだけで、再現性のあるアクションが1つ増えます。
まずは“数字の裏側にある行動”を、毎週チームで覗いてみてください。そこから勝ち筋が見えてきます。
営業成績が悪くてお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「営業成績を上げようとをがんばっているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
毎日アポを取り、提案を磨き、数字のプレッシャーに耐えているのに、結果がついてこないとき、ふと心が折れそうになること、ありますよね。
頑張っても空回りしているような感覚、周囲と比べて焦る気持ち、そんな時こそ一人で抱え込まないことが大切です。
営業は、才能ではなく「戦略」と「仕組み」で変わります。
弊社スタジアムの営業代行サービスでは、IT・Web領域に強い専属担当が、御社の課題に合わせて実働レベルで支援します。
「何から相談したらいいかわからない…」そんな方でも大丈夫。
今、営業活動に迷いを感じている方こそ、まずは一度、私たちにお声かけください。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き
【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説
営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順
【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版
インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集
営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文
【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全
【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集
【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!
アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説
【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略
【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説
法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略
【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説
深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順
営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善
13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド
営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション
営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順
【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版
【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集
営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド
営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別
【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果
【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順
【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順
【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点
営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順
【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド
【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き
営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順
できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法
売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法
プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順
【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き
営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策
【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説
【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説
なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術
新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順
営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説
なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法
ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP
ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集
飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法
【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド
【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版
セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法
セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド
新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版
新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全
【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説
新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ
新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法
【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版
【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集
アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法
インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順
【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版
【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法
SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法
MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説
BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法
BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略
BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順
【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版
【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ
【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説
営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選
FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド
【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方
14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順
アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ
シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ
これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順
【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集
【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP
【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説
営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ
御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP
【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順
【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集
営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法
営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順
27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場
【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順
営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準
新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル
営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント
クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順
営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説
営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順
営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順
最終更新日