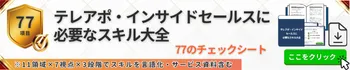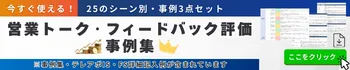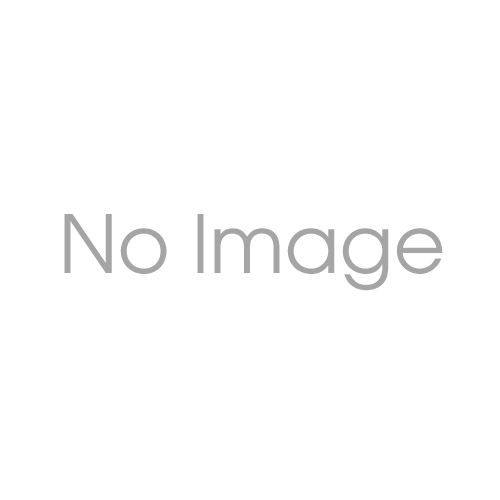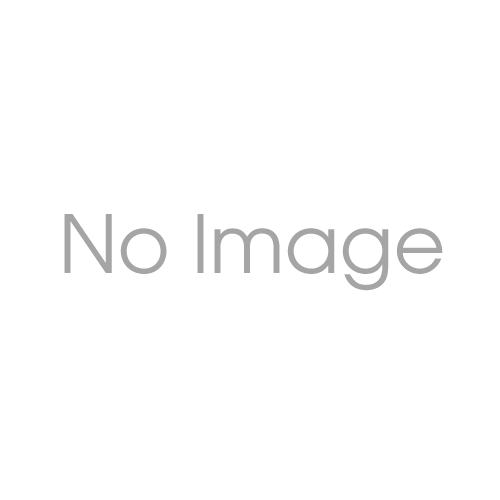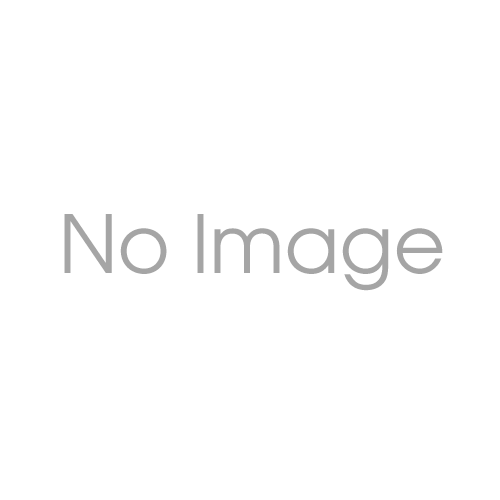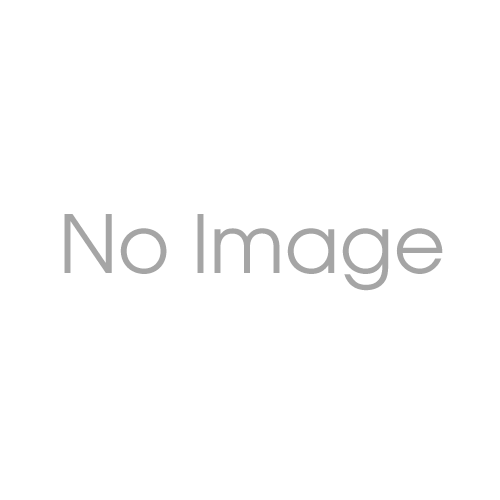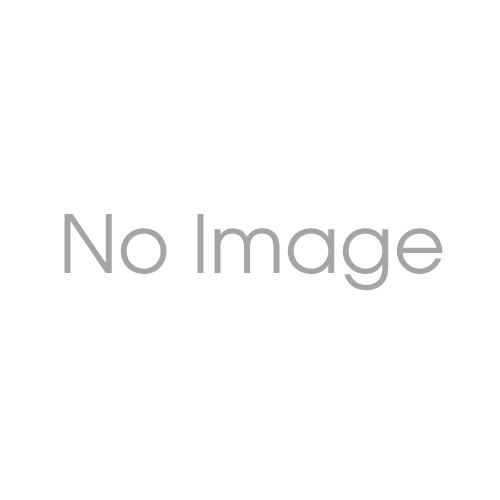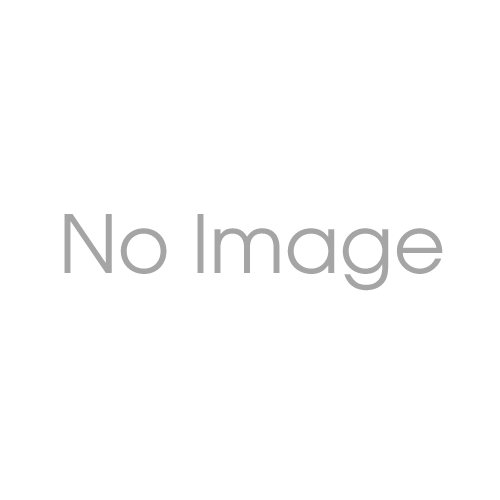【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
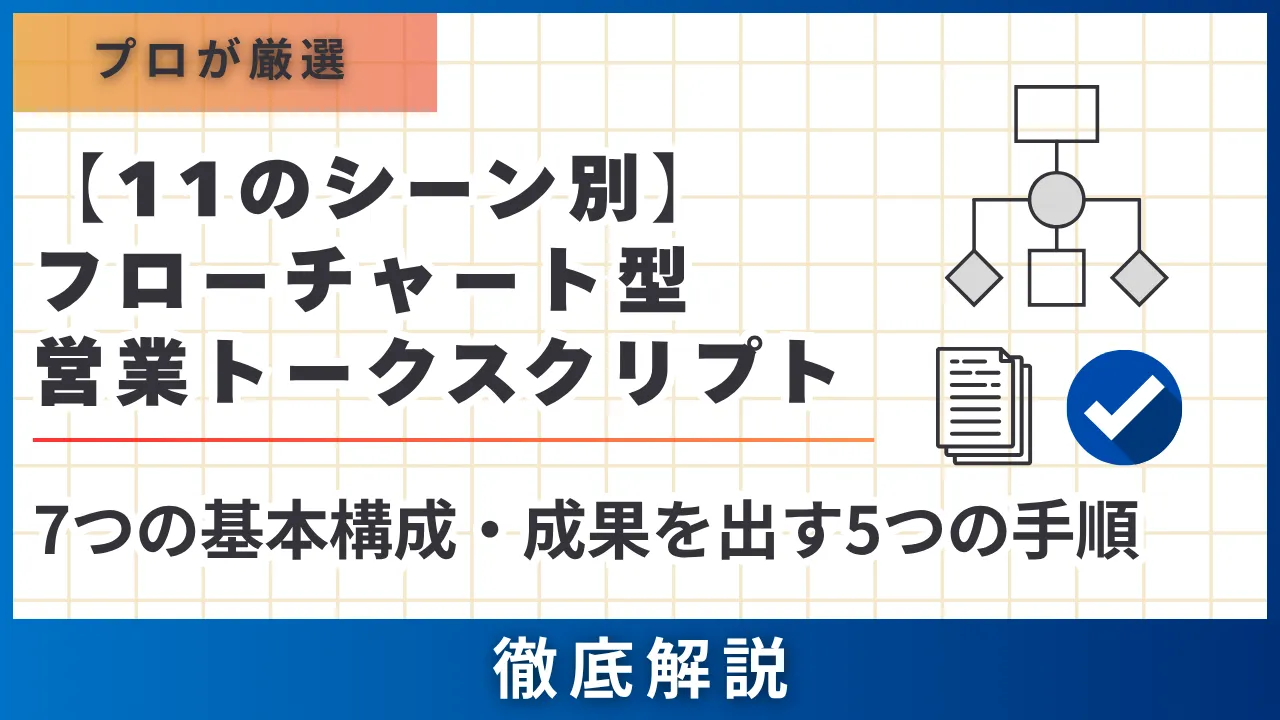
「営業トークスクリプトを準備しても、お客様との会話が詰まってしまった…」そんな経験はありませんか?
本記事では、お客様の反応に応じて柔軟に対応できる「フローチャート型営業トークスクリプト」の設計方法を、11のシーン別・7つの基本構成とともに徹底解説します。
・フローチャート型トークスクリプトの4つの目的と3つのメリット(属人化防止・抜け漏れ防止・失注要因の可視化)
・営業トークの7つの基本構成と11の活用シーン別の具体例(新規開拓・テレアポ・クロージングなど)
・作成時の3つの注意点と役立つツール7選(Miro・Notion・ChatGPTなど)
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、
ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
フローチャート型営業トークスクリプトを活用する4つの目的とは
「分岐型トーク」で会話を"詰まらせない"営業設計をつくる
「お客様の反応が想定外で、会話が止まってしまった…」と感じたことはありませんか?
実は、お客様の反応パターンを事前に分岐設計しておくことで、どんな返答にもスムーズに対応できるようになります。
たとえば、
「興味がある場合は→詳細資料を提示する」
「今は必要ない場合は→導入時期を確認する」
のように、Yes/No/保留など複数のルートを準備しておくことで、会話が詰まらない営業設計が実現します。
ポイントは、「一本道のトーク」ではなく、「複数の選択肢を持つトーク」を設計することです。
どんな反応が返ってきても対応できる準備があれば、営業の成功率は格段に上がります。
まずはお客様の反応を3パターンに分けて、それぞれの対応を考えてみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
興味あり(Yes)の場合 |
「それでは、御社の課題に合わせた具体的な提案書をお持ちしますね」 |
|
今は不要(No)の場合 |
「承知しました。では、どのタイミングでご検討される予定か教えていただけますか?」 |
|
検討中(保留)の場合 |
「他社様と比較検討中なんですね。決め手になるポイントがあれば教えていただけますか?」 |
|
予算が合わない場合 |
「ご予算に合わせたプランもご用意できますので、一度ご相談させてください」 |
|
決裁者不在の場合 |
「ご決裁者様にもお話を伺いたいのですが、次回同席いただくことは可能でしょうか?」 |
このように、分岐型トークを設計しておくと、どんな反応にも柔軟に対応できる営業力が身につきます。
会話を詰まらせない設計が、成約率向上の鍵になります。
「想定質問と回答パターン」を整理して、即答できる体制を整える
よくある質問を事前に想定し、回答パターンを整理しておくことで、どんな質問にも即座に答えられる体制が作れます。
たとえば、
「価格について聞かれたら→具体的な金額とプラン内容を説明する」
「導入期間について聞かれたら→最短スケジュールと標準スケジュールを提示する」
のように、頻出する質問とその回答をセットで準備しておくことで、商談中に迷わず答えられるようになります。
ポイントは、「その場で考える時間を減らし、即答する準備をしておく」ことです。
即答できることが、お客様からの信頼を獲得する第一歩になります。
まずは過去の商談で実際に聞かれた質問を振り返り、回答パターンを整理してみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
価格について |
「基本プランは月額○万円からで、御社の規模に応じてカスタマイズも可能です」 |
|
導入期間について |
「最短で2週間、標準的には1ヶ月程度でご利用開始いただけます」 |
|
競合他社との違い |
「他社様との違いは、専任担当による手厚いサポート体制です」 |
|
導入実績について |
「同業界では○○社様や△△社様にご導入いただいており、満足度は95%以上です」 |
|
契約期間について |
「最低契約期間は6ヶ月からで、その後は月単位での更新が可能です」 |
このように、想定質問と回答パターンを整理しておくと、商談中の不安が減り、自信を持って対応できます。
即答できる体制が、営業の成約率を大きく引き上げます。
「Yes/Noの流れ図」でお客様の心理動線を見える化する
お客様の反応をYes/Noの流れ図で整理することで、心理動線が明確になり、次にどう動くべきかが一目で分かるようになります。
たとえば、
「興味がある(Yes)→詳しい資料を送る」
「今は必要ない(No)→時期を変えて再アプローチする」
のように、お客様の反応ごとに最適なアクションを事前に設計しておくことで、会話が詰まることなくスムーズに進められます。
ポイントは、「すべての反応に対応策を持つ」ことで、どんな展開でも焦らず対応できるようになることです。
フローチャートで心理動線を可視化すると、営業活動の次の一手が明確になります。
|
項目 |
例文 |
|
興味あり(Yes)の場合 |
「それでは、御社の状況に合わせた提案資料を明日までにお送りしますね」 |
|
今は不要(No)の場合 |
「承知しました。では、3ヶ月後に改めてご連絡させていただいてもよろしいでしょうか?」 |
|
検討中(保留)の場合 |
「他社様との比較検討中とのことですね。決め手になるポイントがあれば教えていただけますか?」 |
|
予算が合わない場合 |
「ご予算に合わせたプランもご用意できますので、一度ご相談させてください」 |
|
決裁者不在の場合 |
「ご決裁者様にお繋ぎいただくことは可能でしょうか?もしくは、ご決裁者様向けの資料をご用意いたします」 |
このように、お客様の反応パターンごとに対応を準備しておくと、どんな状況でも自然に会話を続けられます。
心理動線を見える化することで、営業の精度が格段に向上します。
「判断ミスを防ぐトーク構造」で新人でも安定した成果を出せるようにする
トークを構造化して判断ポイントを明確にすることで、経験の浅い新人でも安定した成果を出せるようになります。
たとえば、
「この質問が来たら→この資料を見せる」
「予算の話になったら→このプランを提案する」
のように、判断が必要な場面ごとに明確なルールを設定しておくことで、迷わず適切な対応ができるようになります。
より具体的には、「いつ・何を・どう話すか」を事前に設計しておくことで、現場での判断ミスを大幅に減らせます。
ポイントは、「考える時間を減らし、行動する時間を増やす」ことで、営業活動の質を高めることです。
構造化されたトークがあれば、新人でも判断するべきポイントが明確になり、商談を安定して進めることが出来ます。
|
項目 |
例文 |
|
価格について聞かれた時 |
「基本プランは月額○万円からで、御社の規模に合わせてカスタマイズも可能です」 |
|
導入事例を求められた時 |
「同業界のA社様では、導入後3ヶ月で問い合わせ数が20%増加しました」 |
|
競合と比較された時 |
「他社様との違いは、導入後のサポート体制の手厚さです。専任担当が付きます」 |
|
決裁者が不在の時 |
「それでは、ご決裁者様向けの資料をご用意しますので、ご共有いただけますか?」 |
|
今すぐ決められないと言われた時 |
「承知しました。ご検討に必要な情報があれば、すぐにご用意いたします」 |
このように、判断が必要な場面ごとに対応を準備しておくと、新人でも迷わず行動できます。
トーク構造の明確化が、営業組織全体の底上げにつながります。
フローチャート型営業トークスクリプトの3つのメリット
「属人化を防ぐ」ことで誰でも成果を再現できる営業組織が実現できる
トップセールスのノウハウを誰でも使えるようにすることは、大きなメリットです。
フローチャート型のトークスクリプトがあれば、個人の経験や勘に頼らず、組織全体で成果を再現できる仕組みが作れます。
また、新人でもベテランと同じ水準の対応ができるため、立ち上がり期間を大幅に短縮できるのも強みです。
以下に、属人化を防ぐことで得られる要素を整理しました。
|
項目 |
メリット |
ベネフィット |
|
ノウハウの標準化 |
トップセールスの会話パターンを型化できる |
誰でも同じ質の営業ができるようになる |
|
新人教育の効率化 |
教える内容が明確になり、指導時間を削減できる |
即戦力化までの期間が短縮される |
|
離職時のリスク軽減 |
個人に依存せず、組織にノウハウが蓄積される |
人材の入れ替わりがあっても成果が維持できる |
このように、フローチャート型トークスクリプトによる標準化は、組織全体の営業力を底上げします。
属人化を防ぐことで、安定した成果創出が可能になります。
「会話の抜け漏れ」を防ぎ、信頼を積みあげられる
ヒアリング項目を漏れなく確認できることは、大きなメリットです。
フローチャートで必要な質問項目を整理しておけば、商談後に「聞き忘れた」という事態を防げます。
また、顧客との信頼関係を損なうことなく、スムーズに情報を引き出せるため、提案精度が高まるのも強みです。
以下に、会話の抜け漏れを防ぐことで得られる要素を整理しました。
|
項目 |
メリット |
ベネフィット |
|
ヒアリング漏れの防止 |
必要な質問項目がチェックリスト化される |
商談後の手戻りがなくなり、提案が一度で決まる |
|
顧客満足度の向上 |
的確な質問で顧客のニーズを深く理解できる |
「ちゃんと話を聞いてくれる」という信頼を得られる |
|
提案精度の向上 |
必要な情報が揃った状態で提案できる |
成約率が高まり、失注リスクが減少する |
このように、フローチャート型トークスクリプトによる抜け漏れ防止は、提案精度を高めます。
必要な情報を漏れなく収集することで、成約率の向上につながります。
「失注要因の可視化」で改善サイクルを高速化できる
どの段階で顧客が離脱したかを特定できることは、大きなメリットです。
フローチャートで会話の流れを記録しておけば、失注した原因が「ヒアリング不足」なのか「提案内容」なのかを明確に分析できます。
また、データに基づいた改善ができるため、同じ失敗を繰り返さず、営業力を継続的に高められるのも強みです。
以下に、失注要因の可視化で得られる要素を整理しました。
|
項目 |
メリット |
ベネフィット |
|
失注ポイントの特定 |
どの会話段階で離脱したかがデータで分かる |
改善すべき箇所が明確になり、無駄な施策を減らせる |
|
改善施策の優先順位付け |
最も影響の大きい課題から対処できる |
限られたリソースで最大の効果を出せる |
|
PDCAサイクルの加速 |
仮説検証が短期間で回せるようになる |
営業力が継続的に向上し、組織全体が成長する |
このように、フローチャート型トークスクリプトによる失注要因の可視化は、改善サイクルを加速させます。
データに基づいた改善により、営業組織が継続的に成長します。
フローチャート型営業トークスクリプトの7つの基本構成
「導入トーク」で相手の警戒心を一瞬で解く
「いきなり本題に入るのは気が引ける…」と感じることはありませんか?
実は、最初の一言で警戒心を解くことができれば、その後の商談がスムーズに進む可能性が高まります。この導入トークが上手くいくかいかないかで商談の結果は左右されます。
たとえば、
「天気や季節の話題で共感を生み出してから本題に入る」
「相手のオフィス環境や持ち物に触れて親近感を作る」
のように、営業色を出さない自然な会話から始めることで、相手の心の壁を下げることができます。
ポイントは、「売り込み感ゼロの第一声」で相手をリラックスさせることです。
導入トークの質が、商談全体の成否を左右します。
まずは相手が警戒せずに話せる雰囲気を作ることから始めてみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
天気・季節トーク |
「今日は冷え込みますね。暖房の調整、大変じゃないですか?」 |
|
オフィス環境への共感 |
「この眺め、仕事しやすそうですね。集中できそうな環境ですね」 |
|
移動の話題 |
「こちらまでの道、工事が多くて迷いました。いつもこの状況なんですか?」 |
|
相手の持ち物への関心 |
「そのノート、使いやすそうですね。私も似たタイプを探してたんです」 |
|
地域ネタ |
「このエリア、最近お店が増えましたよね。ランチはどのあたりに行かれるんですか?」 |
このように、導入トークで警戒心を解いておくと、本題に入った時の受け入れ態勢が全く変わります。
最初の一言が、信頼関係構築の第一歩になります。
「課題ヒアリング」で潜在ニーズを引き出す質問設計をする
初対面の相手にいきなり営業の話を切り出してしまって、空気が固まった経験、一度はあるかと思います。
実際、警戒心が高い状態で提案をすると、内容の良し悪しに関係なく「断られやすくなる」傾向があります。
たとえば、
「現状の課題を聞いた後、"理想の状態"を質問して差分を明確にする」
「"もし〇〇ができたら"という仮定の質問で、本当に求めているものを探る」
など、段階的に質問を深めることで、表面的な課題の裏にある本質的なニーズが見えてきます。
ポイントは、共感・関心・安心を生み出す"質問の流れ"を最初に設計することです。
それがあるだけで、相手が本音を話す「心理的安全性」が生まれます。
まずは1つの質問からでも、相手の状況を深く理解する姿勢を示してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
現状確認の質問 |
「現在の営業プロセスで、一番時間がかかっているのはどの部分ですか?」 |
|
困りごとの深掘り |
「その課題が解決しないと、どんな影響が出ていますか?」 |
|
理想状態の確認 |
「もし理想的な状態になったとしたら、どんな状況をイメージされますか?」 |
|
優先順位の確認 |
「いくつか課題がある中で、一番先に解決したいのはどれですか?」 |
|
過去の取り組み確認 |
「これまでに何か対策を試されたことはありますか?その結果はいかがでしたか?」 |
このように、深いヒアリングが提案精度を高め、成約への道筋を作ります。
まずは相手の課題を丁寧に聞くことから始めてみてください。
「共感パート」で"自分ごと化"を促す
沈黙を埋める力とは、商談中のちょっとした間(ま)に自然な言葉を添えて、緊張や違和感を和らげるコミュニケーションの技術です。
つまり、無言の時間を"あえてつくる"のではなく、"自然につなぐ"ことで、相手の警戒心を和らげられるのです。
でも、「提案はしたけど、相手が自分ごととして捉えてくれなかった…」という状況に直面したことはないでしょうか。
共感を示すことで、お客様が課題を"自分ごと"として認識し、解決への意欲が高まります。
たとえば、
「"その状況、本当に大変ですよね"と課題に寄り添う言葉を挟む」
「"同じような悩みを抱えている企業様、実は多いんです"と孤独感を和らげる」
など、相手の感情や状況に共感する言葉を入れることで、信頼関係が深まります。
ポイントは、「相手のこと」か「場のこと」について、無理なく自然に触れることです。
|
項目 |
例文 |
|
課題への共感 |
「その状況、現場は相当大変ですよね。よく分かります」 |
|
状況の理解 |
「人手不足の中で対応するのは、本当に負担が大きいと思います」 |
|
同じ悩みの共有 |
「実は同じ業界の企業様も、同じ課題で悩まれているんです」 |
|
焦りへの寄り添い |
「早く改善したいけど、何から手をつければいいか分からない状況ですよね」 |
|
努力の承認 |
「これまで色々試されてきたんですね。その努力、本当に素晴らしいと思います」 |
このように、こちらがリラックスしている雰囲気が伝われば、相手も自然と心を開いてくれます。
次の訪問では、共感の時間こそ、信頼構築のチャンスとして味方につけてみてください。
「提案パート」で価値を"数字"と"事例"で伝える
「いきなり本題に入るのは気が引ける…」
営業の現場で、このように感じる瞬間は誰にでもあります。
実は、具体的な数字と事例を使うことで、提案の説得力が格段に上がります。
たとえば、
「"導入後3ヶ月で問い合わせ数が20%増加しました"と具体的な成果を示す」
「"同業界のA社様では、月間の作業時間を15時間削減できました"と事例で証明する」
のように、数字と実例を組み合わせることで、相手がイメージしやすい提案になります。
より具体的には、「ROI」「削減時間」「増加率」など、相手が重視する指標で価値を示してください。
ポイントは、「抽象的な良さ」ではなく、「測定可能な成果」で語ることです。
数字と事例が、提案の信頼性を高めます。
まずは自社の導入実績から、具体的な数字を整理してみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
ROIでの訴求 |
「導入費用は初年度で回収でき、2年目以降は純粋な利益改善につながります」 |
|
時間削減の訴求 |
「月間で約20時間の作業時間を削減でき、その分を新規営業に充てられます」 |
|
成果率の訴求 |
「導入企業様の85%が、3ヶ月以内に成果を実感されています」 |
|
同業事例の提示 |
「同じ規模の製造業A社様では、不良品率が15%減少しました」 |
|
リスク軽減の訴求 |
「導入後のサポートで、トラブル発生率を従来の半分に抑えられます」 |
このように、立場に応じた提案をすることで、相手に刺さる説明が実現します。
「想定反論リスト」で"詰まらない会話"をつくる
初対面の相手にいきなり営業の話を切り出してしまって、空気が固まった経験、一度はあるかと思います。
実際、反論に答えられないと、内容の良し悪しに関係なく「商談が止まってしまう」傾向があります。
たとえば、
「"価格が高い"と言われたら→費用対効果を数字で示す」
「"今は必要ない"と言われたら→将来のリスクを提示する」
など、反論パターンごとに切り返しのトークを用意しておくことで、会話が詰まることなく進められます。
ポイントは、共感・理解・代案を生み出す"反論への備え"を最初に挟むことです。
それがあるだけで、「対応できる営業」という印象に変わります。
まずは1つの反論パターンからでも、気楽に準備してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
価格への反論 |
「初期費用だけで見ると高く感じるかもしれませんが、年間で換算すると月々〇万円で、人件費削減効果を考えると十分に元が取れます」 |
|
タイミングへの反論 |
「今は必要ないとのことですが、導入準備に平均2ヶ月かかるため、必要になった時点では遅い可能性があります」 |
|
競合比較の反論 |
「他社様と比較されているんですね。弊社の強みは導入後のサポート体制で、専任担当が付く点が大きな違いです」 |
|
効果への疑問 |
「本当に効果が出るか不安ですよね。同業界での導入実績が50社以上あり、平均で〇〇%の改善が見られています」 |
|
決裁への不安 |
「社内承認が難しいとのことですが、決裁者様向けの資料をご用意しますので、それを使ってご説明いただけますか?」 |
相手の心をひらくための、最初の一歩として活用してみてください。
「クロージング」を明確にして迷わせない
沈黙を埋める力とは、商談の最終局面で自然な言葉を添えて、決断への迷いを和らげるコミュニケーションの技術です。
つまり、無理に急かすのではなく、"自然に次のステップを示す"ことで、相手の決断を後押しできるのです。
でも、「契約を促すタイミングが分からず、機会を逃してしまった…」と後悔したことはないでしょうか。
実は、クロージングのタイミングと言葉を明確に設計しておくことで、自然に契約へと導けます。
たとえば、
「"ご検討状況はいかがでしょうか?"と直接的に意思確認する」
「"それでは、次のステップとして契約書をご用意しましょうか?"と具体的な行動を提示する」
など、曖昧にせず明確に次のアクションを示し、相手へ決断を促します。
ポイントは、「相手のこと」か「決断のタイミング」について、無理なく自然に触れることです。
|
項目 |
例文 |
|
意思確認クロージング |
「ご検討状況はいかがでしょうか?何か不安な点があれば、今お答えできます」 |
|
選択肢クロージング |
「導入時期として、来月と再来月、どちらがご都合よろしいですか?」 |
|
仮定クロージング |
「もしご導入いただけるとしたら、どのプランが御社に合いそうですか?」 |
|
直接クロージング |
「それでは、契約書をご用意させていただいてもよろしいでしょうか?」 |
|
期限クロージング |
「今月中にお申し込みいただくと、初期費用を20%割引できますが、ご検討いかがですか?」 |
このように、こちらが明確に次のステップを示せば、相手も自然と決断に向かってくれます。
次の商談では、クロージングの時間こそ、成約のチャンスとして味方につけてみてください。
「次回への布石トーク」でモチベを高める
「商談後のフォローが弱く、そのまま失注してしまった…」
商談の最後、このように次回につなぐ言葉を見つけられず、関係が途切れてしまうことがあります。
商談の最後に次回への布石を打つことで、関係が途切れず、次のアクションにつながります。
たとえば、
「"次回は〇〇について詳しくお話しさせてください"と次の議題を予告する」
「"1週間後に改めてご連絡しますので、それまでにご質問があればいつでもどうぞ"とフォロー体制を示す」
のように、次回の接点を明確にしておくことで、相手も心の準備ができ、関係が継続します。
ポイントは、「商談を終わらせるのではなく、次につなげる」意識です。
次回への布石が、長期的な関係構築を実現します。
まずは商談の最後に、次回のアクションを明確にする習慣をつけてみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
次回議題の予告 |
「次回は、導入後のサポート体制について詳しくご説明させてください」 |
|
フォロー日程の確定 |
「1週間後の〇日に、改めてお電話させていただいてもよろしいですか?」 |
|
宿題の設定 |
「それでは、御社の現状に合わせた提案書を作成しますので、来週お持ちしますね」 |
|
資料送付の約束 |
「本日の内容をまとめた資料を、明日中にメールでお送りします」 |
|
次回アポの仮押さえ |
「次回は決裁者様もご同席いただきたいので、来週のご都合をお伺いできますか?」 |
このように、次回への布石を残しておくと、関係が途切れず、次のビジネスチャンスにつながります。
フローチャート型営業電話/テレアポのトークスクリプト5つの手順
「アプローチトーク」で第一声から印象を掴む
テレアポの第一声こそが、顧客の"受け入れ態勢"を作るきっかけになることが多いんです。
たとえば、
「突然のお電話で恐れ入ります」
「お忙しいところ恐縮ですが、2分だけお時間よろしいでしょうか?」
のように、第一声に配慮の言葉を入れることで、相手の警戒心が和らぎます。
より具体的には、相手の"時間を奪っている自覚"や"丁寧な姿勢"を言葉で示すことが、会話継続の導線になります。
ポイントは、「いきなり要件を話す」のではなく、「話を聞ける場」をつくることです。
無理に説明しようとせず、相手がリラックスできる第一声をつくることが、最初の信頼構築につながります。
まずは相手が不快に感じない、丁寧で簡潔な挨拶を準備してみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
丁寧な前置き |
「突然のお電話で失礼いたします。〇〇株式会社の△△と申します」 |
|
時間配慮の明示 |
「お忙しいところ恐れ入ります。2分ほどお時間いただけますでしょうか?」 |
|
明るい自己紹介 |
「お世話になっております。〇〇のサービスを提供しております△△と申します」 |
|
担当者確認 |
「営業部門のご責任者様とお話しさせていただきたいのですが、いらっしゃいますか?」 |
|
状況確認 |
「今、お電話お話しできる状況でしょうか?もし難しければ改めさせていただきます」 |
このように、配慮ある第一声が、テレアポ成功の第一歩になります。
「関心喚起トーク」で"相手の課題意識"を引き出す
初対面の相手にいきなり営業の話を切り出してしまって、空気が固まった経験、一度はあるかと思います。
実際、警戒心が高い状態で提案をすると、内容の良し悪しに関係なく「断られやすくなる」傾向があります。
たとえば、
「同業他社様で人手不足による残業増加が課題になっているんですが、御社はいかがですか?」
「最近、営業のDX化を進める企業が急増していますが、ご検討されていますか?」
など、相手が「うちにも関係あるかも」と思える話題を投げかけることで、会話が自然と続いていきます。
ポイントは、共感・関心・安心を生み出す"情報提供"を最初に挟むことです。
まずは1つの業界課題からでも、気楽に試してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
業界課題の提示 |
「最近、同業界で人手不足による業務過多が深刻化していますが、御社はいかがですか?」 |
|
トレンドへの言及 |
「今年に入って、営業のDX化を進める企業が急増しているんですが、ご検討されていますか?」 |
|
他社事例の紹介 |
「同じ規模の企業様で、〇〇を導入して効率が上がったという声が多いんです」 |
|
共通の悩み |
「問い合わせ対応に時間を取られて、本業に集中できないというお悩み、よく伺います」 |
|
数字での訴求 |
「御社と同規模の企業様の8割が、同じ課題を抱えていらっしゃるんです」 |
このように、関心を引くトーク設計が、成功率を高めます。
まずは相手の課題意識を刺激する一言から始めてみてください。
「ヒアリングの分岐」で答えに応じた最適ルートを選ぶ
相手の反応に合わせた対応ができず、会話が途切れてしまったことはないでしょうか。
つまり、一方的なトークを続けるのではなく、"相手の答えに応じてルートを変える"ことで、会話が自然に続くのです。
でも、「反応に対応できず、会話が詰まってしまう…」と感じたことはありませんか?
相手の答えに応じて会話ルートを変える設計をしておくことで、どんな反応にもスムーズに対応できます。
たとえば、
「興味がある→詳しい説明に進む」
「今は必要ない→導入時期を確認する」
「検討中→他社との比較ポイントを聞く」
など、Yes/No/保留など複数の分岐パターンを想定しておくことで、会話が途切れにくくなります。その分岐パターンに沿って、会話の流れを事前に決めておくことでスムーズな会話が成り立ちます。
ポイントは、「相手の反応」か「温度感」について、無理なく自然に対応することです。
|
項目 |
例文 |
|
興味あり(Yes)の場合 |
「ありがとうございます。それでは、具体的にどのような点に関心をお持ちですか?」 |
|
今は不要(No)の場合 |
「承知しました。では、どのタイミングでご検討される可能性がありますか?」 |
|
検討中(保留)の場合 |
「他社様と比較検討中なんですね。決め手になるポイントがあれば教えていただけますか?」 |
|
担当者不在の場合 |
「承知しました。ご担当者様のお名前と、お電話に出やすい時間帯を教えていただけますか?」 |
|
詳しく知りたい場合 |
「それでは、資料をお送りしますので、メールアドレスを教えていただけますか?」 |
このように、こちらが柔軟に対応できる準備があれば、相手も自然と会話を続けてくれます。
次の架電では、分岐設計こそ、成功のチャンスとして味方につけてみてください。
「提案フレーズ」で"売り込み感ゼロ"の流れをつくる
「提案した瞬間に警戒されて断られた…」と経験したことはありませんか?
実は、提案の伝え方を工夫することで、顧客の"抵抗感"を減らすきっかけになることが多いんです。
たとえば、
「もしご興味があれば、一度資料をお送りしてもよろしいでしょうか?」
「同じ課題を抱えている企業様に、こんな方法をご提案しているんです」
のように、提案に選択肢や事例を組み合わせることで、押し付け感が消えます。
より具体的には、相手の"選ぶ権利"や"判断の余地"を残すことが、提案受け入れの導線になります。
ポイントは、「提案する」のではなく、「提案させていただく許可を得る」ことです。
無理に説得しようとせず、相手が選べる提案をつくることが、最初の受け入れにつながります。
まずは相手に選択肢を与える提案の仕方を意識してみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
選択肢を与える提案 |
「もしご興味があれば、詳しい資料をお送りしてもよろしいでしょうか?」 |
|
事例風の提案 |
「同じ課題を持つ企業様には、こういった解決策をご提案しているんです」 |
|
許可を得る提案 |
「一度、具体的なお話をさせていただく機会をいただけませんか?」 |
|
軽い提案 |
「参考程度に資料だけでもお送りしておきますね」 |
|
次回提案 |
「今回はお時間の都合もあると思いますので、改めて日程を調整させていただけますか?」 |
このように、訴求軸を使い分けることで、刺さる提案が実現します。
「再架電・フォロー導線」で"次につながる余韻"を残す
一度断られたら、そのまま関係が途切れてしまった経験、一度はあるかと思います。
実際、フォローをしないと、内容の良し悪しに関係なく「機会損失」が発生する傾向があります。
たとえば、
「それでは、3ヶ月後に改めてご連絡させていただいてもよろしいでしょうか?」
「もし状況が変わりましたら、いつでもご連絡ください」
など、次回の接点を残す一言が、将来の商談機会を生み出します。
ポイントは、丁寧さ・配慮・継続の意思を示す"クロージングトーク"を最後に挟むことです。
それがあるだけで、「また連絡してもいい相手」という印象に変わります。
まずは1つのフォロー導線からでも、気楽に試してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
再架電の許可 |
「承知しました。では、3ヶ月後に改めてご連絡させていただいてもよろしいでしょうか?」 |
|
フォローメール |
「本日の内容をまとめた資料を、念のためメールでお送りしておきますね」 |
|
連絡先の提供 |
「もし何かご質問があれば、いつでもこちらにご連絡ください」 |
|
タイミング確認 |
「ご検討されるタイミングが決まりましたら、ぜひお声がけください」 |
|
丁寧なクロージング |
「本日はお時間いただき、ありがとうございました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします」 |
相手の心をひらくための、最初の一歩として活用してみてください。
フローチャート型営業クロージングのトークスクリプトの作り方・設計5つの手順
「意思確認トーク」で決断のタイミングを逃さない
「クロージングのタイミングが分からず、契約を逃してしまった…」と感じることはありませんか?
実は、意思確認トークを適切に挟むことで、顧客の"決断の準備"を見極めるきっかけになることが多いんです。
たとえば、
「ご検討状況はいかがでしょうか?」
「何か不安な点があれば、今お答えできます」
のように、意思確認の質問を折り混ぜて、確認の姿勢を組み合わせることで、相手の本音が見えてきます。
より具体的には、相手の"購買シグナル"や"決断の兆し"を見逃さないことが、クロージング成功の導線になります。
ポイントは、「急かす」のではなく、「決断しやすい環境を整える」ことです。
無理に契約を迫らず、相手が決断できる状態を作ることが、最終的な成約につながります。
まずは相手の決断の準備状況を確認することから始めてみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
意思確認の質問 |
「ご検討状況はいかがでしょうか?何か不安な点があれば、今お答えできます」 |
|
決断の障壁確認 |
「導入に向けて、何かクリアすべき課題はございますか?」 |
|
温度感の確認 |
「現時点で、前向きにご検討いただけている状況でしょうか?」 |
|
次のステップ確認 |
「ご導入に向けて、次にどのようなステップが必要でしょうか?」 |
|
社内確認の有無 |
「社内でご相談が必要な点はございますか?」 |
このように、適切なタイミングで意思確認をすることで、成約への道筋が明確になります。
「比較検討フェーズ」で他社との差を明確に伝える
競合と比較されて、そのまま失注してしまった経験、一度はあるかと思います。
実際、差別化が曖昧な状態で提案をすると、内容の良し悪しに関係なく「他社を選ばれやすくなる」傾向があります。
たとえば、
「他社様との違いは、導入後のサポート体制の手厚さです」
「弊社の強みは、専任担当が付く点が大きな差別化ポイントです」
など、明確な差別化ポイントを示す一言が、選ばれる理由を作り出します。
ポイントは、優位性・独自性・具体性を生み出す"比較軸"を明確に挟むことです。
それがあるだけで、「選ぶ理由」が相手の中に生まれます。
まずは1つの差別化ポイントからでも、気楽に試してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
サポート体制 |
「他社様との違いは、専任担当が導入後も継続してサポートする点です」 |
|
導入実績 |
「同業界での導入実績が50社以上あり、ノウハウの蓄積が違います」 |
|
カスタマイズ性 |
「弊社は御社の業務に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です」 |
|
価格以外の価値 |
「初期費用は他社より高めですが、導入後のトラブル発生率が半分以下です」 |
|
スピード |
「最短2週間で導入可能な体制が、他社にはない強みです」 |
相手の心をひらくための、最初の一歩として活用してみてください。
「不安要素の分岐」を想定して即答できるようにする
不安要素の分岐とは、顧客が抱える不安を事前に想定し、それぞれに対する回答を準備しておくコミュニケーションの設計手法です。
つまり、不安を放置するのではなく、"事前に想定して対処する"ことで、契約への心理的ハードルが下がるのです。
でも、「どんな不安があるのか分からず、対応できなかった…」という場面に直面したことはないでしょうか。
実は、不安要素を事前にリスト化し、それぞれの対処法を準備しておくことで、どんな不安にも即答できます。
たとえば、
「導入後のサポートが不安→専任担当が付きます」
「効果が出るか不安→同業界での成功事例をご紹介します」
など、不安ごとに対処法を用意しておくことで、相手の懸念が解消されます。
ポイントは、「不安の内容」か「解消方法」について、無理なく自然に伝えることです。
|
項目 |
例文 |
|
サポート不安 |
「導入後も専任担当が付きますので、いつでもご相談いただけます」 |
|
効果への不安 |
「同業界での導入実績が50社以上あり、平均で〇〇%の改善が見られています」 |
|
コスト不安 |
「初期費用は初年度で回収でき、2年目以降は利益改善につながります」 |
|
操作の難しさ |
「導入時の研修と、操作マニュアルを完備していますので、安心してご利用いただけます」 |
|
社内調整の不安 |
「決裁者様向けの資料をご用意しますので、それを使ってご説明いただけます」 |
このように、こちらが不安を先回りして解消すれば、相手も自然と決断に向かってくれます。
次の商談では、不安解消こそ、成約のチャンスとして味方につけてみてください。
「契約導線トーク」で自然にYesを引き出す
「契約を切り出すタイミングが分からず、機会を逃してしまった…」
営業の現場で、このような悩みを抱えることは珍しくありません。
実は、契約導線トークを自然に組み込むことで、顧客の"決断への抵抗感"を減らすきっかけになることが多いんです。
たとえば、
「それでは、契約書をご用意させていただいてもよろしいでしょうか?」
「導入時期として、来月と再来月、どちらがご都合よろしいですか?」
のように、契約への質問に選択肢や行動提案を組み合わせることで、自然にYesが引き出せます。
より具体的には、相手の"決断の準備"や"次のステップ"を明確にすることが、契約成立の導線になります。
ポイントは、「契約を迫る」のではなく、「次のステップを自然に示す」ことです。
無理にプレッシャーをかけず、相手が決断しやすい流れを作ることが、最終的な成約につながります。
まずは相手に選択肢を与える契約導線から始めてみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
直接クロージング |
「それでは、契約書をご用意させていただいてもよろしいでしょうか?」 |
|
選択肢クロージング |
「導入時期として、来月と再来月、どちらがご都合よろしいですか?」 |
|
仮定クロージング |
「もしご導入いただけるとしたら、どのプランが御社に合いそうですか?」 |
|
期限クロージング |
「今月中にお申し込みいただくと、初期費用を20%割引できますが、ご検討いかがですか?」 |
|
次のステップ提示 |
「それでは、次のステップとして契約書の準備を進めさせていただきます」 |
このように、自然な契約導線を設計することで、相手が決断しやすい流れが作れます。
「受注後フォロー」でリピート・紹介につなげる流れをつくる
契約後の関係が途切れて、リピートや紹介につながらなかった経験、一度はあるかと思います。
実際、受注後のフォローが弱いと、内容の良し悪しに関係なく「関係が途切れやすくなる」傾向があります。
たとえば、
「導入後1週間で、状況確認のお電話をさせていただきます」
「何か困ったことがあれば、いつでもご連絡ください」
など、継続的な関係を示す一言が、次のビジネスチャンスへとつながります。
ポイントは、安心・信頼・継続を生み出す"アフターフォロー"を受注時に挟むことです。
それがあるだけで、「長く付き合いたい相手」という印象に変わります。
まずは1つのフォロー施策からでも、試してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
導入後の定期連絡 |
「導入後1週間・1ヶ月・3ヶ月のタイミングで、状況確認のご連絡をさせていただきます」 |
|
満足度確認 |
「ご利用状況に問題がないか、定期的に確認させていただきます」 |
|
追加提案の準備 |
「運用が安定したら、さらに効果を高める追加機能もご提案できます」 |
|
紹介依頼のタイミング |
「もし導入効果を実感いただけましたら、同じ課題を持つ企業様をご紹介いただけると嬉しいです」 |
|
継続的なサポート |
「何か困ったことがあれば、いつでも専任担当にご連絡ください」 |
受注後フォローは次につなげる営業チャンスです。
相手の心をひらくための、最初の一歩として活用してみてください。
フローチャート型営業トークスクリプトの11の活用シーン
「新規開拓営業」で初回アプローチの会話精度を高める
「新規開拓で何度も断られて、アプローチ方法が分からない…」と感じることはありませんか?
実は、フローチャート型のトークスクリプトこそが、新規顧客の"初回接触の成功率"を引き出すきっかけになることが多いんです。
たとえば、
「第一声で警戒されないトークパターンを準備する」
「相手の反応に応じた分岐ルートを設計しておく」
のように、初回アプローチに分岐設計を組み合わせることで、どんな反応にも対応できます。
より具体的には、相手の"温度感"や"関心度"を見極めることが、新規開拓成功の導線になります。
ポイントは、「一方的に話す」のではなく、「反応を見ながら進める場」をつくることです。反応に応じた分岐ルートを作成することで、一方的なコミュニケーションにはならず、相手の状況に沿ったコミュニケーションに変わります。
無理に説得しようとせず、相手が話を聞ける状態を作ることが、最初の信頼構築につながります。
まずは新規顧客の反応パターンを3つ想定することから始めてみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
第一声の工夫 |
「突然のご連絡で恐れ入ります。〇〇の件で2分だけお時間いただけますか?」 |
|
関心喚起 |
「同業他社様で〇〇の課題が増えているんですが、御社はいかがですか?」 |
|
興味あり時の対応 |
「ありがとうございます。それでは、具体的にお困りの点を教えていただけますか?」 |
|
今は不要時の対応 |
「承知しました。では、どのタイミングでご検討される可能性がありますか?」 |
|
次回接点の確保 |
「それでは、3ヶ月後に改めてご連絡させていただいてもよろしいでしょうか?」 |
このように、フローチャートで分岐を設計しておくことで、新規開拓の成功率が高まります。
「テレアポ現場」で"秒で断られないトーク"を設計する
テレアポで第一声から断られて、話を聞いてもらえなかった経験、一度はあるかと思います。
実際、フローチャート化されていないテレアポトークは、内容に関係なく「秒で切られやすくなる」傾向があります。
たとえば、
「第一声→関心喚起→ヒアリング分岐→提案→再架電導線」
「断られた時の切り返しパターンを複数用意しておく」
など、分岐を想定したトーク設計が、会話継続の鍵になります。
ポイントは、反応・分岐・切り返しを生み出す"テレアポ専用フローチャート"を事前に挟むことです。
まずは1つの分岐パターンからでも、気楽に試してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
第一声の設計 |
「突然のお電話で失礼いたします。2分だけお時間いただけますか?」 |
|
関心喚起の分岐 |
「同業界で人手不足が深刻化していますが、御社はいかがですか?」 |
|
興味あり時の対応 |
「ありがとうございます。具体的にどのような点にお困りですか?」 |
|
今は不要時の切り返し |
「承知しました。では3ヶ月後に改めてご連絡してもよろしいでしょうか?」 |
|
担当者不在時の対応 |
「ご担当者様のお名前と、お電話に出やすい時間帯を教えていただけますか?」 |
相手の心をひらくための、最初の一歩として活用してみてください。
「商談前ヒアリング」で必要情報を漏れなく引き出す
商談前ヒアリングとは、本格的な提案の前に顧客の課題や状況を整理し、最適な提案につなげるための情報収集プロセスです。
つまり、いきなり提案するのではなく、"事前に必要情報を集める"ことで、提案の精度が格段に上がるのです。
しかし、「何を聞けばいいか分からず、情報不足で提案がズレた…」という場面に直面したことはないでしょうか。
実は、フローチャートでヒアリング項目を整理しておくことで、漏れなく必要な情報を引き出せます。
たとえば、
「現在の課題→理想の状態→予算→決裁者→導入時期」
「各項目に対する深掘り質問を準備しておく」
など、ヒアリング項目ごとに質問を用意しておくことで、抜け漏れが防げます。
ポイントは、「ヒアリング項目」か「深掘り質問」について、無理なく自然に聞き出すことです。
|
項目 |
例文 |
|
現状課題の確認 |
「現在の営業プロセスで、一番時間がかかっているのはどの部分ですか?」 |
|
理想状態の確認 |
「もし理想的な状態になったとしたら、どんな状況をイメージされますか?」 |
|
予算の確認 |
「ご予算はどれくらいでお考えでしょうか?」 |
|
決裁者の確認 |
「最終的なご判断は、どなたがされる予定ですか?」 |
|
導入時期の確認 |
「導入のタイミングとして、いつ頃をお考えですか?」 |
このように、こちらが体系的にヒアリングすれば、相手も自然と必要情報を提供してくれます。
次の商談では、このヒアリング設計を成約のチャンスとして味方につけてみてください。
「提案フェーズ」で相手の立場に合わせた訴求軸を使い分ける
「提案したけど、相手に刺さらなかった…」と感じることはありませんか?
相手の立場に応じて訴求軸を変えることで、提案の"受け入れ度"を高めるきっかけになることが多くなります。。
たとえば、
「経営層にはROIや経営効果を訴求する」
「現場担当者には業務効率や使いやすさを訴求する」
のように、立場ごとに訴求内容を分岐させることで、それぞれに刺さる提案ができます。
より具体的には、相手の"関心事"や"判断基準"を見極めることが、提案成功の導線になります。
ポイントは、「同じ内容を話す」のではなく、「相手に合わせた訴求をする場」をつくることです。
無理に全てを説明しようとせず、相手が重視するポイントに絞ることが、最初の共感につながります。
まずは相手の立場を3パターンに分けて、訴求軸を整理してみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
経営層への訴求 |
「導入費用は初年度で回収でき、2年目以降は純粋な利益改善につながります」 |
|
現場担当者への訴求 |
「月間で約20時間の作業時間を削減でき、その分を新規営業に充てられます」 |
|
決裁者への訴求 |
「同業界での導入実績が50社以上あり、リスクを最小限に抑えられます」 |
|
IT部門への訴求 |
「既存システムとのAPI連携が可能で、導入の手間を最小化できます」 |
|
人事部門への訴求 |
「操作が直感的で、社員教育のコストを大幅に削減できます」 |
このように、相手の立場に合わせた訴求をすることで、提案の受け入れ率が高まります。
「反論対応」で"詰まらない返答"を即興で出せるようにする
反論に答えられず、その場で商談が止まってしまった経験、一度はあるかと思います。
実際、反論への対応が弱いと、「失注しやすくなる」傾向があります。
たとえば、
「価格が高い→費用対効果を数字で示す」
「今は必要ない→将来のリスクを提示する」
など、反論ごとに切り返しを用意しておくことで、商談を途切れさせずに進められます。
ポイントは、理解・共感・代案を生み出す"反論対応パターン"を事前に挟むことです。
まずは1つの反論パターンからでも、気楽に試してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
価格への反論 |
「初期費用だけで見ると高く感じますが、年間換算で月々〇万円、人件費削減効果で元が取れます」 |
|
タイミングへの反論 |
「導入準備に平均2ヶ月かかるため、必要になった時点では遅い可能性があります」 |
|
競合比較の反論 |
「他社様との違いは、専任担当が導入後も継続してサポートする点です」 |
|
効果への疑問 |
「同業界での導入実績が50社以上あり、平均で〇〇%の改善が見られています」 |
|
決裁への不安 |
「決裁者様向けの資料をご用意しますので、それを使ってご説明いただけます」 |
相手の心をひらくための、最初の一歩として活用してみてください。
「決裁者同席時」に"意思決定のツボ"を押さえる
決裁者同席時の対応とは、最終的な意思決定権を持つ人物の判断基準に合わせて提案を最適化するコミュニケーション設計です。
つまり、担当者向けの話をそのまま続けるのではなく、"決裁者の関心事に合わせる"ことで、契約確度が大きく上がるのです。
でも、「決裁者が同席しているのに、どう話せばいいか分からなかった…」という場面に直面したことはないでしょうか。
決裁者が重視するポイント(ROI・リスク・実績)を押さえた訴求をすることで、決断を引き出せます。
たとえば、
「投資対効果を数字で明確に示す」
「同業界での導入実績を具体的に伝える」
など、決裁者向けの訴求軸を準備しておくことで、その場で決断してもらえる可能性が高まります。
ポイントは、「決裁者の関心事」か「判断基準」について、無理なく自然に訴求することです。
|
項目 |
例文 |
|
ROIでの訴求 |
「導入費用は初年度で回収でき、2年目以降は純粋な利益改善につながります」 |
|
リスク軽減の訴求 |
「同業界での導入実績が50社以上あり、失敗リスクを最小限に抑えられます」 |
|
競合優位性の訴求 |
「業界シェアNo.1で、サポート体制が他社より充実しています」 |
|
導入スピードの訴求 |
「最短2週間で導入可能な体制が整っており、すぐに効果を実感いただけます」 |
|
経営課題への訴求 |
「御社の中期経営計画にある〇〇の目標達成を、このツールが支援できます」 |
このように、こちらが決裁者の視点で話せば、相手も自然と決断に向かってくれます。
次の商談では、決裁者対応こそ、成約のチャンスとして味方につけてみてください。
「オンライン商談」で画面越しでも熱量を伝える構成をつくる
「オンラインだと熱量が伝わらず、成約率が下がった…」と感じることはありませんか?
実は、オンライン商談用のトーク設計をすることで、画面越しでも"熱量と信頼"を伝えるきっかけになることが多いんです。
たとえば、
「声のトーンを対面より1段階明るくする」
「資料共有のタイミングを事前に設計する」
のように、オンライン特有の工夫を盛り込むことで、対面と同等の成約率を実現できます。
より具体的には、「間の取り方」や「視線の向け方」を意識することが、オンライン商談成功の導線になります。
ポイントは、「対面と同じように話す」のではなく、「オンライン用に最適化する場」をつくることです。
無理に詰め込もうとせず、画面越しでも伝わる構成を作ることが、最初の信頼構築につながります。
まずはオンライン商談の3つのポイントを押さえることから始めてみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
声のトーン調整 |
「対面より1段階明るく、ゆっくり話すことで、熱量が伝わりやすくなります」 |
|
資料共有タイミング |
「この資料を画面共有しますので、一緒にご覧いただけますか?」 |
|
視線の向け方 |
「カメラ目線を意識して、相手と目が合っている感覚を作ります」 |
|
間の取り方 |
「オンラインは間が長く感じるため、対面より短めに区切って話します」 |
|
反応の確認 |
「ここまでで、何かご質問はございますか?」と細かく確認を入れます |
このように、オンライン特有の工夫を取り入れることで、画面越しでも成約率を維持できます。
「新人教育」で即戦力化を早めるトレーニング設計に使う
新人がなかなか成果を出せず、教育に時間がかかりすぎている経験、一度はあるかと思います。
実際、教育体制が整っていないと、内容の良し悪しに関係なく「新人の立ち上がりが遅くなる」傾向があります。
たとえば、
「フローチャート型トークをロープレで練習する」
「想定質問と回答パターンを事前に覚えてもらう」
など、型化されたトークを教材にすることが、即戦力化への鍵です。
ポイントは、再現性・標準化・体系化を生み出す"教育設計"を最初に挟むことです。
それがあるだけで、「誰でも成果を出せる組織」に変わります。
まずは1つのトークパターンからでも、気楽に試してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
ロープレでの活用 |
「このフローチャートに沿って、実際にロープレをやってみましょう」 |
|
想定質問の暗記 |
「よくある質問10個と回答パターンを、まず覚えてください」 |
|
分岐対応の練習 |
「相手がYesと言った場合、Noと言った場合、それぞれ練習してみましょう」 |
|
失敗パターンの共有 |
「この分岐でよく詰まるので、事前に対応を確認しておきましょう」 |
|
成功事例の横展開 |
「この先輩のトークが成功パターンなので、真似してみてください」 |
新人教育のフローチャート活用が、即戦力化を生み出します。
相手の心をひらくための、最初の一歩として活用してみてください。
「トークレビュー」で会話データを体系的に改善する
トークレビューとは、実際の商談や架電の内容を振り返り、どの段階で改善が必要かを特定して、次回の精度を高めるプロセスです。
つまり、感覚で振り返るのではなく、"データに基づいて改善する"ことで、営業力が継続的に向上するのです。
でも、「商談後の振り返りが曖昧で、何を改善すべきか分からない…」という場面に直面したことはないでしょうか。
実は、フローチャートに沿ってトークをレビューすることで、どの分岐で問題があったかを明確に特定できます。
たとえば、
「導入トークで警戒された→第一声を改善する」
「クロージングで迷われた→意思確認トークを強化する」
など、分岐ごとに改善点を洗い出すことで、次回の成約率が上がります。
ポイントは、「分岐点」か「改善ポイント」について、無理なく自然に特定することです。
|
項目 |
例文 |
|
導入トークのレビュー |
「第一声で警戒されたので、もっと丁寧な前置きを入れよう」 |
|
ヒアリングのレビュー |
「必要な情報を聞き漏らしたので、チェックリストを作ろう」 |
|
提案のレビュー |
「相手の立場に合わせた訴求ができていなかったので、次は使い分けよう」 |
|
反論対応のレビュー |
「価格への反論に詰まったので、費用対効果の説明を準備しよう」 |
|
クロージングのレビュー |
「意思確認が曖昧だったので、次は明確に聞こう」 |
このように、こちらがデータで振り返れば、改善点も自然と見えてきます。
次の商談では、トークレビューこそ、成約のチャンスとして味方につけてみてください。
「チーム共有」で勝ちパターンを組織知に変える
「トップセールスのノウハウが属人化して、チーム全体に広がらない…」と感じることはありませんか?
フローチャート型トークをチームで共有することで、個人の"成功パターン"を組織全体の資産に変えるきっかけになることが多いんです。
たとえば、
「成功したトークをフローチャートに落とし込んで共有する」
「失敗パターンも共有して、同じミスを防ぐ」
のように、成功と失敗の両方を型化することで、チーム全体のレベルが底上げされます。
より具体的には、「成功トークのパターン化」や「失敗要因の可視化」が、組織力向上の導線になります。
ポイントは、「個人で抱え込む」のではなく、「チームで共有する場」をつくることです。
無理に複雑化せず、シンプルに共有できる仕組みを作ることが、最初の組織知につながります。
まずは1つの成功パターンをチームで共有することから始めてみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
成功パターンの共有 |
「この分岐でこのトークを使ったら成約したので、みんなも試してみてください」 |
|
失敗パターンの共有 |
「この分岐でこう対応したら失注したので、注意してください」 |
|
Notionでの管理 |
「成功トークをNotionのデータベースに登録して、いつでも見られるようにしましょう」 |
|
Slackでの即時共有 |
「今日の商談で使ったトークが効果的だったので、Slackで共有します」 |
|
定例会での振り返り |
「週次ミーティングで、今週の成功・失敗パターンを共有しましょう」 |
このように、成功パターンを積極的に共有することで、個人のノウハウが組織全体の財産に変わり、チーム全体の営業力が底上げされます。
「失注分析」でどの分岐で離脱したかを見える化する
失注した理由が分からず、同じ失敗を繰り返してしまった経験、一度はあるかと思います。
実際、失注要因が不明確だと、内容の良し悪しに関係なく「同じミスを繰り返しやすくなる」傾向があります。
たとえば、
「どの分岐で相手が離脱したかをデータで記録する」
「失注が多い分岐を優先的に改善する」
など、失注ポイントを可視化することで、改善サイクルが高速化されます。
ポイントは、データ化・可視化・優先順位付けを生み出す"失注分析"を定期的に挟むことです。
それがあるだけで、「PDCAが回る組織」に変わります。
まずは1つの失注パターンからでも、気楽に試してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
失注ポイントの記録 |
「この商談は提案フェーズで失注したので、提案内容を見直そう」 |
|
失注要因の分類 |
「価格・タイミング・競合比較のどれが原因かを分類しよう」 |
|
改善優先順位の決定 |
「提案フェーズでの失注が一番多いので、ここを優先的に改善しよう」 |
|
CRMでのデータ管理 |
「どの分岐で離脱したかをCRMに記録して、データを蓄積しよう」 |
|
定期的な分析会議 |
「月次で失注分析会議を開いて、改善策を全員で考えよう」 |
失注分析が、継続的な営業力向上を実現します。
相手の心をひらくための、最初の一歩として活用してみてください。
フローチャート型営業トークスクリプトの作成で気を付けたい3つのこと
「分岐を増やしすぎない」ことで現場が混乱しないようにする
「フローチャートを作ったけど、複雑すぎて誰も使わなくなった…」という経験はありませんか?
分岐パターンを増やしすぎると、現場で判断に迷う時間が増え、かえって営業効率が落ちてしまいます。
理想的なのは、お客様の反応を3〜5パターン程度に絞り、それぞれに明確な対応を設定することです。
たとえば「興味あり・今は不要・検討中・予算不足・決裁者不在」など、実際に頻出する反応に絞ると現場が迷わず使えるフローチャートになります。
一方で、分岐が多いほど対応力が高まると考えがちですが、過度な細分化は逆効果です。
以下に、分岐過多による懸念点と対策を整理しました。
|
懸念点 |
対策の例 |
|
選択肢が多すぎて判断に迷う |
分岐は3〜5パターンに絞り、頻出する反応に限定する |
|
フローチャートが複雑で覚えられない |
シンプルな構造を維持し、視覚的に分かりやすく設計する |
|
現場で使われなくなる |
実際の商談データから頻出パターンを抽出して絞り込む |
このように、シンプルな設計を心がけることで、現場で実際に使われるフローチャートが完成します。
特に、新人でも迷わず使える実用性を重視することが成功の鍵になります。
「実際の現場トーク」と乖離しない言葉づかいにする
「スクリプト通りに話すと、不自然で相手に違和感を与えてしまう…」と感じたことはありませんか?
トークスクリプトが現場の実際の会話と乖離していると、営業担当者が使いにくくなり、結果的に形骸化してしまいます。
理想的なのは、実際の商談で使われている自然な言葉をベースに、スクリプトを作成することです。
たとえば、商談録音を文字起こしして、業績が出ている営業担当者の言い回しを反映させると、現場感のあるトークが完成します。
一方で、型にはめすぎると、営業担当者の個性や柔軟性が失われる危険性もあります。
以下に、現場トークとの乖離による懸念点と対策を整理しました。
|
懸念点 |
対策の例 |
|
硬すぎる表現で不自然になる |
実際の商談録音を文字起こしして、自然な言い回しを反映する |
|
営業担当者が使いたがらない |
トップセールスの実際のトークをヒアリングして言葉を採用する |
|
型通りすぎて個性が消える |
基本の流れは固定し、細かい表現は個人の裁量に任せる |
このように、現場の実態に即した言葉選びをすることで、営業担当者が自然に使えるスクリプトが完成します。
特に、実際に成果を出している言い回しを活用することが、実用性を高める鍵になります。
「仮説検証サイクル」を回して常に最新の会話精度を保つ
フローチャートを一度作成して終わりにしていませんか?
実は、市場環境やお客様のニーズは常に変化するため、定期的に見直しをしないとトークスクリプトの効果が薄れます。
理想的なのは、月次または四半期ごとにトークの成約率や失注要因を分析し、継続的に改善することです。
たとえば
「この分岐での失注が増えている」
「この切り返しトークが効果的だった」
といったデータをもとに、フローチャートをアップデートすることで、常に最適な状態を保てます。
一方で、改善サイクルがないと、時代遅れのトークを使い続けることになり、成約率が低下します。
|
懸念点 |
対策の例 |
|
トークが時代遅れになる |
月次または四半期ごとに成約率・失注率をレビューする |
|
改善点が見えない |
商談データを分析し、どの分岐で失注が多いかを可視化する |
|
PDCAが回らない |
定例会議でトークレビューの時間を設け、改善施策を決定する |
このように、継続的な改善サイクルを回すことで、フローチャートの精度が高まり続けます。
特に、データに基づいた改善を習慣化することが、営業組織全体の成長につながります。
フローチャート型営業トークスクリプト作成に役立つツール7選
「Miro」でトーク全体の流れをビジュアル化する
フローチャートを作りたいけど、どのツールを使えばいいか迷っていませんか?
そのために有効なのが、無限キャンバスで自由に図を描ける「Miro」です。
ポイントは、営業トークの分岐を視覚的に整理し、チーム全員が一目で理解できる構造を作ること。
特にリモートワークが増えた現在では、オンラインでリアルタイム共同編集できる点が大きな強みになります。
|
項目 |
具体例 |
|
無限キャンバス |
「複雑な分岐も広いスペースで自由にレイアウトできる」 |
|
リアルタイム共同編集 |
「チームメンバーが同時に編集でき、意見をその場で反映できる」 |
|
テンプレート活用 |
「フローチャート専用テンプレートで、すぐに作成を始められる」 |
このように、ビジュアル化のツールを使うことで、複雑なトークの流れも整理しやすくなります。
特に、チーム全体での共有や議論がスムーズになる点が、現場での活用を促進します。
「Lucidchart」で分岐構造をチームで共同編集できる
フローチャート作成は、専門ツールを使うことで精度が変わります。
複雑な分岐構造を整理したいときに役立つのが、「Lucidchart」です。
大切なのが、フローチャート専用の機能を使って、見やすく整理された図を作ること。
ポイントは、Google WorkspaceやMicrosoft 365との連携により、普段使っているツールとシームレスに統合できることです。
営業現場では、「分岐の追加や修正」「バージョン管理」を効率的に行えるだけで、運用の負担が一気に軽減されます。
|
項目 |
具体例 |
|
専用図形ライブラリ |
「フローチャート用の図形が豊富で、統一感のある図が作れる」 |
|
Google Workspace連携 |
「Googleドキュメントやスライドに直接埋め込める」 |
|
バージョン管理 |
「過去の変更履歴を確認でき、いつでも以前の状態に戻せる」 |
このように、事前に専門ツールで構造を整理しておくと、運用段階での混乱が防げます。
「Notion」でトークパターンをナレッジ化して共有する
営業現場では、成功したトークをどう蓄積するかが課題になります。
トークパターンを組織の資産として残すために有効なのが、「Notion」でナレッジベースを構築することです。
ポイントは、データベース機能を使って「シーン別」「顧客タイプ別」にトークを分類し、いつでも検索できる状態にすること。
たとえば「新規開拓」「クロージング」「反論対応」などのカテゴリーで整理すれば、必要な時にすぐ参照できます。
営業組織では特に、成功事例と失敗事例の両方を蓄積することで、組織全体の学習サイクルが加速します。
|
項目 |
具体例 |
|
データベース機能 |
「トークをタグ付けして、シーン別・顧客別に分類できる」 |
|
検索性の高さ |
「キーワードで瞬時に必要なトークパターンを探せる」 |
|
更新の容易さ |
「新しい成功事例をその場で追記でき、常に最新の状態を保てる」 |
このように、ナレッジを入口として整理すると、個人の知見が組織の財産へと変わります。
蓄積されたトークパターンが、チーム全体の営業力を底上げしていきます。
「Googleスプレッドシート」で分岐と回答を一覧管理する
フローチャート作成に、高度なツールは必ずしも必要ありません。
この課題を解決する手段として効果的なのが、「Googleスプレッドシート」で管理することです。
ポイントは、自社の営業スタイルに合わせて、相手の反応パターンごとに回答例を一覧化すること。
たとえば「顧客の反応」「対応トーク」「次のアクション」を列で整理するだけで、実用的な管理表が完成します。
使い慣れたツールで運用できることが、継続的な活用につながります。
|
項目 |
具体例 |
|
無料で使える |
「コストをかけずに、すぐに運用を開始できる」 |
|
共同編集機能 |
「チーム全員が同時に編集でき、リアルタイムで更新される」 |
|
関数で自動化 |
「フィルタや条件付き書式で、必要な情報をすぐに抽出できる」 |
このように、大きな仕組みを用意する前に、手軽なツールで始めることが、現場での定着を促進します。
「Rev」や「Notta」で商談録音を文字起こしして改善点を抽出する
実際の商談トークを振り返りたいけど、録音を聞き直す時間がない…と感じていませんか?
そこで役立つのが、商談録音を自動で文字起こしできる「Rev」や「Notta」です。
ポイントは、自社で成果を出している営業担当者のトークを文字化し、成功パターンを抽出すること。
たとえば「この質問で顧客が前のめりになった」
「この切り返しで契約につながった」
といった具体的な言い回しが見えてきます。
営業マネージャーにとっては、感覚ではなくデータに基づいた指導ができる点が、大きなメリットになります。
|
項目 |
具体例 |
|
自動文字起こし |
「音声を自動でテキスト化し、聞き直す手間を削減できる」 |
|
キーワード検索 |
「特定のフレーズや失注ポイントをすぐに検索できる」 |
|
成功パターン抽出 |
「成約につながったトークを分析し、横展開できる」 |
このように、商談内容をデータ化することで、感覚ではなく事実に基づいた改善が可能になります。
文字起こしツールが、トークスクリプトの精度向上を後押しします。
▼編集部のおすすめ動画を見る
(AI議事録作成)Zoom文字起こし|Notta BotでWeb会議文字起こし
「Slack」でトーク成功事例をリアルタイム共有する
営業現場では、成功事例をいかに素早く共有するかが勝負です。
その実現に向けて効果的なのが、「Slack」で専用チャンネルを作り、リアルタイム共有する仕組みです。
ポイントは、成功したトークを即座に投稿し、チーム全員がその日のうちに学べる環境を作ること。
営業組織の中では、受付担当との会話や決裁者とのやり取りなど、成功の瞬間を逃さず共有することが、チーム全体の成長を加速させます。
特にリモート営業が増えた今、オンラインでの即時共有が組織の一体感を生み出します。
|
項目 |
具体例 |
|
専用チャンネル作成 |
「#営業成功事例チャンネルで、良いトークをすぐ投稿できる」 |
|
リアクション機能 |
「いいね!やコメントで、どのトークが有効か可視化される」 |
|
検索性の高さ |
「過去の成功事例を後から検索して、自分の商談に活かせる」 |
このように、営業活動ではなく日々の共有から始めることで、チームの学習サイクルが自然と回り出します。
リアルタイム共有が、組織知の蓄積へと繋がっていきます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
全社で「Slack」を活用するユーザーが実践しているチャンネルを紹介!【活用術】
「ChatGPT(生成AI)」で反論パターンの自動生成と改善案を出す
反論パターンを網羅的に準備したいけど、時間が足りない…と感じていませんか?
この課題に対する答えとして活用できるのが、「ChatGPT」などの生成AIで効率的にパターンを作成することです。
ポイントは、顧客の反応に応じた切り返しトークを、業界や商材に合わせて自動生成させること。特に新しい市場や商材では、AIがたたき台を作ってくれる点が大きな助けになります。
ただし、生成されたトークは必ず現場で検証し、実際に使える形に調整することが欠かせません。
|
項目 |
具体例 |
|
反論パターン生成 |
「"製造業での価格反論パターンを10個"とプロンプトを入力する」 |
|
切り返しトーク作成 |
「"今は必要ない"という反論への対応を複数パターン生成する」 |
|
改善案の提示 |
「既存トークを入力し、改善案を複数提案してもらう」 |
このように、最終的な判断は人が行うとしても、AIでたたき台を作ることで準備時間が大幅に短縮されます。
生成AIが、営業準備の効率化を支援してくれます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【ムダな作業にサヨナラ】ChatGPTで営業先の情報整理が”秒”で終わる!
型化で成果を最大化するフローチャート型営業トークスクリプトのアイディア5選
「感情分岐トーク」で相手の反応に合わせて会話を変える
「相手の表情が曇っているのに、そのまま話を進めてしまった…」という場面に遭遇したことはないでしょうか。
実は、お客様の感情パターンに応じてトークを分岐させることで、共感と信頼を生み出すきっかけになることが多いんです。
たとえば、
「前向きな反応には→具体的な提案をすぐに展開する」
「不安そうな様子には→事例やサポート体制で安心感を提供する」
のように、相手の感情を3パターン(ポジティブ・ネガティブ・中立)に分けて対応を変えることで、話が自然に進みます。
より具体的には、相手の"表情"や"声のトーン"を観察することが、感情に寄り添った対応の導線になります。
ポイントは、「感情を読む」のではなく、「感情に応じた対応が自然と出る場」をつくることです。
無理に一方的な提案を続けず、相手の状態に合わせることが、最初の信頼構築につながります。
|
項目 |
例文 |
|
ポジティブ反応時 |
「ご関心をお持ちいただけて嬉しいです。それでは具体的なプランをご提案しますね」 |
|
ネガティブ反応時 |
「ご不安なお気持ち、よく分かります。同じ状況だった企業様の事例をご紹介しますね」 |
|
中立反応時 |
「まだ判断材料が足りない状況かと思います。まずは御社の現状を教えていただけますか?」 |
|
疲れている様子の時 |
「お忙しいところ恐れ入ります。要点だけ簡潔にお伝えしますね」 |
|
興奮している様子の時 |
「そうなんです!その点、まさに今お困りのポイントですよね」 |
このように、感情分岐を意識することで、相手に寄り添った対応が自然とできるようになります。
感情に応じたトークが、信頼関係構築と成約率向上につながります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業トーク・切り返しトーク】切り返しの営業トーク(テレアポ、商談で成功する話し方)|リクルートで全国1位トップ営業になれた小技
「ロジック分岐」で"Yes"を積み上げるクロージング設計にする
契約を急ぎすぎて、相手の表情が曇ってしまった経験、一度はあるかと思います。
実際、いきなり大きな決断を迫ると「警戒されやすくなる」傾向があります。
たとえば、
「課題に共感いただけますか?→その課題、解決したいですか?→この方法で解決できそうですか?」
「導入メリットは理解いただけましたか?→御社でも活用できそうですか?→では詳しい話を進めませんか?」
など、小さなYesを段階的に積み重ねることで、最終決断のハードルが下がります。
ポイントは、合意・納得・決断を生み出す"段階的な質問"を最初に挟むことです。
それがあるだけで、「自然な流れで契約に進んだ」という印象に変わります。
まずは1つの小さな合意からでも、気楽に試してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
課題の合意 |
「この課題、確かに解決したいですよね?」 |
|
解決策の納得 |
「この方法なら、御社の状況にも合いそうですか?」 |
|
導入イメージの確認 |
「実際に導入した場面、イメージできますか?」 |
|
タイミングの確認 |
「では、いつ頃から始めるのが良さそうですか?」 |
|
最終確認 |
「それでは、具体的な契約内容をご説明させていただいてもよろしいですか?」 |
小さな合意の積み重ねは立派な"成約準備"。
相手の心をひらくための、段階的アプローチとして活用してみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業クロージング術】営業に必要なのは“押し”じゃなく“後押し”だった
「シナリオ別フローチャート」で業界・役職ごとの対応を変える
シナリオ別フローチャートとは、相手の業界や役職に応じて最適なトークパターンを使い分ける営業設計のことです。
つまり、一律のトークで進めるのではなく、"相手に合わせた会話"を用意することで、提案の受け入れ度が大きく上がるのです。
でも、「毎回トークを変えるのは負担が大きい…」と感じたことはないでしょうか。
業界や役職ごとに2〜3パターンのシナリオを準備しておくだけで、大半の商談に対応できます。
たとえば、
「製造業の経営層には→コスト削減とROIを訴求する」
「IT業界の現場担当には→導入のしやすさと操作性を訴求する」
など、相手の属性ごとに訴求軸を変えることで、刺さる提案ができます。
ポイントは、「相手の立場」か「業界特性」について、無理なく自然に切り替えることです。
|
項目 |
例文 |
|
製造業・経営層向け |
「年間コストを15%削減でき、投資回収は1年以内です」 |
|
IT業界・担当者向け |
「既存システムとAPI連携でき、導入は最短2週間です」 |
|
人材業界・マネージャー向け |
「採用業務の工数を月20時間削減でき、コア業務に集中できます」 |
|
小売業・店長向け |
「在庫管理が自動化され、発注ミスを80%削減できます」 |
|
金融業・決裁者向け |
「セキュリティ対策は金融庁のガイドラインに完全準拠しています」 |
このように、相手に合わせた会話を準備しておけば、提案の説得力も自然と高まります。
次の商談では、シナリオ分岐こそ、信頼構築のチャンスとして味方につけてみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
売れる営業トークの作り方を公開!120万円の価格で成約率80%超えの秘密とは?
「共感パート」を明確化して、相手の本音を引き出せるようにする
「質問しても、表面的な回答しか返ってこない…」という壁にぶつかったことはないでしょうか。
実は、共感を示すトークを意図的に設計することで、お客様の本音を引き出すきっかけになることが多いんです。
たとえば、
「その状況、本当に大変ですよね」
「同じ悩みを抱えている企業様、実は多いんです」
のように、相手の状況に寄り添う言葉を会話の中に織り込むことで、心理的な壁が下がります。
より具体的には、相手の"困りごと"や"不満"に対して共感を示すことが、深い会話への導線になります。
ポイントは、「質問だけで進める」のではなく、「共感を挟みながら聞く場」をつくることです。
無理に聞き出そうとせず、共感を通じて話しやすい空気をつくることが、最初の信頼構築につながります。
まずは相手の言葉を受け止めて、共感する一言を添えてみましょう。
|
項目 |
例文 |
|
課題への共感 |
「その課題、現場は相当大変ですよね。よく分かります」 |
|
状況の理解 |
「限られた人数で対応するのは、本当に負担が大きいですよね」 |
|
同じ悩みの共有 |
「実は同じ業界の企業様も、全く同じ課題で悩まれているんです」 |
|
努力の承認 |
「色々試されてきたんですね。その努力、本当に素晴らしいと思います」 |
|
焦りへの寄り添い |
「早く改善したいけど、何から手をつければいいか分からない状況ですよね」 |
このように、共感の言葉を意識的に入れることで、相手が本音で話しやすくなります。
深い共感が、信頼関係と成約を生み出します。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【セールス裏技】お客様に嫌われずにヒアリング!具体的な営業手法を徹底解説!
「データ連携フロー」でCRMと紐づけ、改善を自動化する
トークスクリプトを作成しても、どこを改善すべきか分からず悩んでいませんか?
実際、データで可視化しないと、内容の良し悪しに関係なく「感覚的な改善に終わる」傾向があります。
たとえば、
「提案フェーズでの失注が多い→提案内容を改善する」
「クロージング段階での成約率が高い→この分岐のトークを横展開する」
など、CRMと連携してデータを蓄積することで、継続的な改善サイクルが回り始めます。
ポイントは、記録・分析・改善を生み出す"データ連携の仕組み"を最初に挟むことです。
それがあるだけで、「PDCAが自然と回る組織」に変わります。
まずは1つの分岐データからでも、気楽に記録してみてください。
|
項目 |
例文 |
|
分岐データの記録 |
「各商談でどの分岐を通ったかをCRMに記録する」 |
|
成約率の可視化 |
「分岐ごとの成約率をダッシュボードで確認できる」 |
|
失注要因の分析 |
「どの分岐で離脱が多いかを自動で集計する」 |
|
改善施策の優先順位付け |
「成約率が低い分岐を優先的に改善する」 |
|
トークの自動最適化 |
「成約率の高いトークパターンをAIが提案する」 |
このように、データ連携を活用すれば、感覚ではなく事実に基づいた改善が進みます。
CRMとの連携が、継続的な営業力向上を実現します。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【完全解説】ワークフロー自動化のススメ!成果を出すための3ステップ|HubSpot Japan
フローチャート型営業トークスクリプト作成で、お困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「トークスクリプトを作りたいけど、何から始めればいいか分からない」――そんな悩みを抱えていませんか?
結局どう設計すれば現場で使えるのか分からない、フローチャートを作っても形骸化してしまう、そんな不安、よくわかります。
営業トークの型化やスクリプト作成を支援する会社は数多くありますが、本当に現場で使える仕組みを作れる会社はごくわずかです。
だからこそ、ただテンプレートを渡すのではなく、"現場目線で実際に成果が出る設計"をサポートできるパートナーを見つけることが大切です。
弊社スタジアムでは、営業トークスクリプトの設計から現場への定着支援まで、一気通貫でサポートしています。
IT・Web領域に精通した専任担当が、御社の営業スタイルに合わせたフローチャート型トークスクリプトを設計するため、スピードと成果にこだわる方には特にフィットします。
営業の成約率を上げたい、トークスクリプトを体系化したい営業担当者・マネージャーの方へ。
トークスクリプトの作り方や営業トークの改善に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
"現場を熟知した営業のプロ"に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き
【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説
営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順
【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版
インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集
営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文
【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全
【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集
【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!
アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説
【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略
【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説
法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略
【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説
深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順
営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善
13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド
営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション
営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順
【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版
【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集
営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド
営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別
【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果
【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順
【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順
【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点
営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順
【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド
【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き
営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順
できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法
売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法
プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順
【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き
営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策
【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説
【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説
なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術
新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順
営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説
なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法
ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP
ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集
飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法
【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド
【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版
セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法
セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド
新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版
新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全
【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説
新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ
新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法
【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版
【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集
アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法
インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順
【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版
【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法
SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法
MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説
BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法
BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略
BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順
【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版
【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ
【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説
営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選
FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド
【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方
14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順
アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ
シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ
これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順
【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集
【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP
【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説
営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ
御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP
【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順
【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集
営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法
営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順
27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場
【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順
営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準
新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル
営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント
クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順
営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説
営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順
営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順
最終更新日