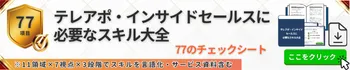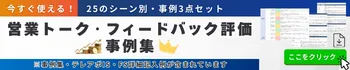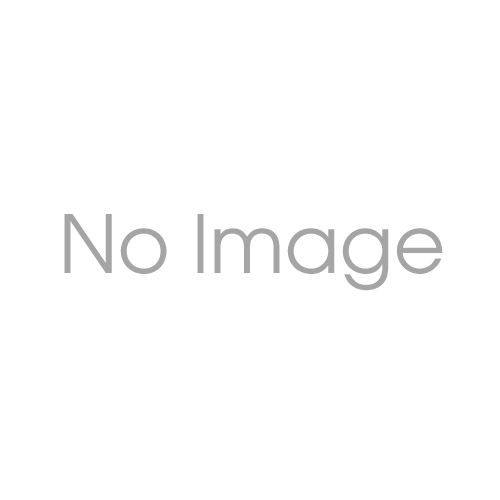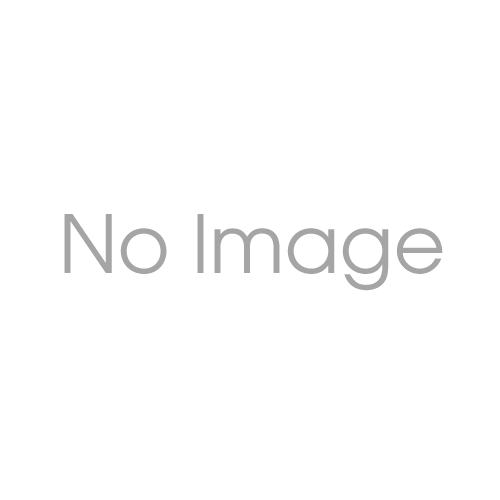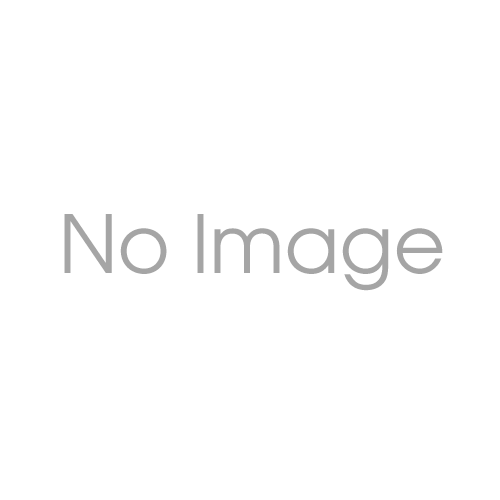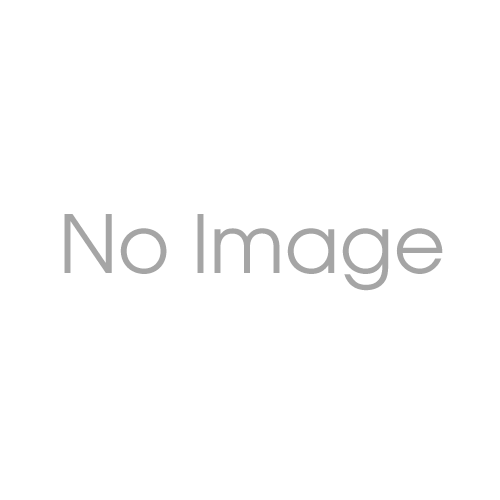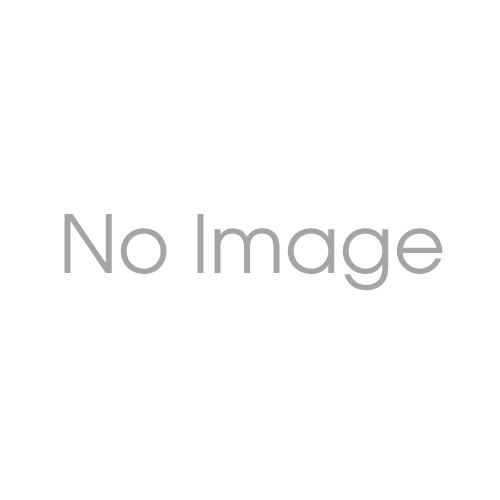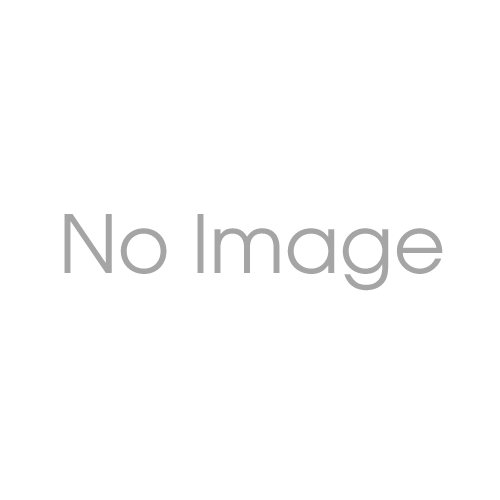【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
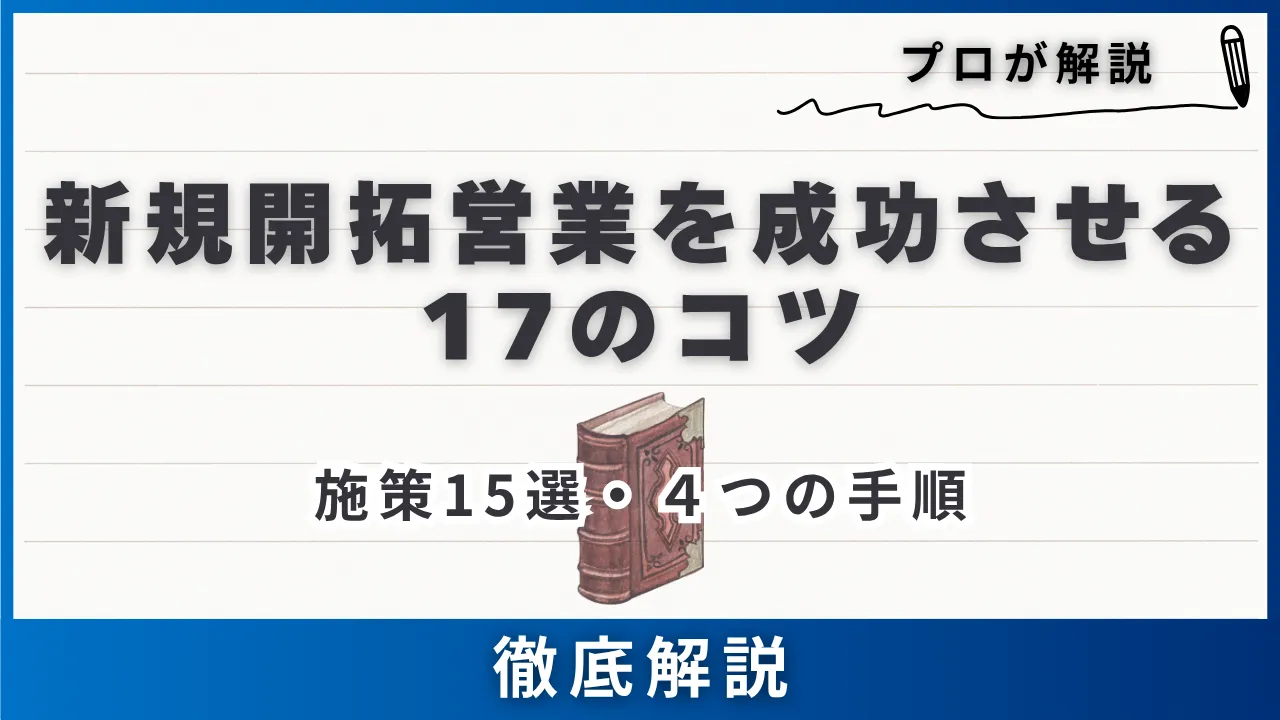
「新規開拓営業、頑張っているのに成果が出ない…」そんな悩みを抱えていませんか?
日々の数字に追われ、手法を試しても成果が伸び悩むと、焦りや不安ばかりが募ります。
しかし正しい考え方と実践手順を押さえれば、商談獲得や受注率は大きく変わります。
・新規開拓営業を成功させる17のコツ(ターゲット企業リスト・断られにくい切り口・決裁フロー)
・新規開拓営業の3つの目的(新規リード獲得・商談接点確保・ブランド認知)
・新規開拓営業の施策15選(飛び込み営業・テレアポ・メール営業)</stro 現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
新規開拓営業を成功させる17のコツ
初回接触で「断られにくい切り口」を準備する
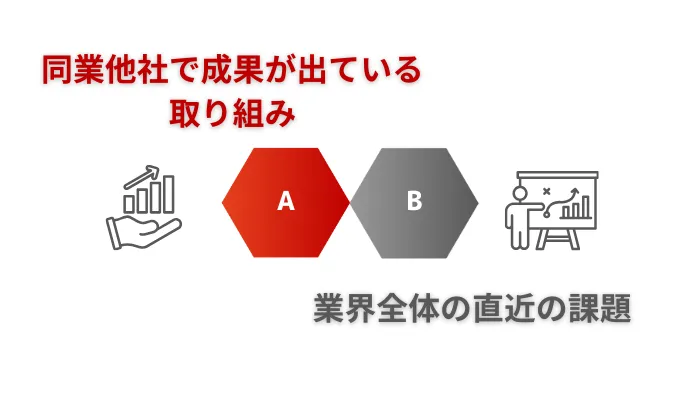
新規開拓で最初に壁になるのが「最初の断り」です。
ここで相手に警戒されると、その後の扉は二度と開きません。
ポイントは、相手が自社の課題解決につながる“自分ごと”として受け取りやすい話題を入口に使うこと。
例えば「同業他社で成果が出ている取り組み」や「業界全体の直近の課題」に触れると、相手は耳を傾けやすくなります。
法人営業では特に、決裁者の関心を外さない一言が、次の打ち合わせにつながる分かれ道になります。
|
項目 |
具体例 |
|
同業他社事例 |
「御社と同じ業界で、最近よく相談を受けているテーマがありまして」 と伝える |
|
業界動向 |
「直近の制度改正で人事労務のご負担が増えていると伺っています」 と切り出す |
|
部門課題 |
「営業チームのオンライン商談比率は、どのくらい変化されていますか?」 と質問する |
このように、相手の立場や状況に合わせた切り口を事前に準備しておくと、会話が自然に広がりやすくなります。
最初の一言に工夫があるだけで、商談の空気は大きく変わります。
「ターゲット企業リスト」を精度高く作成する

新規開拓営業の成否は、最初の「リスト作り」でほぼ決まります。
見込みの薄い企業を追いかけても時間と労力が浪費されるだけです。
ポイントは、単なる業界分類や売上規模ではなく「購買理由につながる条件」を切り口にリストを組み立てること。
たとえば、既存顧客で成果が出た導入背景を分析し、その特徴に近い企業を抽出するだけで、商談化率は大きく変わります。
法人営業では特に、決裁フローや部門構造まで含めて整理しておくと、現場での動きが格段にスムーズになります。
|
項目 |
具体例 |
|
業界特性 |
「採用コスト増加に直面しているIT系企業」を抽出する |
|
部門規模 |
「経理部が30名以上の組織」を条件にする |
|
成功条件 |
「既存顧客の導入理由と同じ課題を抱える企業」を優先する |
このように、条件を表に落とし込むと抜けや迷いが減り、チーム全体で方向性をそろえやすくなります。
狙う相手が明確になれば、商談の質もスピードも一気に高まります。
「課題仮説」を立ててヒアリング精度を上げる
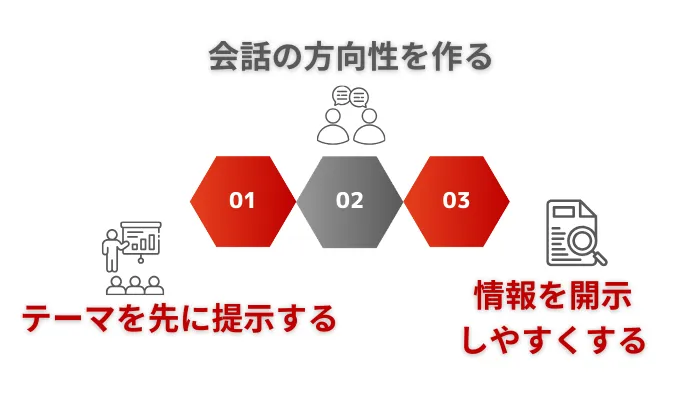
新規開拓の商談では、相手に「何から話していいのか分からない」という空気が生まれやすいです。
そこで役立つのが、事前に「課題仮説」を持って臨むことです。
ポイントは、相手が口にしやすいテーマを先に提示して、会話の方向性を作ってあげること。
仮説があるだけで、相手は“こちらを理解してくれている”と感じ、情報を開示しやすくなります。
|
項目 |
具体例 |
|
導入 |
「同じ業界のお客様から『人材育成の仕組み化』で悩む声をよく聞きます」と伝える。 |
|
ヒアリング |
「御社では営業現場の『データ活用』にどのくらい時間を割いていますか?」と聞く。 |
|
深掘り |
「その作業が減れば、営業の動き方はどのように変わりそうですか?」と尋ねる。 |
このように、仮説を軸にした質問は相手の考えを引き出しやすく、対話が実際の企業の課題感と合致する形で進みます。
ただ聞くのではなく、一緒に課題を整理する姿勢が信頼に変わります。
「決裁者フロー」を早めに把握する
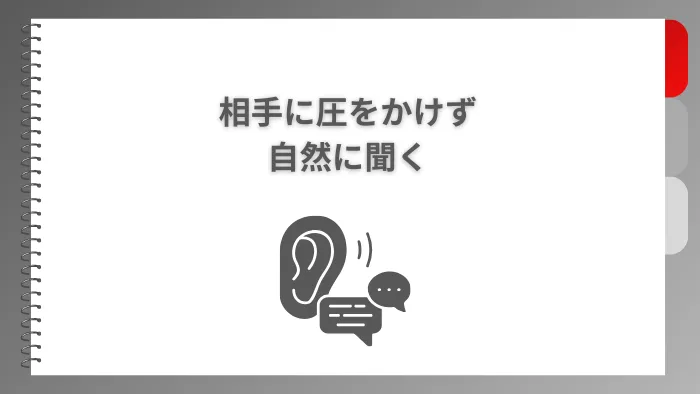
商談が順調に進んでいても、決裁ルートを知らないと契約は長引いてしまいます。
法人営業では、多くのケースで複数の承認者が関わるため、最初の段階で流れを掴んでおくことが欠かせません。
ポイントは、相手に圧をかけず自然に聞くこと。
「ご検討の際には、どなたとご一緒に話をされることが多いですか?」といった質問で、相手に安心感を与えながら情報を得られます。
|
項目 |
具体例 |
|
初期確認 |
「この資料はまず誰に共有されますか?」と聞く。 |
|
承認ルート |
「最終判断の段階で経営層の方もご確認されますか?」と確認する。 |
|
期間把握 |
「社内承認にはおおよそどれくらいかかりますか?」と尋ねる。 |
このように、全体像を早めに掴めば、次の動きを先回りできます。
相手の社内調整を支える姿勢が、信頼とスピードを両立させます。
「キーマン」との関係性を意識して動く
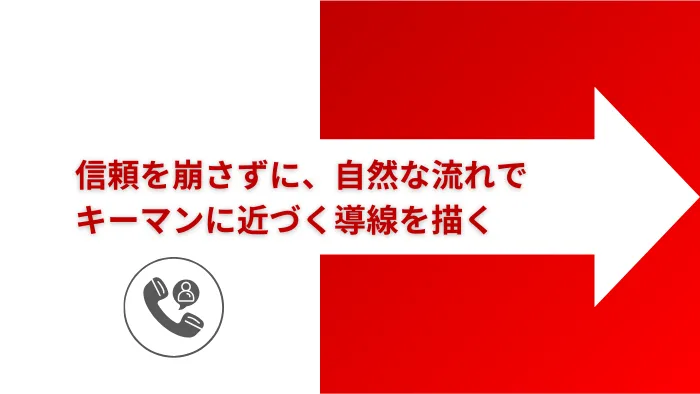
法人営業で成果を大きく分けるのは、最終決裁権を持つ「キーマン」とどう接点を作るかです。
ポイントは、窓口担当との信頼を崩さずに、自然な流れでキーマンに近づく導線を描くこと。
特に、現場担当の課題を把握しつつ、その課題をキーマンの経営目線に置き換えて提示すると、会話の重みが変わります。
自分の理想の形の押し売りでは、キーマンの経営目線との乖離が生まれて商談の中身が希薄になってしまいます。
導入からクロージングまでの一貫した動きの中で、キーマンに“会う必然性”を作ることが実践的な突破口になります。
|
項目 |
具体例 |
|
導入 |
「現場で感じている課題を、経営判断につなげられる形で共有したい」と伝える。 |
|
調整 |
「次回は部長や役員の方も同席いただけませんか?」と依頼する。 |
|
提案 |
「コスト削減だけでなく、全社的な利益構造改善につながります」と示す。 |
このように、現場と経営を橋渡しする視点を持つと、キーマンに会う理由が自然に生まれます。
商談では「差別化ポイント」を具体的に伝える
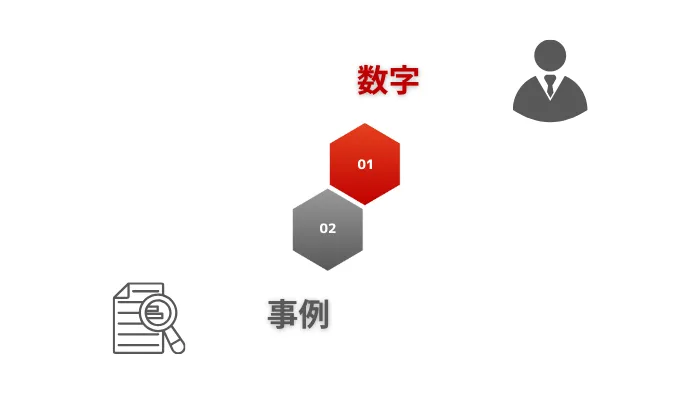
法人営業の場では、機能や価格だけで比較されると消耗戦になってしまいます。。
ポイントは、相手が他社との違いを一瞬で理解できるように、自社ならではの強みを「数字」や「事例」で具体化して話すこと。
特に、成功事例を相手の業界に近い形で紹介すると、相手は自社に置き換えてイメージしやすくなります。
競合比較ではなく、“自社だから得られる成果”を伝えることが、決裁者の判断を後押しします。
|
項目 |
具体例 |
|
実績 |
「同業界で導入後、残業時間が30%削減された」と伝える。 |
|
強み |
「サポート担当が専任でつく体制があります」と説明する。 |
|
他社比較 |
「他社は初期費用が高いですが、当社は月額課金のみです」と示す。 |
このように、数字や実例を交えて話すと、差別化が鮮明になり商談の説得力が高まります。
「次回アクション」を明確にして継続接点を作る

商談の最後に「次に何を一緒に進めるか」があいまいだと、その後の連絡が途切れてしまい、その状態でこちらから何かアクションを起こそうとしても他社に流れていたということになっていたということもございます。
ポイントは、具体的な期日や合意をその場で言葉にして、相手の頭の中に“次の一歩”を残すこと。
特に法人営業では、稟議や社内調整が入るため、こちらから接点を切らさずに関与し続ける姿勢が信頼に繋がります。
|
項目 |
具体例 |
|
日程合意 |
「来週の水曜に進捗を確認する場を作りませんか」と伝える。 |
|
宿題の明確化 |
「御社側で要件を整理いただければ、次回提案に反映します」と依頼する。 |
|
契約への橋渡し |
「次回は契約条件の詳細を一緒に確認しましょう」と伝える。 |
このように、小さな次回アクションでも合意しておくと、案件は途切れず前に進みやすくなります。
「CRM・SFA」で情報を一元管理する

営業活動の情報が担当者の頭やメモに散らばっていると、案件管理はすぐに混乱します。
ポイントは、顧客接点の履歴・見込み度・社内アクションを全員が同じ画面で見られる状態を保つこと。
これにより、属人化を防ぎ、組織全体でのスピード感あるフォローが可能になります。
|
項目 |
具体例 |
|
顧客履歴 |
「前回誰が訪問し、どんな課題を聞いたか」をSFAに残す。 |
|
進捗状況 |
「見積提出済み」「稟議中」などステータスを更新する。 |
|
社内連携 |
「次回は技術担当を同席させたい」とコメントを共有する。 |
このように、CRM・SFAを“見える化の土台”にすることで、誰が見ても案件の温度感が伝わる状態が整います。
「KPI」を設定して活動量を可視化する
新規開拓営業では、成果が出ない原因の多くが「行動量の不足」か「行動の質の偏り」にあります。
そのため、目標を抽象的な「売上」だけで管理するのではなく、日々の活動を数字で追えるようにすることが欠かせません。
ポイントは、架電件数や商談化率といった細かな指標をチーム全体で共有し、進捗が一目でわかる状態をつくること。
これにより、個々の動きが見えにくい法人営業でも、改善点を具体的に議論できるようになります。
|
項目 |
具体例 |
|
架電件数 |
1日「50件」のコールを実施する。 |
|
商談設定率 |
架電全体の「10%」をアポイント化する。 |
|
初回訪問数 |
週「8件」を必ず現場で実施する。 |
このように、KPIを日単位・週単位で区切って可視化すると、数字が会話の共通言語となり、チームの温度感が揃いやすくなります。
「メール・電話・訪問」を組み合わせて接触する
法人営業では、最初の接触で相手に会える確率は低く、単発のアプローチでは簡単に埋もれてしまいます。
そこで有効なのが、メール・電話・訪問を連動させて接点を積み上げる動き方です。
ポイントは、相手の心理に合わせて「メールで情報提供→電話で確認→訪問で深掘り」という流れを意識すること。
接触の手段をずらすだけで、相手の記憶に残る確率が高まり、商談化の扉を開きやすくなります。
|
項目 |
具体例 |
|
メール |
「同業の事例資料」を添付して送信する。 |
|
電話 |
「資料をご覧いただけましたか?」と確認する。 |
|
訪問 |
「導入検討の背景」を直接ヒアリングする。 |
このように、異なる手段を組み合わせると、一方通行ではなく、相手とのリズムを生み出す接触が可能になります。
初回訪問では「雑談」を活用して心理的距離を縮める
初対面の商談では、数字や提案内容に入る前に「雑談」を挟むと空気が柔らかくなります。
ポイントは、相手の表情や反応から安心感を与えられるテーマを選ぶこと。
特に法人営業では、相手の業界や日常に寄り添った話題を投げかけると、相手の本音を引き出しやすくなります。
「雑談」を通じて心理的距離が縮まると、その後のヒアリングも格段にスムーズになります。
|
項目 |
具体例 |
|
季節の話題 |
「今年の展示会は暑さ対策が大変でしたね」と話す。 |
|
業界ニュース |
「最近の法改正で業務に影響はありましたか?」と聞く。 |
|
身近な共通点 |
「御社の近くに新しいカフェができましたね」と触れる。 |
このように、相手が答えやすい小さな話題を先に置くと、緊張感が自然にほぐれていきます。
「競合比較」を示して納得感を与える
商談で提案の説得力を高めるには、「競合比較」を具体的に示すことが効果的です。
ポイントは、自社の強みだけを押すのではなく、他社の特徴も公平に伝えること。
相手は“比較の軸”を持つことで判断がしやすくなり、納得感が増します。
特に法人営業では、決裁者が社内説明に使いやすい資料を用意すると成約率が高まります。
|
項目 |
具体例 |
|
コスト比較 |
「A社は導入費が安いですが、運用コストは高めです」と説明する。 |
|
機能比較 |
「B社は機能が豊富ですが、操作性は少し複雑です」と伝える。 |
|
サポート比較 |
「当社は初年度から専任担当が伴走します」と強調する。 |
このように、相手が意思決定しやすい“比較の地図”を示すと、提案が受け入れられやすくなります。
「紹介営業」で信頼性の高いリードを得る
紹介営業は、最初から「信頼の担保」がある状態でスタートできるのが大きな強みです。
電話やメールで冷たい反応しか得られない時でも、共通の知人のひとことがあるだけで扉が開きます。
ポイントは、依頼の仕方を自然にすること。押しつけ感を出さず、「お役に立てたからこそ、もし良ければご紹介を…」という流れにすると相手も快く動いてくれます。
営業責任者にとっては、属人化しやすい新規開拓を「仕組み」として再現性高く回せるようになるのが魅力です。
慣れてくるとこういった紹介のご依頼も会話の中にスムーズに組み込めるようになっていきます。
|
項目 |
具体例 |
|
紹介依頼の切り口 |
「同じ課題を持つ方がいればご紹介いただけませんか」と依頼する。 |
|
信頼関係の深め方 |
「導入後の成果や改善点」を定期的に共有する。 |
|
決裁者への接点作り |
「◯◯社の△△様からご紹介いただきました」と切り出す。 |
このように、紹介営業は一本のリードの質を飛躍的に高め、無駄な工数を減らしていきます。
「フォローアップ」を徹底して見込みを温める
新規開拓では、初回商談だけで終わらせず「温度を冷まさない工夫」が欠かせません。
そのために大切なのが、相手の記憶が残っているうちに行動すること。商談後すぐに要点を整理し、感謝と次回のきっかけを添えたメールを送ると信頼感が増します。
さらに、中長期では情報提供を続けることで「忘れられない存在」になれます。業界ニュースや他社事例を共有するだけでも相手にとって価値になります。
営業責任者の視点では、担当者の裁量に任せず、フォローのプロセスを標準化することで案件化の歩留まりを確実に高められます。
|
項目 |
具体例 |
|
商談直後の対応 |
「議論した要点と次回提案」をまとめて送る。 |
|
中期的な接点 |
「業界レポートやイベント情報」を共有する。 |
|
検討状況の確認 |
「次の予算時期はいつ頃ですか」と尋ねる。 |
このように、フォローアップは一度の商談を継続的な関係へ変え、結果として受注率を底上げしていきます。
「PDCA」を素早く回して改善を継続する
新規開拓営業は、量よりも改善の速さが結果を左右します。
ポイントは、PDCAを「小さく・早く」回すことです。
法人営業では、相手業界や決裁フローごとに最適なアプローチが異なるため、試行と修正を短期間で繰り返すほど、成功確率が高まります。
改善が早いほど、成功パターンをチームで共有でき、組織全体の成果が底上げされます。
|
項目 |
具体例 |
|
Plan |
「受付で使う導入トーク」を仮定する。 |
|
Do |
「新規架電スクリプト」を一日20件実践する。 |
|
Check |
「アポ率や反応率」を毎週数値で振り返る。 |
|
Act |
「反応の良かったフレーズ」を次回に定着させる。 |
このように短いサイクルで回すと、営業活動のムダが減り、勝ち筋が早く見えてきます。
新規開拓営業とは?
新規開拓営業とは、自社と取引実績のない潜在顧客にアプローチし、新たな顧客を獲得するための営業活動です。
企業が市場を拡大し、新たなビジネスチャンスを掴むために非常に重要な活動であり、既存顧客への営業とは異なり、ゼロから信頼関係を築く必要があるため、戦略的なアプローチと粘り強さが求められます。
新規開拓営業の必要性は?
新規開拓営業は、既存顧客の売上に依存せず、安定的に「新しい収益源」を確保するために欠かせません。
特に、市場環境や競合状況の変化に左右されない強固な基盤をつくる上で、新規顧客の継続獲得は営業責任者にとって最重要課題です。
短期的な成果だけでなく、長期的な「顧客ポートフォリオの最適化」にも直結します。
- 「既存依存リスク」を回避するために新規顧客を開拓する
- 「市場シェア拡大」を実現するために潜在層へ提案する
- 「紹介・派生案件」を生むために新しい接点を増やす
このように、新規開拓営業は収益の安定と成長を支える経営戦略そのものになります。
プッシュ型営業とプル型営業とは?
新規開拓営業には、大きく「プッシュ型」と「プル型」の2つのアプローチがあります。
プッシュ型は、営業側から積極的にアプローチし「短期成果」を狙う手法であり、プル型は情報発信や信頼構築を通じて「自然に顧客を引き寄せる」手法です。
営業責任者は、この両者を組み合わせ、自社の商材特性や顧客の購買行動に合わせて最適化することが重要です。
- 「電話・訪問」でアポイントを獲得する
- 「セミナー・展示会」でリードを創出する
- 「コンテンツ発信」で問い合わせを獲得する
このように、プッシュとプルを戦略的に使い分けることが、新規開拓の成功率を高める最大のポイントになります。
新規開拓営業でよくある誤解
新規開拓営業は「がむしゃらにアポを取る仕事」と誤解されがちですが、実際には市場を見極め、顧客の課題に刺さる切り口を用意することが欠かせません。無計画に数を追えば追うほど、無駄な労力が増え成果は遠のきます。現場で特に多い誤解は次の3つです。
- 「電話件数が多ければ成果が出る」と考える誤解をする
- 「訪問回数を重ねれば信頼が得られる」と思い込む誤解をする
- 「商品説明の情報量で勝負できる」と勘違いする誤解をする
このように、誤解を捨てて「顧客の購買プロセス」に沿った動きを設計することが、新規開拓を成果につなげる最大の近道になります。
新規開拓以外の営業の種類
営業は新規開拓だけではなく、既存顧客との関係性を深める活動や導入後の成果を支援する活動も重要です。営業責任者が全体像を把握して役割を分けることで、チーム全体の成果は飛躍的に伸びます。代表的な種類は以下の通りです。
- 「ルート営業」で既存顧客を定期的に訪問して関係を維持する
- 「深耕営業」で既存顧客の未開拓ニーズを掘り起こす
- 「カスタマーサクセス営業」で導入後の成果を実感させる
このように、新規開拓と既存営業をバランスよく組み合わせることが、安定した売上を生み出す最大のポイントになります。
新規開拓営業の3つの目的
「新規リード獲得」で見込み客の母数を増やす
新規開拓営業の目的は、接触できる見込み客の母数を最大化し、将来の商談につながる基盤をつくることです。
数字を追うだけではなく、効率的にターゲットを広げる戦略が重要です。
リスト精度を高めることで、無駄打ちを減らし、有効な接点を量産できます。
・「ターゲット選定条件」を明確に設定して抽出する
・「アプローチチャネル」を複数組み合わせて実行する
ポイントは、無差別に声をかけるのではなく、精度と量を同時に担保することです。
このように、戦略的なリード獲得は、商談につながる母数を安定的に増やすために欠かせません。
商談・受注につながる接点を確保する
新規開拓営業の目的は、単なるアプローチで終わらせず、次の商談や受注につながる接点を確実に生み出すことです。
一度の接触で完結させるのではなく、段階的に関係を深めることが成果への近道となります。
信頼を積み重ね、顧客が話したくなる状況を意図的につくり出すことが重要です。
・「初回面談後のフォロー」を必ず仕組みに落とし込む
・「意思決定者との接触機会」を逃さず確保する
ポイントは、接点を単発で終わらせず、次の行動につながる布石に変えることです。
このように、計画的に接点を重ねる力は、商談化率と受注率を大きく左右します。
「ブランド認知」を高めて選ばれる確率を上げる
新規開拓営業の目的は、顧客に自社の存在を覚えてもらい、選定時に第一候補として思い出してもらえる状態をつくることです。
競合と比較された際に「知っている会社」であるかどうかが、受注確率を大きく左右します。
短期的な商談獲得だけでなく、中長期での案件発生を見据えた種まきが欠かせません。
・「定期的な情報発信」で記憶に残る接点をつくる
・「顧客課題に直結する事例紹介」を武器として活用する
ポイントは、商談が今すぐ生まれなくても、認知を積み重ねて選ばれる確率を底上げすることです。
このように、ブランド認知の強化は、長期的なリード育成と受注拡大に直結します。
新規開拓営業の施策15選
「飛び込み営業」で現場からの生情報を収集する
飛び込み営業は、机の上だけでは分からない“現場の温度感”を直接つかめる貴重な機会です。
ポイントは、商談を強引に作るのではなく「情報交換の姿勢」で臨むことです。
相手のちょっとした表情や一言から、営業資料には載らない課題や本音を拾うことができます。
特に法人営業では、担当者の現場感覚を聞くことが、その後の提案内容を磨くヒントにつながります。
|
項目 |
やり方の例 |
|
入り口の切り出し |
「近くでご挨拶回りをしている」と柔らかく伝える。 |
|
課題の聞き出し |
「現在お使いの仕組みで不便な点」を短く尋ねる。 |
|
会話の広げ方 |
「同業で増えている取り組み」を話題に混ぜる。 |
このように、飛び込み営業は即成果よりも“課題発見の場”として活かすと大きな価値を生みます。
「テレアポ」で短時間に接触数を最大化する
テレアポは、一日の限られた時間を最大限に活かして多くの企業に接触できる方法です。
ポイントは、数をこなすだけでなく「最初の一言に意味を持たせること」です。
相手が耳を傾けやすい切り口を工夫するだけで、会話の流れが大きく変わります。
断られた場合も、その場で得た情報をメモに残しておけば、次のアプローチに役立ちます。
|
項目 |
やり方の例 |
|
リストの精度 |
「業界と役職」で絞り込み、決裁者に届く確度を上げる。 |
|
最初の一言 |
「御社と同業の成功事例」を簡潔に伝える。 |
|
断られた時 |
「検討時期や担当部署」を控えて次に活かす。 |
このように、テレアポは単なる数打ちではなく、接点の質を高める工夫次第で成果を伸ばせます。
「手紙・DM営業」で意思決定者に確実に情報を届ける
手紙やDMは、メールよりも「目に留まりやすい」点で効果的です。
ポイントは、決裁者が手元で一度は開封する工夫をすることです。
例えば、役職名を明記した封筒や「担当者様ではなく〇〇部長宛」と書くことで、直接届きやすくなります。
より具体的には、読み手の課題に沿った短文で、自社の価値を一瞬で理解できるメッセージを載せることです。
以下の表を参考にしてみてください。
|
項目 |
やり方の例 |
|
宛名の工夫 |
「経営企画部長〇〇様」と明記する。 |
|
開封率の向上 |
「手書き風の封筒」で差別化する。 |
|
記憶に残す仕掛け |
「導入事例の一文」を冒頭に入れる。 |
このように、紙の温度感を活かしたDMは、信頼感を伴いながら意思決定者に情報を届けやすくなります。
「フォーム営業」で効率的にアプローチする
問い合わせフォームは「企業の公式窓口」であり、正しい情報を記録に残せるため見てもらえる確率が高いです。
ポイントは、営業色を強く出さず「相談」や「情報提供」の形で書くことです。相手企業のために「提案させてください」という一方的な依頼は、相手からしたら「こちらのことを良く知らないのに提案なんて出来るのだろうか」と不安視されてしまいます。
より具体的には、導入事例や数値を短く添えることで更に信頼度が上がります。
特に法人営業では、企業HPのフォーム経由で送ると受付担当を経由せず意思決定者に届くケースも多くあります。
以下の表を参考にしてみてください。
|
項目 |
やり方の例 |
|
件名 |
「〇〇社様向けの事例共有のご相談」と記載する。 |
|
本文冒頭 |
「同業界の導入事例」を一文で伝える。 |
|
本文末尾 |
「オンライン15分で情報交換」の提案を添える。 |
このように、営業要素を抑えた自然な文章にすると、効率的に面談獲得へつながります。
「SNS・ソーシャルセリング」で信頼関係を築く
SNSでの営業活動は、ただ商品の宣伝を流すだけでは相手の心に届きません。
ポイントは「相手が本当に知りたい情報」を発信し、営業色を薄めながら自然に接点を重ねることです。
より具体的には、事例紹介や業界ニュースを混ぜて、顧客の課題に直結する情報を届けると効果が高まります。
特に法人営業では、役職者の視点に寄り添った言葉を使うことで「この人は信頼できる」と感じてもらえます。
|
項目 |
やり方の例 |
|
業界知識の共有 |
「業界トレンド記事」を要約してLinkedInで発信する。 |
|
顧客課題への共感 |
「よくある失敗事例」を取り上げ、改善のヒントを投稿する。 |
|
信頼関係の強化 |
「導入企業の成果」をストーリー形式で紹介する。 |
このように、SNSは単なる発信の場ではなく、信頼を積み重ねる営業ツールとして活かすことができます。
「ウェビナー・セミナー」で見込み客を集客する
ウェビナーやセミナーは、短時間で多くの見込み客に接触できる有効な施策です。
ポイントは「テーマ選び」にあり、顧客が日常で直面する課題を切り口にするほど参加率が上がります。
より具体的には、成功事例の紹介や実務で役立つノウハウを交えると、聞き手にとって価値が高まります。
営業担当者が最後に質疑応答で一人ひとりと会話することで、その後の商談へ自然につなげやすくなります。
|
項目 |
やり方の例 |
|
集客 |
「メルマガやFacebook」で開催告知を流す。 |
|
コンテンツ設計 |
「顧客の課題」を題材にし、解決の手法を提示する。 |
|
フォローアップ |
「アンケート結果」を基に個別連絡して商談化する。 |
このように、ウェビナーはただのプレゼンの場ではなく、次のアポイントへ自然に移す仕組みとして機能します。
「展示会・イベント」で短期間にリードを獲得する
展示会やイベントは、見込み顧客と一度に多数接点を持てる効率的な場です。
ポイントは「数」ではなく「質」を意識し、名刺交換だけで終わらせず、その後のフォロー体制まで設計しておくことです。
より具体的には、事前に声をかけたいターゲット企業をリスト化し、当日の会話で課題感を引き出せる質問を準備しておくと成果につながります。
|
項目 |
やり方の例 |
|
事前準備 |
「ターゲット企業リスト」を作成する。 |
|
接点作り |
「デモ体験ブース」でサービスを体感してもらう。 |
|
フォロー |
「お礼メール」にヒアリング内容を添えて送る。 |
このように、展示会は名刺を集める場ではなく「商談の入口」をつくる場として活用できます。
「オウンドメディア」で専門性を発信する
オウンドメディアは、営業活動を補完する「信頼づくりの武器」になります。
ポイントは「売り込み」ではなく「専門家の視点」で記事を届けることです。
より具体的には、顧客が日常で感じる課題をテーマにし、解決策をわかりやすく示すことで、自然に問い合わせにつながります。
|
項目 |
やり方の例 |
|
記事テーマ |
「顧客のよくある悩み」を記事化する。 |
|
信頼構築 |
「成功事例インタビュー」を公開する。 |
|
商談導線 |
「資料ダウンロード」へのCTAを設置する。 |
このように、オウンドメディアは営業マンが訪問する前に「会社の専門性」を伝えてくれる強力なツールになります。
「インターネット広告」で潜在層を狙う
インターネット広告は、まだ課題を自覚していない「潜在層」に気づきを与える場面で力を発揮します。
ポイントは、検索広告やSNS広告を単発で打つのではなく、情報収集段階にいる相手の心理を想定して接点を設計することです。
より具体的には、「比較サイトに広告を出す」「ホワイトペーパーを広告経由で配布する」など、営業とマーケティングをつなぐ導線をつくることが効果的です。
|
項目 |
やり方の例 |
|
興味喚起 |
「課題解決事例」をLPで紹介する |
|
教育 |
「無料資料ダウンロード」でリードを集める |
|
検討促進 |
「成功事例動画広告」をSNSで流す |
このように、広告は単なる集客手段ではなく、営業が話しかけやすい土壌を整える役割を果たします。
「オフライン広告」で地域や業界特化の層に届く
オフライン広告は、デジタル広告では拾いきれない「地域密着型」「業界特化型」の企業に刺さりやすい手法です。
ポイントは、ターゲットが集まる場所に広告を置き、営業の声を代弁するようなメッセージにすることです。
より具体的には、「業界紙への広告掲載」「駅や展示会場への看板出稿」など、現場での視認性を高める仕掛けが有効です。
|
項目 |
やり方の例 |
|
地域密着 |
「主要駅のデジタルサイネージ」に出す |
|
業界特化 |
「専門誌の広告枠」を活用する |
|
信頼醸成 |
「展示会カタログ広告」で存在感を示す |
このように、オフライン広告は「営業が訪問したときに名前を知ってもらえている状態」を先につくり出してくれます。
「ビジネスマッチングサービス」で効率的に接点を作る
ビジネスマッチングサービスは、営業の「入口づくり」を一気に加速させる仕組みです。
ポイントは、「相手の課題感」に即した切り口で会話を始めることです。
ただ自己紹介を並べるだけでは印象に残りにくいので、より具体的には「同業界の成果事例」や「コスト削減の実例」を交えて話すと、商談に自然につながりやすくなります。
|
項目 |
やり方の例 |
|
接点作り |
「業界別のマッチングイベント」に参加する。 |
|
課題の深掘り |
「直近の業界トレンド」を切り口に話す。 |
|
次アクション |
「初回面談日程」をその場で仮押さえする。 |
このように、マッチングをきっかけにすれば、効率よく信頼の最初の一歩を踏み出せます。
「アライアンス営業」で相互に新規開拓する
アライアンス営業は、「互いの強み」を組み合わせて新規顧客を広げる方法です。
ポイントは、「補完関係にある企業」と手を組むことです。
より具体的には、既存顧客に対して「合同提案」を行うと、相手は紹介された安心感を持ちやすく、商談化の確率が高まります。
単独では届かない相手にも、協業の信用を借りてアプローチできるのが大きな利点です。
|
項目 |
やり方の例 |
|
協業先探し |
「競合しない業界パートナー」と接点を持つ。 |
|
信頼づくり |
「合同セミナー」を開催して顧客と接触する。 |
|
案件拡大 |
「クロス紹介」で見込み客を広げる。 |
このように、アライアンスを組むことで、一人では届かない市場を一気に広げることができます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【アライアンス営業】正しいアライアンス営業の進め方 第1夜
「代理店制度」で営業チャネルを広げる
代理店制度は、自社だけでは届きにくい業界や地域に販路を広げる大きな武器になります。
ポイントは、代理店が「自分の顧客に提案しやすい状態」を整えることです。
たとえば「短時間で説明できる提案資料」を用意すると、代理店の担当者が自信を持って営業できます。
また「成果事例」を一緒に訪問先で紹介すると、商談の信頼性が一気に高まります。
|
項目 |
やり方の例 |
|
教育サポート |
「勉強会」で業界別の成功事例を共有する |
|
提案支援 |
「提案資料」を代理店専用にカスタマイズする |
|
伴走体制 |
「商談同行」で現場の不安を減らす |
このように、代理店を“仲間の営業チーム”として支えることで、売上拡大のスピードが加速します。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【代理店営業マンは必見】パートナーセールスで絶対やってはいけないこと|営業アカデミー
「紹介営業」で高確度なリードを得る
紹介営業は、既存顧客の信頼を橋渡しにして新規リードを得る手法です。
ポイントは、紹介が「自然に生まれる仕掛け」を作ることです。
たとえば「契約後のフォロー面談」で満足度を確認しながら紹介をお願いすると、顧客は前向きに動いてくれます。
さらに「紹介特典」をシンプルに用意すると、顧客が紹介しやすい雰囲気が生まれます。
|
項目 |
やり方の例 |
|
依頼の切り口 |
「契約直後の成功体験」を共有する |
|
仕掛けの工夫 |
「紹介特典」で顧客にメリットを示す |
|
信頼維持 |
「定期フォロー」で関係を温め続ける |
このように、紹介営業は信頼の連鎖から生まれるため、成約率の高い案件を安定して獲得できます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
トップセールス流「見込み客」の広げ方!紹介営業で上手くいく人の特徴まで徹底解説
「外部パートナー」と連携して営業力を補強する
外部パートナーとの連携は、自社単独では届かない市場へ一気に踏み込む有効な手段になります。
ポイントは、互いの「強み」を組み合わせて顧客接点を増やすことです。
例えば、販売代理店を通じて「新規リード」を獲得する、専門コンサルと組んで「提案の厚み」を増す、業界団体と協働して「信頼性」を高めるといった具体策が挙げられます。
単なる紹介にとどまらず、営業活動のプロセス全体を共有しながら進めることで、案件化までのスピードと確度が大きく変わってきます。
|
項目 |
やり方の例 |
|
新規リード獲得 |
「販売代理店」の顧客リストを活用する |
|
提案力強化 |
「専門コンサル」との共同セミナーを実施する |
|
信頼性向上 |
「業界団体」とタイアップして情報発信を行う |
このように、外部パートナーを活かすことは、一社単独では到達できない成果を現実に引き寄せます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
アライアンス営業を強化する意味とは?事業提携の有効性や意義を解説|営業アカデミー
新規開拓営業で成果を出すための4つの手順
ターゲット企業の「セグメンテーション」を徹底的に行う
新規開拓では、誰に時間を使うかを最初に決めることが成果を左右します。
「セグメンテーション」とは、業界・規模・地域・課題感などで企業を分類し、優先度をつける作業を指します。
ポイントは「数値で切り分ける基準」を明確にし、曖昧な感覚に頼らないことです。
よくあるのは、営業担当の好き嫌いで訪問先を選んでしまい、結果として商談化率が低下するケースです。
STEP
① 業界・従業員数・成長率などの軸を決める
② 過去の受注実績から“反応が良い企業像”を洗い出す
③ データベースや生成AIを使い、候補企業を自動で抽出する
④ 優先度をS・A・Bでランク分けしてリスト化する
具体的には、営業支援ツールで「従業員300名以上・直近で資金調達あり」の条件を入れると、有望なターゲットが浮かび上がります。
まずは“狙うべき相手を見える化すること”から始めてみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
B2Bにおけるセグメンテーション、ターゲッティング、ポジショニング
「ヒアリング」で顧客の真の課題を掘り起こす
商談では、表面的な要望だけで終わらせず、相手が抱える「本音の課題」を聞き出すことが大切です。
「ヒアリング」とは、顧客が言葉にしていない問題や優先順位を会話の中から明らかにする行為を指します。
ポイントは「質問を投げる」より「相手の言葉を深掘りする」ことです。
よくあるのは、用意した質問を機械的に読み上げ、会話がアンケートのように単調になるパターンです。
STEP
① まず現状の取り組みを自由に語ってもらう
② 出てきた言葉をオウム返しで確認する
③ 「それで一番困っていることは?」と優先度を聞く
④ 「理想はどうなれば嬉しいですか?」と未来像を描いてもらう
具体的には、「現在の営業体制はどんな流れですか?」と聞き、出てきた課題を「なるほど、それが遅れると他に影響はありますか?」と掘り下げると、真の悩みが浮き彫りになります。
“聞く姿勢”を持つことで、自然と信頼関係も生まれていきます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
顧客提案を成功させる 「顧客ヒアリング方法」 を解説
「提案資料」をカスタマイズして意思決定者に響かせる
商談で成果を出すには、資料を相手ごとに調整する工夫が欠かせません。
「カスタマイズされた提案」とは、相手の課題や立場に沿った情報を盛り込んだ資料のことです。
ポイントは「相手の言葉や事例を資料に反映すること」です。
よくあるのは、汎用の資料をそのまま使い、どの会社にも同じように見えてしまうケースです。これでは相手の心に残りません。
STEP
① 相手企業のニュースや決算資料を事前に確認する
② そこから「直近の課題」を一つ仮説として入れる
③ 事例や数字は業界に近いものを選んで載せ替える
④ 相手の名前や部署名を資料内に散りばめる
具体的には、「◯◯様の現場で起きている△△に、この仕組みが直結します」と書くだけで特別感が出ます。
一手間の工夫が、意思決定者の記憶に残るきっかけになります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【売上が伸びる】提案資料の作り方(構成・デザインのテンプレ)/パワーポイント
「フォローアップ」で失注を次の商談につなげる
失注は終わりではなく、次のチャンスを生む入口になります。
「フォローアップ」とは、結果が出なかった後でも信頼を積み重ねて再提案につなげる動きのことです。
ポイントは「売り込みではなく、情報提供で接点を残すこと」です。
よくあるのは、失注後に連絡が途絶え、そのまま関係が途切れてしまうケースです。これでは再チャンスは訪れません。
STEP
① 商談終了直後に「お礼メール」を必ず送る
② 1〜2週間後に業界ニュースや他社事例を共有する
③ 季節の挨拶や簡単な一言で存在を思い出してもらう
④ 半年後に再び課題が変わっていないか確認する
具体的には、「最近◯◯業界でこんな動きがありました。御社にも関係があるかと思い共有です」といった軽い連絡が効果的です。
このように、小さな接点の積み重ねが、次の商談を呼び込みます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【10分で解説】トップ営業は「失注」したあとが違う!
新規開拓営業のやり方・施策改善でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「新規開拓営業のやり方・施策を工夫しているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
どれだけリストを作り、架電やメールを繰り返しても、商談化につながらない状況が続くと、自信も揺らいできますよね。
実際に多くの営業現場では、やり方が分かっていても人手や経験が不足し、成果につながらず疲弊するケースが後を絶ちません。
そんなときこそ、営業を熟知した外部のプロに頼るという選択肢が大きな力になります。
スタジアムが提供する営業代行サービスは、IT・Web領域に強い経験豊富な営業のプロが、戦略立案から実行まで一貫して支援。
新規開拓営業に特化したノウハウを持つ担当者が1商材に集中する体制で、成果創出に直結する活動を代行します。
特に「新規案件を短期間で増やしたい」「営業リソースが足りない」といった課題を抱える企業に最適です。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き
【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説
営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順
【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版
インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集
営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文
【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全
【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集
【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!
アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説
【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略
【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説
法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略
【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説
深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順
営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善
13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド
営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション
営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順
【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版
【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集
営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド
営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別
【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果
【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順
【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順
【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点
営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順
【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド
【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き
営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順
できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法
売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法
プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順
【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き
営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策
【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説
【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説
なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術
新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順
営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説
なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法
ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP
ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集
飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法
【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド
【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版
セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法
セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド
新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版
新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全
【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説
新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ
新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法
【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版
【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集
アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法
インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順
【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版
【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法
SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法
MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説
BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法
BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略
BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順
【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版
【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ
【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説
営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選
FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド
【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方
14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順
アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ
シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ
これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順
【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集
【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP
【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説
営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ
御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP
【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順
【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集
営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法
営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順
27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場
【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順
営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準
新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル
営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント
クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順
営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説
営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順
営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順
最終更新日