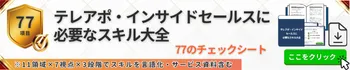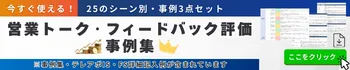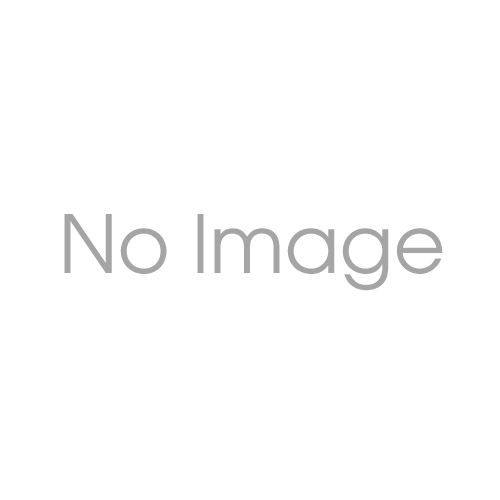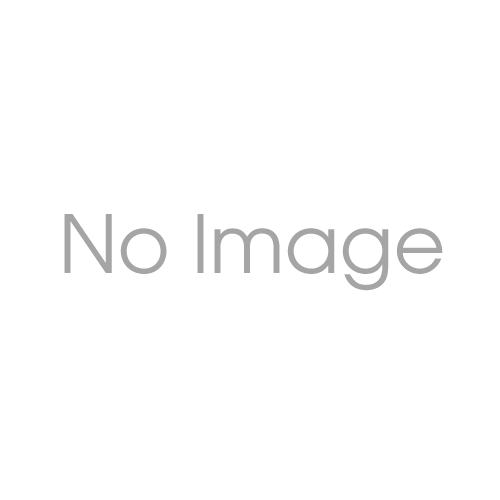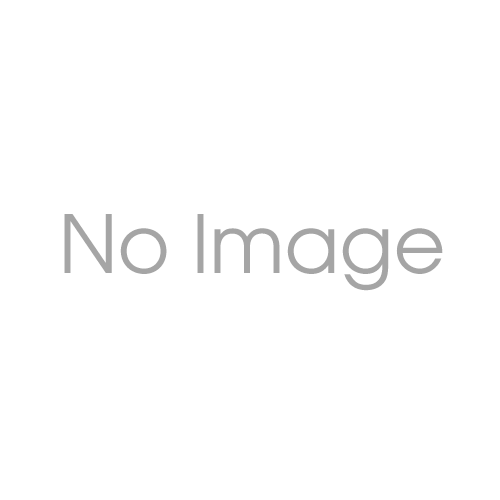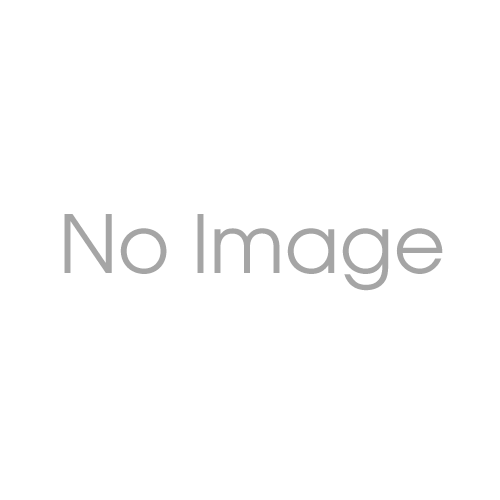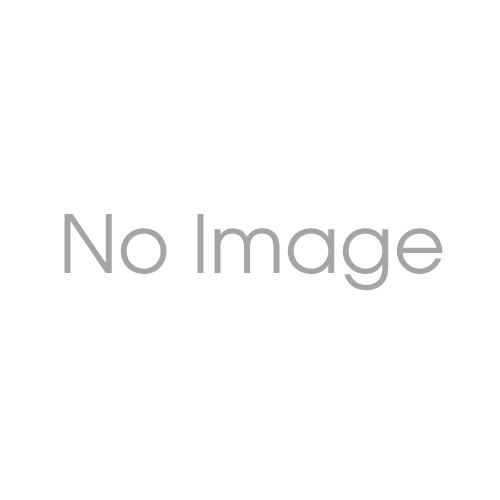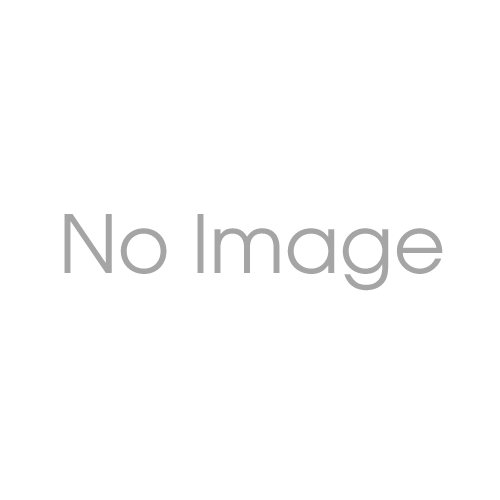法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
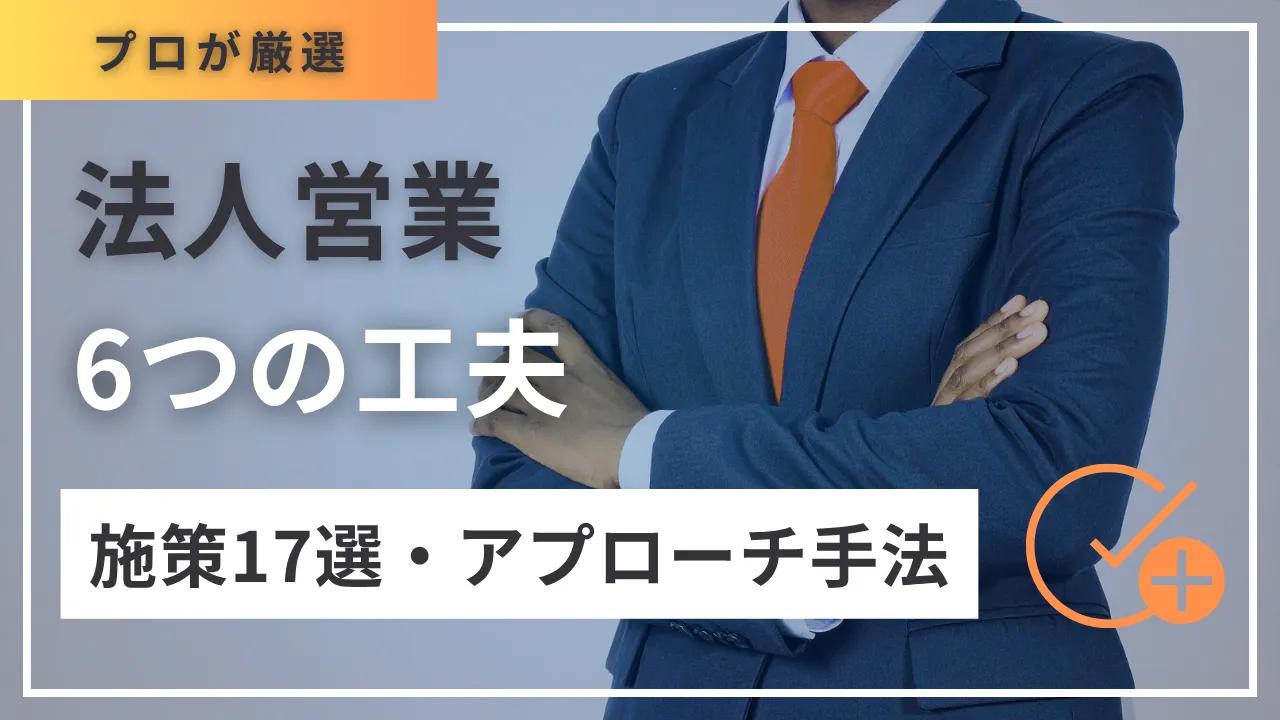
「法人営業って成果につながりにくい…」そんな悩みを抱えていませんか?
顧客は情報を自分で集める時代。従来のアプローチだけでは成果が頭打ちになり、不安や焦りを感じている方も多いはずです。
そこで本記事では、実際の現場で成果を出すための具体策を徹底解説します。
・法人営業のアプローチ手法・施策17選(展示会・ウェビナー・テレアポ)
・法人営業をする3つの目的(新規開拓・既存深耕・市場シェア)
・法人営業を効率的におこなうための6つの工夫(SFA活用・外部リソース・分業)
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
施策17選・法人営業のアプローチ手法
「展示会・イベント活用」で質の高いリードを獲得する
展示会や業界イベントは、単なる名刺交換の場ではなく「意欲の高い担当者」と直接会える特別な機会です。
ポイントは、事前準備から当日の会話まで一貫して「次の打ち合わせ」に繋げる流れをつくることです。
より具体的には、来場者の興味度合いを見極める質問を用意し、話を深めながら相手企業が解決したい課題を把握することが効果的です。
以下の表を参考にしてみてください。
|
項目 |
やり方の例 |
|
事前準備 |
「導入事例シート」を作成して来場者の関心を引き出すようにする |
|
当日の声かけ |
「課題に直結する質問」を投げかけて商談モードに持ち込むようにする |
|
フォロー |
「翌日中のメール連絡」で温度感を冷まさず次回商談に繋げるようにする |
このように、展示会は単発の出会いで終わらせず、商談化の確率を高めるための仕掛けを組み込むことが大切です。
「セミナー・ウェビナー」で専門性を示し、見込み顧客を教育する
セミナーやウェビナーは「知識提供の場」として信頼関係を築く強力な手段です。
ポイントは、商品の説明ではなく「業界課題の解決策」を語り、聞き手にとって学びがある時間にすることです。
より具体的には、最新トレンドを交えた資料を用意し、質問タイムを積極的に活用して双方向性を強めると効果的です。
以下の表を参考にしてみてください。
|
項目 |
やり方の例 |
|
コンテンツ設計 |
「業界調査データ」を交えて客観性を持たせるようにする |
|
参加者との接点 |
「Q&Aセッション」で現場の悩みを引き出すようにする |
|
フォロー |
「録画リンクと要点資料」を送付して記憶に残るようにする |
このように、セミナーは営業色を抑えつつ「専門家」としての立場を確立できる場となります。
「インサイドセールスの強化」で初期接触を効率化する
インサイドセールスは、見込み顧客との最初の接点を効率的につくる仕組みです。
電話やメールだけでなく、最近では「ウェビナー」や「資料DL後の即フォロー」を活用することで、短期間で温度感を把握することができます。
ポイントは、「顧客が動いた瞬間」を捉えて、営業につなげることです。
|
項目 |
やり方の例 |
|
リード反応の即時対応 |
「資料請求直後」に担当者から電話する |
|
スコアリング活用 |
「アクセス回数」が多い顧客を優先的に架電する |
|
情報共有 |
「商談メモ」をCRMに即時入力する |
このように、インサイドセールスを強化すると、無駄なアプローチを減らしながら商談化率を高める流れをつくることができます。
「テレアポ営業」で短期的にアポ数を確保する
テレアポは、即効性のある新規開拓手段として有効な手法です。。
ただ数をこなすのではなく、「事前調査」や「話し出しの一言」を工夫するだけで、アポ取得率は大きく変わります。
ポイントは、「断られる前に相手の関心を引く」ことです。
|
項目 |
やり方の例 |
|
事前調査 |
「業界ニュース」を調べてから電話する |
|
切り出しの工夫 |
「共通の取引先」を会話に入れる |
|
クロージング |
「来週火曜の午後」など具体的な候補を提示する |
このように、テレアポは「準備」「一言」「締め方」の三点を押さえるだけで、短期間で成果を確保できる手法になります。
「飛び込み営業」で未開拓領域を直接攻める
飛び込み営業は、未知の市場に一歩踏み込み、競合がまだ手を付けていない企業に直接アプローチできる手段です。
ポイントは「警戒感を減らす工夫」と「短時間で信頼を得る一言」を用意しておくことです。
事前に業界ニュースや決算情報を把握し、「共通の関心事」を差し込むと、会話が途切れにくくなります。
より具体的には、受付突破の言葉選びや、名刺交換後の次の質問が商談の行方を大きく左右します。
|
項目 |
やり方の例 |
|
第一声 |
「近隣で担当しているのでご挨拶だけでも」と伝える。 |
|
共通点 |
「御社のニュースを拝見して興味を持ちました」と切り出す。 |
|
次の一手 |
名刺交換後に「課題感をお聞きしてもよろしいですか」と続ける。 |
このように、飛び込み営業は「不意の訪問」から「意外な共感」に変えることで、最初の一歩を確かな接点に変えることができます。
「メールマーケティング」で継続的に接点を維持する
メールマーケティングは、直接訪問が難しい法人営業において「継続接触の武器」となります。
ポイントは「開封される件名」と「読まれる本文」の組み合わせです。
より具体的には、相手の業界課題に即した記事リンクや、自社導入事例を短文で添えると反応が上がります。
送信タイミングも重要で、出社直後や昼休憩後など、相手が余裕を持って読める時間帯を意識すると効果的です。
|
項目 |
やり方の例 |
|
件名 |
「人事ご担当者向け:採用効率化の最新事例」と記載する。 |
|
本文 |
「同業界で導入いただいた活用事例」を簡潔に紹介する。 |
|
送信タイミング |
「火曜の午前9時台」に送る。 |
このように、メールは単なる情報提供に留めず、相手の業務に役立つ小さなヒントを積み重ねることで、自然と商談へとつながります。
「オウンドメディア」で認知度を高める
オウンドメディアは、法人営業で「まだ会えていない決裁者層」に知ってもらうための有効な手段です。
単なる情報発信ではなく、「業界課題に直結するテーマ」で記事をつくることで、自然にリード獲得の導線を作ることができます。
ポイントは、自社の強みを押し出すよりも「顧客が日々悩んでいる課題」に寄り添った切り口にすることです。
以下の表は、実際に活用できるやり方の一例です。
|
項目 |
やり方の例 |
|
顧客の課題を起点にする |
「人材定着」に悩む企業向けに、成功事例をまとめる。 |
|
決裁者を意識する |
「役員会で説明しやすい数字」を記事に載せる。 |
|
継続発信で信頼を積む |
毎月「市場動向レポート」を更新する。 |
このように、オウンドメディアは「知ってもらう場」を超えて、商談の入口を広げる仕組みになります。
「Facebook運用」で役職者からの認知を得る
Facebookは、法人営業において「会社役員や部長クラス」とつながる入口になりやすいSNSです。
名刺交換後にフォローしておくだけで、投稿を通じて定期的に存在を思い出してもらえます。
ポイントは、自社の宣伝ばかりではなく「顧客に役立つ情報」を自然体で発信することです。
以下の表は、効果的な運用の具体例です。
|
項目 |
やり方の例 |
|
信頼を構築する投稿 |
「展示会で得た業界トレンド」をシェアする。 |
|
成功事例を発信する |
「導入事例の紹介記事」を投稿する。 |
|
個人の人柄を伝える |
「日常の営業体験から学んだこと」を書く。 |
このように、Facebookは接触回数を増やし、役職者に自然と名前を覚えてもらう場になります。
「Web広告」でターゲット企業を効率的に集める
Web広告は、法人営業で新規リードを獲得する際に欠かせない手段です。
特に「決裁者が情報収集する時間帯」に表示を合わせると、反応率が変わります。 ポイントは、広告を単なる露出ではなく「問い合わせまでの導線」として設計することです。
より具体的には、導入事例やホワイトペーパーのダウンロードを入り口にして、商談につなげる流れを組むことが効果的です。
|
項目 |
やり方の例 |
|
ターゲティング |
「役職」や「業種」で広告配信を絞り込む |
|
コンテンツ設計 |
「導入事例ダウンロード」を入り口にする |
|
フォロー体制 |
「リード獲得後すぐにインサイドセールスが架電する」流れをつくる |
このように、広告は単発ではなく営業活動全体の流れに組み込むことで、効率的にターゲット企業を集められます。
「アライアンス営業」で互いの顧客基盤を広げる
アライアンス営業は、自社だけでは届きにくい顧客にアクセスできる点が魅力です。
共通の課題を持つ企業と組むと、紹介のスピードが速くなります。。
ポイントは、互いの強みを活かして「補完関係」を築くことです。
より具体的には、システム会社とコンサル会社が共同で提案することで、顧客の安心感を高めるような形です。
|
項目 |
やり方の例 |
|
協業先の選定 |
「同じ顧客層に別の角度で提供している企業」を探す |
|
価値提案 |
「合同セミナー」で両社の専門性をアピールする |
|
クロージング |
「紹介案件は両社で訪問し、信頼感を強める」スタイルにする |
このように、アライアンス営業は単なる紹介にとどまらず、長期的な関係を育てる仕組みに変えていけます。
「カスタマーサクセス連携」で既存顧客から追加受注を生む
カスタマーサクセスとの連携は、既存顧客から自然に追加受注を得る流れを作ります。
ポイントは「顧客の成果」を自社サービスで実現する場面を一緒に発見することです。
営業だけでは気づけない利用シーンや課題を、日常的に顧客と接点を持つカスタマーサクセスが拾ってくれることがあります。
その一例として、「導入支援後の定着状況」を把握して追加のトライアルを提案する流れが挙げられます。
以下の表を参考にしてください。
|
項目 |
やり方の例 |
|
成果の見える化 |
「導入前後の業務時間の変化」を一緒に数値化する。 |
|
ニーズの深掘り |
「利用部門からの小さな要望」を拾って営業に繋ぐ。 |
|
提案のきっかけ化 |
「アップデート機能の案内」を既存課題の解決策として提示する。 |
このように、営業とカスタマーサクセスが役割を補い合うことで、顧客が「次に欲しいもの」を自然に引き出す関係が生まれます。
「SFA/CRM活用」でアプローチ履歴を一元管理し効率化する
SFAやCRMを活用すると、顧客ごとのアプローチ履歴を整理し、再現性のある営業活動につながります。
ポイントは「記録を残すこと」が目的ではなく、「次の一手を決める材料」として活かすことです。
その一例として、「失注理由を履歴化」しておくと、再アプローチ時に同じ失敗を避けられます。
以下の表を参考にしてください。
|
項目 |
やり方の例 |
|
商談履歴の蓄積 |
「初回訪問時の課題感」を簡潔にSFAへ入力する。 |
|
フォロー状況の可視化 |
「メール送信の反応」をCRMで追跡して優先度を整理する。 |
|
失注情報の共有 |
「決裁者不在で失注」の記録をチームで共有する。 |
このように、SFA/CRMを「営業のナレッジベース」として活かすと、属人的になりがちな活動をチームで再利用できる形に変えられます。
「ナーチャリング施策」で潜在顧客を商談化に育てる
ナーチャリング施策とは、まだ検討段階にある企業へ「情報提供」や「関係構築」を積み重ねて、商談のタイミングに導く取り組みです。
ポイントは、一方的な売り込みではなく「相手の購買プロセス」に寄り添うことです。
より具体的には、業界事例を交えたセミナー案内や、担当者の悩みに直結するコンテンツを提供することで、潜在層が自然に検討層へ移行する流れをつくります。
|
項目 |
やり方の例 |
|
メール配信 |
「業界別の成功事例」を小分けにして配信する。 |
|
セミナー施策 |
「最新トレンド解説セミナー」に既存リードを招待する。 |
|
個別フォロー |
「導入後の効果イメージ資料」を担当者に合わせて送付する。 |
このように、相手が「まだ早い」と思っている段階で接点を持ち続けると、いざ検討が始まった時に真っ先に声がかかります。
「ターゲットリスト精緻化」で成約確度の高い企業を絞り込む
ターゲットリスト精緻化とは、見込み企業を「業界・規模・課題感」で分類し、受注につながりやすい相手を優先的にアプローチする工夫です。
ポイントは、表面的な情報だけでなく「購買意欲のシグナル」を拾うことです。
例えば、Webサイトで資料を繰り返しダウンロードしている企業や、競合他社の導入実績を気にしている企業は、検討度が高いサインになります。
|
項目 |
やり方の例 |
|
情報収集 |
「過去3か月の資料請求履歴」を営業DBで抽出する。 |
|
優先順位づけ |
「商談化率が高い業界」にマークをつけてリストを整備する。 |
|
データ連携 |
「マーケティング部門のリード情報」を営業リストに統合する。 |
このように、精度の高いリストを作れば、無駄な訪問や電話を減らし、商談化率を大幅に高められます。
「キーパーソン特定」で決裁ルートを明確にする
法人営業では、最終的に誰が契約を決めるのかを見誤ると、時間も労力も無駄になってしまうことがあります。
ポイントは、「表に出る担当者」と「裏で影響力を持つ人」を切り分けて見ることです。
より具体的には、面談の中で質問を投げかけ、意思決定の流れを自然に聞き出すやり方が効果的です。
現場担当の共感を得つつ、決裁者の関心事に直結する情報を拾っておくことが重要です。
|
項目 |
やり方の例 |
|
役職確認 |
「決裁に関わる方はどなたか?」と自然に聞く。 |
|
影響力把握 |
部長の一言で動く、といった社内の力学を探る。 |
|
決裁ルート整理 |
稟議書の流れを担当者に教えてもらう。 |
このように、キーパーソンを押さえておくと、商談の進行が一気に早くなることがあります。
「業界別課題リサーチ」で刺さる提案を準備する
法人営業では、業界ごとに抱えている「特有の悩み」が存在します。
ポイントは、一般的な情報ではなく、取引先の現場に直結する課題を事前に把握することです。
より具体的には、業界紙や展示会の情報、競合事例から課題を抽出し、自社の提案に落とし込むやり方が有効です。
提案の場で「それ、まさにうちの課題です」と言われれば、信頼は一気に深まります。
|
項目 |
やり方の例 |
|
業界ニュース調査 |
最新の法改正や市場動向をチェックする。 |
|
競合ベンチマーク |
他社導入事例を分析し、自社の強みと比較する。 |
|
顧客ヒアリング |
同業他社への訪問で現場の声を拾う。 |
このように、業界の文脈を踏まえた提案は「刺さり方」が違い、商談成立の確度を高めます。
法人営業をする3つの目的
「新規開拓」で継続的に売上を拡大する
法人営業の目的は、新しい顧客を獲得し続けることで安定した売上基盤を築き、将来の成長余地を広げることです。
既存顧客だけに依存すると市場変化に弱くなるため、常に新規パイプラインを確保する必要があります。
・「ターゲットリスト」を業界別に分類して優先順位を決める
・「初回接触後のアクション」を必ず3日以内に実行する
ポイントは、狙う市場を絞り込み、接触から提案までの速度を落とさないことです。
このように、新規開拓を仕組み化すれば成果が積み重なり、継続的な売上拡大につながります。
「既存の深耕」でLTVを最大化する
法人営業の目的は、既存顧客との関係を深めることで取引単価や継続率を高め、LTV(顧客生涯価値)を最大化することです。
新規開拓よりもコスト効率が高く、安定収益の土台を築けます。
・「利用状況データ」を定期的に分析して追加提案を行う
・「決裁者以外のキーマン」とも接点を増やして関係を強化する
ポイントは、顧客の現場に入り込み、潜在ニーズを拾い上げることです。
このように、既存の深耕は利益率の高い営業活動として成果を積み重ねられます。
「市場シェア獲得」で競合優位を確立する
法人営業の目的は、市場内でのシェアを拡大し、競合との差別化を明確にすることで優位性を固めることです。
シェアを握れば価格競争を避け、長期的な影響力を発揮できます。
・「競合比較表」を作成し、優位性を数値で提示する
・「導入事例」を武器に、他社見込み客へ横展開する
ポイントは、自社の強みを顧客視点で翻訳し、競合に勝てる理由を明確に伝えることです。
このように、市場シェアの獲得はブランド力と収益性の両立を実現します。
法人営業における新規顧客開拓が重要な3つの理由
「売上の安定化」を図るために新規を取り続ける
法人営業において新規顧客を取り続ける理由は、既存だけに依存すると売上が急減するリスクがあるためです。
安定的な収益基盤を作るには、新規開拓を「習慣化」する仕組みが欠かせません。
・「既存売上が減少した時の穴埋め」を想定して新規リストを常時準備する
・「毎週の商談数」をKPIとして固定し、数字で管理する
ポイントは、新規が売上の変動を吸収し、全体の安定を支えること。
このように、新規を継続的に取る力は、不測の事態でも売上を崩さないために有効です。
「顧客の入れ替わりリスク」に備えるために必要とされる
法人営業で新規顧客が必要とされる理由は、取引先の予算削減や担当交代など、突然の変化で売上が失われるリスクが常に存在するためです。
安定した収益を守るには、入れ替わりを前提に「常に新しい柱」をつくる行動が重要です。
・「解約の可能性が高い顧客」を定期的に洗い出し、代替案件を先行して仕込む
・「業界別の新規ターゲット」をあらかじめリスト化し、交渉を進めておく
ポイントは、既存を守るだけでは変化に対応できないこと。
このように、新規を積み上げる姿勢が、長期的な売上維持につながります。
「成長市場」を先取りして競合を出し抜くことができる
新規顧客開拓が不可欠なのは、市場全体が拡大する領域を誰よりも早く押さえることが、競合優位を築くために必要なプロセスだからです。
拡大市場に食い込むことで、シェア拡大とブランド強化の両方を実現できます。
・「成長性のある業界」を定期的にリサーチし、初期段階で営業を仕掛ける
・「競合が未着手のニッチ市場」に小さく入り、成功事例を早期に作る
ポイントは、成長市場での先行は後発との差を決定的に広げること。
このように、先取りの動きが営業成果を長期的に高めるとともに、今後の営業活動においても優位に働きます。
法人営業を効率的におこなうための6つの工夫
「ターゲットリスト」を精緻化して無駄打ちを減らす
ただ数を当てる営業は、時間も体力も消耗しやすいです。
大切なのは、「誰に届けると響きやすいか」を先に決めることです。
たとえば業界や規模を絞ると、その相手ならではの課題が見えてきます。
提案の切り口が相手の現場感に合えば、「うちの状況を理解している」と思ってもらえる可能性が高まります。
ポイントは、「ターゲットを広げる」ではなく「ターゲットを絞る」です。
- 「成約に結びついた業種」を再確認して深掘る
- 「反応率の高かった企業規模」を優先する
- 「過去の受注企業と似た特徴」を持つ先に当たる
狙いを定めることで、打ち手の精度がぐっと上がります。
「SFA/CRM」を活用して営業活動を可視化する
営業がうまく回らないときは、情報が点で散らばっていることが多いです。
SFAやCRMに活動をまとめると、進捗も案件状況も一目で確認できます。
見える化されれば、どの案件が止まっているのか、どの顧客に再接触が必要なのかがはっきりします。
結果として、個人任せではなくチーム全体でフォローがしやすくなります。
ポイントは、「記録する」ではなく「次の行動を生む仕組み作り」です。
- 「商談内容」を簡潔に残して後で検索できる形にする
- 「ステージ管理」で確度の違いを明確にする
- 「優先度の高い案件」をダッシュボードで共有する
見える情報が増えるほど、チーム全体での動きが速くなります。
「アポ獲得代行」や外部リソースを使い分ける
営業担当だけでアポを追うと、数字の波に振り回されやすいです。
負荷が高いときに「アポ獲得代行」を併用すると、商談に集中できる時間が生まれます。
外部リソースを使うと、社内の強みを活かす場面がはっきりします。
大切なのは、「外注=丸投げ」ではなく「戦略的な補完」と考えることです。
ポイントは、「コスト削減」ではなく「商談の質向上」です。
- 「新規開拓」は外部に任せて、既存顧客対応に集中する
- 「アポ数の波」を代行活用で平準化する
- 「導入前の条件設定」を明確にして成果をコントロールする
「KPI管理」でプロセス改善を仕組み化する
売上だけを追うと、改善の糸口が見えにくいです。
「KPI管理」を導入すると、過程でのボトルネックが浮き彫りになります。
例えば、アポ率が低いのか、受注率が低いのかで手の打ち方が変わります。
大切なのは、数字を監視することではなく、改善の行動に結びつけることです。
ポイントは、「結果管理」ではなく「プロセス管理」です。
- 「週次レビュー」で小さな変化を確認する
- 「フェーズごとの指標」を分けて測定する
- 「改善仮説」を必ず1つ試す習慣をつくる
「インサイドセールス」と「フィールドセールス」を分業する
最初の接点からすぐに訪問するのではなく、電話やオンラインで絞り込むことが大切です。
インサイドセールスが温度感を見極め、フィールドセールスが最後の一押しを担う流れが効率を高めます。
「効率」ではなく「確度」を上げる役割分担が成果につながります。
- 「初回ヒアリング」はインサイドセールスが短時間で実施
- 「優先度付け」は反応の速さや予算感で判定
- 「訪問提案」は見込み度が高い案件だけに集中
無駄な訪問を減らし、商談の質を高める分業がポイントです。
「提案資料・サービス資料」に独自性を持たせ、競合と差をつける
資料が似ていると、どの会社の話かわからなくなることがあります。
実際の事例や数字を入れるだけで、説得力が大きく変わります。
大切なのは「形式」ではなく「リアリティ」です。
- 「導入前後の変化」を1枚の図で見せる
- 「現場の声」を短文で差し込む
- 「競合では語れない強み」を冒頭に置く
相手が「自分ごと」として感じる資料は、商談の決定率を変える力があります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業リーダー必見‼️】もう値引きに頼らない!法人営業での差別化とは⁉️
法人営業で商談化させるための3つのポイント
1「ニーズ顕在化質問」で潜在課題を引き出す
潜在課題を引き出すには、相手が自覚していない問題点を「言葉」にさせることが肝です。
法人営業では、顕在化したニーズよりも、まだ整理されていない違和感を掘り起こした瞬間に、商談化の扉が開きます。
このとき大切なのは、質問の順序と深さで相手の思考を揺さぶりながら、自然に気づきを促すことです。
・「業務フローの中で一番負担に感じている場面はどこですか?」と聞いて、無意識の摩擦を言語化させる
・「解決できればどの数字が改善しますか?」と問い、課題を経営指標に直結させる
このように、表面的な要望を追うのではなく、相手が“本音で困っていること”を引き出すことが、商談を動かす最大のポイントになります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
表面的なニーズで終わらない!トップセールスのニーズの聞き方
2「導入事例の提示」で安心感を与える
相手が最も警戒するのは「失敗したくない」という不安です。
この不安を取り除く最短ルートが、具体的な導入事例を示すことです。
法人営業では、同業種や同規模の企業の成功事例を提示するだけで、納得感と信頼感が一気に高まります。
・「同業他社で成果が出た指標」を数字で見せ、説得力を高める
・「導入前後の比較グラフ」を用意して、効果を直感的に伝える
このように、事例は説明ではなく“証拠”として使うことで、相手の不安を安心に変える武器になります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【完全保存版】事例の話し方6ステップ|営業トークを一段引き上げるトップセールスの技術
3「課題解決ストーリー」で導入後の未来を描かせる
提案が刺さらない原因の多くは、相手が導入後の姿をイメージできていないことです。
だからこそ、課題解決ストーリーを描き、未来の状態を相手に追体験させることが重要です。
営業の役割は、製品説明ではなく「導入後にどんな成果が待っているか」を語ることにあります。
・「1年後に残業時間が何時間削減されるか」を具体的に示す
・「導入で削減されたコストを別の投資に回す未来像」を提案する
このように、未来を数字とストーリーで同時に描くことで、相手に“導入しない理由がない”と感じさせられます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【完全版】スタート2分で商談が決まる「導入テクニック」を徹底解説!ロープレを交えながら明日から使えるフレーズを公開していきます!
法人営業で成果を出すための4つの手順
「情報収集」で顧客の現状を把握する
商談の入口は「情報収集」で始まります。
「情報収集」とは、顧客の課題や意思決定の流れを知るための土台づくりです。
ポイントは「一次情報」と「公開情報」を組み合わせて整理することです。
よくあるのは、表面的な会社概要だけで終わり、意思決定に影響する人物や直近の動きを見落とすケースです。
STEP
① 商談前にニュースやプレスリリースを確認する
② LinkedInや商談履歴から決裁者や担当者の役割を把握する
③ 過去の受注・失注理由を社内CRMで確認する
④ 得た情報を一枚のシートにまとめて仮説に活かす
具体的には「誰が決めて、何に困っていて、どんな動きをしているか」を一目で見える化すると会話が深まります。
まずは今日の訪問前に、顧客を“5分で語れる状態”を目指してみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業のプロが伝授】結果につながる案件の作り方/受注率と単価の上げ方/顧客にささる提案内容/顧客のリサーチ方法
「仮説立案」で提案シナリオを準備する
「仮説立案」は、顧客が“欲しい答え”を先回りして用意する作業です。
仮説とは、顧客の課題に対して「こういう背景があるのでは?」と筋道を立てた想定のことを指します。
ポイントは「課題・原因・解決策」を一連でつなげておくことです。
よくあるのは、解決策だけを先に用意してしまい、顧客の本音に合わずズレが生じるパターンです。
STEP
① 情報収集で得た材料から“顧客が口にしていない課題”を想像する
② その課題が生まれた原因を3パターン用意する
③ 各原因に対応する解決策をセットで考える
④ 仮説ごとに「想定質問」と「返答」を書き出しておく
具体的には「御社の人員不足が原因かもしれません。その場合は外部リソースを活用する形で…」と仮説を提示すると、相手が修正や補足をしてくれます。
まずは仮説を“外れを恐れず投げる姿勢”を意識してみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
『仮説起点の営業論』から学ぶ仮説営業の神髄! セールス・スキルを磨くたった一つの方法
「商談」で意思決定者を巻き込む
商談の核心は「意思決定者を巻き込む」ことにあります。
「巻き込む」とは、単に同席させるだけでなく、会話の中で決裁権者を“議論の中心”に置くことを指します。
ポイントは「担当者を尊重しながら、決裁者の関心事に自然と話題を移すこと」です。
よくあるのは、担当者との関係性を気にするあまり、決裁者に切り込めずに終わってしまうケースです。
STEP
① 商談冒頭で担当者の努力を称えたうえで、決裁者に視線を送る
② 「◯◯様のお立場から見た課題はどうですか?」と一言添える
③ 議題を経営視点に置き換え、意思決定者の発言を促す
④ その場で出た発言を整理して、次のアクションに結びつける
具体的には「現場からはこう伺っていますが、経営の視点ではどう映りますか?」と投げかけると、決裁者が自然と会話に入ってきます。
まずは“決裁者の声を引き出す質問”を一つ用意して臨んでみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業術:初対面】お客さんに確実に好かれる3つのポイント... 契約までの土台を決める初対面の攻略方法
「クロージング」で契約条件を明確に詰める
最後の山場は「クロージング」で、契約条件を具体的に形にする瞬間です。
「クロージング」とは、顧客が納得できる形で条件を整理し、合意の一歩手前まで進めることを指します。
ポイントは「価格」よりも「条件の明確化」に焦点を当てることです。
よくあるのは、値引きの話に流されて、導入時期や支払い方法などの細部を詰めきれないまま持ち帰ってしまうパターンです。
STEP
① これまでの合意点を一度整理して言葉にする
② 支払い条件・導入スケジュール・サポート体制を具体化する
③ 想定されるリスクや障害についても確認しておく
④ 最後に「この条件で進めるイメージは合っていますか?」と確認する
具体的には「費用は月額◯◯円、導入は4月開始、サポートは週次対応で進めます。これでご安心いただけますか?」と伝えると、顧客は判断しやすくなります。
まずは“価格以外の条件を整理するメモ”を持参して話すことから始めてみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【クロージングの悩み解消】トップ営業の「クロージングトーク」 元リクルート 全国営業成績一位、リピート9割超の研修講師)
法人営業のアプローチ方法でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「法人営業のアプローチ方法を工夫しているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
顧客リストを作り、提案資料を磨き、何度もアプローチしているのに、思ったほどの反応が得られないと、不安や焦りが募るものです。
このまま同じやり方を続けても、時間と労力ばかりかかり、成果が伸び悩んでしまうこともあります。
そこで解決策となるのが、営業代行を専門にしているプロの力を借りる方法です。
スタジアムの営業代行サービスなら、IT・Web領域に精通した経験豊富な営業のプロが、貴社の商材に最適なアプローチを設計し、実行まで一貫して支援します。
「新規開拓を強化したい」「営業組織を立ち上げたい」といった法人企業様に特化した支援体制が整っています。
期間や案件ごとに柔軟に活用できるので、自社の営業リソースに無理をかけず成果を伸ばせるのが特徴です。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き
【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説
営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順
【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版
インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集
営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文
【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全
【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集
【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!
アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説
【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略
【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説
法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略
【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説
深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順
営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善
13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド
営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション
営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順
【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版
【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集
営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド
営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別
【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果
【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順
【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順
【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点
営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順
【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド
【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き
営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順
できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法
売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法
プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順
【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き
営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策
【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説
【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説
なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術
新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順
営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説
なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法
ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP
ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集
飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法
【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド
【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版
セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法
セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド
新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版
新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全
【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説
新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ
新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法
【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版
【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集
アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法
インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順
【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版
【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法
SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法
MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説
BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法
BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略
BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順
【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版
【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ
【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説
営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選
FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド
【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方
14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順
アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ
シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ
これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順
【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集
【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP
【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説
営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ
御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP
【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順
【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集
営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法
営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順
27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場
【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順
営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準
新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル
営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント
クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順
営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説
営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順
営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順
最終更新日