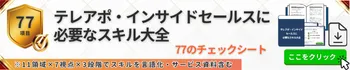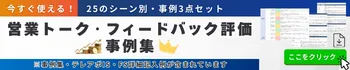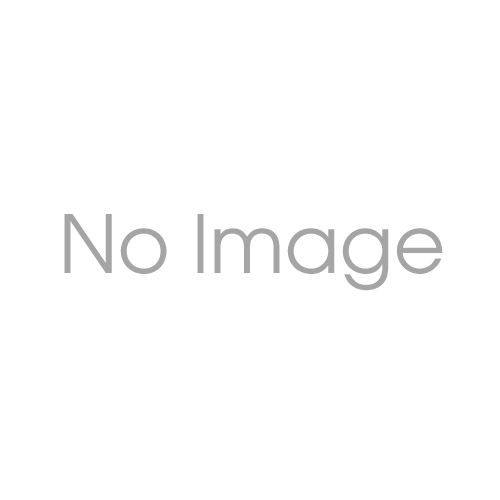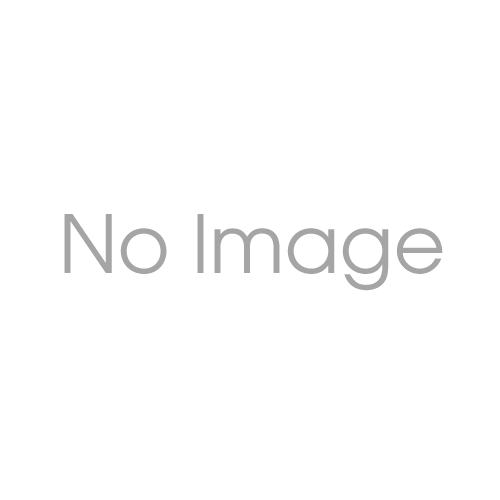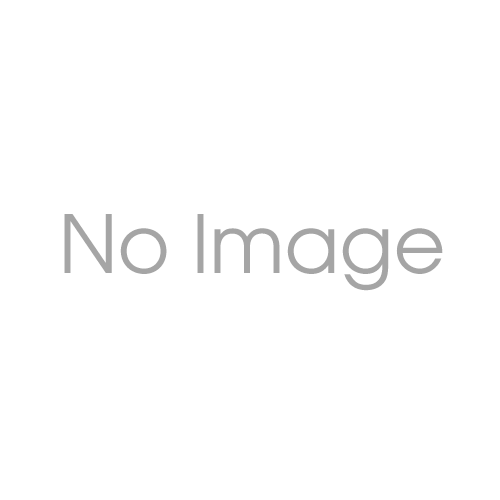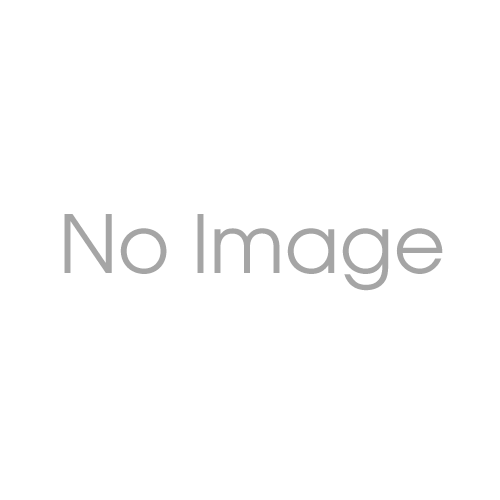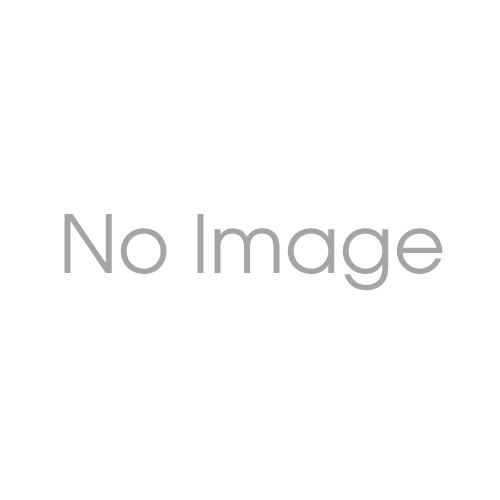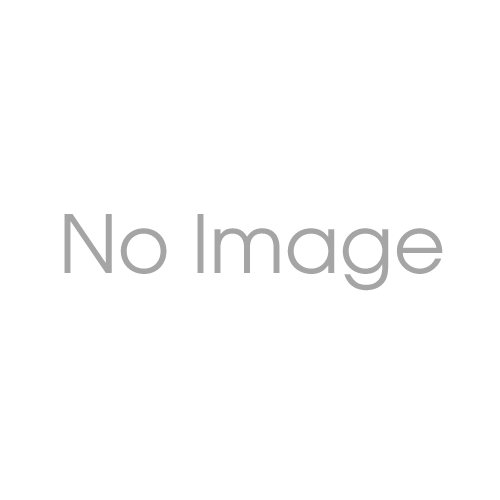営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
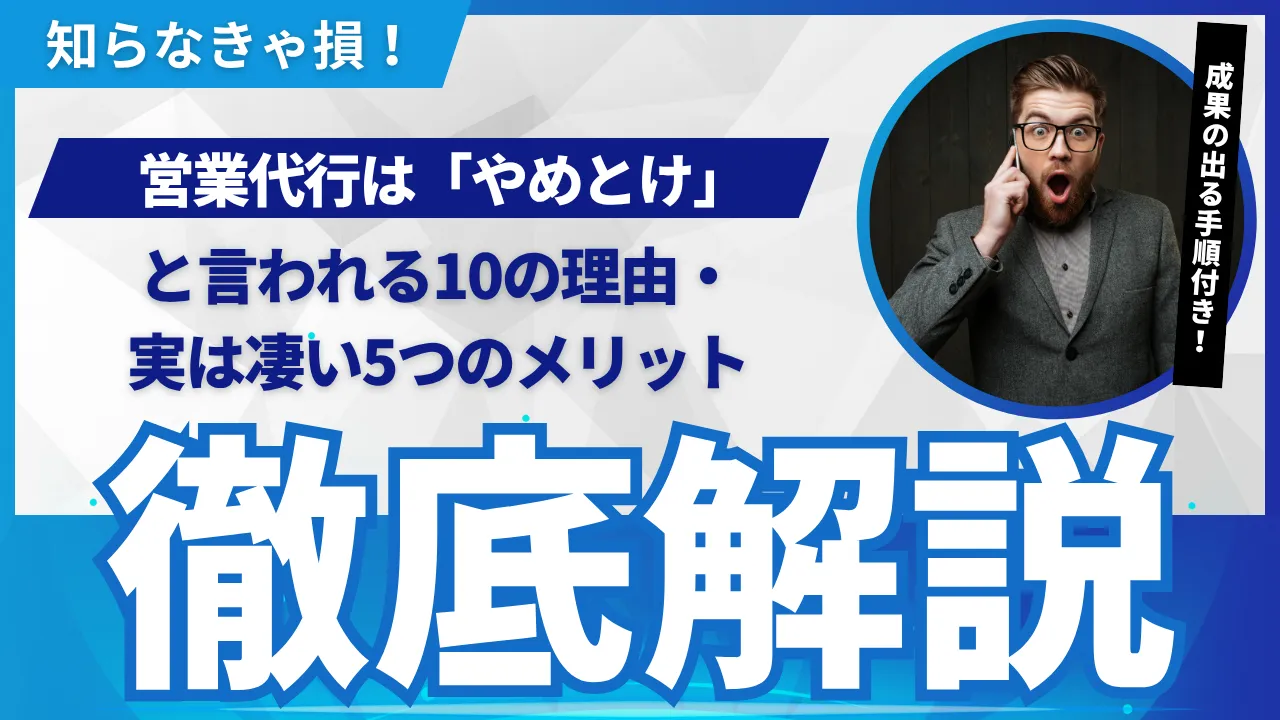
「営業代行、結局“やめとけ”って本当なのか?」
「外注したのにアポが増えない」「社内に何もノウハウが残らなかった」──そんな後悔、他人事ではありません。
実は、正しく選べば“成果直結の武器”にもなるのが営業代行です。
本記事では、よくある失敗パターンから本質的な判断基準まで、営業責任者が知っておくべき全てを解説。
営業代行の「落とし穴」も「強み」も、現場目線で丸裸にします。
・依頼の落とし穴とは?成果が出ない代行の共通点(アポ件数重視、情報連携不足、ノウハウ不在)
・正しく使えば強力な営業エンジンになる理由(短期での成果、柔軟なコスト、一部工程の外注)
・選ぶ際に絶対チェックすべき6つの軸(業界相性、KPI設計、実績)
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
営業代行とは?簡単に(やめとけと言われる前に)
営業代行とは、自社の営業活動を外部の専門組織に委託することで、営業成果を最大化する手段の一つです。
つまり、自社の営業マンが担っていた“リード獲得”や“商談設定”といったプロセスを、プロの代行チームが代わりに担ってくれる仕組みです。
また、自社の人的リソースやノウハウに依存せず、営業成果を生み出す新しい手段として認識されています。
実際、営業代行の多くは、単なる“アポ取り”に留まらず、戦略立案からKPI設計、顧客管理まで一気通貫で支援する体制を持っています。
具体的には
・ターゲットの業種や役職に応じて、リストを最適化する
・テレアポ担当者を増員させ、アウトバウンド型 営業を強化する
・インサイドセールスとフィールドセールスを分業しザモデル型組織を立ち上げる
このように、営業代行会社で必要な知識を改めて整理しておきましょう。
営業代行が注目されている背景について
近年、営業代行が注目される背景には、企業が人材不足や人件費の抑制を求めていることが挙げられます。
また、営業人材を社内で育成するには時間や費用がかかるため、すぐに結果を出したい企業は外注を検討しやすい状況にもあります。
さらに、売り手市場の人材環境や、ITやSaaS業界を中心とした商談スピードの高速化といった外的要因も存在しています。
「採用が追いつかない」「営業教育に時間がかかる」などがその一例です。
また、転職先として「営業職や営業代行会社に興味を持っている人」は是非、最新の知見を深めておきましょう。
営業代行が「やめとけ」と言われる10の理由【丸投げは慎重に】
営業代行は一見便利な外部リソースですが、1ヶ月導入しても「受注につながらなかった」ということを経験した方もいらっしゃるかもしれません。
獲得した商談が曖昧なままとなり「商談ログ」が不透明で、社内と外部の認識に齟齬が生じるケースも稀に起こり得るのです。
また、KPIが「アポ件数」偏重になり、本来追うべき成果からズレてしまうこともあります。
現場では、このようなズレが信頼や売上に直接影響するため、「営業代行はやめとけ」と言われるという一側面があります。
さらに詳しく見ていきましょう。
依頼の仕方によって「アポ件数」ばかり追ってしまう
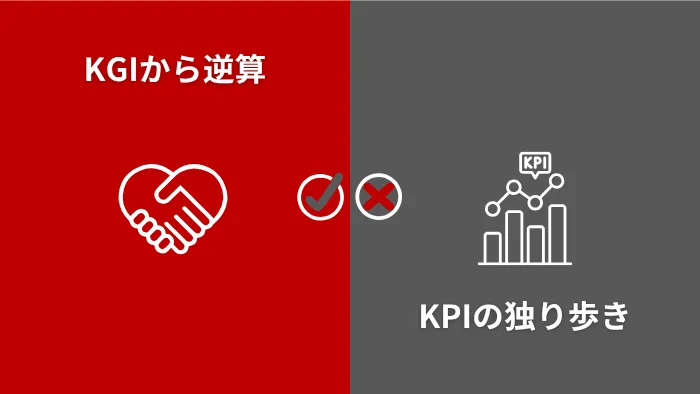
アポ件数は営業活動の“量”を示す指標です。
つまり、商談の質や受注率とは直結しない“表層の数字”とも言えます。
「毎日10件の商談があるのに全く受注できない」「決裁者不在のヒアリングで終わってしまう」そんな営業の違和感、感じたことはありませんか?
実は、KGIとの連動がないままKPIだけが独り歩きすると、“ノルマ達成=成果”という誤解が生まれてしまうのです。
その一例です。
・「ファネル設計を無視してアポだけ増やす」
・「意思決定者への到達率を指標化していない」
アポ数に惑わされず、受注までの“営業プロセス全体”をきちんと営業代行会社とすり合わせて行くことが大切です。
情報連携が不足して、営業組織の課題が見えなくなる
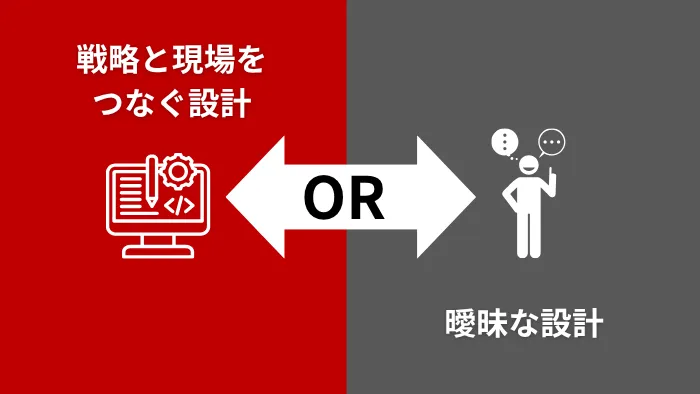
営業代行は、商談獲得やリード創出を外部に委託する手段です。
つまり、自社の営業資源やスキルを補完する役割を担います。
「商談単価が高すぎる」「CV数に対し成約率が低い」そんな営業の悩み、感じたことはありませんか?
実は、こうしたズレは代行側の質ではなく“発注側の設計ミス”でも起きることがあります。
「インサイドとフィールドの連携がない」「ターゲット設計が曖昧」などがその一例です。
設計が曖昧なままだと、社内でも代行業者でもせっかくの成果も売上や見込み顧客の成果に繋がらなくなってしまいます。。
営業代行を使うときこそ、戦略と現場をつなぐ設計に目を向けてみてください。
ツールなし・コミュニケーションなしで頼りすぎると自社にノウハウが残りにくい

営業代行は、自社に必要な営業組織を、金額的にも時間的にも採用コスト・育成のコストをかけずに立ち上げ・拡大をしていく仕組みです。
つまり、短期成果に特化する一方で、自社にスキルや知見が残りづらい特徴があります。
「属人化を脱却したい」「提案トークを体系化したい」そんな営業の悩み、感じたことはありませんか?
実は、代行を頼りすぎると“ナレッジが社内に蓄積されない構造”になってしまうことが多いです。
「提案資料がブラックボックス化する」「商談ログが社内で活用されない」などがその一例です。
より具体的には
・SFAに案件ログと失注理由を一元管理する
・定例MTGでISとFSの商談要点を共有する
営業力を内製化するには、代行から“ナレッジを引き取る設計”が必要になります。
短期成果と並行して、長期視点で自社に残る資産づくりも意識してみてください。
「リードの質」が低く商談化率が上がらないこともあるため
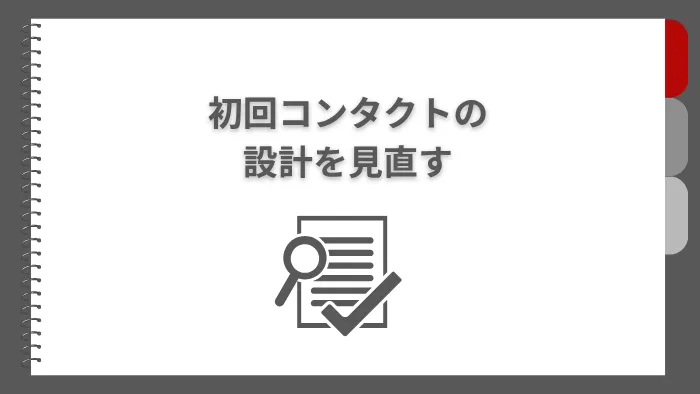
営業で「数は打ってるのに商談が生まれない」と感じたことはありませんか?
原因の多くは、リードの“案件化ポテンシャル”が低いことにあります。
営業代行を使っていても、ターゲティング精度が甘いと、初回接触からズレが生じやすくなります。
現場でよく起きている具体例は以下の通りです。
- 「決裁権のない担当者にアプローチする」
- 「ニーズ顕在前のリストで初回架電する」
- 「名寄せ未対応のリードに重複接触する」
リードは“数”ではなく“質”が成果を左右します。
営業代行とすり合わせるべきは、リード定義とセグメント軸の設計です。
「商談化する前提条件」を明確にした上で、初回コンタクトの設計を見直すだけで、成果は変わってきます。
獲得した商談が「受注に直結しない」こともあるため
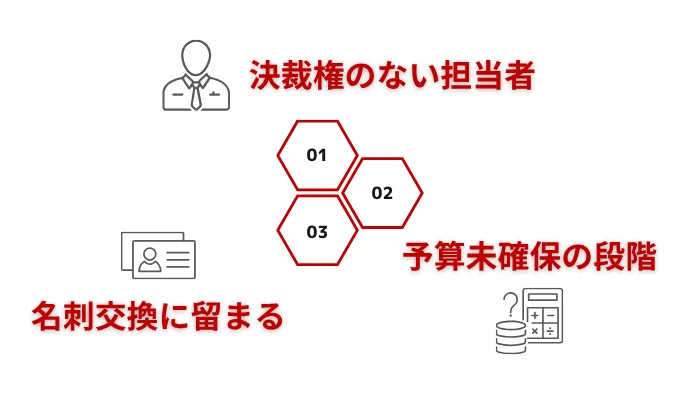
営業で「商談数は増えたのに売上が伸びないのはなぜ?」と感じたことはありませんか?
これは、営業代行が獲得するアポが「決裁権者不在」や「検討フェーズ前」の状態であることが多いためです。
つまり、商談の“質”よりも“数”を優先した結果、受注確度が下がってしまうケースがあります。
現場でよくあるズレは以下のような内容です。
- 「決裁権のない担当者」と話す
- 「予算未確保の段階」で提案する
- 「興味レベル」での名刺交換に留まる
商談数だけで判断すると、営業代行の価値を見誤る可能性があります。
アポの段階で“受注条件”を満たしているかを確認することが、成果への近道になります。
「商談ログ」が不透明で認識の齟齬が発生することがある

営業で「なんで同じ顧客に二重で連絡してしまったんだろう?」と困ったことはありませんか?
それは、営業代行側の「商談ログ」が可視化されておらず、情報の受け渡しにズレが起きやすいからです。
特に法人営業では、認識のわずかなズレが信頼の低下につながるため、商談の記録精度は成果に直結します。
現場でよく起きている具体例は以下の通りです。
- 「過去提案内容」が営業代行内で共有されない
- 「失注理由」がログに残らず次回に活かせない
営業代行を活用する際には、ログの共有方法を事前にすり合わせておくことがポイントになります。
「情報の透明性」を担保することで、無駄なコミュニケーションミスを減らし、スムーズな営業連携が実現しやすくなります。
「オンボーディング」が甘く商材理解が浅いこともある
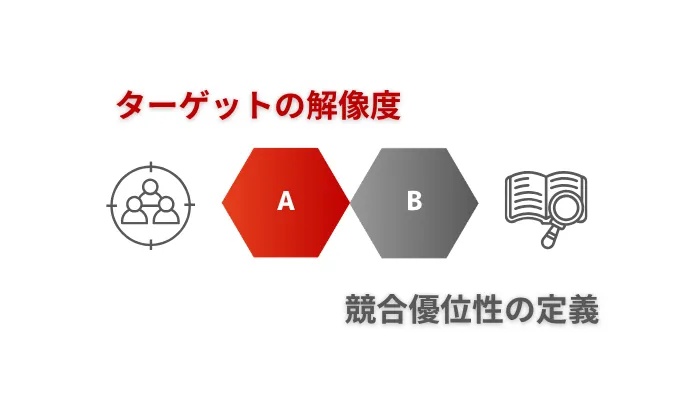
営業代行に「この商材、ほんとに理解できてるの?」と感じたことはありませんか?
初期のオンボーディングが形だけだと、ヒアリングでの深掘りやクロージングにズレが生じやすくなります。
とくにBtoB商材では、導入背景やKPIの設計意図まで把握していないと、相手の意思決定を動かす“本質トーク”ができなくなります。
現場でよくある具体例は以下の通りです。
- 「“導入前の課題”をすり合わせず初回商談に入る」
- 「“活用シーン”を理解せず提案が抽象的になる」
- 「“決裁構造”を把握せず稟議フローを誤る」
営業代行を導入する際は、案件開始前に“ターゲットの解像度”と“競合優位性の定義”を一緒に深掘ることがポイントです。
現場でズレが出たとき、“軸”に戻れる設計をしておくと、提案の説得力がぐっと上がっていきます。
「ヒアリング営業」が上手くできていないこともある

ヒアリング営業とは、相手の課題や背景を深く聞き出し、それに即した提案を行う営業スタイルのことです。
つまり、お客様の“声”を正確に引き出す力が、提案の精度や受注率に直結するということです。
「提案内容がズレる」「ニーズが最後まで不明瞭」そんな営業の違和感、感じたことはありませんか?
実は、ヒアリングの型がないまま商談を進めると、“提案=押し売り”に変わってしまうリスクがあります。
「決裁者の課題を聞き出せない」「現場と経営でニーズがズレている」などがその一例です。
より具体的には
・「営業初回で導入目的とKPIをすり合わせる」ようにする
・「5W1Hを使って現場の業務プロセスを洗い出す」ようにする
このように、“聞く力”を磨くことが、提案の説得力を支える土台になります。
小さな質問の積み重ねが、信頼と受注につながっていきます。
情報漏洩のリスクもある
営業代行は、外部パートナーが見込み顧客に接触し、商談を創出する手法です。
つまり、社外の人間が自社の顧客リストや営業資料にアクセスする状態になります。
「見積根拠が他社に漏れた」「競合に提案内容が流れた」そんな営業のトラブル、心当たりはありませんか?
実は、営業代行では“情報の扱い”が曖昧なまま運用されているケースもあり、機密が外部に出る可能性もゼロではありません。
「業務委託契約がざっくりしている」「営業資料の共有範囲が無制限」などがその一例です。
信頼関係だけに頼ると、意図せず大きな損失に繋がることもあります。
安心して代行を使うために、“情報管理の仕組み”から整えてみてください。
「KPI設計」がずれて現場とズレが生じる
KPI設計とは、営業活動の目標を数値で明確に定義し、達成状況を管理する仕組みのことです。
つまり、営業の現場が“何に向かって動けばよいか”の道しるべを数値で示す作業です。
「訪問件数だけを追う」「商談数だけを評価する」こんなKPI設計、営業で経験ありませんか?
実は、これらは“営業活動のプロセス”と“成果”のつながりが曖昧なKPI設計が原因で、現場が「本当にやるべき行動」に迷う要因になることが多いです。
「アポ獲得数だけを目標にする」「受注金額だけで評価する」などがその一例です。
より具体的には
・リードの質を評価せず、架電数だけを追い続けてしまう
・クロージング率が低いのに、受注数だけでメンバーを評価してしまう
このように、KPIは“現場の意思決定”に直結するからこそ、「行動に落ちる設計か?」を常に問い直してみてください。
営業KPIに迷いがあるときは、いったんプロセスごとに指標を分解してみることをおすすめします。
▼編集部のおすすめ動画を見る
営業の方、特に必見! KGI・KPIの設定方法!
営業代行サービスを利用する【5つのメリット】
短期間で新規の商談件数を増加できる
短期間で商談数を増やすとは、今いる営業人数・工数を変えずに「商談テーブルの母数」を一気に増やす取り組みです。
つまり、営業代行の“初期接点創出力”を借りて、トップファネルを一気に拡張する手法です。
「決裁者にピンポイント架電する」「リード獲得後3時間以内に初回架電する」などがその一例です。
営業代行は、ターゲット設計・KPI管理・スクリプト改善まで一気通貫でPDCAを回せるのが強みです。
より具体的には
・“案件化率”を逆算し、必要アポ数から逆引きする
・SFA連携で商談ステータスを常時可視化する
このように、「人ではなく仕組みで商談を湧かす体制」を、一緒に構築してみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
新規がバンバン増える! アポ獲得率を上げる営業テクニック
営業コストを柔軟に調整できる
営業コストの柔軟な調整とは、固定費になりがちな営業リソースを「可変費化」して、繁閑や戦略に応じて最適化することです。
つまり、成果に応じた“変動費モデル”で、無駄なく営業活動を展開できる状態を指します。
「展示会前後だけ増員する」「新商品ローンチ時だけ短期導入する」などがその一例です。
営業代行は、月単位での稼働調整やKPI連動の報酬設計も可能なため、予算やフェーズに合わせて運用できるのが強みです。
より具体的には
・商談単価ベースでCPA(商談獲得単価)を可視化する
・フェーズ別にKGIと人員設計を連動させる
このように、「固定人件費に縛られない柔軟な営業戦略」を、営業代行と一緒に設計してみてください。
営業の型やナレッジを社内に残せる
営業代行を通じて得られる最大の価値のひとつが、「再現性のある営業の型」や「属人化しないナレッジ」の社内蓄積です。
つまり、成功する営業の動き方や勝ちパターンをチーム全体で共有できるようになるということです。
例えば、「商談トークを可視化する」「失注理由を定量分析する」などがその一例です。
営業代行は、提案資料・トーク・失注理由の整理といった“型化”を徹底するプロセスを伴走してくれるのがメリットです。
より具体的には
・商談録画やCRMメモを使い、トーク改善点を整理する
・成果の出たストーリーをテンプレ化し、新人教育に転用する
このように、成果を生み出した営業の再現パターンを、営業代行と共につくってみてください。
初回アプローチを任せられる
初回アプローチを任せるとは、見込み顧客への“最初の接触”を外部に委託することを指します。つまり、ヒアリング・課題喚起・商談設定までを“分業体制”で進める営業モデルです。
「初回接触が後回しになる」「ターゲットリストはあるが動けていない」そんな営業の悩み、ありませんか?
実は、ファーストコンタクトを社内で回そうとすると、重要度が下がり、結果として“失注予備軍”が増えることが多いです。
「インサイドセールス部門でアポ取りを任せる」「決裁者リストを元に電話で突破する」などがその一例です。
営業代行では、アプローチの型化・KPI設計・トークスクリプトの最適化まで含めて設計できます。
より具体的には
・“商談化率”の高いシナリオで接触する
・“業種別トーク”で共感を引き出す
こうした外部の力を借りて初動を仕組みにすれば、営業は“クロージングに集中”できるようになります。
テレアポのみ等の一部をアウトソースできる
営業代行の強みは、全体ではなく「一部工程だけ」を柔軟に切り出して任せられることです。
つまり、リード獲得や初回接触といった“負荷の高い前工程”を、外部に頼る選択肢があるということです。
例えば、「リスト精査〜アポ設定を代行する」「初回ヒアリングを分業する」などがその一例です。
営業代行は、商談前のプロセスだけを切り出し、KPI設計から実行、検証まで伴走できるのが特長です。
より具体的には
・決裁者に繋がるキーマン架電を集中的に任せる
・営業の稼働を“商談以降”に専念させる設計をする
このように、業務の一部を任せることで、営業全体の生産性を底上げしてみてください。
失敗を防ぐ!営業代行サービスの選ぶ際の6つの判断基準
得意な業界領域と自社がマッチしているか
営業代行の「得意な業界領域」とは、その会社が最も成果を出しやすい市場や業種のことを指します。
つまり、営業代行が経験や知見を多く持ち、営業フローや商習慣に精通している分野のことです。
「営業で成果が出ないのは代行側の力不足?」「そもそもマッチしてない業界を依頼していないか?」と感じたことはありませんか?
実は、成果が出にくい背景には、営業代行と自社業界との“非相性”が潜んでいることが非常に多いです。
「SaaS業界に強い会社に製造業を依頼する」「法人決裁商材を個人営業特化の会社に任せる」などがその一例です。
より具体的には
・営業代行が過去に扱った商材リストを確認する
・決裁者との接点創出力があるかをヒアリングする
このように、まずは「その会社が得意としている業界」と「自社の業界ニーズ」が一致しているかを見極めてみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
上位2割が実践するB2B法人営業の基本戦略 〜会話する相手の選別が鍵〜
KPIの管理体制がしっかりしているか
営業代行における「KPIの管理体制」とは、商談化率や架電件数など、成果指標を正しく設計し、定期的に可視化・改善していく仕組みのことを指します。
つまり、行動量や成果の“見える化”と、改善サイクルがきちんと回っている状態を意味します。
「営業の成果がブラックボックス化している」「活動状況が不透明で改善もできない」そんなモヤモヤ、営業で感じたことはありませんか?
実は、営業代行が機能しない大きな要因は、KPIの粒度が粗すぎたり、管理ツールや報告体制が曖昧だったりすることが根本にあります。
「月次レポートだけで改善点が見えない」「リアルタイムで進捗を共有しない」などがその一例です。
より具体的には
・週次単位でKPI進捗をグラフで可視化する
・Slackなどで即時の状況報告を共有する
このように、KPIをどの粒度・頻度で“管理しているか”を契約前に確認してみてください。
実績・評判が高いか
実績・評判とは、営業代行が過去にどんな成果を出し、誰に評価されたかを示す信用情報のことです。
つまり、案件創出の「再現性」や「汎用性」があるかを見極める判断軸になります。
「SaaSで商談数3倍にした」「決裁者アポ率50%超えた」そんな事例、営業の現場で聞いたことはありませんか?
実は、“実績あり”と言っても、特定業界や狭い商材に偏っているケースも多いです。
その一例です。「SMB向け無形商材でCV率改善」「上場企業向けエンタープライズ商談を連続創出」などが挙げられます。
より具体的には
・支援事例の「業種×成果×KPI設定」を確認する
・担当が「営業目線」で改善提案できるかを確かめる
「実績」ではなく「使える実績かどうか」に注目して、しっかり見極めてみてください。
迅速で丁寧なサポート体制があるか
サポート体制とは、営業代行会社が案件進行中にどれだけスピーディーに、かつ実務目線でフォローしてくれるかを指します。
つまり、トラブル対応だけでなく、日々の「営業PDCA」にどれだけ寄り添ってくれるかが鍵になります。
「リード反応が悪いのに音沙汰なし」「急なFBにも返信は翌日」そんな営業のストレス、感じたことはありませんか?
実は、サポートが形だけで“報告会しか動かない”代行会社も珍しくありません。
その一例です。「毎日のSlackでリード状況を共有する」「商談化率に応じて即トーク改善を提案する」など、運用現場に深く入り込む姿勢が重要です。
より具体的には
・KPIレビューを週次で回してくれるかを確認する
・提案精度よりも、即レス・即修正の対応力に注目する
“対応が早い”は営業で価値が高いです。
どれだけスピード感をもって動いてくれるかを見てみてください。
週次で報告があるか
週次報告とは、営業代行が毎週「KPI進捗」や「打ち手の仮説」を提示する仕組みです。
つまり、成果を“作りながら振り返る”プロセスの土台になります。
「月末にレポートがまとめて届く」「数値だけで改善策がない」そんな営業、現場で感じたことありませんか?
実は、週次が抜けるとPDCAが止まり、“改善の打ち手”がズレやすくなります。
「失注理由を週次で分析する」「獲得リードの質を比較する」「ネクストアクション仮説」を毎回提案するなどがその一例です。
数字の“意味”まで共有できる営業代行かどうか見てみるのも良いでしょう。
商談化まで対応してくれるか
商談化対応とは、営業代行がリード獲得だけでなく「アポ取得後の接続」まで担う支援のことです。
つまり、見込み顧客を“案件化”させるまでを伴走する設計です。
「アポは入るが受注につながらない」「初回商談が温度低すぎる」そんな営業、現場で感じたことはありませんか?
実は、商談化の質は“事前のヒアリング設計”と“初回アプローチ”で8割決まることが多いです。
「興味喚起で終わるリードを精査する」「温度感別にフォロー設計を変える」「BANT条件の確認」まで代行側が行うなどがその一例です。
“商談化”まで、責任を持って巻き取ってくれる営業代行かどうか見極めてみるのも良いでしょう。
営業代行会社を上手く活用して自社で成果を出す!4つの手順
まずは商材や顧客の課題をインプットする
新しい営業代行先で成果を出すには、最初の“情報収集フェーズ”がカギになります。
ここで言うインプットとは、「商材の強み」と「顧客の困りごと」を“ズレなく理解する”ことです。
ポイントは、「誰が・なぜ・何に困っているか」を具体的に言語化して、提案の軸をつかむこと。
よくあるのは、「カタログに書いてある特徴」をそのまま覚えて満足してしまうパターンです。これだと“顧客が本当に欲しい提案”に届きません。
例えば、「月額コストが安いSaaS」でも、ターゲットが求めているのは“導入後に楽になる運用フロー”だったりします。
具体的には、
①商材の導入事例を3件以上読み、
②顧客インタビューやFAQから“現場の言葉”を拾い、
③競合との違いを自分の言葉で説明できるように整理します。
まずは、相手の課題を“自分の頭でかみ砕いて”から会話を始めてみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
顧客の課題を引き出すコツは情報提供から!元リクルートNo.1
成果が出てる人のトークを真似る
現場で成果を出している先輩のトークには、成果が出る“理由”が隠れています。
ここでいう「真似る」とは、単なる言い回しのコピーではなく、“なぜその言い方をしているか”まで読み取って実践することです。
ポイントは、「流れ」と「間の取り方」も含めて、言葉のリズムごと体に染み込ませること。
よくある間違いは、トークの“型”だけを借りて自分のキャラや顧客の状況に合わせないまま話してしまうことです。これだと、逆に不自然に聞こえてしまうこともあります。
例えば、
①録音を聞いて、どの場面でどんなワードを使っているかをメモし、
②実際に声に出して何度もなぞる、
③その後、自分の商材やスタイルに合うように一部を調整して取り入れていきます。
まずは、“そのまま言ってみる”をスタートに、体に馴染ませる感覚を持ってみてください。
毎日の数字を自分で振り返る
まず最初に、自分の数字を「毎日」見返す時間を、あえて5分でもいいので固定化してみてください。
数字を振り返るとは、単に売上やアポ数を見るだけでなく、「何ができたか」「どこが惜しかったか」を確認する行為です。
ポイントは、「感情を入れずに事実だけ」を拾うことと、「次の一手につながる仮説」を立てること。
よくあるのは、数字が良くない日に自分を責めてしまい、行動が鈍るパターンです。数字を感情評価に使うと、振り返りの効果は落ちてしまいます。
具体的には、「午前は3件電話して1件話せた。話せた相手は◯という反応だった。午後は◯件回ったが決裁者不在が多かった」など、動きと反応をセットで書き出します。
一日の終わりに、今日の動きと数字を1行メモしてみてください。それだけで、翌日の打ち手が自然と見えてきます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
営業必見】少ない経験から最大限学ぶ振り返りの技術 | トップセールスが語る成功の秘訣
高速で PDCA を回す
まずは「完璧を目指さず、早く試して早く直す」を意識して動き出してみてください。
PDCAとは、計画(Plan)→実行(Do)→振り返り(Check)→改善(Action)のサイクルですが、営業現場で成果を出すにはこの回転スピードが鍵になります。
ポイントは、「1週間単位ではなく、半日〜1日単位で回すこと」と「仮説を“軽く”持っておくこと」です。
よくあるのは、完璧なトークを練ってから動こうとするケース。結果、動きが遅くなり、改善のチャンスを逃してしまいます。
例えば、「午前はこの切り口でトークして、午後に反応を比べてみる」と決めて小さく実験して、夕方には次の仮説にアップデートしていきます。
うまくいかなくてもいいので、まずは「今日中に1つ試して、夜に1つ直す」を習慣にしてみてください。気づけば改善の精度もスピードも上がってきます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
高速なPDCAサイクルで経験値が貯まるクーリエの営業
営業代行会社選びでお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「法人営業をがんばっているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
いざ探しはじめても、各社の違いが分からず、選んだあとに「思っていた支援と違った…」と後悔してしまう方も少なくありません。
営業は売上に直結する重要な業務。だからこそ、相性や実績、体制など、見極めるべきポイントは想像以上に多いのです。
スタジアムでは、営業戦略の立案から実働までを一貫で支援し、商材ごとに専任担当が伴走します。
特にIT・Web領域に強く、これまで多くの成果を積み上げてきた営業のプロが在籍しています。
「どの会社が自社に合うのか分からない」「具体的な比較の軸が欲しい」といった段階でも、まずは気軽にご相談ください。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き
【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説
営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順
【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版
インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集
営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文
【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全
【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集
【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!
アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説
【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略
【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説
法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略
【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説
深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順
営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善
13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド
営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション
営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順
【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版
【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集
営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド
営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別
【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果
【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順
【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順
【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点
営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順
【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド
【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き
営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順
できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法
売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法
プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順
【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き
営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策
【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説
【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説
なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術
新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順
営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説
なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法
ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP
ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集
飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法
【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド
【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版
セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法
セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド
新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版
新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全
【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説
新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ
新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法
【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版
【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集
アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法
インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順
【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版
【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法
SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法
MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説
BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法
BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略
BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順
【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版
【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ
【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説
営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選
FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド
【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方
14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順
アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ
シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ
これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順
【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集
【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP
【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説
営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ
御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP
【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順
【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集
営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法
営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順
27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場
【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順
営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準
新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル
営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント
クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順
営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説
営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順
営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順
最終更新日