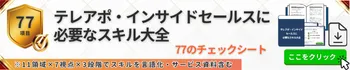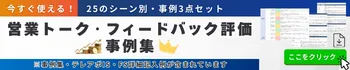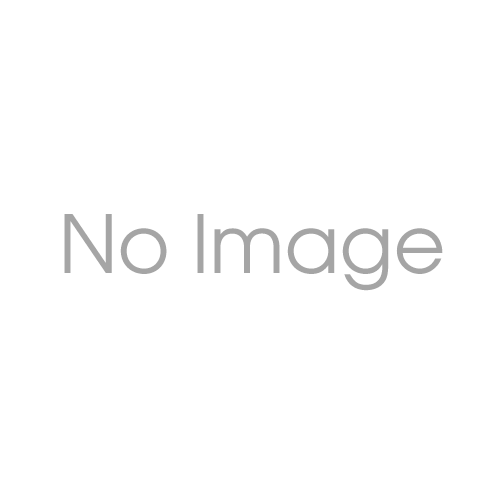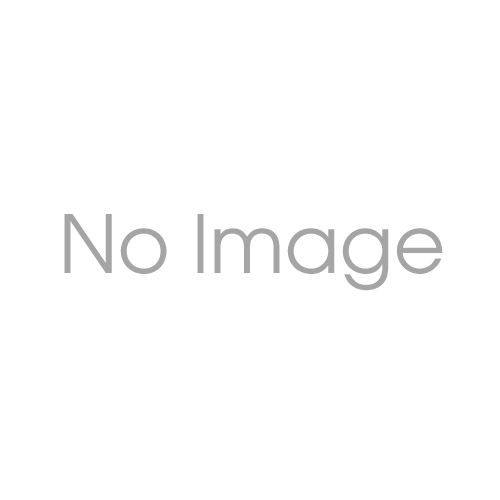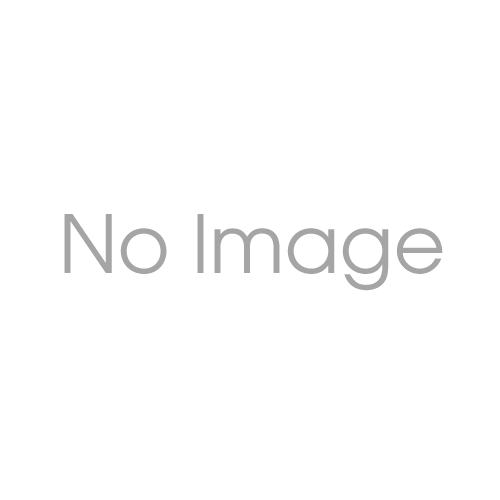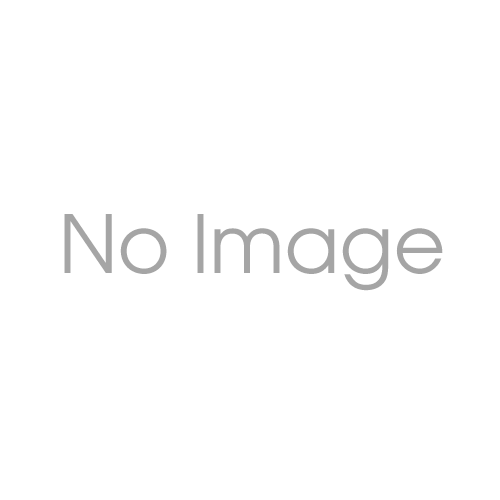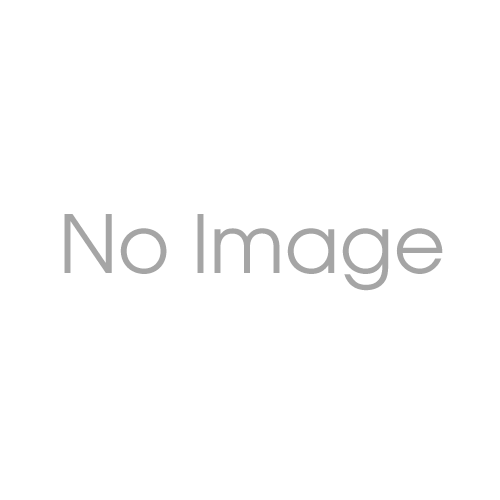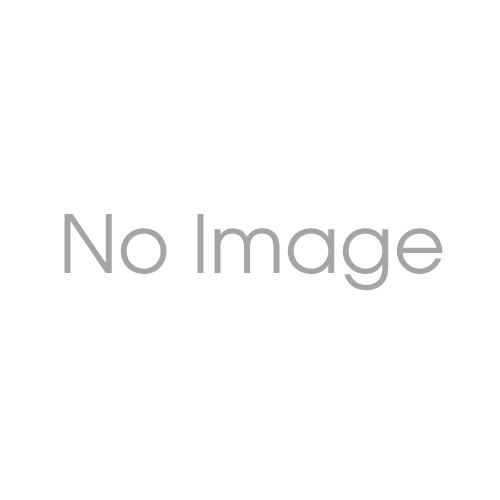【11の目的別×7シーン】営業のヒアリング質問項目テンプレート完全保存版
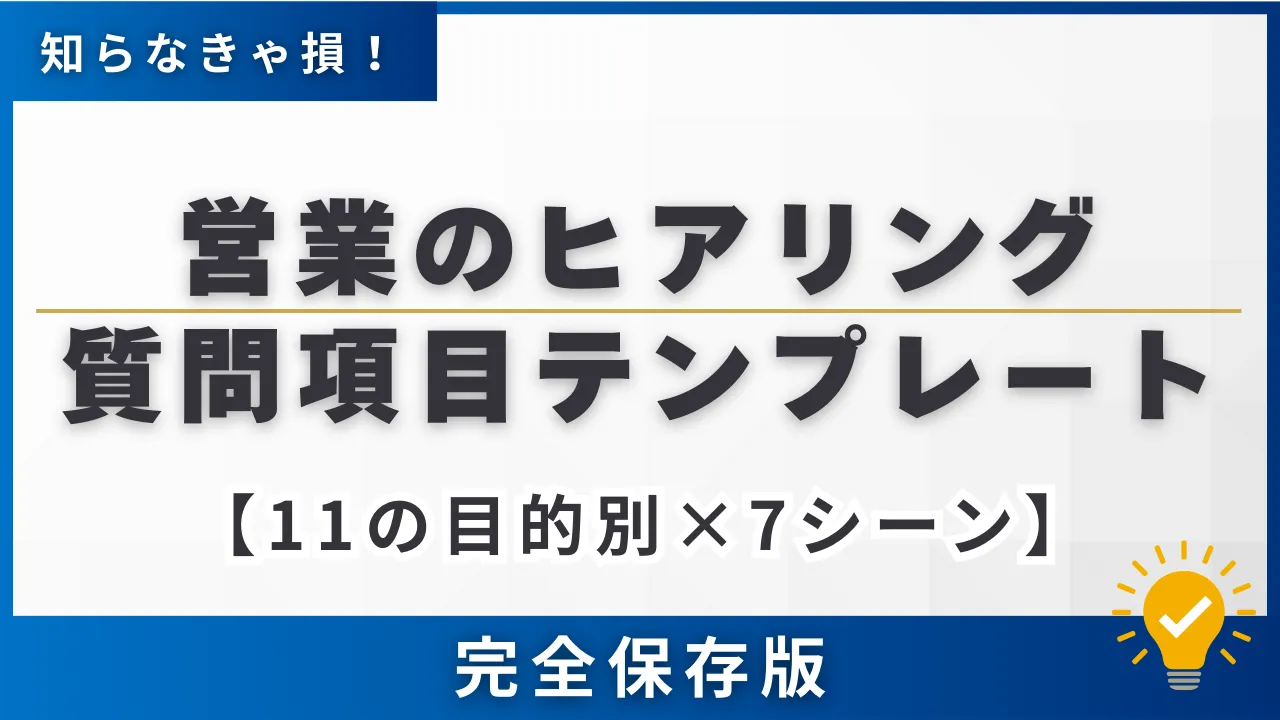
「“ヒアリングって、結局いつも手応えがない…”」
「どこまで聞いていいのか分からない」「深掘りできずに終わってしまう」──そんな悩み、営業現場では珍しくありません。
でも実は、少しの工夫で“聞き方”は大きく変わります。
本記事では、現場ですぐ使えるヒアリング質問を【目的】【活用シーン】【良い質問の条件】の3つの切り口で具体的に紹介。
相手の本音を引き出し、提案に直結する“効くヒアリング”を身につけましょう。
・11の目的別!営業のヒアリング質問項目テンプレート(雑談/業務フロー/課題/KPI)
・7つのよくあるシーン別で有効な聞き方!ヒアリング質問項目テンプレート(背景/本音/現場感/経営課題)
・営業成果を左右する!成果の出る営業ヒアリング質問の9つの条件(答えやすさ/緊急度/真因)
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
【11の目的別】営業のヒアリング質問項目テンプレート
「今いちばん困っていること」に真っ先に触れる
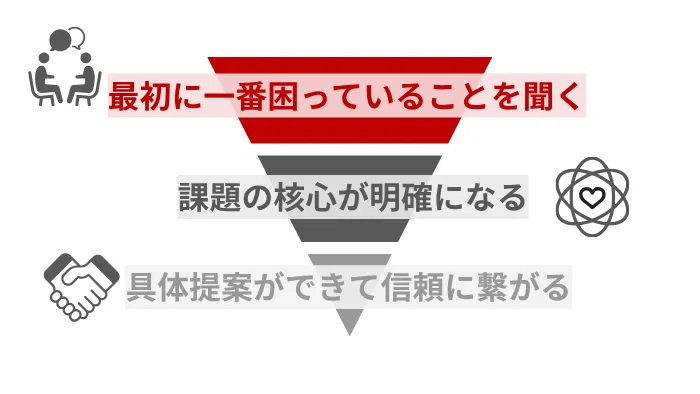
商談の最初に「いちばん困っていること」を聞くと、相手の言葉で課題の“核心”が明確になります。
遠回りせず、最も熱を持っている部分から話せるため、こちらの提案にもリアリティが生まれ、信頼の立ち上がりが早くなります。
あれこれ聞く前に、真っ先にここに触れることで、会話の温度が一気に上がります。
テンプレート例文
さっそくですが、〇〇について、いま一番「正直困っているな」と感じることって何かありますか?
↓(返答)
なるほど、〇〇が毎回ネックになると、現場の方もかなりストレス感じてますよね。
↓(業務感覚に寄り添う)
たとえば他社さんでは、同じ〇〇の部分を〇〇に変えただけで、1週間の工数が3割減った事例があります。
↓(興味が乗ったタイミングで提案)
もしよければ、御社の状況に近いパターンを簡単にまとめた資料があるので、5分ほどで共有できます。いかがでしょうか?
この一連の流れは、「何から話すか」でその後の商談の温度が決まることを意識した組み立てです。
いきなり核心に触れることで、共感と具体提案のスピードが一気に加速します。
「予算の決まり方」をやんわり確認する
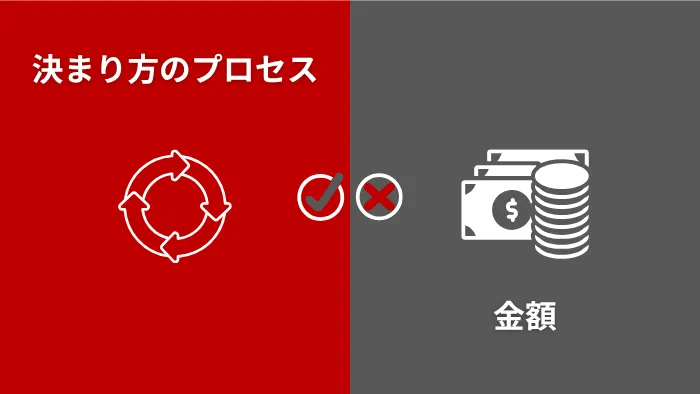
予算の話はデリケートですが、タイミングと聞き方を工夫すれば自然に引き出せます。
ポイントは、「今すぐ使えるお金があるか」ではなく、「社内でどう通るのか」という流れを一緒に確認するスタンス。
金額ではなく“決まり方のプロセス”に焦点を当てることで、相手も安心して本音を話しやすくなります。
テンプレート例文
〇〇のご相談を伺っております○○株式会社の△△です。〜サービス説明〜ちなみに、こういった〇〇の取り組みって、社内ではどういう流れで検討・決裁されることが多いですか?
↓(返答)
ありがとうございます。たとえば、〇〇部門で決裁が完結される感じなのか、それとも一度どこかで稟議に上がるような形になりますか?
↓
過去に似たご検討があった場合、だいたいどれくらいのタイミングで「金額感を調整する」ようなフェーズになるか分かれば、その時期に合わせたご提案も可能です。
↓
ちなみに、同じ業界の〇〇社様は「最終的に役員会で通す必要がある」という流れが事前にわかったことで、提案内容も段階的に整理してスムーズに決まりました。もしよければ、そちらの進め方を5分ほどでご紹介できますが、いかがでしょうか?
この会話のコツは、金額ではなく「決まり方」にフォーカスすること。
聞きにくいことほど、プロセスの“確認”という形に変えて、やんわり聞く姿勢が信頼につながります。
「アイスブレイクや雑談」で心を開いてもらう
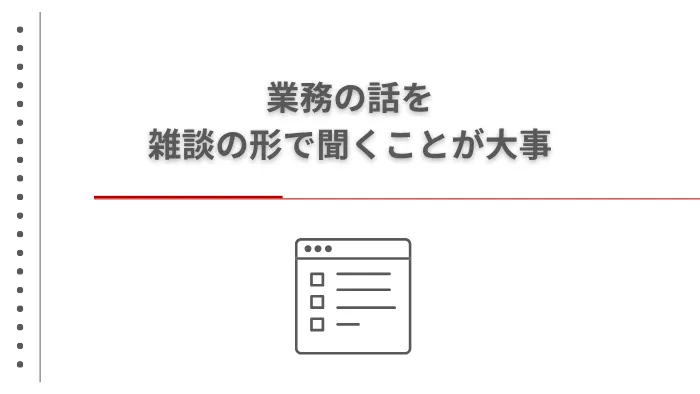
最初の5分で空気が決まります。商談の前に「一緒に話すと気持ちがいい」と思ってもらえるかどうかが、その後の会話の質を大きく左右します。天気や業界トレンドの話ではなく、「相手の文脈」に合わせた雑談ができるかがカギです。雑談も立派な営業の技術。共通点を探すのではなく、“相手が話したくなる余白”をつくることが大切です。
テンプレート例文
〇〇の件でお時間いただいております○○株式会社の△△です。〜サービス説明・日程調整〜今日はこの後もお打ち合わせ続きですか?最近、本当に皆さん忙しそうですよね。
↓(返答)
そうなんですね。ちなみに、最近の〇〇って、現場的にはどんな感じですか?お客様ごとにかなり違うって聞いてまして。
↓
実は先週も同じ業界の方とお話したんですが、「〇〇が大変で…」って話が出ていて。御社ではどうですか?やっぱり似たような感じですか?
↓
なるほど、やっぱりそうなんですね。ちなみに皆さんどんな工夫されてるんですか?もし差し支えなければ、ちょっと参考にさせてもらえたら嬉しいです。
この会話のポイントは、「業務の話を雑談の形で聞く」こと。形式ばらず、共感から入って相手のリズムに合わせることで、本音が出やすい空気をつくることができます。
「他に見ている会社」をストレートに聞く

競合他社の情報は営業の生命線です。遠回しに聞くより、「他にも検討されている会社があれば教えてください」とストレートに質問する方が、お客さまも答えやすく感じるかもしれません。
テンプレート例文
今回の〇〇導入にあたり、他にも検討されている会社があれば教えていただけますか?差し支えない範囲で構いません。
↓(競合名を教えてくれた場合)
ありがとうございます。〇〇社さんは確かに実績のある会社ですね。弊社との違いで言うと、〇〇の部分で特に差別化できる部分があります。
↓(具体的な違いを聞きたい場合)
〇〇社さんは〇〇が強みですが、弊社は〇〇業界に特化した〇〇機能で、御社のような〇〇課題に対してより具体的なソリューションをご提供できます。
↓(比較検討段階)
もしよろしければ、〇〇社さんとの提案内容を簡単に比較できる資料をお作りしますが、いかがでしょうか?
このトークのポイントは、競合を否定せずに「違い」を明確にすること。お客さまが比較しやすい環境を作ることで、自社の優位性が自然と伝わる可能性があります。
「業務フロー」を聞いて日常のリアルを知る

表面的な課題ではなく、実際の業務フローを聞くことで真の問題点が見えてきます。「一日の流れを教えてください」という質問から、お客さまの本当の困りごとを発見できるかもしれません。
テンプレート例文
〇〇業務について、実際の一日の流れを教えていただけませんか?朝一番から〇〇時頃までの具体的な作業内容を知りたいです。
↓(業務フローを説明してくれた場合)
なるほど、〇〇の作業に毎日〇時間もかかっているんですね。その中で一番手間に感じる部分はどちらでしょうか?
↓(具体的な課題が見えた場合)
〇〇の集計作業だけで〇時間というのは確かに負担ですね。弊社の〇〇を使えば、その作業を〇分程度まで短縮できる可能性があります。
↓(解決策への関心を示した場合)
実際に〇〇社様でも同じような課題があり、導入後は〇〇業務が〇%効率化されました。御社の現在のフローに合わせたデモをお見せできますが、いかがでしょうか?
このトークのポイントは、業務の「時間軸」で質問すること。数字で具体化することで、改善効果をお客さまがイメージしやすくなります。
「失敗経験」から導入の地雷を見抜く
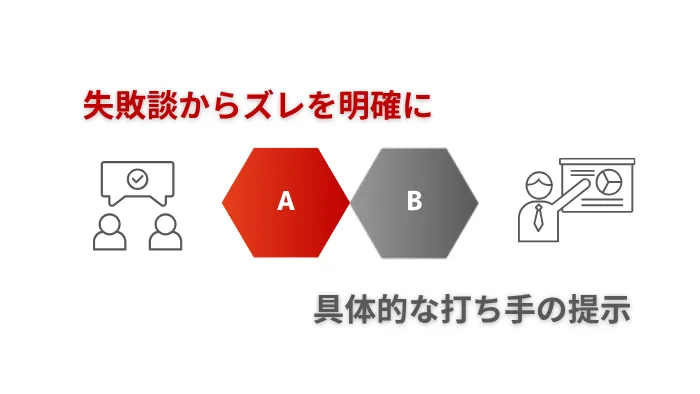
お客さまが過去に直面した「失敗経験」には、導入時の懸念や“見落としがちな地雷”が潜んでいます。その原因と背景を丁寧に深掘りすることで、「今回は同じ轍を踏まない」ための具体策を一緒に考える流れが自然に生まれます。事前に共有してもらうことで、導入時のハードルを先回りして取り除くことが可能になります。
テンプレート例文
〇〇の導入支援を行っております○○株式会社の△△と申します。〜サービス説明〜これまで類似のサービス等をご検討されたことはございますか?差し支えなければ、過去に〇〇のようなサービスを導入や検討された際、どんな点でご苦労があったか教えていただけますか?
↓(失敗談を共有してくれる)
ありがとうございます。たとえば「導入後に現場の使い方が浸透しなかった」といった背景がある場合、弊社では最初の2週間で現場向けトレーニングを短時間×高頻度で実施しております。
↓
さらに、以前〇〇で失敗されたお客さまには、「現場の声を毎週拾う仕組み」も併せてご提供し、1ヶ月後には利用率が9割を超えた事例もございます。
↓(導入後をイメージ)
今回の導入においても、過去の〇〇の失敗を踏まえて、同じことが起こらないように進めてまいりますので、どうぞご安心ください。
このトークのポイントは、「過去の失敗=導入前の設計ミスや運用のズレ」と捉え、そこに対する“具体的な打ち手”をセットで提示すること。
お客さまの不安を「今回は違う」という確信に変えることで、信頼が大きく深まります。
「理想の導入後の姿」を一緒に描く
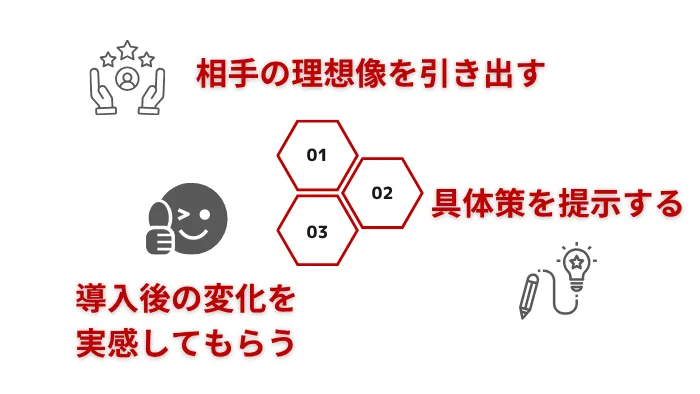
「導入すること」が目的ではなく、「導入後にどうなりたいか」を一緒に具体化することで、提案の軸が明確になります。お客さま自身がゴールを言語化できていない場合も多いため、会話の中でイメージを整理してあげることが営業の価値になります。「何が・いつ・どれだけ変わるか」を共に描くプロセスが、導入への納得感を高めます。
テンプレート例文
御社では〇〇導入後、どのような状態になっていたら理想的だと感じられますか?具体的にどの部署のどなたが、どうなっていることを目指しているのかをしっかり把握させていただきたいと思っています。
↓(理想の状態を話してくれる)
ありがとうございます。「営業が資料作成に追われず、提案に集中できる状態」というお話を受けて、たとえば導入から2週間で既存資料のテンプレート化と自動出力を実現できます。
↓
実際に、同じような課題をお持ちだった〇〇社さまでは、3ヶ月後には提案準備の工数が半分になり、月あたり20時間以上の業務改善につながっています。
↓(自社にも当てはめて想像)
御社のチーム体制や業務フローに合わせた最適な導入ステップもご提案できますので、5分ほどで全体像を共有させていただければと思うのですが、いかがでしょうか?
このトークのポイントは、「理想像を本人の言葉で引き出す」ことと、「それを実現できる具体策」を即座に提示すること。導入後の変化を“自分ごと”として実感してもらえるようにするのが肝心です。
「決裁者は誰か」を会話の中でつかむ
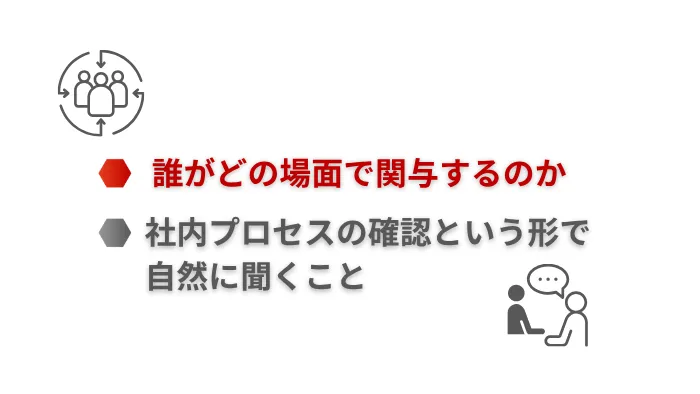
決裁者を直接聞くと壁ができやすいため、「役割」や「社内プロセス」の話から自然に確認するのがポイントです。会話の中で“誰がどの場面で関与するのか”を探り、決裁構造を把握することで、提案の質とスピードが格段に上がります。
テンプレート例文
お話を進める際、御社内で〇〇のご判断はどなたが主に関与されることが多いでしょうか?
↓(返答)
ありがとうございます。ちなみに、〇〇のようなシステム導入だと、現場の方と一緒に部長クラスの方もご検討に入られるケースが多いのですが、御社ではいかがでしょうか?
↓
なるほど、そうなんですね。念のため確認なのですが、最終的に〇〇の導入可否をご決定されるのは、〇〇部長か〇〇本部の方になるイメージでお間違いないでしょうか?
↓
承知しました。では次回、ご判断に関わる〇〇様にも共有できるよう、〇〇の費用対効果や導入後の運用案まで整理した資料を準備して伺いますね。
このトークのポイントは、「誰がどの場面で関与するか」を相手に無理なく語ってもらえるよう“社内プロセス”の確認という形で自然に聞くことです。決裁者に直接当たる前に、話が通るルートを丁寧に描くことが成功へのポイントです。
「導入のタイミング」を探る
「いつから使いたいのか」「なぜその時期なのか」を雑談の中で引き出すことで、お客さまの本気度や社内事情が見えてきます。無理に聞かず、“業務スケジュールとの関係性”を軸にすれば、自然な流れで導入のタイミングを知ることができます。
テンプレート例文
もし仮に〇〇を導入されるとしたら、御社ではどのくらいの時期にスタートできると理想でしょうか?
↓(返答)
ありがとうございます!たとえば繁忙期などがある場合、導入のご準備は〇〇前の◯月頃がちょうど良いと伺うことも多いのですが、御社はいかがでしょうか?
↓
なるほど、そうなんですね。ちなみに、社内稟議やご調整も含めると、実際のご決定までは◯週間〜◯ヶ月ほど見ておいた方が良さそうでしょうか?
↓
承知しました。では◯月頃の稼働に向けて、◯月中にはご提案内容を固め、社内でご検討いただけるようなスケジュール感で動かせればと思います。資料もそれに合わせてご準備いたしますね。
このトークのポイントは、「スケジュール感」を会話の中で共有しながら、お客さまのペースと自社の提案タイミングをすり合わせていくことです。導入の時期感がわかると、逆算で次の打ち手が組み立てられます。
「比較ポイント」を明確にして刺さる提案につなげる
比較の軸がわからないまま提案しても、ピントはなかなか合いません。「何を重視しているか」を早い段階で聞き出せれば、相手の頭の中に沿った提案ができます。特に“どこで迷っているか”を探ると、提案は一気に具体的になり、他社との違いが伝わりやすくなります。
テンプレート例文
今回〇〇を選ばれるうえで「ここは外せない」というポイントってございますか?
↓(返答)
ありがとうございます。お客さまによっては「サポート体制」や「使いやすさ」で比較されるケースもあるのですが、御社ではどんな点が判断基準になりそうでしょうか?
↓
なるほどです。たとえば御社のように〇〇の運用を現場で回される場合、「誰でもすぐ使えるか」「トラブル時にすぐつながるか」は特に大事なところですよね。
↓(他者との違いも教えて欲しい)
では、他社との違いが伝わるように、〇〇の操作性や実際のサポート対応まで含めて、比較しやすい形でご提案をまとめてまいります。
このトークのポイントは、「どこで迷っているか」を会話の中で探りながら、相手の選定基準を言語化してもらうこと。聞いた瞬間に、「この人、わかってるな」と感じてもらえる空気がつくれます。
【7つの活用シーン別】営業のヒアリング質問項目テンプレート
初回商談では「背景」と「温度感」をまず拾う
初回商談では、相手の「導入背景」と「温度感(どれくらい前向きか)」を丁寧に拾うことが、次の打ち手を決める最大のヒントになります。相手の置かれている状況や、課題の認識度合いを把握することで、解決策の提案にリアリティが生まれます。ここで温度を見誤ると、的外れな提案になり、失注リスクが一気に高まります。
テンプレート例文
はじめまして、〇〇のご支援をしております○○株式会社の△△と申します。改めて本日はお時間をいただきありがとうございます。いただいたお時間をぜひ有意義なものにさせていただきたくてお伺いしたいのですが、まずは、今回〇〇にご興味を持たれた背景から伺ってもよろしいでしょうか?
↓(実は上司から言われて…)
ありがとうございます。そのご状況、私たちも他社様でよく耳にします。ちなみに、今回の〇〇については、現場で具体的に「こんな課題がある」という声は出ていたりしますか?
↓(課題感はあるけど、まだ比較段階で…)
なるほど、比較段階とのことでしたが、導入のご検討自体はいつ頃までにというイメージがございますか?
↓(急いでるわけじゃないけど…)
承知しました。ちなみに、同じようなご状況だった〇〇業界の○○社様は、事前に1時間ほど現場部門のヒアリングを行うことで、スムーズに導入判断が進みました。よければ、御社向けにその進め方の概要を5分ほどで共有できますが、いかがでしょうか?
このトークのポイントは、「背景(なぜ今)」「温度感(どれだけ本気か)」を分けて確認すること。営業側の仮説ではなく、相手のリアルな足元の事情を聞くことで、ズレない提案ができるようになります。
オンライン商談では「リアクション」から本音を探る
オンライン商談では、対面と違って空気感や反応が伝わりづらいため、相手の「ちょっとした間」や「反応のトーン」に意識を向けることが、本音を引き出すカギになります。とくにカメラ越しの頷きや沈黙、言葉の選び方から、興味・懸念・温度感がにじみ出る瞬間があります。相手の表情や間合いを見逃さずに、その都度さりげなく言葉を添えることで、相手の本音に近づけます。
テンプレート例文
〇〇の活用についてご説明させていただきましたが、今のお話を聞かれて率直にどう感じられましたか?
↓(画面越しに少し間がある)
ありがとうございます、今、少し考えるお時間を取られていたように感じたのですが、どこか気になる点や「本当に使えるのかな」と感じた部分などございますか?
↓(そうですね、実は●●が…)
教えてくださってありがとうございます。実はそこ、多くの企業様でも最初に不安視されるポイントでして、〇〇を使った実際の改善事例がございます。
↓(それは気になります)
では、もしよければそちらの事例をベースに、御社向けの活用シーンを整理して、5分ほどでご案内を後ほど追加させていただきますね。
このトークのポイントは、「反応の小さな揺れ」に言語で寄り添うこと。相手の“言ってない本音”に言葉をかけられるかどうかが、オンライン商談の質を決める分かれ道になります。
訪問時は「現場の違和感」に気づいて質問する
訪問商談ならではの最大の強みは、実際の“現場の空気”を五感で感じ取れることです。商談前後の社内の雰囲気や、ホワイトボードのメモ、机の上に積まれた紙資料、張り出された掲示物などに目を配ることで、相手も言語化しきれていない「リアルな課題」に先回りできます。その“違和感”に自然に触れながら質問を投げかけると、ぐっと本質的なヒアリングにつながります。
テンプレート例文
先ほどエントランスのところで〇〇の掲示がされていたのを拝見したのですが、あれはどのような背景があって始められたものなんでしょうか?
↓(ああ、それ実は…)
ありがとうございます、なるほど、そういった取り組みをされているということは、やはり〇〇に課題感をお持ちだったご経緯があるのでしょうか?
↓(実は現場の〇〇がうまくいってなくて…)
そうだったのですね。ちなみに今、その〇〇については、皆さまどのように対応されているんですか?
↓(そこが属人的になってて…)
実は、同じような状況で〇〇を導入された○○社様では、現場のフローを整理してから週次で振り返る仕組みを入れることで、業務のムラが解消されたという事例もございます。御社にも合うかもしれません。
このトークのポイントは、「目で見える情報」から話を切り出すことで、相手も自然体で“言葉にしていなかった課題”を話しやすくなるということです。気づいたことを素通りせず、丁寧に問いかけてみる姿勢が信頼につながります。
エンジニア相手には「要件」を先に
エンジニアに提案する際は、抽象的な話よりも「要件定義がどこまで進んでいるか」を早めに言語化することで、話が噛み合いやすくなります。前提条件・システム連携・運用負荷などの項目を先に整理し、共通認識を持つことで、話のブレが減り、導入の是非をスムーズに判断してもらいやすくなります。
テンプレート例文
〇〇のご提案を担当しております○○株式会社の△△と申します。まず、〇〇の導入にあたり、御社で現在想定されている要件について少し整理させていただければと思っております。
↓(どうぞ)
ありがとうございます。たとえば〇〇との連携要否や、〇〇で処理するデータの種類・件数、ユーザー数など、現時点でお聞かせいただける範囲で問題ございません。
↓(そこは検討中です)
承知しました。よろしければ、他社様でよく検討材料にされている〇〇(例:CSV連携の有無、運用部門との役割分担、セキュリティの条件)など、チェックリストベースで初期設計のヒントを共有できます。
↓(ぜひお願いします)
ありがとうございます。それではまず「現在お使いの〇〇と今回の〇〇の関係性」から整理し、最短で現場にフィットする導入案を一緒に作らせていただければと思います。
このトークのポイントは、「要件定義の解像度を営業側から能動的に引き上げること」。エンジニアは抽象論よりも具体条件の整理に価値を感じるため、先回りして論点を言語化することが信頼獲得の鍵になります。
検討後半は「導入のイメージ」を言葉にしてもらう
商談が後半に入ったら、相手に「導入後の利用シーン」を自分の言葉で語ってもらえるかがカギになります。頭の中でしか想像していない状態では、決裁に踏み切りにくいため、どの部署で・誰が・どのように使うかを一緒に言語化することで、一気に導入の現実味が増します。
テンプレート例文
〇〇のご提案をしております○○株式会社の△△です。ここまでのご説明を踏まえて、もし〇〇を導入するとしたら、どの部門やどなたが最初に使い始めそうでしょうか?
↓(たぶん〇〇部ですね)
ありがとうございます。ちなみにその〇〇部では、現状〇〇の作業はどのように行っていらっしゃいますか?
↓(Excelで手作業してます)
なるほどです。では仮に〇〇を導入いただいた場合、初月は〇〇部で既存のフローと並行稼働しつつ、2ヶ月目には完全移行…といった段階的な運用も可能です。
↓(その進め方なら現実的ですね)
ありがとうございます。他社様でも「最初に一部門だけで試し、次に展開」の形が多く、社内調整もしやすいとのことでした。導入ステップを1枚にまとめた資料もございますので、よければお送りします。
このトークのポイントは、「相手の頭の中にある“想定利用シーン”を引き出すこと」。その上で、営業側から一歩踏み込んだ「現実的な導入ステップ」を見せることで、決裁者が“今動く理由”を納得しやすくなります。
決まりかけたら「競合の印象」をあえて聞いてみる
クロージング直前では、あえて「他社サービスの印象」を聞くことで、最後に残る迷いや不安の正体を引き出すことができます。競合と比較されているからこそ、お客さまの中には“言語化されていない判断軸”が残っているケースが多く、そこを丁寧に聞き出すことで、一歩踏み込んだ意思決定につながります。
テンプレート例文
〇〇のご提案を担当しております○○株式会社の△△と申します。お話も最終段階かと思いますが、念のため、他社さんの〇〇についてどんな印象をお持ちか、率直に伺ってもよろしいでしょうか?
↓(感想)
ありがとうございます、そういった視点はとても大切ですよね。ちなみに、操作感以外で何か気になった点や逆に御社に合いそうな点はありましたか?
↓(サポート体制が少し弱い印象がありました など)
なるほど、たしかに導入直後のフォロー体制は不安要素になりますよね。弊社では初月から週次でサポート対応し、実運用が軌道に乗るまで併走しています。
↓(感想)
ありがとうございます。他社さんとの違いも踏まえた上で、御社に最適な導入形をご提案できるよう、資料を再整理いたしますので、最終確認として一度ご覧いただけますでしょうか?
このトークのポイントは、「決め手になる視点は、競合の印象の中に隠れている」こと。競合の良さも弱点も一緒に整理することで、相手の中にある判断軸を可視化し、前向きな決断を後押しすることができます。
営業ヒアリングで特に意識したい3つの目的
「キーマンの意思決定基準」を聞き出して提案の軸をつくる
「なぜうちの提案が通らないんだろう?」そんな疑問を抱えたまま、また次の商談に向かっていませんか? 実際、決裁者の頭の中にある「判断の物差し」を知らずに提案するのは、暗闇で的を狙うようなものかもしれません。
キーマンが最終的に「GO」を出すとき、必ず心の中で何かと天秤にかけています。 「前回の失敗は繰り返したくない」「上司への説明がしやすい方がいい」といった、表には出てこない本音があるものです。
・「過去に導入で苦労した点」を聞くと、地雷ポイントが浮き彫りになる
・「稟議を通すときの決め手」を探ると、プレゼンの構成が見えてくる
決裁者の価値観を掴んでしまえば、競合との差別化も自然と生まれます。 同じ機能を説明するにしても、彼らが重視する角度から語ることで、「これは違う」という手応えを感じられるはずです。
「予算と決裁フロー」を把握して失注リスクを減らす
予算と決裁フローの把握とは、「誰がいくらまで決められるか」を正確に掴むことです。 つまり、提案する相手が本当に決定権を持っているのか、予算枠が確保されているのかを事前に確認するということです。
けれども実際は、「検討します」と言われた後に音沙汰がなくなる経験、ありませんか? 実は、相手に決裁権がなかったり、そもそも予算が確保されていなかったりするケースが意外と多いものです。
より具体的には、「稟議書の承認ルートを確認する」「予算の執行権限を聞き出す」ことで見えてきます。 ポイントは、「ご予算はおいくらぐらいで?」ではなく「どなたが最終的にご判断されますか?」と聞くことかもしれません。
決裁者と予算枠を早めに把握できれば、無駄な提案工数を削減できます。 その一例として、初回商談で決裁フローを整理しておくチームは、確実にクロージング率が上がっています。
「導入の背景と課題」を言語化して本音を掴む
導入背景の言語化とは、「なぜ今この検討をしているのか」の真意を明確にすることです。 つまり、表面的なニーズではなく、組織が抱える根本的な問題や緊急性を理解するということです。
しかし多くの場合、「効率化したいんです」という漠然とした回答で終わってしまいがちです。 実は、その背景には人手不足や売上低下、競合対策など、もっと切実な理由が隠れている可能性があります。
より具体的には、「現状の業務フローを聞き出す」「過去の失敗事例を確認する」ことで本音が見えてきます。
ポイントは、「課題は何ですか?」ではなく「今一番困っていることは何でしょうか?」と聞くことかもしれません。
真の課題を言語化できれば、競合との差別化ポイントも自然と浮かび上がります。 その一例として、背景をしっかり掘り下げる営業は、提案の刺さり方が格段に変わってきます。
成果の出る!営業ヒアリング質問の9つの条件
「その場で答えやすい質問」で会話のハードルを下げる
「予算はいくらですか?」といきなり聞かれたら、誰だって身構えますよね。
ヒアリングは相手が気軽に答えられる質問から始めることで、自然な会話の流れを作れます。
営業トークの例
顧客「システムの相談で来ました」
営業「導入時期はいつ頃をお考えですか?」→NG
営業「今日は電車でいらっしゃいましたか?駐車場、分かりにくくて申し訳なくて」→OK
答えやすい質問には共通点があります。
「はい・いいえ」で答えられる、事実を聞いている、相手の判断を求めていない、この3つです。
「こちらの部署は何名くらいですか?」「毎日使われるシステムですか?」など、相手がサラッと答えられる内容から入ると、警戒心が和らいで本音を話してもらいやすくなります。 会話の入り口を軽やかにすることで、重要な情報まで自然に引き出せるようになります。
「なぜ今なのか?」で検討の緊急度を見極める
「検討しています」と言う顧客の中には、本当に急いでいる人と、なんとなく情報収集している人が混在しています。
この違いを見極めるために「なぜ今なのか?」という質問が威力を発揮します。
営業トークの例
顧客「来期から新システムを検討中です」
営業「どちらの製品がご希望ですか?」→NG
営業「来期からということは、何か今のタイミングで動く理由があるんですね?」→OK
緊急度の高い顧客は必ず具体的な理由を持っています。
「4月から新しい部署ができるので」「今の契約が3月で切れるから」「監査で指摘されたため」など、明確な答えが返ってきます。
逆に「そろそろ古くなってきたので...」「上司に言われて...」といった曖昧な回答の場合は、検討の優先度が低い可能性があります。
この一言で案件の温度感を正確に把握でき、提案のスピードや内容を適切に調整できるようになります。
「その課題で困ると何が起きるか?」で真因に踏み込む
表面的な課題だけを聞いても、顧客の本当の痛みは見えてきません。
「困ると何が起きるか?」で一歩踏み込むことで、解決すべき本質的な問題が浮かび上がります。
営業トークの例
顧客「データ入力に時間がかかって困っています」
営業「自動化できるシステムがありますよ」→NG
営業「データ入力に時間がかかると、他にどんな影響が出るんですか?」→OK
この質問で顧客の真の課題が明らかになります。
「残業が増えて人件費がかさむ」「他の業務が後回しになる」「ミスが増えてクレームにつながる」など、根本的な問題が見えてきます。
単に「作業を早くしたい」ではなく「コスト削減したい」「品質向上したい」という本音を引き出せれば、提案の方向性も大きく変わります。
「その場にいない関係者の意向」を聞いてボトルネックを探る
商談で一番怖いのは「部長がダメと言いました」という後日の連絡です。 見えない決裁者や影響者の本音を事前に掴んでおかないと、どんなに完璧なプレゼンも水の泡になってしまいます。
理由は簡単で、現場担当者が「いいね」と言っても、最終的にお金を出すのは別の人だからです。 その人の価値観や懸念点を知らずに進めるのは、目隠しで営業しているようなものかもしれません。
営業トークの例
顧客「上司に相談してみます」
営業「分かりました。いつ頃お返事いただけそうですか?」→NG
営業「承知しました。上司の方って、新しいシステム導入する時に一番心配されるのはコスト面ですか?それとも現場への影響でしょうか?」→OK
こうして聞けば、決裁者の地雷がどこにあるかが見えてきます。 事前に地雷を察知できれば、提案書にその対策も盛り込めるので受注確率が一気に上がるでしょう。
「現状の運用フロー」をたどって提案の切り口を見つける
お客様の「今のやり方」を詳しく聞くだけで、提案の切り口は自然と見えてきます。 現状の運用フローを一つずつ確認していくと、必ずどこかに「面倒だな」「時間がかかるな」というポイントが隠れているものです。
なぜなら、完璧な運用フローなんて存在せず、どんな会社にも改善したい部分があるからです。
営業トークの例
顧客「今は手作業でやってます」
営業「手作業だと大変ですね」→NG
営業「手作業の場合、朝一番から何時頃まで作業されることが多いですか?」→OK
このように具体的な時間軸で聞くと、「朝の2時間がつらくて」といった本音が出てきます。
そこが提案の入り口になるかもしれません。 フローの中で一番時間のかかる部分、一番ミスの起きやすい部分を特定できれば、そこを解決する提案で刺さる確率が格段に上がります。
「競合と何を比べているか?」で勝負ポイントを絞り込む
競合の名前を聞くより「何を基準に比べているか」を聞いた方が勝てる提案ができます。 お客様が重視するポイントが分からないまま提案すると、的外れな強みをアピールしてしまう可能性があります。 なぜなら、価格重視のお客様に機能の話をしても、機能重視のお客様に価格の話をしても響かないからです。
営業トークの例
顧客「他社とも比較検討中です」
営業「どちらの会社と比較されていますか?」→NG
営業「比較される時に一番重要視されるのは、導入しやすさでしょうか?それとも機能の豊富さでしょうか?」→OK
こうして比較軸を明確にすれば、勝負すべきポイントが見えてきます。
相手が「コスト削減効果」を重視しているなら、ROIの話で攻める。 「使いやすさ」なら操作性をデモで見せる。
戦う土俵を間違えなければ、競合に負ける確率はぐっと下がるはずです。
「導入後の理想状態」を聞いてゴールを共有する
「半年後、この導入で一番嬉しい変化は何ですか?」この質問で、営業の勝率が劇的に変わります。
課題ヒアリングで終わる営業は多いですが、理想の未来を聞けば顧客の本音が見えてきます。
理由は簡単で、人は「困っていること」より「実現したいこと」を語る時の方が本気度が高いからです。
営業トークの例
顧客「効率化したいんです」
営業「どこが非効率ですか?」→NG
営業「効率化できたら、浮いた時間で何をやりたいですか?」→OK
こうすることで、製造業の案件では、「残業を減らしたい」という課題から「家族との時間を増やしたい」という理想を引き出せます。
結果、単なるシステム提案ではなく「働き方改革のパートナー」として信頼を得て受注できたんです。
理想状態を数値化してもらえれば、提案書でその実現可能性を示せるので説得力も増します。
顧客と同じ夢を見ることで、営業は「売り込む人」から「実現を支援する人」に変われるかもしれません。
「今のままだとどうなるか?」で背中を押す
「現状維持を続けた場合、1年後はどうなっていると思いますか?」この質問が、迷っている顧客の決断を後押しします。
人は変化を嫌う生き物なので、現状維持バイアスに陥りがちです。 だからこそ、「何もしないリスク」を顧客自身の口から語ってもらうことで、行動への動機が生まれます。
営業トークの例
顧客「もう少し検討したいです」
営業「承知いたしました」→NG
営業「このまま検討が長引くと、どんな影響がありそうですか?」→OK
こう聞くと、商談中に「手作業が続けば年間300時間のロス、優秀な人材の離職リスクも高まる」と顧客が自ら気付くこともあります。
結果、「今決めないと損失が拡大する」という危機感から、即日で導入が決まったりもします。
危機感を煽るのではなく、現実を客観視してもらうスタンスが大切かもしれません。
「選択肢」を提示してスピード感を持って商談を進める
「A案とB案、どちらがお客様の状況に合いそうですか?」選択肢を用意することで、商談のスピードが格段に上がります。
「検討します」で止まってしまう営業の多くは、顧客に白紙の状態で判断を委ねているからです。
人は無数の選択肢があると決められませんが、2〜3個に絞られると判断しやすくなります。
営業トークの例
顧客「どんなプランがありますか?」
営業「色々ありまして...」→NG
営業「スタンダード版と機能充実版、まずはどちらに興味がありますか?」→OK
このように実際、「来月スタートか、4月の新年度スタートか」と2択で確認すると、「4月がいいですね」と即答されることもあります。
選択肢があることで、顧客は「買うかどうか」ではなく「どれを買うか」を考えるようになるかもしれません。
営業ヒアリングする5つのメリット
「決裁者への最短ルート」がつくれるようになる
「この案件、半年も引っ張ってるのに全然前に進まない…」そんな経験、営業なら一度はありますよね? 実は、その原因の9割は最初のヒアリングで決裁ルートを掴めていないことなんです。
商談相手が現場担当者だった場合、どれだけ熱心に話を聞いてくれても、結局は「部長に相談してみます」で終わってしまいます。 逆に、最初から「誰が最終判断するのか」「稟議はどう回るのか」を聞いておけば、無駄な時間を使わずに済むかもしれません。
・「承認フロー」を把握すると、提案書の作り方が変わってくる
・「キーマン」を早期発見すると、アポ取りの成功率が上がる
結局、営業ってキーマンを見つけるゲームです。
組織図の裏側まで理解できれば、競合他社が気づかないうちに本丸へ直接アプローチできるようになります。
「意思決定の流れ」が見える化される
提案しても「持ち帰って検討します」で終わる…。そんなモヤモヤ、ありませんか?
その正体は“誰がどう決めているか”が見えていないこと。決裁までの流れが不透明だと、打ち手が曖昧になります。
ヒアリングで社内の意思決定プロセスを具体的に聞き出せれば、次に誰に何を届けるべきかがはっきりします。
それだけで、提案の順序や説得材料の準備もピンポイントに進められます。
・「最終決裁者の役職と関心」を聞いて“着地点”を明確にする
・「稟議を通す順番」を聞いて“通し方”を逆算する
誰がYESと言えば決まるのか。
そこが見えるだけで、営業の動き方はまるで変わってきます。
「検討の壁」が早期にわかる
商談が順調に進んでいたのに、突然ストップがかかる…。その正体、多くは“見えない検討の壁”です。
「予算が通らない」「競合と比較中」「担当者が懸念を抱えている」など、障害は意外と序盤から潜んでいます。
だからこそ、ヒアリングの段階で“何が引っかかっているか”を掘り起こすことが鍵になります。
事前に壁を把握できれば、手の打ちようが変わり、商談の迷走も減ります。
・「社内で反対されそうなポイント」を聞いて“懸念材料”を炙り出す
・「過去に検討が止まった理由」を聞いて“つまずきやすい箇所”を予測する
壁は、進んでからでは遅いです。
聞く力で先に見抜けば、対策は打てるようになります。
「紹介や横展開」のきっかけが生まれる
商談中、「この話、他の部署にも刺さるな」と思ったこと、ありませんか?
でも何も聞けずに終わると、チャンスは目の前で消えてしまいます。
だからこそ、“その先の話”を引き出すヒアリングが、営業の広がりを決めます。
紹介はお願いするものではなく、「言いたくなる空気」をつくるもの。
・「別部署でも同じ課題があるか」を軽く聞いて共感の種をまく
・「他にも気にされてる方いらっしゃいますか?」と自然に紹介を促す
こうすることで、ヒアリング一つで営業の射程が変わっていきます。
営業ヒアリングする際に気をつけたい3つのこと
「質問の順番」を間違えると本音が引き出せなくなる
質問の順番、つまり本音にたどり着くには、段階的な質問を通じて心を開いてもらう必要があるのです。
しかし実際には、「どこに課題ありますか?」と初手で核心を突いて、空気が凍る場面もあります。
実は、警戒されずに本音を引き出すには、まず“相手が話しやすい話題”から入る設計が鍵になります。
たとえば、「現場の困りごとを先に聞く」「今の流れを教えてもらう」で自然に壁を溶かしていく
ポイントは、いきなり答えを求めず、会話を“掘る準備”として位置づけることです。
本音は、聞くものではなく、相手が「つい話してしまった」と感じる流れから生まれていきます。
「情報ばかり聞き出す姿勢」が相手を警戒させる
営業ヒアリングとは、情報を集めるだけでなく「信頼を築く場」でもあります。
つまり、質問が多くなるほど、相手は“詮索されている”と感じやすくなります。
なぜか、営業が聞き手に徹すると、相手は「この人、自分の都合だけで動いてるのかも」と不安になります。
実は、「質問の目的」を伝えないまま掘り下げると、商談の空気が一気に硬くなってしまいます。
たとえば、「決裁者の人数だけ聞いてしまう」「競合の名前を急に聞いてしまう」など
ポイントは、聞く前に「なぜ聞くのか」をたった一言添えることです。
「比較検討を整理したくて」「社内展開の参考にしたくて」など、意図があると相手の緊張が緩みます。
会話を進める前に、安心を先に届けてみる。
それだけで、情報は自然と引き出されていきます。
「自分の仮説」に固執すると見落としが生まれる
仮説を持つ事は大事ですが、固執しすぎると「目の前の事実」が見えなくなります。
つまり、想定通りに話を運ぼうとすると、大事なヒントを聞き逃すことがあるのです。
でも本当にそれ、今の相手の優先順位と合っていますか?
実は、ヒアリング中に仮説通りの回答が得られないときこそ、チャンスが隠れています。
たとえば、「課題を“コスト”と決めつけてしまう」「導入障壁を先回りしすぎてしまう」など
ポイントは、仮説は“仮の想定”であり、途中で変えていいという前提で使うことです。
「なるほど、想定と違ったんですね」と言える営業は、相手に安心を与えます。
仮説はあくまで入口。正解は、相手の口から出てくる言葉の中にあります。
営業ヒアリングで役立つのツールの使い方5選
「Geminiを活用(文字起こし)」で聞き漏れゼロにする
「商談のあと、あの発言ってどういう意味だったんだろう?」と悩んだ経験はありませんか?
実は、Googleの「Gemini」を活用してリアルタイムで文字起こしを行うことで、“聞き漏れ”や“認識ズレ”を防ぐことができます。
音声を自動で文字化することで、ヒアリングの精度が上がり、顧客の「本音」を見逃さず拾えるようになります。
とくに法人営業の現場では、課題やニーズが一言のなかに隠れていることも多く、記録の正確さがそのまま提案の質に直結します。
たとえば以下のような場面で効果を発揮します。
- 「要望が曖昧の場合」→「顧客の発言を即テキスト化する」
- 「メモが追いつかない場合」→「全発言を自動で記録する」
重要なのは、聞く力より“残す力”です。
Geminiを活用することで、営業活動の再現性が高まり、社内の連携スピードも上がっていきます。
「ヒアリングの漏れをなくしたい」と感じたら、一度Geminiの導入を検討してみてください。
小さな発言の積み重ねが、次の受注に繋がっていくかもしれません。
「Notion」で商談メモをチームに即シェアする
「商談後のメモ、もっと早くチームに渡せたら」と思うこと、ありませんか?
「Notion」を使えば、話した内容をその場で整理しながら、チーム全員に一瞬で届けられます。
テキストだけでなく、チェックリストやタスクも一緒にまとめられるため、引き継ぎやアクションのズレも起きにくくなります。
現場で実際に活用されている具体例は以下の通りです。
- 「商談テンプレ」で入力の手間を減らす
- 「タグ機能」で案件ごとに整理する
- 「メンション通知」で即対応を促す
打ち合わせ直後の“熱”が冷めないうちに、そのままメモを共有できるのは想像以上に価値があります。
情報の鮮度と正確さを保ったまま、組織全体の動きが早くなるのが最大のポイントです。
まずは1件だけでもNotionに残してみると、その効果を実感しやすくなります。
「Googleスプレッドシート」で案件状況を可視化する
「進捗が見えづらくて、対応が後手に回る…」と感じたことはありませんか?
「Googleスプレッドシート」を使えば、案件ごとのステータス・担当者・次アクションが一覧で“見える化”されます。
共有もリアルタイムで反映されるので、営業チーム全体の動きを整えやすくなります。
現場で実際に活用されている具体例は以下の通りです。
- 「条件付き書式」で遅延案件を色分けする
- 「フィルター表示」で未対応だけを抽出する
- 「コメント機能」で確認依頼を残す
進捗が視覚的にわかるだけで、判断や対応が一歩早くなります。
結果として、漏れや重複も減り、営業フロー全体がスムーズになります。
まずは既存の案件一覧をスプレッドシートで整理してみるのがおすすめです。
「画面録画」で上司や同僚と振り返りできるようにしておく
「このヒアリング、本当に伝えきれてるかな?」と感じたことはありませんか?
実際、法人営業では商談の“細かな一言”が成否を分けることがよくあります。
画面録画を残しておくと、顧客の表情・声のトーン・間の取り方まで正確に振り返ることができ、曖昧な共有や記憶のズレを防げます。
さらに、社内報告・案件レビュー・提案の見直しまで一貫して活用できるため、1本の録画が営業プロセス全体を底上げします。
現場で実際に活用されている具体例は以下の通りです。
- 「顧客の“導入障壁”を録画で再確認する」
- 「提案の方法を録画で振り返り、改善する」
録画は、ただの“記録”ではなく“再現可能なナレッジ”になります。
商談を点で終わらせず、線で育てるための武器として、積極的に活用してみてください。
「Slack共有」でうまくいった質問例を蓄積しておく
営業ヒアリングで「この質問、前もうまく刺さった気がする」と思ったことはありませんか?
Slackでその場のやり取りを記録し、再現性のある「刺さる質問例」を蓄積しておくと、現場の提案精度が格段に高まります。
Slackなら即時性があり、会話の流れも含めて残せるため、ニュアンスやトーンまで共有できる点が強みです。
実際に活用されている具体例は以下の通りです。
- 「決裁者フローを聞き出したやり取りを残しておく」
- 「競合比較の質問がヒットした商談を共有しておく」
- 「担当者の”困りごと”を残しておく」
こうした質問の共有が積み上がることで、若手の型づくりにもつながり、ヒアリングの質がチーム全体で底上げされていきます。
Slackの営業ログは、まさに「現場の知見の宝庫」になります。小さな成功を拾って残していくことが、強い組織づくりの第一歩かもしれません。
成果の出る営業ヒアリングの基本の4つの手順
「雑談」で警戒心をゆるめて話しやすくする
最初に少し雑談を挟むだけで、相手の表情がほぐれやすくなります。
いきなり本題に入ると、「売られるかも」という警戒モードに入られてしまいやすいです。
とくに初対面やオンライン商談では、最初の空気づくりが相手の話す量に直結します。
営業トークの例
顧客「今日はよろしくお願いします」
営業「こちらこそ、ちなみに今日ってすごく暑くないですか?道中大変じゃなかったですか?」→OK
営業「今日はよろしくお願いします。では早速ですが…」→NG
「売る前に、まず打ち解ける」そんな一言が、その後のヒアリングの深さを変えてくれます。
雑談は点なる会話ではなく、営業の入口です。
「現状と課題」を聞き出してズレを見つける
表面的な満足の裏に、本音の不満が眠っていることがよくあります。
だからこそ、「今どうか」だけでなく「本当はどうなりたいか」まで聞くことが大事です。
多くの営業がここで終わるから、差がつきます。
営業トークの例
顧客「まぁ今のままで困ってないです」
営業「承知しました。ちなみに“もっと理想的な状態”って、どんなイメージですか?」→OK
営業「そうなんですね。では何かあればまた…」→NG
理想を聞くと、現状との差=“ズレ”が見えます。
このズレに、提案の余地が生まれます。
ヒアリングは「現状確認」ではなく、「変化を引き出す対話」です。
「支援できること」を相手目線で明確に伝える
相手が「自分ごと」として受け取れるように伝えないと、ヒアリングの意図が伝わらず、信頼関係が深まりません。
「こちらができること」を話す前に、「相手が求めていること」を具体的に想像し、それに応じた支援内容に言い換えることが大切です。
営業トークの例
顧客「ちょっと困っていて…」
営業「それなら弊社のサービスをご紹介させてください」→NG
営業「たとえば、今の状況でよくあるのが〇〇なんですが、もし近いようでしたら整理しながらご支援方法を一緒に考えたいです」→OK
相手の立場に立って、実際の課題や状況を言語化しながら提案すると、安心感が生まれ、商談が前に進みやすくなります。
「次のアクション」をその場で具体的に決める
その場で「次、何するか」を決めないと、商談はほぼ流れます。
曖昧なまま終わると、相手も熱量も一気に冷めてしまいます。
営業トークの例
顧客「ちょっと社内で検討してみます」
営業「ありがとうございます。ちなみに、来週水曜までに一度ご状況うかがってもよろしいでしょうか?」→OK
営業「では、ご検討よろしくお願いします」→NG
「誰が」「いつまでに」「何をするか」をその場で共有するだけで、商談は一気に動き出します。
“次の一手”が決まっていると、お互い迷わず進める空気が自然に生まれます。
営業のヒアリング質問項目でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「営業のヒアリング質問項目を工夫しているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
ヒアリングの質を高めようと質問項目を見直しても、なかなか商談が前に進まない。
相手の本音を引き出せず、毎回「とりあえず検討します」で終わってしまうと、正直つらいですよね。
そんなときこそ、営業の現場で実績を積んだプロに頼るのもひとつの手です。
スタジアムの『営業代行サービス』なら、Web・IT・SaaS領域に強い営業のプロが、ヒアリングからクロージングまで一貫してサポート。
1商材1担当制だから、細かなニュアンスまで丁寧に対応します。
今、ヒアリングで悩んでいる方こそチャンスです。
まずは営業に関するちょっとしたお悩みを、今すぐ無料で相談してみませんか?
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き
【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説
営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順
【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版
インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集
営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文
【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全
【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集
【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!
アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説
【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略
【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説
法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略
【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説
深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順
営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善
13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド
営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション
営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順
【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版
【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集
営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド
営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別
【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果
【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順
【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順
【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点
営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順
【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド
【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き
営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順
できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法
売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法
プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順
【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き
営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策
【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説
【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説
なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術
新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順
営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説
なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法
ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP
ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集
飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法
【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド
【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版
セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法
セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド
新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版
新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全
【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説
新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ
新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法
【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版
【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集
アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法
インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順
【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版
【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法
SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法
MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説
BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法
BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略
BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順
【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版
【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ
【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説
営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選
FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド
【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方
14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順
アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ
シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ
これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順
【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集
【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP
【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説
営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ
御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP
【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順
【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集
営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法
営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順
27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場
【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順
営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準
新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル
営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント
クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順
営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説
営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順
営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順
最終更新日