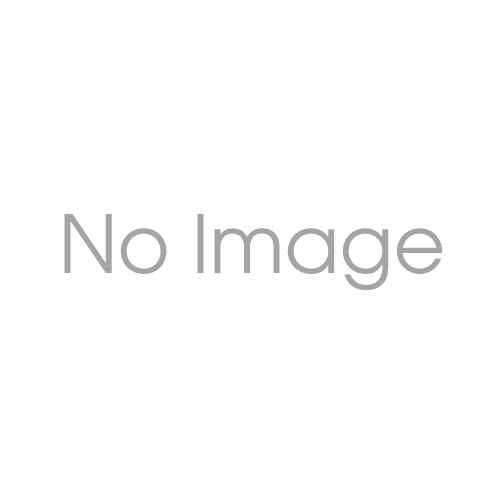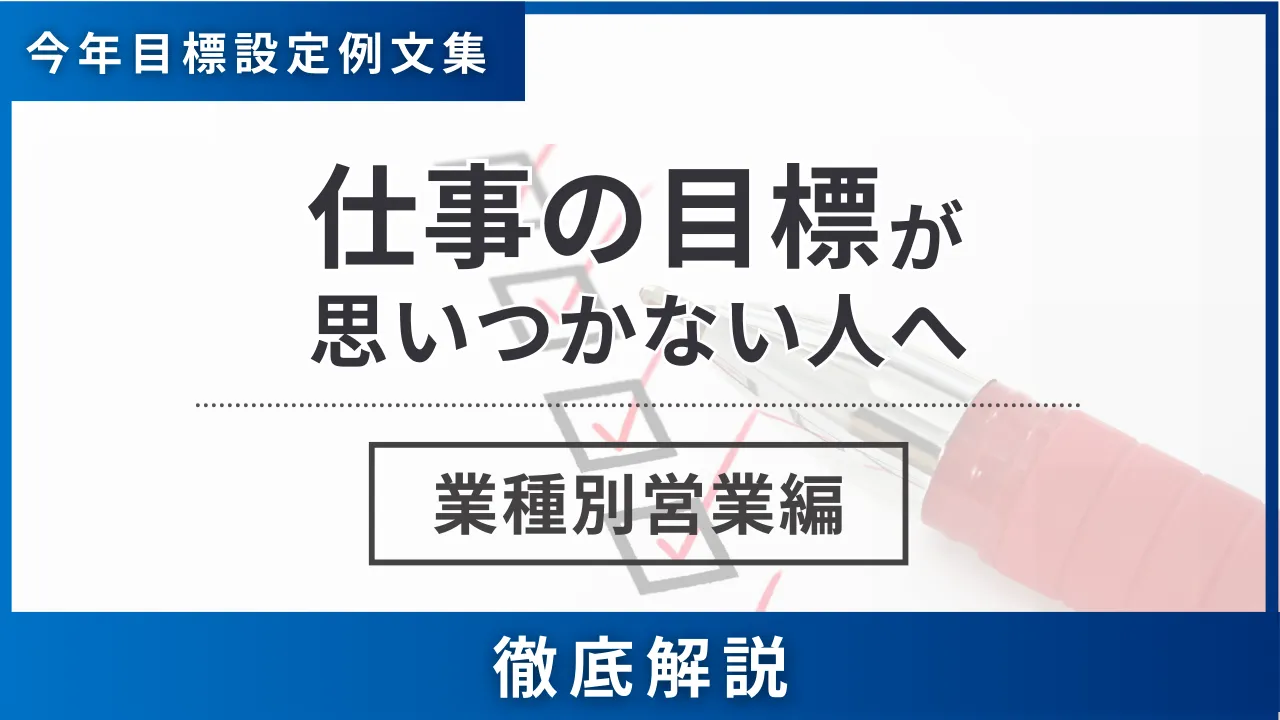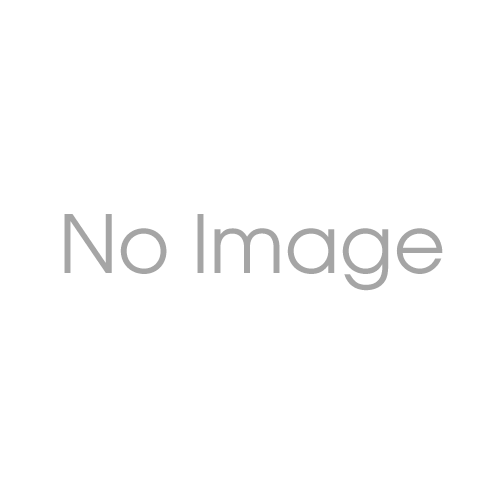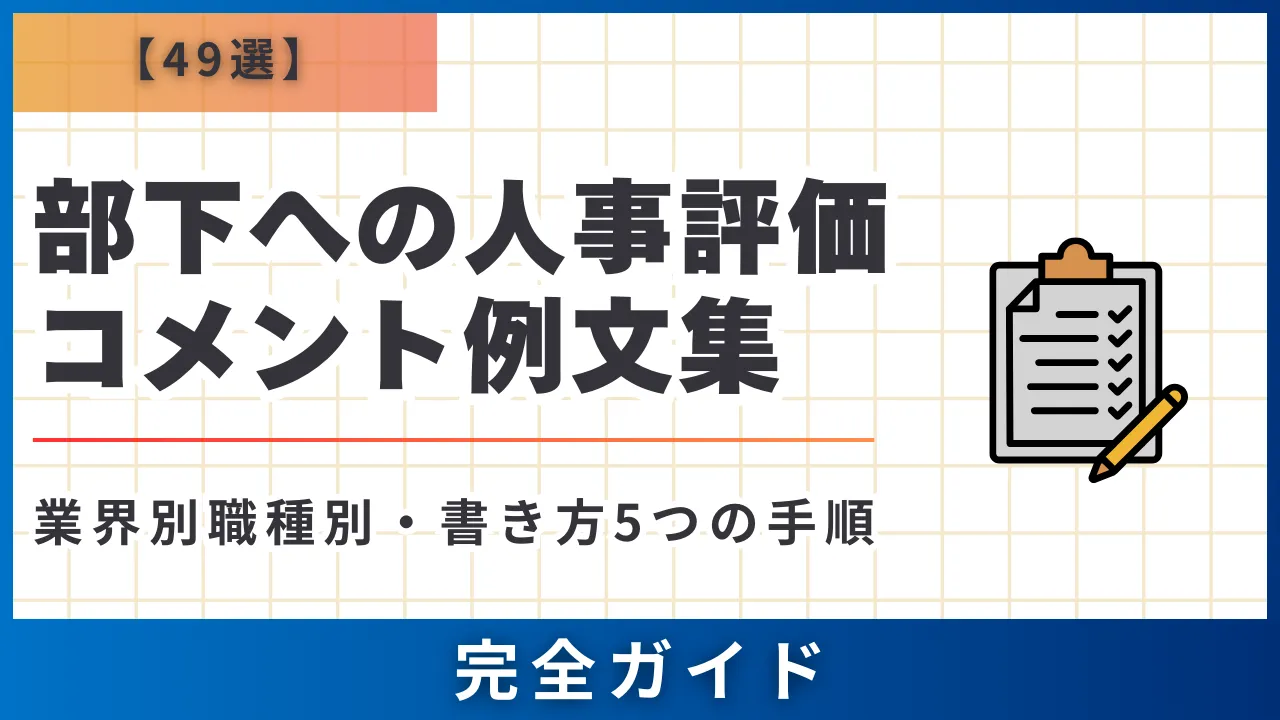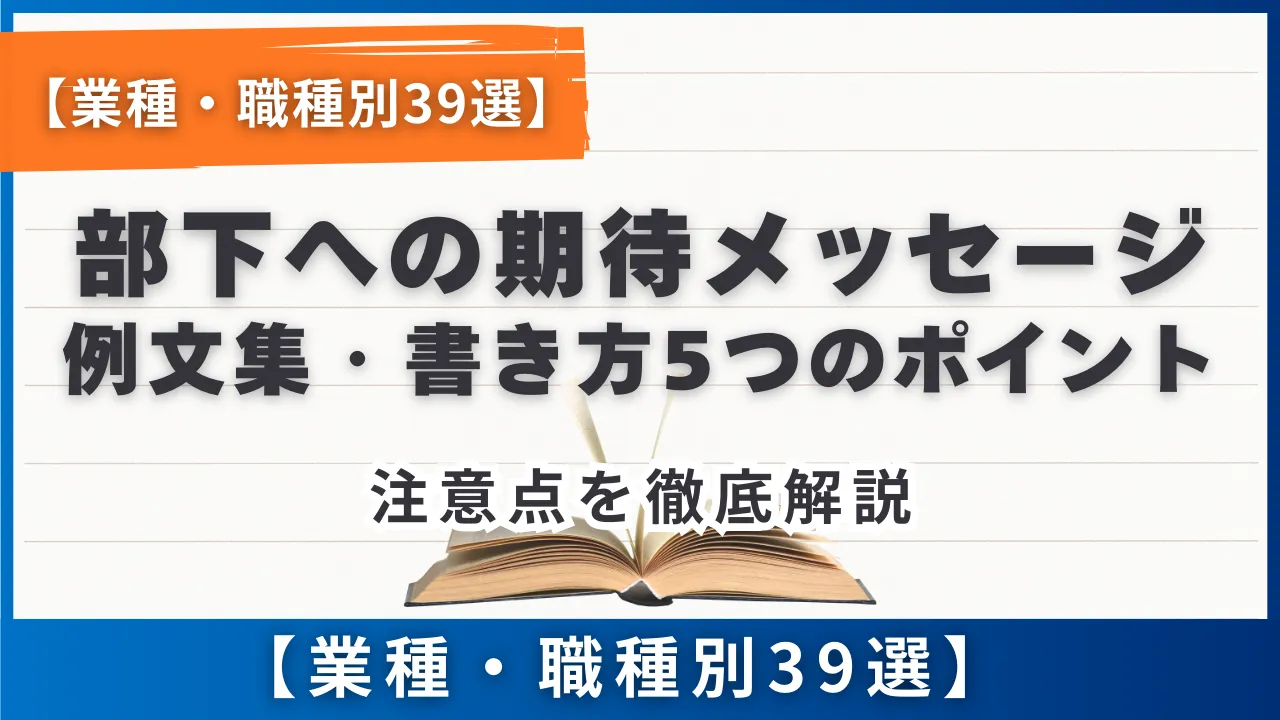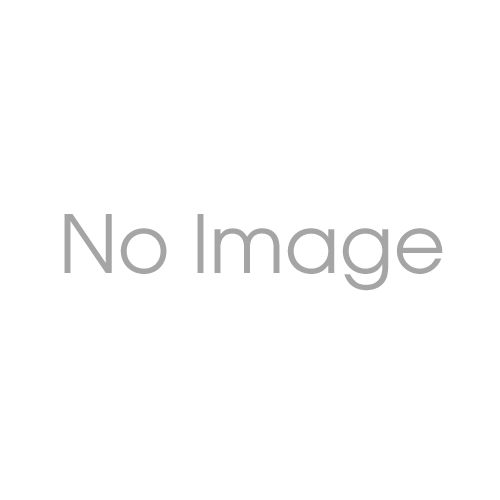営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
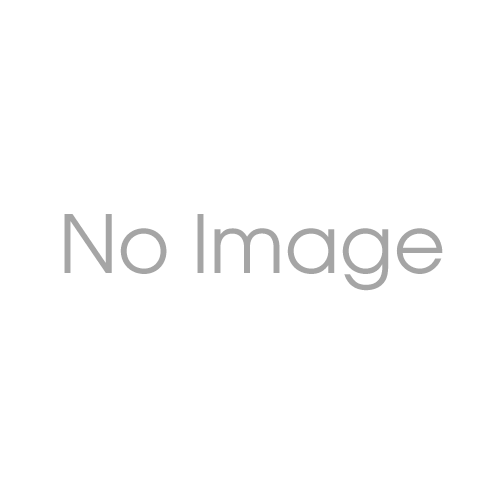
「営業効率化、何から始めればいいか分からない」
「施策を試しても、チームに浸透しない」──そんなモヤモヤ、抱えていませんか?
営業の非効率は、属人化・ムダな業務・情報の分断から生まれます。
今こそ、成果につながる“再現性ある仕組み化”が必要です。
明日から使える方法を、現場目線で徹底解説します。
本記事を読むと分かること
・営業を効率化をする5つの目的(型化・リード最大化・再現性)
・営業現場で即実践できる17の効率化施策(自動化・テンプレ・SFA活用)
・効率化がもたらす営業組織への7つのメリット(生産性・新人育成・残業削減)
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
営業を効率化をする5つの目的
「属人営業」をやめて、誰でも売れる型をつくる
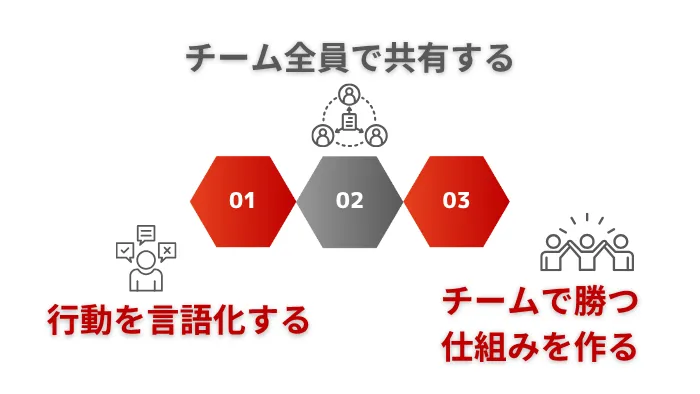
属人営業とは、「売れる人」と「売れない人」の差が、仕組みではなく“人”にある状態です。
つまり、成果が「再現できない技術」に頼っていることが根本の問題です。
でも、営業って本当に「才能」だけで決まるのでしょうか?
実は、成果を出している人のやり方には、誰でも真似できる“共通パターン”が隠れています。
たとえば、「初回面談で必ず“決裁者の参加有無”を確認する」「提案前に“顧客のKPI”を聞き出す」など
具体的にやるべき行動を言語化して、チーム全員で共有することが重要です。
ポイントは、“上手くいった理由”を本人任せにせず、会話の中身まで型に落とし込むことです。
一人のスゴ腕営業に依存せず、「チーム全体で勝てる仕組み」をつくっていきましょう。
「各ファネルの移行率」を最大化して、商談機会・ビジネスチャンスを増やす

現代の営業活動では、「リード獲得」「ナーチャリング」「課題提起」「サービス訴求」‥などいくつものファネルに分解して顧客を管理する手法が取られます。
管理するセクションが細かいことでアクションが起こしやすい反面、全体に対しての影響を常に見ておかないと何が本当に重要なのか見落としてしまうこともあります。例えば、その中でももっとも重要なのは「リード数」です。
リード数とは、「見込み顧客との最初の接点」を指します。
つまり、営業活動の起点となる“種まき”の数をどう増やすかがカギになるのです。
でも、「リードが足りない」と感じたとき、つい手当たり次第に動いていませんか?
実は、リードは“数”だけでなく“質”も意識することで、商談化率が大きく変わります。
たとえば、「セミナー後のアンケートで“課題選択型”の設問を入れる」「問い合わせフォームに“導入検討時期”を追加する」など
接点時点での情報設計を見直すだけで、優先すべきリードが浮き彫りになります。
ポイントは、“作る”だけでなく、“見極めて活かす”ところまで設計することです。
単なる名刺リストではなく、「次に会うべき人を見つける手段」として、リードを増やしていきましょう。
このようにどのファネルが重要で、どんな仕組みがその数字を最大化させるのか。ここを抑えることは営業の成否に直結していると言っても過言ではないのです。
「提案の質」を揃えて、受注率を底上げする
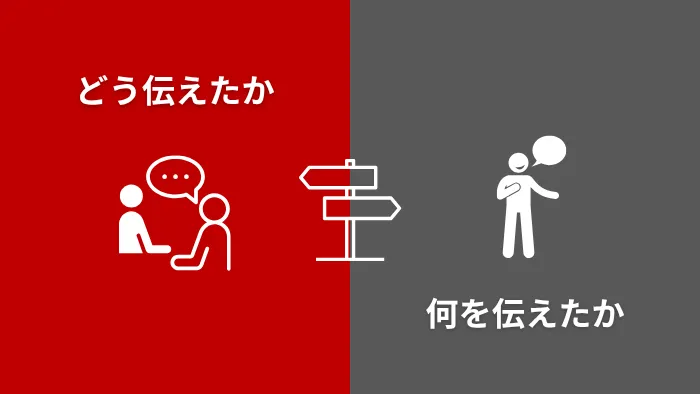
提案の質とは、「顧客の課題にどれだけ深く刺さっているか」を指します。
つまり、商品説明ではなく“相手の現実”に即した提案かどうかが勝負の分かれ目です。
でも、同じ資料を使っているのに、なぜ人によって受注率が大きく違うのでしょうか?
実は、“提案の順番”と“言葉選び”のズレが、響き方に大きく影響します。
たとえば、「提案書の冒頭に“現状の課題整理”を加える」「導入後の“期待変化”を図で示す」など
提案ストーリーの型を全員で揃えるだけで、説得力が一段と増します。
ポイントは、「何を伝えたか」ではなく「どう伝えたか」を揃えることです。
一部のベテランだけが勝てる状態を脱し、全員が勝ち筋を描ける提案に変えていきましょう。
「対応スピード」を上げて、競合に勝てるようにする
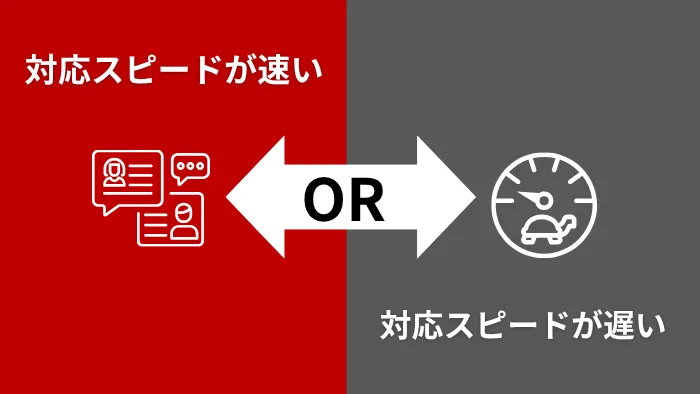
対応スピードとは、「顧客からの反応にどれだけ早く返せるか」の時間軸の勝負です。
つまり、提案の質より先に“速さ”が信頼を生む場面が増えているということです。
では、なぜスピードが営業成果に直結するのでしょうか?
実は、BtoBでも「最初に的確に動いた会社がそのまま商談を押さえる」ケースが非常に多いです。
たとえば、「問い合わせから30分以内に“次回打ち合わせ日程”を提示する」「資料請求後すぐに“ヒアリング希望”を送る」など
レスポンスの“型”を事前に整えておけば、誰でも素早く動けるようになります。
ポイントは、考える前に“動けるテンプレ”を持っておくことです。
スピードは才能ではなく準備でつくれる武器なので、競合より一歩早く動ける仕組みをつくっていきましょう。
「売れ筋の再現性」をつくって、チーム全体を伸ばす
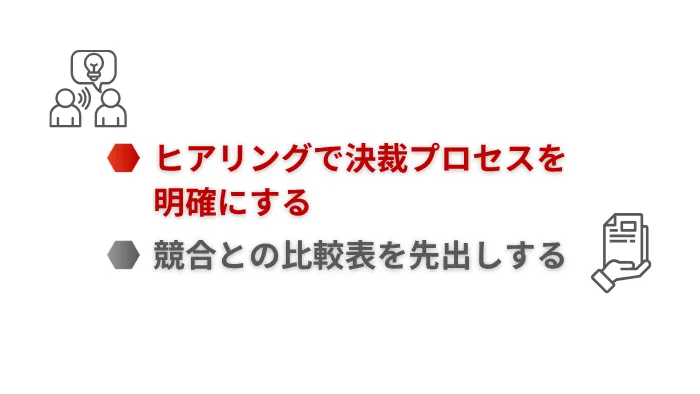
売れ筋の再現性とは、「なぜ売れたか」を分解し、他のメンバーも同じ動きをできるようにすることです。
つまり、偶然のヒットを“勝ちパターン”に変える仕組みづくりとも言えます。
でも、「なぜ売れたのか?」を、なんとなくの感覚で済ませていませんか?
実は、成約には“買った理由”が必ず存在し、それを言語化すれば再現性は高められます。
たとえば、「ヒアリングで“決裁プロセス”を明確にする」「競合との比較表を“先出し”して安心感を与える」など
実際の動きや言葉をストックしておくことで、誰でも売れ筋に沿った提案ができます。
ポイントは、“成功の偶然”を“再現できる手順”に変えることです。
成果が属人化しないチームは、一人ひとりの成長スピードも加速していきます。
営業効率化する17のコツ「具体的なやり方・施策・方法」
「問い合わせ対応」を自動化して一次対応を減らす

問い合わせ対応の自動化とは、営業に届く質問のうち“判断を必要としない定型対応”を、仕組みで先回りして処理する方法です。
つまり、営業が「動く前」に対応が終わる状態をつくることです。
現場では、「それってお客様に冷たくない?」「結局あとから対応が必要じゃない?」という声もよく出ます。
実は、多くの問い合わせは“同じ内容の繰り返し”で、最初から自動で処理できるものも多いというのも事実です。
たとえば、
・「料金プランの詳細を聞かれる」
・「導入までの流れを確認される」
より具体的には、
・「フォーム入力後すぐに自動返信で資料を送る」
・「Webサイト上でAIチャットが即答できるようにする」
ポイントは、“人が考えなくてもいい質問”に、営業が時間を使わないことです。
1つでも多くの無駄な一次対応を減らせば、提案に向き合う時間が自然と増えていきます。
「見込み顧客リスト」を毎週精査して精度を上げる
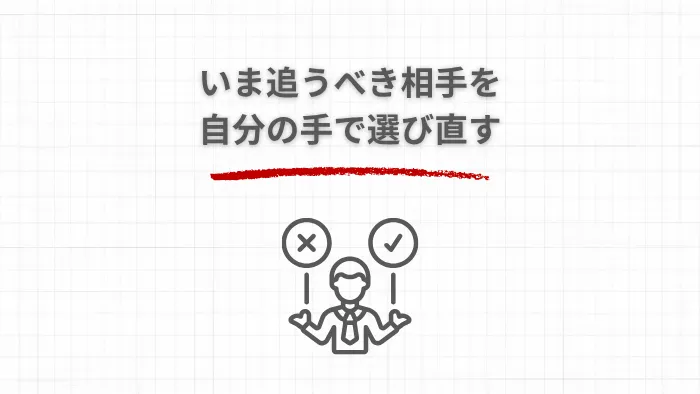
見込み顧客リストの精査とは、営業先として「本当に追うべき相手かどうか」を毎週見直す営みのことです。
つまり、営業の“時間の使い方”そのものを見直す作業です。
でも現場では、「せっかくリスト化したし」「あとで当たるかも」と、惰性で動いてしまうケースも多いです。
実は、リストの更新頻度と受注確度には明確な相関があり、“放置リスト”が動きを鈍らせてしまいます。
たとえば、
・「反応がないリードを放置してしまう」
・「情報が古いまま営業し続ける」
より具体的には、
・「週1回、未接触10日超のリードを除外する」
・「商談化した企業と類似する条件でリストを再抽出する」
ポイントは、“いま追うべき相手”を自分の手で選び直すことです。
手元のリストを週に一度“磨き直す”ことで、営業の打率が目に見えて変わっていきます。
「初回メール」をテンプレ化して反応率を上げる
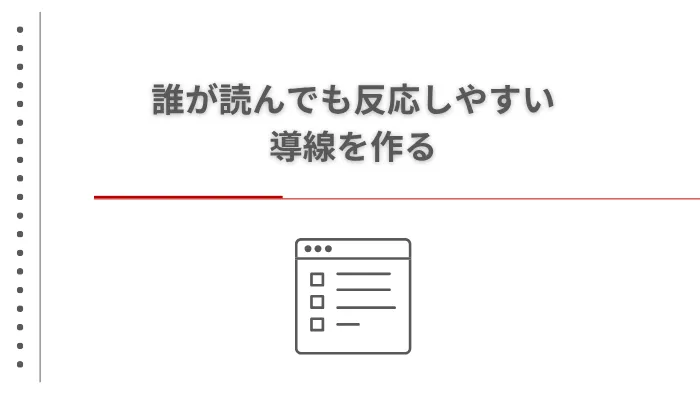
初回メールのテンプレ化とは、「誰にでも同じ内容を送る」のではなく、「最も反応が取れた型」をベースに営業文を仕立てることです。
つまり、“試行錯誤の結果”を型に落とし込んで、次のアクションを早める考え方です。
こちらも現場では、「相手ごとに文章を変えないと失礼では?」「テンプレは見抜かれるのでは?」といった不安もあります。
テンプレ化の目的は“個別対応をなくすこと”ではなく、“反応率の高い構成を使い回すこと”ということを全員が理解した上で、「顧客にとって価値のある、汎用的なコミュニケーション」+「個別のコミュニケーション」を設計する意識で仕組みを作っていきましょう。
たとえば
・「冒頭に実績を書く」
・「結論を最初に伝える」
より具体的には、
・「件名に“●●業界での成功事例”と入れる」
・「3行以内で導入メリットを端的に伝える」
ポイントは、“誰が読んでも反応しやすい導線”を作っておくことです。
テンプレを元に微修正するだけで、毎日の営業がスピードも成果もグッと変わっていきます。
「商談録画」をチームで見て、勝ちパターンを共有する
商談録画の共有とは、個人の会話内容を“映像で見える化”し、チーム全体で再現性のある営業手法を掘り起こす取り組みです。
つまり、「うまくいった理由」を感覚で終わらせず、チームの資産に変える方法です。
でも現場では、「時間がない」「見る意味ある?」という声も出がちです。
実は、話し方・間の取り方・提案の切り出し方など、成果を生む“営業の動作”は、録画でこそ可視化できます。
たとえば、
・「決裁者が話し出した瞬間を逃さない」
・「値段提示の前に成果事例を挟む」
より具体的には、
・「週1で15分だけ商談の“良かった場面”を切り抜いて共有する」
・「トップ営業の録画に“なぜ今これを言ったか”をつけてナレッジ化する」
ポイントは、“言葉の流れ”ではなく“勝ち筋の構造”をみんなで捉えることです。
録画を一緒に見る習慣がつくと、チーム全体の底上げが自然と始まっていきます。
「ヒアリング項目」を定型化して情報の抜け漏れを防ぐ
ヒアリング中に「何か聞き忘れてる気がする…」そんな違和感、営業で一度はありますよね。
質問が漏れると、あとからの提案が浅くなり、信頼も一気に遠のきます。
だからこそ、“聞くべきこと”は最初から決めておくのが得策です。
項目を定型化しておけば、どんな業種でもベースがぶれず、初回商談でも核心に迫れます。
・誰が「決裁権」を握ってるかを把握すると、流れが明確になる
・「今何に困っているか」を先に聞くと、提案の突破口になる
営業は、準備で8割決まります。
その場のトークより、抜けない“設計”が結果を変えていきます。
「失注理由」から改善点を見つけるのをルーティンにする
「あの商談、どこでズレたんだろう?」
失注した後にふと湧くこの疑問を、毎回ちゃんと拾えてますか?
振り返りを後回しにすると、同じミスをまた繰り返します。
逆に、失注直後の“生っぽい違和感”は、次の提案を鋭くします。
1日1件でも「なぜ負けたか」をメモに残すだけで、提案の制度が上がっていきます。
・「キーマンの温度感」を読み違えると、案件は静かに失速していく
・「予算感のズレ」に気づけないと、提案の土俵にも上がれない
失注には、未来の勝ちパターンが隠れています。
スルーせず、習慣にして拾いにいく。
それだけで営業の精度が底上げされます。
「リマインド送信」を自動化して追客を仕組み化する
「ご提案いかがでしたか?」
そう送るだけなのに、つい後回しになるリマインド。気づいたら1週間経っていた…そんな経験、ありませんか?
この“うっかり”が、せっかくの商談を“自然消滅”させてしまいます。
だからこそ、追客は気合でなく“仕組み”で回すのが得策です。
SFAやメールツールにテンプレと送信タイミングを設定しておけば、機械的に動いてくれます。
結果、温度感の高い相手にだけ時間を使えるようになります。
・「ステータス別テンプレ」で返信率のばらつきを減らす
・「自動送信設定」で抜け漏れや属人化を防ぐ
“あとで送ろう”が、一番の失注リスクです。
追客は、気持ちより仕掛けで回していくのが現実的です。
「過去事例資料」を即出しできるように整理しておく
「似た事例、前にあった気がする…でも、どこだっけ?」
そんな探しものに3分かかるだけで、商談の熱は一気に冷めてしまいます。
事例資料は、“出せること”より“すぐ出せること”が価値です。
クライアントの業界や課題に合わせて、パッと出せる状態にしておくと、提案の説得力が一段上がります。
営業フォルダをタグごとに分けるだけでも、使える事例の出番がグッと増えます。
・「業種別フォルダ」で同業事例を即提示できる
・「課題別タグ付け」で提案に一貫性が生まれる
記憶ではなく“整理された引き出し”が、提案のスピードと厚みを決めていきます。
今すぐ出せる状態か?この問いが、受注率を変えていきます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【法人営業×情報の整理法】整理する順番、内容、使い方を完全解説。
「日報」はSlackで簡潔に報告し、記入する手間を減らす
毎日の「日報」、気づけば“書くために仕事してる感覚”になっていませんか?
営業は動いてなんぼ。報告に時間を取られすぎると、本末転倒です。
Slackでの“ひとこと日報”なら、数分で済んで、振り返りにも使えます。
たとえば
・「今日業務内容と気づき」をSlackで箇条書きで入力する
・「次のアクション」をスレッドにメモして、思考を見える化する
数字も熱量も伝わる報告は、長文じゃなくて“濃度”が勝負です。
面倒な日報を、チームを前に進める“リアルなログ”に変えてみませんか?
「インサイドセールス、フィールドセールス」を分業する
「全部ひとりでやってて、結局どっちも中途半端…」そんな感覚に心当たりありませんか?
インサイドもフィールドも、それぞれに求められる“型”や“集中力”がまったく違います。
だからこそ、分業によってパフォーマンスの質が一気に上がる場面は多いんです。
アポ獲得に専念する人と、商談に集中する人が分かれるだけで、思考のノイズが消えます。
・「初回アポ獲得」は、専任で追客精度を最大化する
・「商談提案」は、専任で決裁者の温度を見極めて進める
ひとつの役割に集中するからこそ、型が磨かれ、勝ち筋が見えてきます。
分業は、ラクをするためじゃなく“成果を分けて積み上げる”ための仕組みかもしれません。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業のシステム化】インサイドセールスとフィールドセールス
「事前準備シート」で商談の質を均一化する
商談のあと、「なんでこの話、もっと早く聞けなかったんだろう…」そう悔やんだことありませんか?
場当たりで進めると、相手の“本音”までたどり着けず、結果、提案の芯がズレてしまいます。
だからこそ、全員が同じ視点で臨める「事前準備シート」が効いてきます。
何を聞くか、どこまで掘るかを事前に“型”にしておけば、誰が出ても情報の質が落ちにくくなります。
属人的な営業から、チームで勝つ営業に変わっていく感覚、味わってみたくないですか?
・「意思決定のフローと温度感」を押さえると、提案の着地が見えてくる
・「過去の失敗理由」を深掘ると、ニーズの“根”にたどり着ける
トークの巧さより、準備の設計で勝負が決まる。
そんな営業に、そろそろシフトしてみませんか?
▼編集部のおすすめ動画を見る
【使い方・解説動画】商談前準備シート
「見積作成」を自動化してクロージングを早める
「すぐ見積出せますか?」と言われて、内心ヒヤッとした経験ありませんか?
手作業での見積作成は、思っている以上に時間を食い、クロージングの熱量を一気に冷まします。
その“待たせる時間”こそ、商談の熱が冷める最大の敵かもしれません。
だからこそ、見積作成の自動化は営業スピードを上げる有効打になります。
商品の組み合わせや条件を入力するだけで、数分で見積が出る仕組みがあれば、即決の確率も高まります。
・「商品別の価格テンプレート」を整えておくと、入力の迷いがなくなる
・「営業別の承認フロー」を明確にしておくと、社内調整が早まる
クロージングは、提案内容より“スピード”で決まることもあります。
見積書類は、自動化を進めていきましょう。
「顧客情報」をSFAに全件入力して属人化をなくす
「あの案件、担当がいないと何も分からない…」そんな状況、意外と多くありませんか?
口頭の共有や個人メモに頼っていると、情報はどんどんブラックボックス化していきます。
その属人性が、引き継ぎや提案スピードを大きく妨げているかもしれません。
SFAに全件入力しておけば、商談履歴も課題もすぐに見える化され、誰でもすぐに会話の続きに入れます。
それは、個人の“記憶”からチームの“資産”に変わる瞬間です。
・「担当者の過去発言」を記録しておくと、次回の切り出しが自然になる
・「競合との比較内容」を残しておくと、提案の打ち手に深みが出る
属人化の逆を行くのが、継続受注の近道かもしれません。
まずは、全件入力から始めていきましょう。
PDCAを高速で回せる仕組みを作る
「振り返りはしてるのに、結局何も変わらない」そんな現場、意外と多いですよね。
会議で課題を出しても、次に繋がらなければPDCAはただの自己満です。
ポイントは、“仕組み”で回すこと。感情や気合いに頼らず、自然に改善が回り続ける設計があるだけで、チームのギアが一段変わります。
・「案件失注の理由を1行でSlackに投稿」すると、学びが共有資産になる
・「前日の仮説検証を朝会で発表」すると、現場に“勝ちパターン”が根づく
大事なのは、やる気じゃなくて“仕掛け”です。
改善が動く環境をつくれば、PDCAは勝手に回り始めます。
顧客の事業内容や事前調査は生成AIを活用する
「この会社、結局なにやってるの?」と、商談前に調べ直すこと、ありませんか?
事前情報があやふやなままだと、質問も表面的になり、商談の深度が浅くなりがちです。
でも、今は生成AIを使えば、5分で“会話のネタ”も“仮説”も揃います。
時間をかけるより、“質”を担保するための道具として、AIを使う時代です。
・「コーポレートサイト×IR資料を要約」すると、事業の全体像が瞬時に掴める
・「過去のプレスリリースをAIに整理させる」と、直近の戦略や課題が見えてくる
リサーチは、調べる行為じゃなく“考える準備”です。
生成AIをうまく使えば、インサイトに辿り着くまでのスピードが圧倒的に変わります。
朝会だけでなくリアルタイムでこまめに進捗共有する
「さっきの商談、どこまで話が進んだんだろう?」と感じたことはありませんか?
朝会だけでは、全体像はつかめても、その日のリアルな動きまでは見えにくいものです。
特に、複数案件が同時並行で動く中では、ちょっとした共有の遅れが次のアクションを鈍らせてしまうこともあります。
だからこそ、SlackやSFAを活用して“リアルタイムの小さな進捗”を流すだけで、チームの温度感はグッと上がります。
情報が自然と流れてくれば、他のメンバーがすぐに支援に入ったり、次の打ち手を提案できたりします。
・「Slackに商談メモをリアルタイム投稿」すると、周囲の反応がその場で得られる
・「SFAでタスクの変更点を即更新」すれば、全体の進捗が一目でわかる
進捗共有は“報告”ではなく“つなぎ”です。
こまめな共有が、結果としてスピードある連携を生み出していきます。
成功パターンを社内でナレッジ化する
「あの案件、なんでうまくいったんだっけ?」と聞かれて、言葉に詰まったことはありませんか?
営業現場では成功が“偶然の産物”のように扱われがちですが、それでは再現性が育ちません。
せっかくの勝ちパターンも、記憶の中だけでは次の誰かに引き継がれずに終わってしまいます。
だからこそ、うまくいったプロセスや一言を“ナレッジ”として形に残すことで、チームの底力が上がります。
特別なことをしなくても、日報や共有スプレッドシートに「気づき」を残すだけで効果は十分です。
・「受注理由のヒアリング内容」を残すと、他のメンバーも同じツボを押せる
・「刺さった営業トーク」を蓄積すると、現場の引き出しが増える
ナレッジとは、成功を“仕組みに変える手段”です。
個人の経験が、次の誰かの武器になります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業中級編】成功する営業は知っている”提案の勝ちパターン”
営業の効率化をする7つのメリット
「商談数」が増えて1人の生産性が上がる
商談数が増えるとは、営業1人が扱える案件がシンプルに多くなることです。
つまり、同じ時間で“濃い接点”をたくさん持てる状態を指します。
でも実際は、「数が増えると1件ずつが浅くならないか?」と感じることもあるかもしれません。
実は、質を落とさずに数を増やすには、“前さばき”が鍵になります。
たとえば、「空振りを防ぐために“失注理由でリストを分類する”」「温度感で商談を3ランクに分けて“型”を変える」など、
ポイントは、全部を同じように扱わないことと、入る前に“勝負の見極め”をすることです。
商談が多い=しんどい、ではなく、見通せる=さばける、という状態をつくるだけでも、生産性は驚くほど上がります。
「受注率」が上がってムダな営業が減る
受注率が上がるとは、提案した案件のうち契約につながる確率が高まることを指します。
つまり、同じ動きをしても“成果が出る確度”がぐっと上がるということです。
けれども実際は、「頑張ってもなぜか決まらない…」という商談が続くこともあります。
実は、ムダな営業とは“通らない理由が見えないまま動いてしまう”状態のことが多いです。
たとえば、「意思決定フローを初回で聞き出す」「担当者の評価軸に合わせて資料を作り直す」など、
ポイントは、“誰に”“なぜ”刺さるかを毎回言語化して、再現性を高めることです。
受注率が見える化されると、動きの精度が上がって、商談の質もチームの士気も一気に変わっていきます。
「新人」が早く戦力化できるようになる
新人の戦力化とは、現場で1人分の売上をつくれるようになるまでの時間を短縮することです。
つまり、ゼロからの立ち上がりを“効率よく引き上げる”状態を指します。
でも実際は、「何から教えるべきか」「どこで詰まっているか」が曖昧なまま進んでしまうこともあります。
実は、新人がつまずくのは“何が正解かわからないままやらされる”からです。
たとえば、「初回訪問でのヒアリング項目を“スクリプト化”する」「商談録画に“良い例・悪い例”のコメントをつけて共有する」など、
ポイントは、“型”を見せたうえで、自分で“言語化”させるプロセスをつくることです。
最初の数週間でつかんだ感覚が、その後の成果スピードを大きく左右していきます。
「報連相」が減ってマネジメントが楽になる
報連相が減るとは、現場が自走し、上司への依存が減っていく状態のことです。
つまり、いちいち確認せずとも、営業が自ら判断し、動けるようになるということです。
けれども実際は、「報告が少ない=現場が見えない」と感じ、不安を抱くマネージャーも少なくありません。
実は、仕組みが整えば、報連相を減らしてもマネジメントの精度は落ちないどころか、むしろ楽になります。
たとえば、「SFAで提案進捗を自動記録する」「Slackで商談ログを可視化する」など、
・定型業務を見える化する
・意思決定の基準を事前に共有する
という2点が整えば、細かい報告がなくても判断がズレなくなります。
ポイントは、「報告を減らす=放任」ではなく「判断軸を共有すること」にあります。
一人ひとりが自律的に動けるチームこそ、マネジメントの手間が一番少なくなります。
「資料探し」が不要になって時間が浮く
資料探しが不要になるとは、必要な情報がすぐに手元にある状態のことです。
つまり、誰が・いつ・どこで作ったかを覚えていなくても、探す時間をゼロにできるということです。
けれども実際は、「あの資料、どこにあったっけ?」と、毎回過去のフォルダを掘り返してしまうケースが多いです。
実は、検索性の高い共有環境とルールを整えるだけで、このムダは大きく減らせます。
たとえば、「全商談資料をNotionで一括管理する」「顧客別にBoxでフォルダ整理する」など、
・資料の置き場を一元化する
・検索キーワードをチームで揃える
という2点を意識するだけで、日々の無駄が確実に減っていきます。
ポイントは、「探す」ではなく「すぐ出せる」に変えることです。
1日5分の時短でも、月で見れば営業に使える時間が何時間も生まれます。
「業務分担」が進んで残業が減る
業務分担が進むとは、タスクの偏りがなくなり、全体の稼働効率が上がる状態のことです。
つまり、「できる人に集中する」状態を防ぎ、チーム全体で回すということです。
けれども実際は、「この案件はあの人しか知らない」「引き継ぎが面倒」といった理由で属人化が進んでしまいます。
実は、分担の見える化と引き継ぎの仕組みを整えることで、残業の原因は自然と減らせます。
たとえば、「案件の進捗をTrelloで共有する」「商談履歴をSalesforceに残す」など、
・タスクの可視化を習慣化する
・引き継ぎの基準を明文化する
という2つの工夫で、チームで支え合う体制が作れます。
ポイントは、「頼れる人に任せる」ではなく「誰でも対応できる状態」に変えることです。
属人化をなくすだけで、自然と残業の時間が減っていきます。
「売上予測」が当たるようになって経営判断が速くなる
売上予測が当たるとは、実際の着地に近い数字を早い段階で把握できる状態のことです。
つまり、希望的観測ではなく、根拠に基づいた見立てが立てられるということです。
けれども実際は、「この案件はいけそう」「たぶん今月決まる」など、感覚に頼った見込みが多くなりがちです。
実は、予測の精度は、現場の入力と定義を整えるだけで、大きく変わってきます。
たとえば、「ステージごとの定義を統一する」「失注理由をSalesforceに記録する」など、
・案件の状態を客観的に判断する
・失注要因を定量的に蓄積する
といった仕組みを整えることで、精度の高い数字が自然と溜まっていきます。
ポイントは、「どう感じたか」ではなく「どの状態か」に基づいて判断することです。
正確な売上予測があるだけで、打ち手のスピードと経営判断が格段に変わっていきます。
営業の効率化をする際に気をつけたい3つのポイント
「営業フロー」を固めずにツールを先に入れない
商談の効率を上げたいとき、つい「便利そうなツール」を先に入れたくなることってありませんか?
でも、営業フローが曖昧なままツールだけ導入しても、現場の混乱を招くだけになる可能性があります。
たとえるなら、地図がないのにナビアプリを開くようなものです。
先にやるべきは、チーム全員が迷わず動ける「型」をつくること。
どこで誰が何を入力するか、案件がどの順で進むか——そこを決めてからツールに落とし込むと、仕組みが活きてきます。
では、「何を固めておくと失敗しにくいか?」がポイントです。
・「架電→日程調整→初回訪問→クロージング」の「全体フロー」を整理しておく
・各工程で必ず使う「入力項目」をチームで統一しておく
ツールは、決まった流れがあるからこそ力を発揮します。
その逆に、流れが決まっていないうちは、ツールが足かせになってしまうかもしれません。
「ツール導入」で満足せず、現場が使える設計にする
新しいツールを導入したとき、「これで効率化できるはず」と期待が先行すること、よくありますよね。
でも実際には、現場から「使いにくい」「よくわからない」という声が出て、定着しないまま終わるケースも少なくありません。
その原因の多くは、“現場の流れ”を反映した設計がされていないこと。
導入したツールが、今のワークフローに自然に組み込めていないと、かえって手間が増えることになります。
・「入力項目」が現場のヒアリング内容とズレていないかを確認しておく
・「通知やリマインド」が実務のタイミングに合っているように設計しておく
ツールを“現場に合わせる”視点を持つと、使われ続ける仕組みに変わっていきます。
使えるかどうかは、設計段階で決まっているかもしれません。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【神ツール実演】営業活動をまるごと時短!商談3 …
「数値目標」が曖昧なままでは改善が進まない
営業チームでよくある悩みの一つが、「目標はあるけど、何をすればいいかわからない」という現場の声です。
この背景には、「数値目標」の設計があいまいなまま、現場に落とされてしまっていることがあります。
たとえば、「受注を増やす」という指示だけでは、何に注力すべきか判断できません。
改善には、行動に直結する“目指すべき数字”が必要です。
・「アポ数」「初回訪問率」などの「分解目標」を定めておく
・「週次で見直すKPI」を営業チームと共通認識にしておく
改善のヒントは、抽象的な“売上”ではなく、日々のアクションを数字で見える化することにあります。
動きを変えるには、まず数字を明確にすることからかもしれません。
営業効率化支援サービスを導入する際の3つのポイント
「営業現場に強い会社」かを実績で見極める
導入前はどこも「成果が出る」と言います。でも、現場で使われなければ、結局はただの飾りです。
数字よりも、“誰が・どう使って・どう変わったか”が語れるかが肝です。
営業現場を歩いたことがない会社には、現場の泥臭さも、小さなつまずきも見えません。
だからこそ、実績は「導入数」ではなく「現場が動いたか」で見ると、失敗が減ります。
・「現場の営業が自走した実例」があると、再現性が高まる
・「商談の勝ち筋を変えた事例」があれば、現場にも刺さりやすい
実績の見方ひとつで、パートナー選びの精度は大きく変わってくるかもしれません。
「定着支援」までしてくれるかを確認する
ツールは“入れたら終わり”じゃありません。
導入だけで現場が動くなら、誰も苦労しませんよね。
結局、支援の質は「使いこなすまで並走してくれるか」で決まります。
現場が迷ったとき、すぐ伴走できるかどうかが、定着と形骸化の分かれ道です。
・「現場向けの運用マニュアル」があると、導入後の混乱を減らせる
・「初動3ヶ月の伴走支援」があると、定着率が格段に高まりやすい
定着とは、システムが使われ続けることではなく、成果につながる運用が根づくことかもしれません。
「導入〜成果までの期間」が明確かどうかを聞く
「成果が出るまでどのくらい?」この質問に、明確に答えられない会社は要注意です。
導入の決断は、“ゴールまでの道筋”が見えてこそ価値があります。
現場が動くには、いつ何をするのかを具体的に描ける計画が必要です。
ふわっとした説明では、現場の温度感は上がりません。
・「導入から成果までのスケジュール」を提示できると、動きが加速しやすい
・「週単位のアクション設計」があると、営業も目的意識を持って取り組める
時間はコスト。成果までの距離が測れない支援に、現場は付き合いきれないかもしれません。
営業効率化で役立つCRM/SFAツール7選
「HubSpot」で初回接触〜ナーチャリングを自動化する
初回接触〜ナーチャリングの自動化とは、見込み顧客との最初の接点から継続的な情報提供までを、シナリオ設計に基づいて自動で進めることです。
つまり、「最適なタイミングで最適な情報を届ける仕組みを先に作っておく」ということです。
けれども実際には、「誰に・何を・いつ送るか」を都度考えている営業チームも多く、対応が後手に回ってしまう場面があります。
実は、HubSpotの「ワークフロー機能」や「スコアリング機能」を活用することで、こうした手動対応から脱却しやすくなります。
たとえば、「資料DL後に自動でフォローメールを送る」「スコアが一定以上のリードにだけ電話で接触する」など
・ホットリードを見極める
・情報提供を自動で進める
といった動きを、営業が介入せずに仕掛けられます。
ポイントは、売り込みではなく「関係性の設計」として自動化を使うことです。
初回接触から提案前までの時間を、もっと価値ある時間に変えるために、自動化の流れを見直してみるのもいいかもしれません。
「Salesforce」で案件の全体像を可視化する
案件の全体像を可視化するとは、営業活動の各プロセスやボトルネックを一画面で把握できる状態にすることです。
つまり、個別の営業活動を“つながったストーリー”として見えるようにすることが目的です。
ですが実際には、「今どの案件がどの段階か?」が曖昧なまま進めてしまい、抜け漏れやタイミングロスが発生しているケースが多いです。
実は、情報は記録していても、それが見える形で整理されていないと、チームでの連携も、次の一手も判断できない状態になってしまいます。
たとえば、「フェーズが停滞している案件を一覧で確認する」「決裁者との接点履歴をチームで共有する」など、Salesforceのレポートやダッシュボードを使うことで、
・案件ごとの進捗を把握する
・ボトルネックを可視化する
という動きが、現場レベルで可能になります。
ポイントは、単なる入力ではなく、「誰が・いつ・どの情報を見るか」を前提に、可視化の設計をすることです。
情報が整理されていれば、進捗確認も、次のアクション設定も、迷いなく進めやすくなります。
「Senses」で直感的に商談を管理できるようにする
商談管理の直感性とは、感覚的に「今どこに何があるか」を理解できるUIや操作性のことを指します。
つまり、「見るだけで次の動きがわかる」状態をつくることです。
とはいえ現場では、「管理のための入力作業」に追われ、かえって営業効率が下がってしまうケースも少なくありません。
実は、Sensesには営業の思考の流れに沿って設計されたボードやステータス機能があり、入力も確認も、考える順番のままで操作できます。
たとえば、「ボード画面で提案中の案件を一目で把握する」「タグ機能で条件別に案件を抽出する」など
・進捗の滞留を早期に察知する
・打ち手を先回りで検討する
といった動きが、誰でも自然にできるようになります。
ポイントは、「使いやすいから使う」環境を作ることです。
商談の状況をチームで共有しやすくするためにも、まずは自分の商談をSensesで“見える化”してみると良いかもしれません。
「Sansan」で名刺から自動で接点を記録する
接点の記録とは、顧客との最初の接触情報を、正確かつ漏れなく残すことを指します。
つまり、「営業個人の頭の中」にある情報を、チーム全体で共有できる形にするということです。
とはいえ現場では、名刺交換だけして記録せず、商談の入り口がブラックボックス化してしまうケースもあります。
実は、Sansanを使えば、名刺をスキャンするだけで相手の企業情報・部署・接触履歴が即時にデータ化され、顧客管理の初動を自動で整えられます。
たとえば、「展示会で集めた名刺を即日で共有する」「担当変更時に過去の接点履歴を把握する」など
・初回接触を可視化する
・営業引き継ぎを円滑にする
といった動きが、入力の手間なく自然に実現できます。
ポイントは、「データをためること」ではなく「いつでも引き出せる状態をつくる」ことです。
まずは名刺をスキャンする習慣から、情報の土台を整えていくといいかもしれません。
「Mazrica」で受注確度を見ながら優先順位を決める
受注確度とは、商談が成約に至る可能性を数値で可視化した指標です。
つまり、進行中の案件の中で「どこにどれだけ注力するべきか」を判断する軸になります。
ですが実際には、「感覚」でフォローしている営業現場も少なくありません。
実は、Mazricaの「受注確度機能」を活用すると、温度感ではなく確度別に案件を整理できます。
たとえば、「受注確度80%以上の案件を集中フォローする」「確度30%以下は失注理由を再確認する」など
・「確度順に商談を並べ替える」
・「高確度案件にリマインドを設定する」
ポイントは、営業の手応えではなく、確度という“共通言語”で優先順位を整理することです。
確度を使って動く習慣がつくと、チーム内での意思決定も一気にスムーズになります。
「ホットプロファイル」でアポ率の高いリードを見つける
アポ率の高いリードとは、訪問や商談につながる可能性が高い見込み客のことです。
つまり、時間をかけるべき相手を絞り込むことで、無駄なアプローチを減らすという考え方です。
でも実際には、「なんとなく」でテレアポやメールをしてしまうことも多いです。
実は、「ホットプロファイル」ならWeb閲覧履歴や名刺交換履歴をもとに温度感の高い相手を可視化できます。
たとえば、「資料をダウンロードした直後のリードに電話する」「3回以上サイト訪問した企業に優先連絡する」など
・「閲覧ログから関心度を判定する」
・「営業接点履歴から優先度を上げる」
ポイントは、相手の行動から“今まさに情報を探している人”を見つけることです。
目の前にいる“買いたいモード”の相手を逃さないことが、アポ率アップの一番の近道になります。
「kintone」で営業とサポートの情報をつなぐ
営業とサポートの情報連携とは、顧客対応に関するやり取りを部署をまたいで一元管理することです。
つまり、営業が獲得した顧客の背景を、サポート側でも正確に把握できるようにするということです。
けれども現場では、「誰が何を話したか分からないまま引き継がれている」ケースが意外と多いです。
実は、「kintone」を使えば、問い合わせ履歴や要望の経緯を営業とサポートでリアルタイムに共有できます。
たとえば、「導入時の課題をkintoneに記録して引き継ぐ」「問い合わせ対応履歴を営業が事前に確認する」など
・「対応履歴を案件にひも付けて記録する」
・「営業メモをサポート側にも見えるように設定する」
ポイントは、情報の断絶を防ぐことで、顧客の“過去と今”をつなげることです。
チーム全体で同じ顧客に向き合える環境が、信頼のある継続関係を築く支えになります。
営業を効率化する5つの手順
「業務棚卸」でムダな作業をあぶり出す
まずは、普段の業務を棚卸して全体を“見える化”するところから始めます。
業務棚卸とは、日々のタスクをひとつひとつ洗い出し、「必要か」「成果につながっているか」を見極めることです。
ポイントは、「作業単位」で分解し、主観を交えずに“フラットに並べる”ことです。
よくあるのは、「前からやってるから」「誰かに頼まれてるから」で続けている無意識タスクが温存されてしまうこと。
具体的には、「毎朝の報告資料」「手書きで管理しているリスト」「重複している入力作業」など、目的不明な作業を棚卸リストであぶり出します。
一度紙に書き出して、「この作業、無くせないか?」と一歩引いて見直してみてください。
「KPI設計」で注力すべき数字を決める
最初に、「売上を上げるために何を増やすか?」という視点でKPIの軸を整理します。
KPI設計とは、ゴール(売上)から逆算して“注力すべき数字”を明確にする作業です。
大切なのは、「受注数」だけでなく「面談数」や「アポ率」など“手前の行動指標”に落とし込むことです。
ありがちなのは、数字を見て「結果論」で振り返るだけで、改善につながる行動が見えていない状態です。
たとえば、「週5件アポ→面談→成約1件」といった流れが見えていれば、「週7件に増やすには?」という改善も具体的になります。
成果の分岐点になる“行動指標”を、ひとつ決めて日々追いかけてみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
営業の方、特に必見!KGI・KPIの設定方法!
「時間配分」を見直して訪問数を増やす
まず、「1日の使い方」を可視化することで、訪問に使える時間を増やすヒントが見えてきます。
時間配分の見直しとは、訪問以外の“無意識に消えている時間”を棚卸して再配分することです。
カギになるのは、「移動時間」「報告作業」「社内対応」など、訪問以外の時間を具体的に測ることです。
よくあるのは、「今日は動けなかった」と曖昧に終わり、何に時間を取られたかを見直さないままにしてしまうパターンです。
たとえば、「午前のルートを変えて1件増やす」「報告は移動中に音声入力」など、小さな工夫の積み重ねで訪問数は確実に変わります。
“あと1件”のチャンスをつくる意識で、時間の使い方に向き合ってみてください。
「ツール導入」の前に運用の型を決める
営業ツールを入れる前に、「誰が」「何を」「いつやるか」の運用の型を固めておくと、導入後の混乱がかなり減ります。
これは、ツールが“答え”ではなく“手段”だからです。目的や流れが曖昧だと、機能はあっても現場で使われません。
ポイントは「行動の分岐点(たとえば商談化した時など)で、誰がどの情報を記録・共有するのか」を事前に決めておくこと。
よくあるのが、「とりあえず使ってみよう」と始めてしまい、入力ルールがバラバラになって可視化できなくなるケースです。
具体的には、「初回商談後に必ずトークログを記入」「案件の失注理由は週末までに上長がチェック」など、シーンごとの行動ルールを明文化します。
まずは、今の営業フローを紙に書き出すことから始めてみてください。
「毎月レビュー」で改善PDCAを定着させる
営業活動の「やりっぱなし」を防ぐには、月1回の定例レビューが効果的です。
レビューとは、数字だけでなく「なぜそうなったのか?」をチームで振り返る機会のことです。
ポイントは、「事実→仮説→行動」の順で話せる場をつくること。単なる反省会では意味がありません。
ありがちなのは、「〇件足りませんでした」で終わってしまい、具体的な次の一手が見えないケースです。
たとえば、「初回アポの決裁率が前月より低下→提案資料の入りが遅かった可能性→資料テンプレの改善を次週中に実施」というように、1テーマを深掘りします。
まずは、ひとつの数字にフォーカスして「なぜそうなったのか?」を一緒に言語化してみてください。
営業の効率化でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「営業の効率化をがんばっているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
一生懸命テレアポしてもアポが取れず、商談が詰まっても受注に結びつかない。
そのままでは、限られた時間とリソースがムダに消耗されてしまいます。
がんばっているのに結果が出ないのは、単に努力が足りないからではありません。
いま必要なのは、“売れる仕組み”を持つ営業のプロと手を組むことです。
スタジアムの営業代行サービスなら、IT・Web領域に精通した営業経験者が、戦略設計から実行まで一貫してサポート。
「いま忙しくて新しいことに手が回らない…」という方こそ、ぜひ一度頼ってみてください。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
BtoB営業で「売れる人」になる15のコツ|トップ営業が実践する思考法と手順
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業マンが「化ける」まで【11の共通項】マネージャーのための3つの習慣
【脱ダメ営業マン】特徴13選共通パターンと改善4ステップ
営業は数字が全ては錯覚?9つの理由営業の不振を脱却する実践的方法
2025年 最新アウトバウンド営業で成果を出す15のコツ
【完コピOK】テレアポが上手い人の頭の中話し方と思考法をインストールする15の具体的な方法
テレアポの教科書「13のコツ」と電話営業で避けたい5つのNG行動
【例文7選】営業メールの教科書|返信率を高める13のコツ準備〜書き方まで完全解説
営業で「結果を出す」心構え15選|プロが教える思考・習慣・行動原則
営業で結果が出ない5つの理由と13の打開策【考え方が肝】
営業成績が悪い9つの理由|売れない営業の共通点と今日からできる改善策
インサイドセールス15のコツと今すぐ使えるトークフレームワーク3選
2025年最新トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
なぜ勝てない?「勝てる営業組織」のあるべき姿と9つの改革ポイント
営業組織の強化方法「完全ガイド」属人化を防ぐ8ステップ・11の特徴
【管理職必見】部下の飛び込み営業が怖い10の理由/成果に変える7つの指導法
飛び込み営業が「上手い人」に共通する再現性ある11の技術
最終更新日