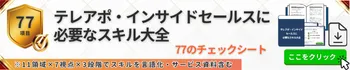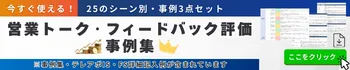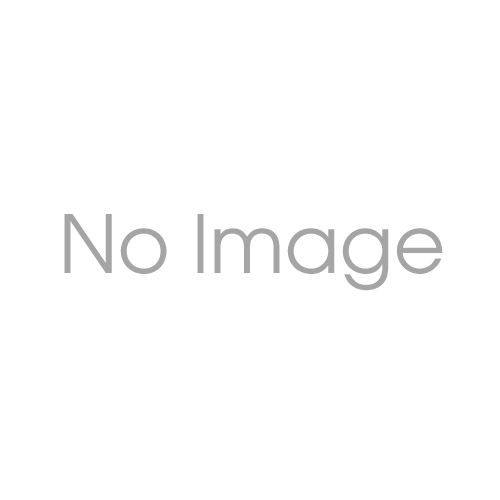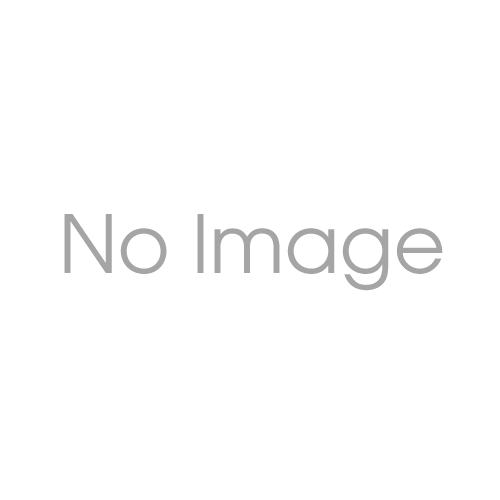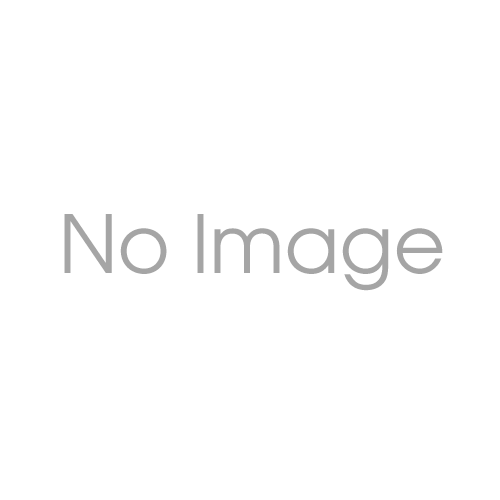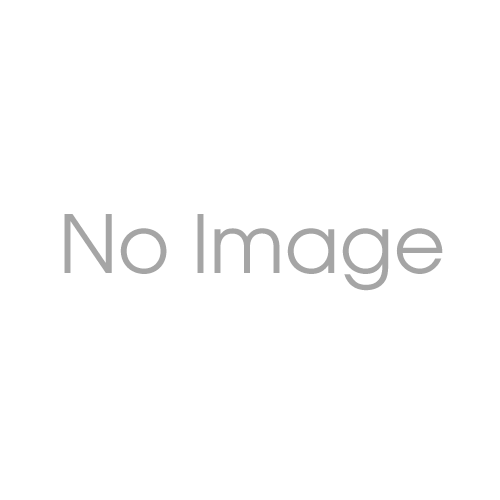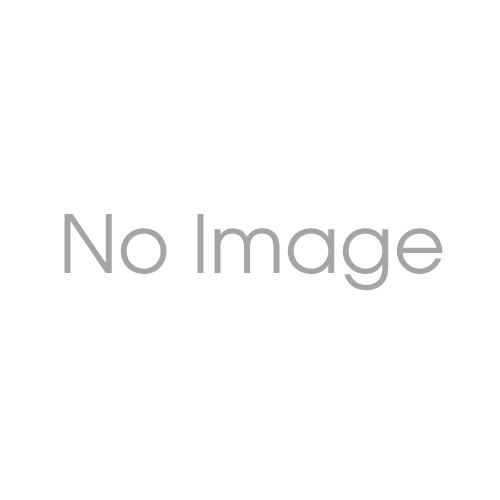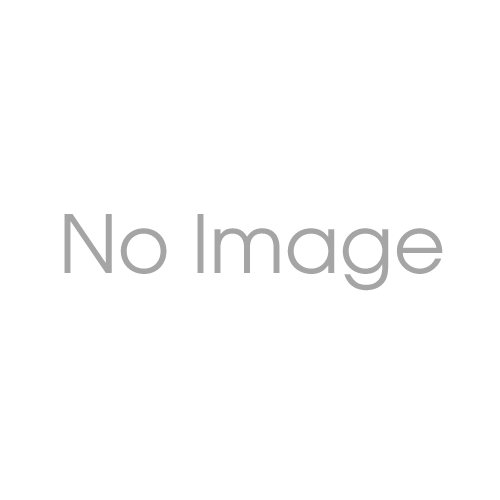【脱ダメ営業マン】特徴13選共通パターンと改善4ステップ
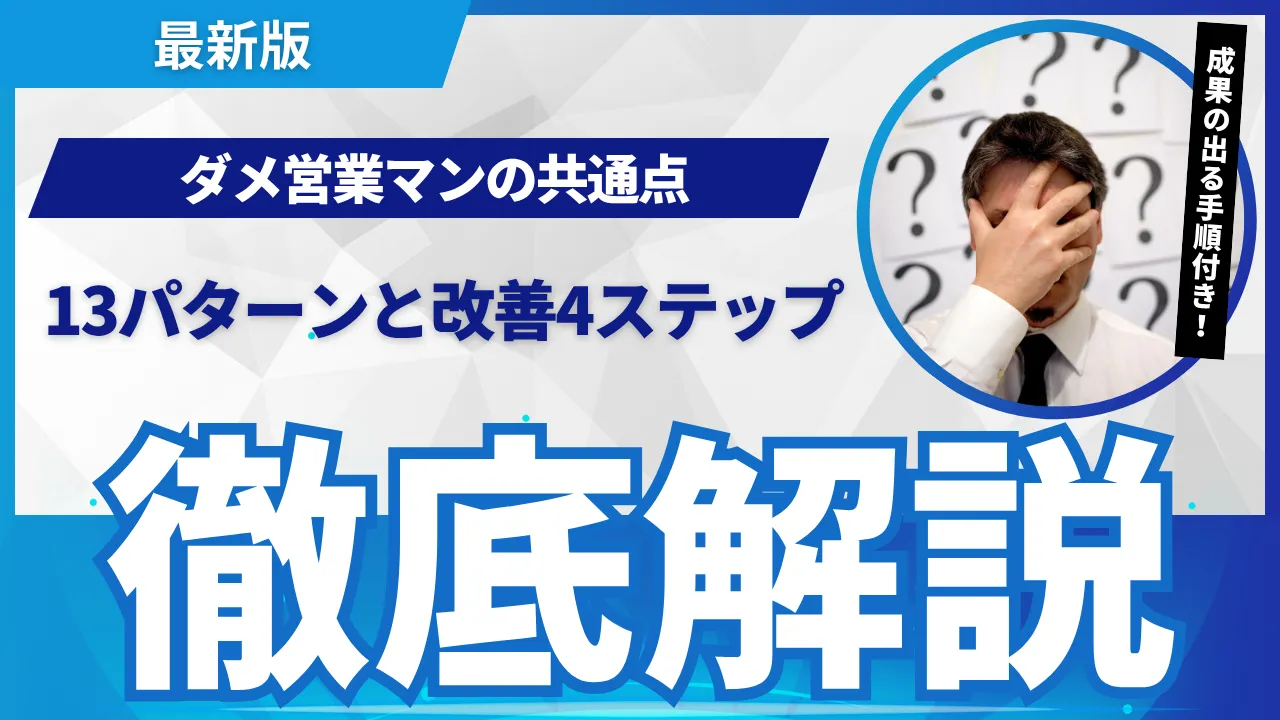
「毎月数字を追ってるのに、なぜか営業で成果が出ない…」
本記事では、現場のプロが見抜いた“ダメ営業の13パターン”から、改善への具体的な打ち手まで徹底解説。
今の自分を変えたい営業マンの方、必見です。
・ダメ営業マンによくある13の共通点(印象・提案ズレ・信頼喪失)
・自分がダメ営業か見抜くための3つのチェック項目(初回商談・ヒアリング深度・ログ改善)
・ダメ営業脱却のための4ステップ改善法(失注分析・AI活用・顧客視点再構築)
現場の営業マンだけでなく、営業マネージャー必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
ダメ営業マンの特徴13選よくある共通パターン
提案のたびに「ヒアリング漏れ」でピントがズレている

ヒアリング漏れとは、商談前〜初回アポ時に「課題の本質」や「社内稟議の構造」を聞きとれず、的外れな提案をしてしまう状態を指します。
つまり、“解像度の低い仮説”のまま提案すると、信頼も意思決定も遠のいてしまうということです。
「この提案、たしかに正しいけど今じゃないんだよね…」営業でそんな反応をされたことはありませんか?
実は、事前に“決裁構造・導入背景・ペインの優先順位”まで押さえきれていないまま資料を作ってしまっている可能性があります。
営業での具体例
・「“稟議ルート”を聞かずにタイミングを見誤る」
・「“内製の事情”を知らずに外注提案してしまう」
・「“KPIインパクト”を聞かずに課題の重みを見誤る」
提案の精度を上げる鍵は、「誰が・何に困り・いつ動けるか」を握っておくことです。
提案前にもう一度、顧客の“決裁者の温度感”と“今動く理由”を自問してみてください。
そこがズレていると、提案は何度でも空回りしてしまいます。
お客様の課題を「プロダクトで押し切る」から刺さらない

「プロダクトで押し切る営業」とは、顧客の課題や背景を深く掘り下げずに、自社サービスの機能や特徴だけを一方的に伝えてしまうアプローチのことです。
つまり、顧客が求めているのは“機能の列挙”ではなく、“状況に合った解決策”であるということです。
「なぜ、こんなにスペックが優れているのに響かないのか?」と営業中に疑問を感じたことはありませんか?
実は、顧客の“ペインの重さ”や“導入の障壁”を整理しないまま提案してしまうと、どうしてもピントがズレてしまいます。
営業での具体例
・「“現場の運用課題”に触れずに機能推しする」
・「“導入コスト感”を把握せずに価格を提示する」
・「“競合との差分”を示さずに強みを押し出す」
営業は商品を売る仕事ではなく、状況に“フィットする活用案”を一緒に描く仕事です。
提案の前に、「この人はなぜ今それを必要としているのか?」を自分の中で一度言語化してみてください。
そのひと手間が、プロダクトを“選ばれる理由”に変えてくれます。
スケジュール調整すら「レス遅すぎ」で商機を逃している
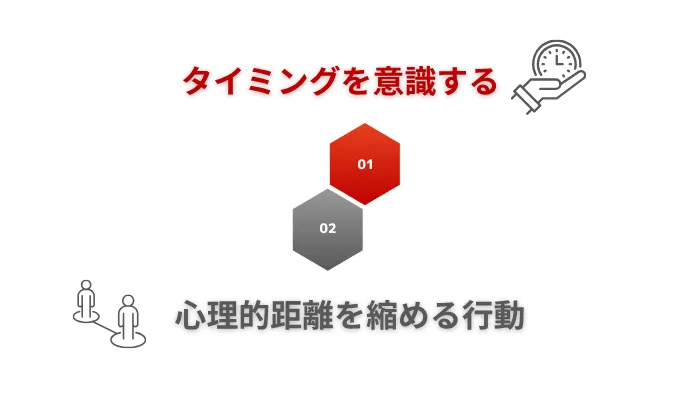
スケジュール調整のレスが遅いとは、顧客からのアポ調整や日程提案への返信が後手に回り、商談の機会を逃してしまう状態を指します。
つまり、“提案前”のスピード感だけで、信頼も優先順位も下がってしまうということです。
「営業って、ここまで反応スピードが大事なの?」と感じたことはありませんか?
実は、BtoB営業でも初動のレスポンスは“タイミングの争奪戦”であり、そこで一歩遅れるだけで他社に流れてしまうケースが多いです。
営業での具体例
・“一次返信”に半日かかり熱が冷める
・“3候補”出すのが遅く競合に先約される
・“調整中”のまま1週間放置して信用を落とす
営業にとって“即レス”は、お客様との“心理的距離を縮める行動”でもあります。
特に日程調整は、スピードと配慮のバランスが問われる最初の関門です。
候補日はその場で3つ送り、Slackや携帯連絡も迷わず活用してみてください。
スピードが、信頼と商機を引き寄せてくれます。
「商談の立ち上がり」で印象悪くしてチャンスを潰している
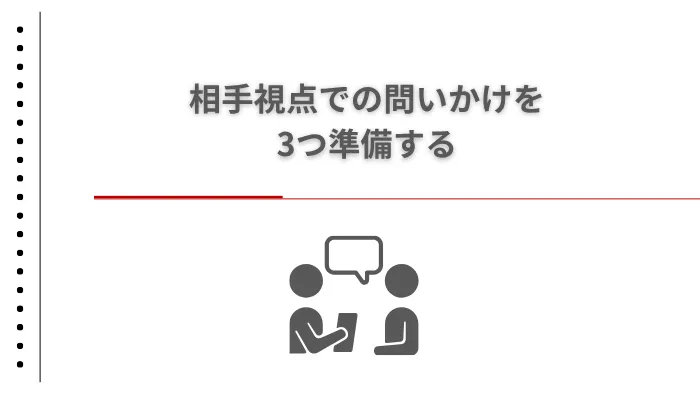
商談の立ち上がりとは、最初の3分間で信頼を得られるかどうかを決める重要な時間帯のことです。
つまり、第一声・第一表情・第一姿勢で、その後の話がどれだけ刺さるかがほぼ決まってしまうということです。
「なぜ、最初は良い反応だったのに途中から空気が冷えたのか?」と感じたことはありませんか?
実は、その違和感の多くは“冒頭の入り方”が相手の期待値に合っていないことが原因かもしれません。
営業での具体例
・「入口の世間話」で雑な印象を与えてしまう
・「本題に急ぎすぎて」警戒感を与えてしまう
・「アイスブレイクで沈黙を作ってしまう」
だからこそ、事前に相手企業の「今の状態」や「関心事」を抑えておくことが、冒頭3分の質を高める最大のポイントになります。
初回訪問の前日は、提案資料ではなく「相手の視点」での問いかけを3つだけ準備してみてください。
空気が変わり、会話が動き出します。
訪問準備なしで「ファクト詰めが甘い」から信頼されない
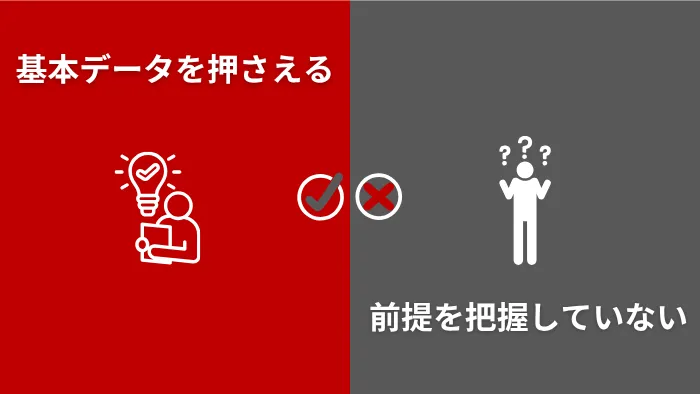
営業における「ファクト詰めが甘い」とは、相手の事業状況や課題を把握せずに訪問することを指します。
つまり、企業情報や市場動向などの基本データを押さえずに話すと、提案が根拠を欠き「なんとなく」の印象になってしまうということです。
「なぜ、この提案は悪くないのに信用されないのか?」と感じたことはありませんか?
実は、その違和感の多くは“調べればわかる情報”を持っていなかったことで、相手の心証を損ねている場合があります。
営業での具体例
・「上場企業なのに業績を知らず訪問する」
・「競合の動きを把握せずに提案する」
・「相手の導入ツールを確認せずに話す」
このように、訪問前に“3つの基本データ(決算・競合・課題)”だけを整理しておくことで、信頼される会話の土台ができます。
準備は難しくありません。
最新トレンド調査とIR情報に15分だけ時間を使ってみてください。相手の反応が一変します。
「受注=ゴール思考」でオンボーディング後が崩壊している
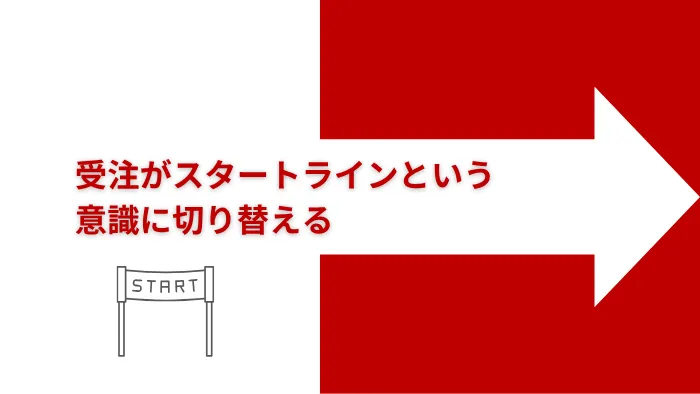
「受注=ゴール思考」とは、契約を取ることだけを目的にし、その後の顧客対応や成果創出まで目を向けない営業スタンスのことです。
つまり、受注した瞬間に気が抜けてしまい、肝心のオンボーディングや立ち上げ支援が疎かになる状態を指します。
「営業は契約までが仕事」と考えてしまっていませんか?
実は、法人営業では受注後こそ信頼が問われ、本当の意味での「価値提供」が始まるタイミングです。
営業での具体例
・「納品直後の問い合わせ」に対応せず信頼を失う
・「運用初月の成果確認」を怠りクレームにつながる
・「カスタマー部門に丸投げ」し社内で孤立する
だからこそ、商談時点でオンボーディング後の支援設計まで描けているかが、営業としての本当の実力に直結します。
“受注がスタートライン”という意識に切り替えることで、契約後の継続や追加提案につながる関係性を築きやすくなります。
まずは、次回商談で「導入後の最初の1ヶ月」まで一緒に設計してみてください。お客様の反応が変わります。
「ロジックなきクロージング」で墓穴を掘っている
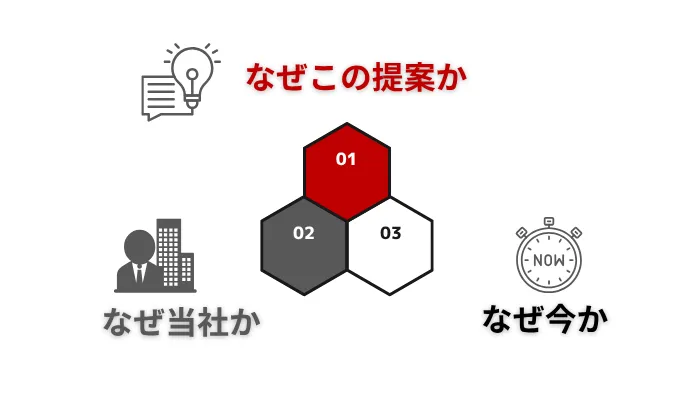
「ロジックなきクロージング」とは、感情や圧力で無理に締めにいこうとし、論理的な筋道が抜け落ちてしまっている営業手法を指します。
つまり、クロージングの根拠が曖昧なまま「決めませんか?」と迫ってしまうことで、相手の不信感を招くケースです。
「なぜこのタイミングで契約なのか?」営業の中で自信を持って説明できていますか?
実は、営業の“押し”が効果を持つのは、その前に「納得の土台」がしっかり積み上がっている時だけです。
営業での具体例
・「導入理由」を整理しきれず不安を残す
・「決裁者のKPI」に触れず反応が鈍る
・「競合との比較軸」が弱く選定理由が曖昧になる
だからこそ、クロージングの前には「なぜこの提案か」「なぜ今か」「なぜ当社か」の3つの納得ポイントを一緒に設計しておくことが鍵になります。
論理が整えば、営業は無理に押す必要がなくなり、お客様自身が“決めたくなる状態”に自然と近づきます。
次の商談では、クロージング前に「この提案を通すと〇〇部の何が変わるか?」を相手と一緒に言語化してみてください。突破口になります。
提案資料が「汎用テンプレ」で相手に刺さらない
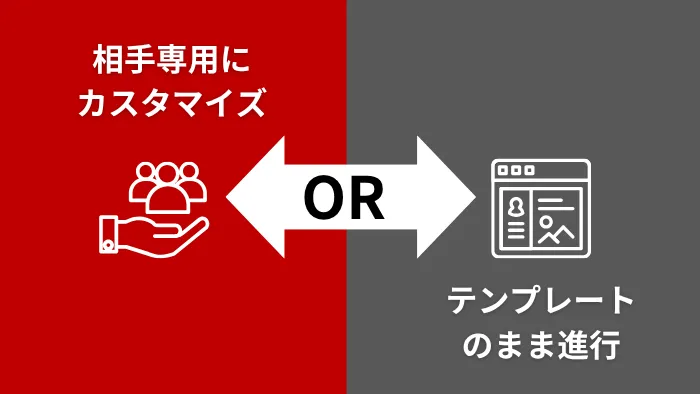
提案資料が“汎用テンプレ”とは、業種も課題も聞かずに最初から用意されているスライドを使いまわす状態を指します。
つまり、どんな相手にも同じ内容を見せてしまい、「自社都合の提案」に見えてしまう可能性があるということです。
「営業でなぜ提案が刺さらなかったのか?」と悩んだ経験はありませんか?
実は、資料の構成が“顧客の課題順”になっていないと、どれだけ優れたサービスでも心に届かないことがあります。
営業での具体例
・「業界特有の課題が一切反映されていない」
・「相手のKPIと関係ない成功事例を出す」
・「ヒアリング内容を資料に落とし込めていない」
だからこそ、資料の冒頭には“相手の課題の言語化”を置いてみることがポイントです。
テンプレのまま進めるのではなく、1スライドでもいいので相手専用にカスタマイズしてみてください。
そのひと手間が、提案の信頼感につながっていきます。
失注理由を「外部要因」で片づけて、自分を省みない
失注の原因を「価格が高かったから」「タイミングが悪かったから」といった外部要因だけで片づけてしまうことは、心理学でいう“自己奉仕バイアス”が働いている状態です。
つまり、自分の責任を避けて「運が悪かった」と思いたくなる心の動きです。
「営業でなぜ成約できなかったのか?」と聞かれて、外部要因ばかりが浮かんだことはありませんか?
実は、見直すべきは“伝え方”や“事前準備”にあるかもしれません。
営業での具体例
・「決裁者の参加を確認せずに商談する」
・「他社比較を深掘りせず提案する」
・「課題の言語化が甘くヒアリングが浅い」
だからこそ、失注の理由に「自分の関わり」を1つ入れてみるだけで、次の商談準備が具体的になります。
商談後の振り返りは、1人で完結せず、チームメンバーと一緒に棚卸ししてみてください。学びが何倍にもなります。
競合比較されても「差別化ポイント」を語れない
差別化とは、顧客に「他社ではなくあなたを選ぶ理由」を明確に伝えることを指します。
つまり、似たような商品やサービスが並ぶ中で、“この会社から買いたい”と思わせる独自性の打ち出しです。
「競合と比べて何が違うの?」と営業で聞かれたこと、ありませんか?
実はこの問いに即答できないと、価格競争に巻き込まれやすくなります。
営業での具体例
・「サービス内容の違い」を言語化できず沈黙する
・「事例トーク」が弱く、納得感を生み出せない
・「貴社専用の提案」に見えず、テンプレ感が出てしまう
だからこそ、“業界特化の実績”や“支援後の成果”など、数字と具体例を使って語れる差別化がカギになります。
自社の強みを「比較される前に」伝える意識を持つだけで、商談の流れは驚くほど変わります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【知らないと危険】競合と差別化する方法について徹底解説!
「トスアップの質」が低く、インサイドに負担をかけている
トスアップとは、アポ獲得時に顧客情報や温度感をインサイドセールスに引き継ぐ行為を指します。
つまり、営業のバトンリレーで「渡し方が雑」だと、せっかくの商談機会を無駄にしてしまうんです。
「ちゃんと聞いたって言ってなかった?」そんな会話、営業現場でありませんか?
実は、トスアップの質が低いと、受注率に直結して悪影響が出る可能性があります。
営業での具体例
・「決裁者の有無」をヒアリングせずに引き継ぐ
・「興味のポイント」が曖昧で、初回提案がズレる
・「他社導入状況」を未確認で、競合負けする
だからこそ、「誰に」「何を」「なぜ今」を正確に伝えるだけで、インサイドの負担も軽くなり、商談の質も上がります。
商談ログのテンプレに3つの必須情報を入れておくだけで、トスアップの質は一気に改善できます。
商談ログや録音を「活用せず放置」で改善しない
商談ログや録音は、営業の行動や提案の質を振り返り、改善につなげるための「可視化された財産」です。
つまり、一度きりの商談を“振り返ることなく流してしまう”と、何度やっても同じミスを繰り返してしまう可能性が高いということです。
「なぜ、同じような失注が続くのか?」と悩んだことはありませんか?
実は、営業パフォーマンスの多くは“再現性”よりも“気づき”の積み重ねによって磨かれる傾向があります。
営業での具体例
・「失注理由」が毎回ふわっとしていて残る
・「提案タイミング」を間違えたまま気づけない
・「競合対策トーク」が弱いまま放置してしまう
だからこそ、過去の録音を聞き返し、「どの瞬間で流れが変わったのか?」を冷静に見つめることが、次の打ち手につながる一歩になります。
まずは週に1回だけ、自分の商談録音を10分聞き返す時間をつくってみてください。話し方や流れのクセに、気づけるはずです。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【徹底解説】文字起こしAI「tl;dv」で議事録生成/商談分析/Slack&Notionへの通知
生成AIを「アイデア出しや壁打ち」に使わず機会損失している
生成AIとは、大量の情報を元に文章やアイデアを即時に出力できるツールの総称です。
つまり、“アイデアが浮かばない”“何から考えていいか分からない”という営業の思考停止状態を打破できる存在です。
「提案書が毎回パターン化して、マンネリしていないか?」と感じたことはありませんか?
実は、生成AIは“思考のたたき台”として使うことで、発想の幅や仮説の質を高める支援をしてくれる可能性があります。
営業での具体例
・「ヒアリング質問」が毎回似た内容になってしまう
・「提案書の切り口」が毎回同じで通らない
・「クロージングトーク」で詰まり沈黙してしまう
だからこそ、「まずAIに聞いてみる」という習慣が、思考のバリエーションを一気に広げてくれます。
“壁打ち役が社内にいない”ときこそ、生成AIに問いかけてみてください。驚くほど思考が進みます。
ダメ営業マン脱却のために明日からできること
生成AIで「失注ログ分析」し、打ち手を即日で再設計
失注ログ分析とは、過去の失注理由や商談の流れを記録・整理し、次のアクションに活かす営業手法のことです。
つまり、「なぜ失注したか」を言語化することで、改善の方向性が見えてくるということです。
「営業で、何をどう変えたら再現性のある勝ちパターンになるのか?」と悩んだことはありませんか?
実は、生成AIを使えば、過去のログから“今すぐ”改善すべきポイントが具体的に浮かび上がります。
営業での具体例
・「失注理由の共通点」を自動で抽出する
・「決裁者NGの傾向」を分類して可視化する
・「提案内容のズレ」を構造的に言語化する
だからこそ、生成AIによって、失注の山も貴重な“勝ちパターンの地図”に変わっていきます。
今日の失注を、明日の受注につなげる第一歩として、AIにログを読ませてみるとヒントが得られるかもしれません。
「プリカスタマージャーニー」から逆算して提案を組み立てる
プリカスタマージャーニーとは、商談前の顧客の行動や心理変化を予測・設計する営業視点のフレームワークです。
つまり、「お客様が商談に至るまでに、どんな情報や体験を経ているか」を見立てておくことが鍵になります。
「営業で、なぜあの提案は刺さったのに、今回は全く響かなかったのか?」と感じたことはありませんか?
実は、事前の“顧客の思考ルート”を理解しているかどうかで、提案の精度も反応も大きく変わってきます。
営業での具体例
・「Webで製品比較を済ませてから」問い合わせする
・「過去に別部署で導入を検討していた」経緯がある
・「稟議前に現場の声を吸い上げる必要がある」状況である
だからこそ、商談の前に「このお客様は今、どの段階にいるか?」を想定し、その前提に沿った提案を組み立てることが重要になります。
“誰に、どのタイミングで、何を届けるか”を少しだけ立ち止まって考えてみると、受注にぐっと近づくかもしれません。
今、自分大丈夫?ダメ営業マンかどうか見分ける3つの方法
「初回商談の掴み」で信頼を取りこぼしていないかを見る
「営業の初回商談、“興味を持たれる前提”で話していませんか?」
実は、お客様は最初からこちらの話を聞く気満々ではありません。
だからこそ「掴み」のひと言で空気を変えられるかどうかが、商談の成否を左右します。
ここで信頼の種をまけなければ、いくら商品説明を頑張っても刺さりません。
「他社でも同じ話してるんでしょ」と思われた瞬間、営業は終わります。
だから冒頭は“相手視点”でドキッとさせる問いかけが効果的です。
たとえば
- 「御社の“○○のKPI”、今期どう変わってますか?」
- 「前任の方が一番苦戦された“業務プロセス”、今も残ってますか?」
掴みは準備が9割。リサーチと仮説で、相手の“今”に触れる一言を投げるだけで、信頼の温度が一気に変わります。
提案内容が「ヒアリングの深度」に比例しているかを確認する
「営業の提案、それは本当に“聞いたこと”に基づいていますか?」
商談後に残る違和感の正体は、実は“浅いヒアリング”からくるものが多いです。
課題の表層だけを拾って提案しても、「ありがちな提案ですね」で終わってしまいます。
深度が浅ければ、提案の精度も熱量も上がりません。
本当に刺さる提案は、「なぜ今やるのか」「放置したら何が起きるのか」まで踏み込んだヒアリングから生まれます。
たとえば
- 「そのKPIが最重要になった背景って、何か変化があったんですか?」
- 「もし現状を半年放置すると、どんな影響が出そうですか?」
営業は“聞き方”で未来の説得力が変わります。
提案が通るかどうかは、ヒアリングの“掘り方”次第です。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業のプロが解説】最高な提案に繋げるヒアリング術とは?
お客様のKGI/KPIから逆算した「売上貢献ストーリー」を描ける
KGI/KPIとは、企業が目指す最終ゴール(KGI)と、その達成度を測る中間指標(KPI)のことです。
つまり、お客様が追っている数字の構造を理解することで、営業提案も“売るため”から“成果に繋げる”提案に変わります。
「営業で、提案内容が良かったはずなのに決まらなかった…」そんな経験はありませんか?
実は、商材の魅力よりも、“自社の目標にどう効くか”が語られていないと、決裁者は動かないことがあります。
営業での具体例
・「リード数を3倍にしたい」KPIに対して提案する
・「営業単価を20%向上させたい」背景を深掘る
・「来期のARR成長率を重視している」意図を共有する
だからこそ、提案書には“この施策が御社のKGIにどう効くのか”というストーリーを一行で語れることが強みになります。
資料を作る前に「この提案は、どの数字に寄与するのか?」と1回自問してみると、受注率は一気に変わるかもしれません。
『脱ダメ営業マン』を叶える習慣
「商談録音×生成AI」で自分のトークを棚卸しする習慣をつける
「この営業トーク、本当に響いているんだろうか?」と感じたことはありませんか?
感覚に頼った営業は、気づかぬうちに“ズレ”が蓄積します。とくに、自分の話し方や質問の深さは、主観では見えにくいからです。
だからこそ、商談録音を生成AIで振り返る習慣が、ズレ修正の最短ルートになります。
生成AIなら、自分のトークを要約・可視化し、「何を」「どう」伝えていたかが一目で整理できます。曖昧だった仮説やヒアリングの甘さも、毎回の録音で浮き彫りになります。
- 「録音内容から“提案前の質問数”を自動でカウント」
- 「生成AIが“温度感の高い発言”だけを抽出して一覧化」
こうした機能を活かせば、毎回の商談が“検証素材”になります。
営業は、振り返る習慣があるかないかで、伸び幅がまるで違います。
▼編集部のおすすめ動画を見る
AiNote×ChatGPTで営業トークを分析。激変する営業
案件ごとに「仮説→検証→打ち手」の流れを仕組み化する
営業の打ち手、行き当たりばったりになっていませんか?
気合いや感覚に頼るだけでは、成果は安定しません。特に複雑なBtoB営業では、仮説の精度と検証の仕方が、受注率を大きく左右します。
だからこそ「仮説→検証→打ち手」の流れを、案件ごとに“型”として回すことが重要です。
仮説は、決裁者の課題や導入目的に紐づけて立てます。検証は、商談中のやり取りや反応で裏を取る。打ち手は、検証結果に基づいて提案内容やアプローチを調整する。
これを繰り返せば、商談の精度が着実に上がっていきます。
- 「初回商談で“決裁者のKPI仮説”をメモに明記」
- 「反応を基に“次回の提案軸”をスライド1枚で明文化」
この流れが定着すれば、商談のたびに精度が磨かれ、再現性の高い営業力へと変わっていきます。
「フェーズ別KPI」を自分で再定義して行動を具体化する
「今月、何をどれだけやれば受注に近づくのか?」営業でこの問いに即答できますか?
多くのKPIはチーム全体で定められた“共通指標”ですが、案件の質や営業スキルによって必要な行動量は大きく異なります。
だからこそ、自分の営業プロセスに合わせて「フェーズ別KPI」を再定義することが、最短ルートで成果を出す鍵になります。
たとえば、初回アポでは「決裁者との接点率」、提案フェーズでは「再訪時の合意率」など、各フェーズで“成果に直結する行動”を明確に設定する。
すると、日々の行動が数字とつながり、迷いがなくなります。
- 「初回訪問から“次回打ち合わせ確約率”をKPI化」
- 「提案段階では“決裁者同席商談率”を追うように変更」
この再定義を自分の言葉で行えば、指標が“ノルマ”から“行動の地図”に変わります。行動の濃度が、自然と上がっていきます。
商談ごとに「バリュープロポジション」を明確にする癖をつける
バリュープロポジションを曖昧なまま話すと、相手の頭に「で、何がいいの?」が残ります。
商談前に「このお客さんにとっての“嬉しい変化”は何か?」を一言で言えるまで、言葉を削ぎ落とす作業が欠かせません。
ポイントは「自社視点の強み」ではなく、「相手の現場で何が変わるか」の一点に絞ることです。
よくある間違いは、機能や価格の話で説得しようとすること。これは“モノの話”であって、“意味”の話ではありません。
例えば、「人事評価の面談時間が半分になります」と言えば、相手の中に“時短=評価制度の効率化”という具体イメージが立ちます。
商談前に30秒、自問してみてください。「この人にとって何が変わる?」と。そこから始まる言葉には、説得力が宿ります。
「失注理由の言語化」から逃げずに自己分析を徹底する
商談が終わった直後の5分は、営業を変える一番のゴールデンタイムです。
「なぜダメだったか」を、感覚ではなく“相手の言葉ベース”で言語化する習慣が大切です。
ポイントは「価格が高いと言われた=価格がネック」ではなく、「なぜ高く感じたのか?」まで掘ること。
よくあるのは、「フィーリングが合わなかった」「競合に負けた」で済ませてしまうことですが、これは“逃げ”に近いです。
例えば、「担当者が上司を説得できる材料を渡せなかった」という分析なら、次からは資料の構成や説明順を変えるヒントになります。
悔しさの熱が冷めないうちに、自分の言葉で“なぜ”を一行で書き出す。これを繰り返すことで、営業の質は確実に変わります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
営業×生成AI】業務効率化の方法おすすめ8選を解説!【ChatGPT】
生成AIで「過去成功パターン」を抽出し提案フローを構築する
まずは、過去に受注につながった商談記録を、生成AIに読み込ませてみてください。
成功の共通点を抽出してもらうことで、「どの順番で」「どんな切り口で」話を進めたときに決まりやすいかが見えてきます。
ここで重要なのは、“話した内容”だけでなく、“相手の反応や質問内容”にも注目することです。
ありがちなミスは、提案書の構成だけを真似してしまい、商談の流れ自体をなぞらないことです。
具体的には、ChatGPTなどに「過去5件の受注内容から提案の切り出し方と受注理由を整理して」と指示を出すと、流れの型が見えてきます。
その型に沿って、次の提案トークの台本を仮組みしてみると、受注確率が一気に高まる可能性があります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
営業に生成AIはどう活かす?「リアルな事例」から考える
「カスタマージャーニーに沿った打ち手」を再設計してPDCAを回す
まずは、見込顧客が出会いから契約に至るまでの行動をステップごとに書き出してみてください。
「いつ、どこで、何を考えているか?」を見える化することで、打ち手のズレがはっきりします。
ポイントは、各ステージごとに“次の一歩”を自然に後押しできているかを見直すことです。
よくあるのは、興味を持った直後にいきなり提案を押し込んで、相手の温度感とチグハグになるパターンです。
例えば、「比較検討フェーズ」には事例記事を送る、「導入検討フェーズ」には初期費用の柔軟対応を提示するなど、段階に応じた打ち手に調整するのがコツです。
その上で、一度設計した流れは終わりではなく、反応を見て定期的に微調整していくことで、成果に直結していきます。
営業でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「営業をがんばっているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
数字に追われ、リードも枯渇気味。部下のモチベーションも上がらず、自分ばかりが空回りしているような感覚に、心が折れそうになることもありますよね。
でも、そんなときこそ、一人で抱え込まず、頼れる外部の力を借りる選択肢があることを思い出してください。
弊社スタジアムの営業代行サービスなら、実績ある営業のプロが戦略立案から実行まで一貫して支援します。
今まさに、営業組織の見直しや新規開拓を強化したいと考えているマネージャーの方にこそ、一度ご相談いただきたいです。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き
【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説
営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順
【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版
インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集
営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文
【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全
【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集
【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!
アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説
【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略
【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説
法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略
【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説
深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順
営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善
13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド
営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション
営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順
【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版
【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集
営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド
営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別
【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果
【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順
【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順
【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点
営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順
【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド
【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き
営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順
できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法
売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法
プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順
【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き
営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策
【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説
【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説
なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術
新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順
営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説
なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法
ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP
ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集
飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法
【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド
【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版
セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法
セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド
新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版
新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全
【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説
新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ
新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法
【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版
【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集
アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法
インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順
【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版
【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法
SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法
MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説
BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法
BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略
BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順
【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版
【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ
【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説
営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選
FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド
【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方
14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順
アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ
シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ
これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順
【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集
【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP
【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説
営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ
御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP
【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順
【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集
営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法
営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順
27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場
【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順
営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準
新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル
営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント
クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順
営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説
営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順
営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順
最終更新日