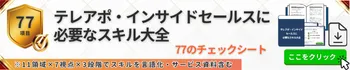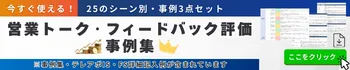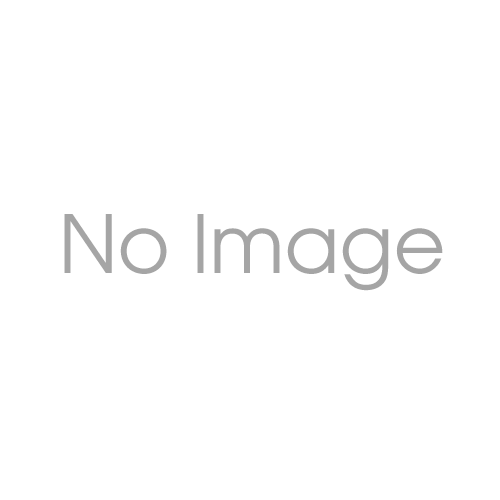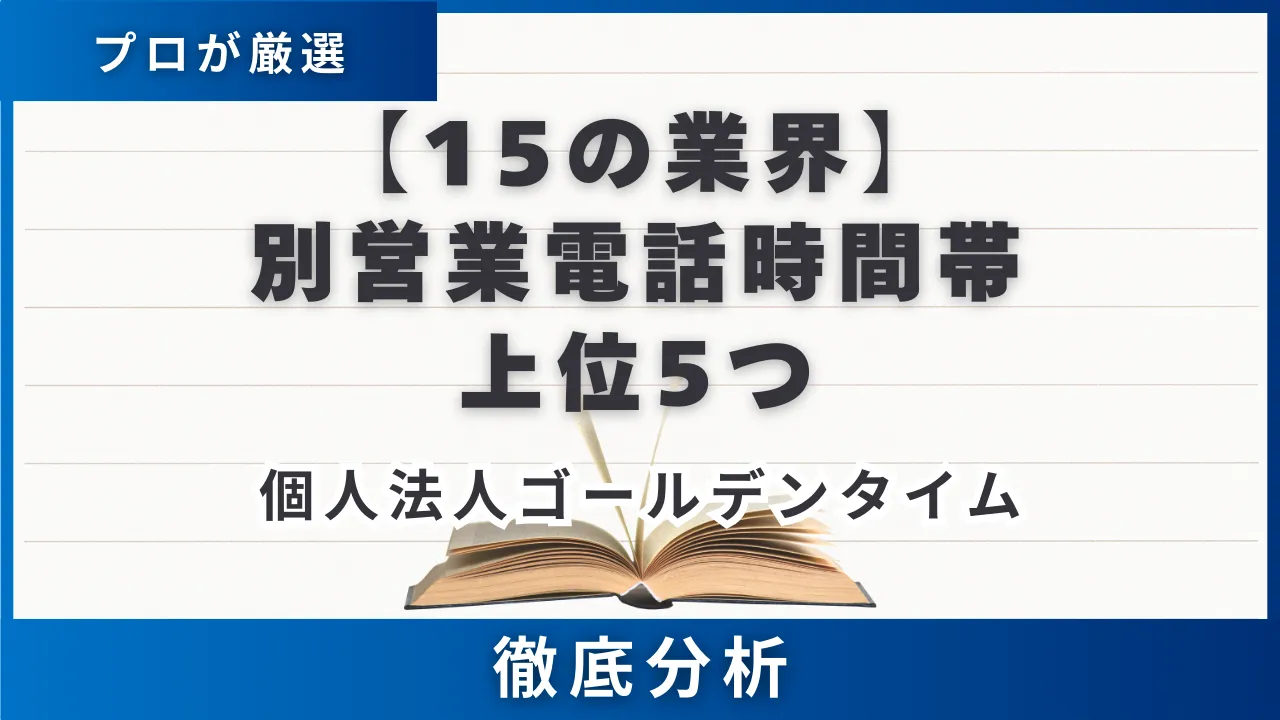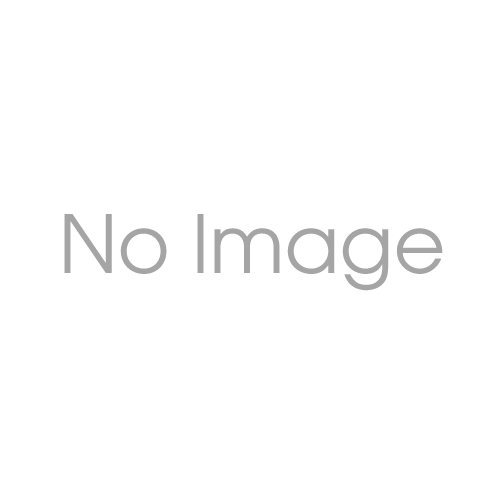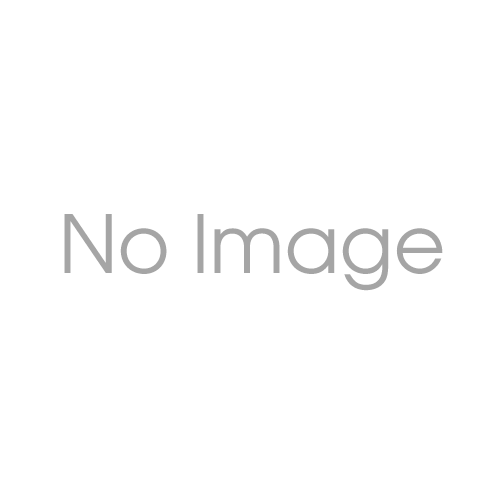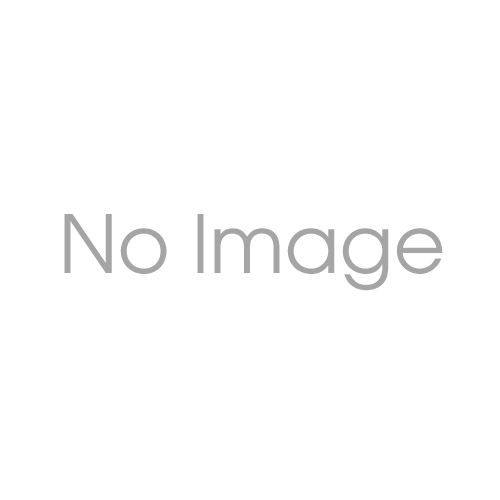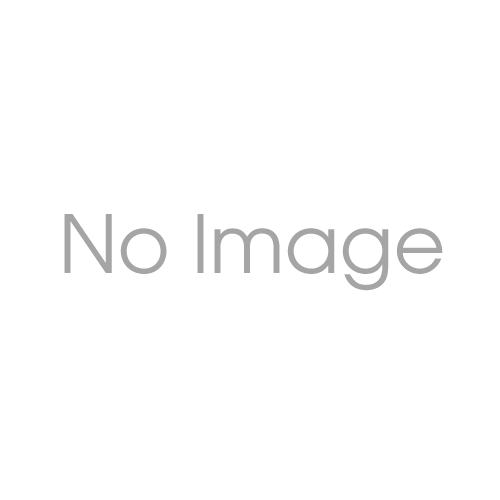【プロが解説】THE MODELとは?要約・営業プロセスを徹底解説
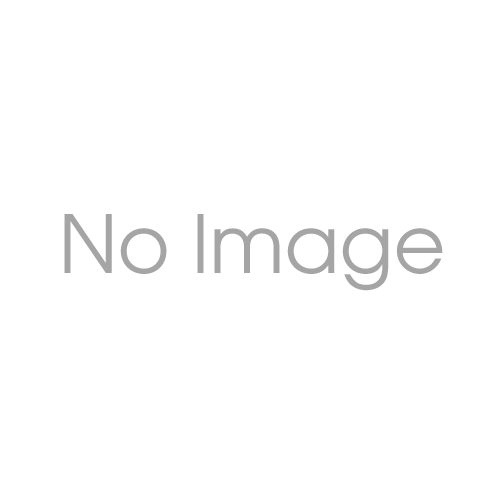
「THE MODEL型営業」、SaaSサービスの台頭と並行して組織作りの1つのパターンとして語られるシーンも増えてきている一方でその目的や効果、推進する上での課題を知る機会は多くありません。
実際、分業スタイルを導入したものの成果に結びつかず悩む企業も多いのではないでしょうか?。
しかし正しい理解と運用次第で、その真価は確実に発揮されます。
・「THE MODEL」型分業スタイルの強み(生産性・ボトルネック解消・購買行動の変化)
・「THE MODEL」型分業スタイルの注意点(部門間連携・負担増・全体最適)
・「THE MODEL」分業プロセスを担う4部門(マーケ・IS・FS・CS)
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
THE MODEL(ザ・モデル)とは?1分で要約
THE MODEL(ザ・モデル)とは
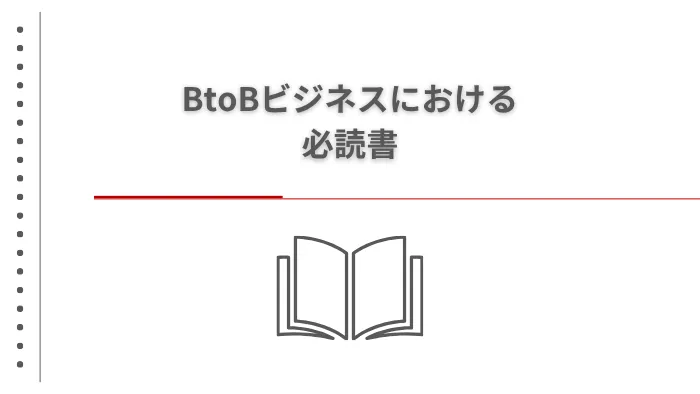
『THE MODEL(ザ・モデル)』は、2019年に翔泳社から刊行された福田康隆氏による著書で、米セールスフォース・ドットコム社で実践されていた営業分業の仕組みを体系的にまとめた、BtoBビジネスにおける必読書です。
近年ではSaas事業やリモートワークの普及や多様なITツールの台頭を背景に、多くの企業が営業体制を見直しています。そうした潮流の中で、この一冊は営業プロセスを抜本的に改善するための知見が得られる書籍として、高い支持を集めています。
THE MODELの概念

本書で語られる「THE MODEL」とは、セールスフォース社が実践するBtoBマーケティングおよび営業活動を、明確に役割分担した体制のことです。
具体的には以下の4つのプロセスに分かれています。
- マーケティング:見込み顧客の創出
- インサイドセールス:顧客育成・商談化
- フィールドセールス:クロージングを担う営業
- カスタマーサクセス:成約後の顧客支援と成功体験の提供
それぞれのフェーズごとに責任範囲とKPIを明確に設定し、部門横断的に連携することで、営業の効率化と売上拡大を実現する仕組みです。
THE MODELが注目される理由
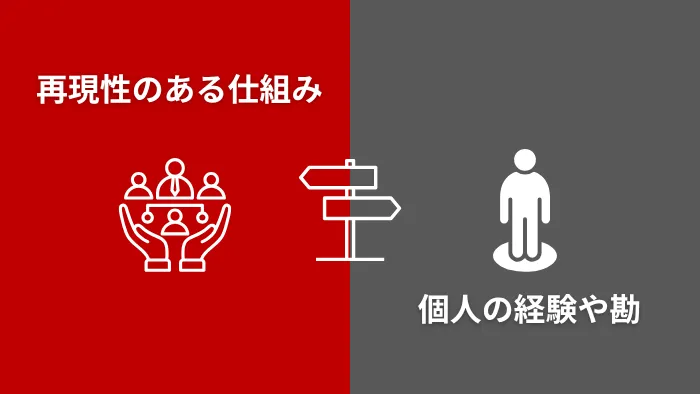
THE MODELが注目される理由は、営業を「個人の経験や勘」に頼らず、再現性のある仕組みに変えることができるからです。
プロセスを分業化し、各部門が専門性を発揮することで、成果が属人化せず安定して積み上げていきます。
このように役割を明確に分けることで、見込客を集め、育成し、商談化し、契約につなげ、その後の継続利用や追加契約にまでつなげられる流れが整います。
具体的には、
1.マーケティングがリードを獲得し、
2.インサイドセールスが関心度を高め、
3.営業が契約をまとめ、
4.カスタマーサクセスが顧客満足を維持する
という一連の連携です。
このようにして、ザモデル型営業を取り入れている組織は人材に依存せずに成長を続けられ、多くの経営者や現場から支持を集めているのです。
著者・福田康隆氏について
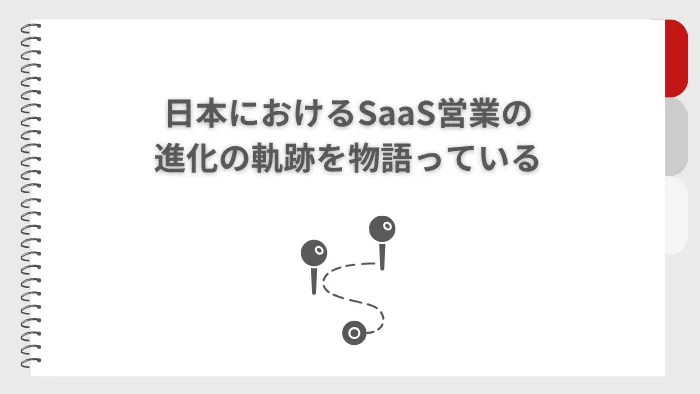
福田康隆氏は、日本のSaaS業界を牽引してきた第一人者です。
IT企業にて営業キャリアを積み、Salesforce.comにて日本市場のオペレーションを担当。
『THE MODEL』は理論だけでなく、実務で成果を出すための生きた知恵の集大成です。
福田氏の歩みそのものが、日本におけるSaaS営業の進化の軌跡を物語っていると言えます。
【THE MODEL(福田康隆 著):マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス】
参考【SaaS時代に必須の本『The Model(ザ・モデル)』とは – FLUED】
THE MODEL(ザ・モデル)要約・営業プロセス詳細解説
THE MODELの仕組み
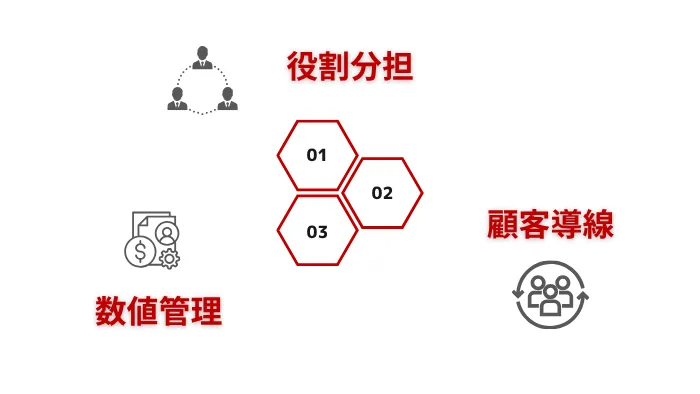
THE MODELの仕組みは、営業活動を四つの役割に分けて、それぞれがリレーのように顧客を引き渡しながら成果を積み上げる点にあります。
なぜなら、マーケティングが集めたリードをインサイドセールスが育成し、営業が契約をまとめ、カスタマーサクセスが継続や拡大を担うことで、流れが途切れず収益が最大化するからです。
部門ごとにKPIを設定して数値で管理すれば、どこで停滞しているかを即座に把握でき、改善の打ち手を明確にできるのです。
たとえば、商談数が少なければリード育成を強化し、解約率が高ければサクセスの支援体制を見直すなど、具体的な改善が可能になります。
だからこそTHE MODELは、現場の活動を数値で結びつけ、全体最適で収益を伸ばす強力な仕組みといえるのです。
レベニューモデルとは?
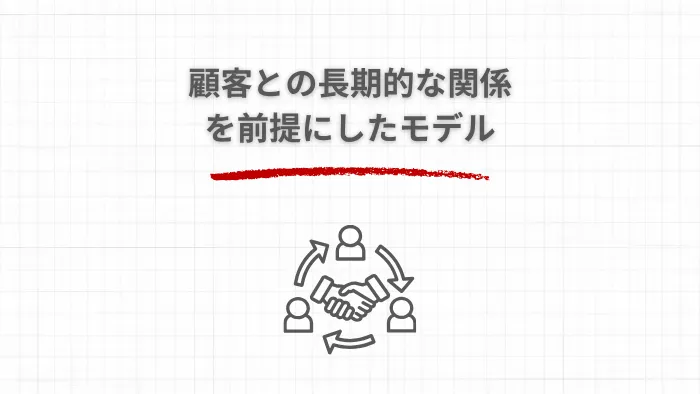
レベニューモデルとは、企業が「どのように収益を生み出し続けるか」を設計する考え方です。
単に売上を上げる方法ではなく、顧客との長期的な関係を前提にしたモデルです。
顧客獲得だけでなく、継続利用・アップセル・クロスセルまで含めて戦略的に組み込むことで、売上が一過性ではなく積み上がるものになります。
具体的には、SaaS企業が月額課金で安定収益を得ながら、機能追加でアップセルを行い、関連サービスでクロスセルを狙うといった形です。
だからこそ、レベニューモデルは成長戦略の核心であり、THE MODELの運用と組み合わせることで最大の効果を発揮するのです。
アメリカ発・分業型営業のプロセス
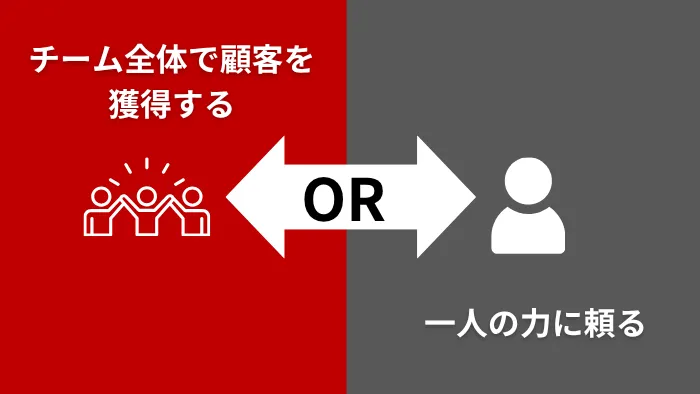
分業型営業とは、営業活動をリード獲得・商談化・クロージングという工程に切り分け、それぞれを専門の担当が担う仕組みです。
なぜ有効かというと、各担当が自分の得意領域に集中できるため、成果を安定して出しやすいからです。
ポイントは役割を明確にすることで、属人的な営業から脱却することです。
組織全体で再現性のある成果を積み上げられます。
例えば、インサイドセールスが電話やメールでアポイントを創出し、フィールドセールスが訪問や商談で決定率を高める流れを作ります。
つまり、一人の力に頼らず、チーム全体で顧客を獲得する仕組みを確立できるのです。
日本市場でTHE MODELを導入する際の鍵とは

日本市場で分業型営業を導入する際には、「効率」と「信頼関係」の両立が肝になります。
日本では短期的な成果よりも長期的な関係構築が重視され、形式的な分業だけでは顧客が離れる可能性が高まります。
例えば、資料ダウンロードやセミナー参加の履歴をスコア化し、温度感の高いリードだけを営業に引き渡す流れを作るのです。
つまり、効率化しつつ顧客に寄り添う体制を築くことで、日本企業に合った分業型営業を根付かせられるのです。
THE MODELの成果を左右する3つの戦略
営業の成果を決めるのは偶然ではなく、計算された戦略の組み立て方です。
第一に「狙う市場と顧客を絞り込む」ことが欠かせません。広く浅くではなく、誰に価値を届けるのかを一点集中で定めるのです。
第二に「伝えるメッセージを磨き込む」ことです。商品説明ではなく、相手の課題に直結する解決策として言葉を届けます。
第三に「信頼関係を積み上げる」ことです。短期的な売上に飛びつかず、約束を守り続ける姿勢が長期の成果を呼びます。
ポイント、このようにターゲット・メッセージ・信頼の三本柱を揃えると、営業は再現性を持って成果を伸ばせます。
結論として、戦略とは抽象的な理念ではなく、実際の現場で動ける具体的な設計図に仕上げることが肝心なのです。
誰にアプローチし、何を伝え、各役割の中でどのように信頼を獲得するか。この設計にこだわって初めて効果的な組織戦略になります。
人材・組織・リーダーシップを機能させる
強い営業組織を作るうえで、人材・組織・リーダーシップは切り離せません。
人材は「知識やスキル」以上に、変化に学び続ける姿勢が評価されます。
組織は個の力を閉じ込めず、情報や成功事例を共有し合う仕組みを整えることが重要です。
リーダーはただ指示するのではなく、自ら現場に立ち、行動で背中を見せることで信頼を築きます。
ポイント、このように人材・組織・リーダーシップが三位一体で機能することで、停滞した組織も一気に躍動します。
つまり真価とは、単体の強さではなく、三つを連動させて成果へと変換できる仕組みにこそ宿るのです。
▼編集部のおすすめ動画を見る
リーダーシップ・マネジメントのすべてがわかる動画!(元リクルート 全国営業一位 研修講師直伝)
THE MODEL型分業・営業プロセスの強み
生産性を最大化できる
「THE MODEL」型は、営業プロセスを役割ごとに分けることで一人ひとりが集中しやすい環境を作ります。
リード獲得からクロージングまでを一貫して担うと、どうしても情報整理や優先度判断に時間を奪われます。
一方で分業制にすると、各担当が自分の領域に専念でき、時間のロスが減り、チーム全体の商談効率が上がります。
ポイントは、分業によって「誰が、どこまで、どの質で」対応するのかを明確に線引きすることです。
特に法人営業では、リード育成と案件化の分離が成果を押し上げる大きな要素になります。
|
項目 |
具体例 |
|
SDR(リード創出) |
「セミナー後の参加者へ即日フォローする」 |
|
ISR(商談化) |
「初回商談で課題を整理し要件をまとめる」 |
|
AE(受注) |
「決裁者向けにROI試算を提示する」 |
このように、役割を分けるだけで作業のムダが減り、一人あたりの生産性は大きく跳ね上がります。
ボトルネックを可視化し、迅速に解決できる
法人営業の現場では、案件が停滞する原因が「どこで止まっているのか」分かりにくくなることが多いです。
そのために有効なのが、THE MODEL型分業スタイルによる工程ごとの分解と可視化です。
ポイントは、リード獲得からクロージングまでの各フェーズに明確な責任者を置き、数字で進捗を把握すること。
ボトルネックが「リード不足」なのか「商談化率の低下」なのかを即座に特定でき、担当者が課題解決に集中できるようになります。
|
項目 |
具体例 |
|
リード |
「展示会経由のリード獲得が減少している」と共有する |
|
商談化 |
「初回面談のアポ率が20%下がっている」と把握する |
|
クロージング |
「決裁者同席の回数が不足している」と特定する |
このように、工程ごとに深く振り返りことで、責任者が次に打つ手を迷わず決められます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
全体像の可視化からボトルネックを見極め解消する方法
顧客は営業と出会う前に購買プロセスの7割を終えられる
近年の法人営業では、顧客が営業担当と会う前に、すでに自社サイトや比較サイトで情報収集を進めています。
より具体的には、課題の整理や候補比較まで済ませており、営業が介在するのは「最終確認」や「条件交渉」の段階が多くなっています。
ポイントは、早期接点を持つためにマーケ部門と連携し、顧客が情報を探している段階からコンテンツやセミナーで関わること。
営業は、会った瞬間から「顧客が何を求めているか」を把握でき、打ち手を一歩前倒しできます。
|
項目 |
具体例 |
|
情報収集 |
「導入事例記事を読んでから問い合わせをしてくる」と把握する |
|
比較検討 |
「競合A社とB社の見積りを持参して面談に来る」と認識する |
|
意思決定 |
「社内会議用の資料を営業に求める」と対応する |
このように、顧客の購買行動を前提に営業を組み立てると、商談の質がぐっと上がります。
THE MODEL型分業・営業プロセスの注意点
部門間のコミュニケーション不足がボトルネックになる
「THE MODEL」型の分業スタイルでは、案件がマーケティングからインサイドセールス、フィールドセールスへと流れる過程で情報が途切れがちになります。
ポイントは、どの部門も“自分の役割”に集中しすぎると、顧客の背景や本音が十分に共有されないこと。
より具体的には、ヒアリングした課題が伝わらず、商談の場で同じ質問を繰り返してしまう。
あるいは、受注確度の高いリードでも、部門間で温度感の共有が甘く、失注に繋がる場面もあります。
営業責任者にとっては、この分断がパイプライン全体の効率を下げる最大の落とし穴になります。
|
注意点 |
具体例 |
|
二重対応 |
「同じ顧客に二度も同じ質問をする」ことで不信感を与える。 |
|
認識のずれ |
「マーケは優良リードと言ったが、実際は温度感が低い」と判断が食い違う。 |
|
温度感の共有不足 |
「決裁者の反応が曖昧なのにポジティブと誤解する」ことで見込みを誤る。 |
このように、流れの中で小さな伝達漏れが積み重なると、大きな失注リスクへと繋がります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業組織改革】部署間連携で売上最大化!マーケ×セールス×CSのリアル実践解説
部門ごとの目標達成に注力しすぎると、次のフェーズの部門に負担がかる
「THE MODEL」型の分業は、一部門ごとにKPIが明確になる一方で、各部門が“自分の数字”だけを追いかけがちです。
ポイントは、その姿勢が次のフェーズの仲間に大きな負荷を残すこと。
より具体的には、インサイドセールスが質より量を優先し、アポイントを大量に渡すことで、フィールドセールスが不成立な商談に時間を取られてしまう。
また、案件情報が整理されないまま引き渡されると、受け取った部門は準備不足のまま顧客に向き合うことになります。
|
項目 |
具体例 |
|
量の重視 |
「温度感の薄いアポを大量に渡す」ことで現場の負担が増える。 |
|
引き渡しの粗さ |
「顧客課題を整理せず商談に渡す」ことで準備不足に陥る。 |
|
直近のKPI優先 |
「KPI達成だけを目的に質を犠牲にする」ことで成果効率が落ちる。 |
このように、一見成果を積み上げているようで、実は全体の営業力を弱める構造が生まれてしまいます。
全体最適の意識が低下する
分業制の枠組みでは、自分の範囲以外は関心を持たなくなる傾向があります。
ポイントは、その結果として「パイプライン全体をどう成功に導くか」という視点が薄れてしまうこと。
より具体的には、マーケティングが“リードの量”に偏り、インサイドが“アポ化率”に集中し、フィールドは“受注率”だけを見る。
この分断が続くと、全体像を誰もコントロールできず、数字の連鎖が途切れていきます。
|
項目 |
具体例 |
|
個別最適 |
「マーケは数だけ、営業は成約だけ」に注目して全体が噛み合わない。 |
|
ゴールの不一致 |
「部門ごとに目標が違い、同じ顧客を別方向に見ている」状況になる。 |
|
連携不足 |
「数字は達成しても顧客体験が悪化する」ことで信頼を失う。 |
このように、各部門が正しく頑張っていても、全体の成果が伸びない状態が生まれます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
「部分最適」の組織を「全体最適」に変えるDXとは?
THE MODELの分業プロセスを担う4部門
マーケティング:見込み顧客を前進させる
マーケティングの役割は、ただ問い合わせを集めることではなく、営業につながる「前進した見込み顧客」をつくることにあります。
その一例です。単に資料請求をもらうだけでは商談化は難しく、意思決定プロセスのどの段階にいるかを把握して「次の行動」へ導く工夫が必要になります。
ポイントは、「顧客が自分から話したくなる仕掛け」を設計することです。メール一通の工夫で返信率が変わり、ウェビナーの内容次第で次の打ち合わせ依頼に直結します。以下の表に具体例を整理しました。
|
項目 |
取り組みの例 |
|
興味段階を測る |
「資料請求後に3日以内のフォローコールを入れる」 |
|
次の一歩を促す |
「セミナー参加者へ限定動画を送り、視聴後に個別相談を案内する」 |
|
行動を可視化する |
「メールの開封やクリック状況を営業に共有する」 |
このように、マーケティングが“熱量を持った見込み顧客”を営業に渡すと、無駄打ちが減り、成約に近づく商談だけが残っていきます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【今すぐ使える】見込み顧客育成術!リードナーチャリングの基本
インサイドセールス:商談供給のハブ機能
インサイドセールスは、商談の“入口”を支える役割です。
電話やメールでの第一声が重く感じられる相手には、「情報提供です」と伝えるだけで空気が柔らかくなります。
ポイントは、案件化できる見込みがあるかどうかを素早く見極めること。
その一例として、初回の会話で「導入の目的」や「意思決定の流れ」を軽く確認しておくと、その後の営業が驚くほどスムーズになります。
|
項目 |
取り組みの例 |
|
最初の接触 |
「展示会で名刺交換した相手に翌日フォローする」 |
|
課題把握 |
「今の業務で困っていることを質問する」 |
|
案件化判断 |
「決裁者に繋がる可能性を確認する」 |
このように、インサイドセールスは“ただの架電”ではなく、営業全体の質を底上げする入口の要になります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【最新版】インサイドセールスとは何かを徹底解説します。
フィールドセールス:商談を成果に変える
フィールドセールスは、供給された商談を“受注”に結びつける現場の主役です。
訪問の初回からいきなり製品説明をすると温度差が生まれやすいので、まずは相手の言葉を引き出すことがポイントになります。
その一例として、商談冒頭で「今期の目標」や「直近の課題」を尋ねると、相手の思考と自社提案を自然にリンクさせられます。
提案の際には、単なる機能説明ではなく「導入後にどう変わるか」を数字や実例で具体的に示すと、納得感が一気に高まります。
|
項目 |
取り組みの例 |
|
信頼構築 |
「初回商談では信頼されるための雑談を交えて安心感をつくる」 |
|
提案設計 |
「顧客のKPIに沿って改善効果を数字で伝える」 |
|
クロージング |
「導入後の運用イメージを一緒に描いて確認する」 |
このように、フィールドセールスは“売り込む人”ではなく、顧客の未来を共に設計するパートナーのような存在になります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
1日密着!フィールドセールスの1日に迫る(商談を成果に繋げる現場の動き)
カスタマーサクセス:利用継続と拡大を実現する
カスタマーサクセスは、単なるサポート窓口ではなく「契約後の売上を最大化する営業部門」として機能します。
ポイントは、「利用を止めさせない仕組み」と「追加契約を自然に導く流れ」を両立させることです。
より具体的には、顧客がどこでつまずくのかを定期面談で拾い、課題を解決しながら導入効果を数字で示すことが有効です。
既存顧客の解約率を下げつつ、クロスセルやアップセルを提案する流れを日常的に組み込むことが、長期的な収益に直結します。
|
項目 |
取り組みの例 |
|
利用定着 |
「定例ミーティング」で顧客の活用状況を確認する |
|
クロスセル提案 |
「利用部門以外のケース」を紹介して導入を広げる |
|
解約防止 |
「KPIレポート」を提示して成果を共有する |
このように、カスタマーサクセスは解約を防ぐだけでなく、追加受注や紹介案件を生み出す重要な役割をになっています。
▼編集部のおすすめ動画を見る
最強営業モデルのカスタマーサクセス部門の役割と極意
THE MODELに関するよくある質問
Q:「分業化」とは何を意味するのか?
A:「分業化」とは、営業プロセスをいくつかの役割に切り分けて、それぞれが専門的に取り組むことです。
例えば「リード獲得」をインサイドセールスが担い、「商談・提案」をフィールドセールスが行い、「契約後のフォロー」をカスタマーサクセスが担当する。
この流れを分けることで、1人が全部を抱え込む負担を避け、スピードと精度を高められます。
結果的に「売れる人」だけに依存せず、チーム全体で成果を出せる仕組みがつくれます。
このように、分業化は“手間を分ける”のではなく、“得意分野を強みに変える”ための考え方なのです。
Q:なぜ分業は「分析」から始まるのか?
A:分析なしで分業すると、ただの作業分けに終わり、逆に非効率になります。
例えば、アポイントの獲得率が低いのか、商談の成約率が低いのか、どこに課題があるかを特定しなければ意味がありません。
CRMやSFAのデータ、日々の営業日報を見返すと、どの工程がボトルネックになっているかが浮かび上がります。
その上で分業を組み立てれば、無駄な人員配置を避けて最小コストで成果を最大化できます。
このように、分業は“勘”ではなく“分析”を起点にしてこそ、本当に機能する体制をつくれます。
Q:「分業化」を進めるうえで「デジタル化」が欠かせないのはなぜか?
A:「分業化」は役割を分けるだけでは不十分で、情報をスムーズに渡せなければ意味がありません。
例えば、インサイドセールスが獲得したリードをエクセルやメールで渡すと、更新漏れや確認遅れがすぐ起きます。
一方で「CRM」に入力すれば、最新状況が誰でも見られ、商談の途中で案件が止まることもありません。
つまりデジタル化は、分業を“効率化の仕組み”に変える土台となります。
Q:「チーム連携」で営業リスクを最小化するにはどうすればいいのか?
A:営業の失敗は、情報やノウハウが一人に偏る「属人化」から生まれやすいです。
例えば、担当者だけが顧客の事情を知っている状態では、急な退職や休暇で案件が止まります。
そこで「定例ミーティング」で進捗を共有し、「ナレッジツール」に提案内容や失注理由を残すことが重要です。
さらに「ロールプレイ」で想定問答を練習しておけば、誰が対応しても一定の品質を保てます。
こうした仕組み化が、リスクを断ち切る最も現実的な方法になります。
THE MODEL型営業・営業プロセスの改善でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「THE MODEL型営業を工夫しているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
分業体制を取り入れたはずなのに、連携がうまくいかず、リードが途中で取りこぼされてしまう。そんな状況が続けば、せっかくの努力も数字につながらず、営業現場の士気も下がってしまいます。
本来、THE MODEL型営業は効率を高め、再現性ある成果を出すための仕組みです。けれども、設計や運用に細かな工夫が欠けると、逆に生産性を落とす原因になりかねません。そんなときこそ、現場に精通した営業のプロに相談することが最短の解決策となります。
弊社スタジアムは、戦略立案から実働までを一気通貫で支援できる体制を持ち、IT・Web領域に特化した営業代行サービスを提供しています。新規開拓を強化したい企業様や、営業組織をゼロから立ち上げたい企業様にこそ、ご活用いただきたいサービスです。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き
【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説
営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順
【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版
インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集
営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文
【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全
【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集
【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!
アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説
【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略
【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説
法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略
【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説
深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順
営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善
13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド
営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション
営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順
【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版
【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集
営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド
営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別
【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果
【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順
【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順
【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点
営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順
【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド
【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き
営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順
できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法
売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法
プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順
【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き
営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策
【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説
【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説
なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術
新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順
営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説
なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法
ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP
ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集
飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法
【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド
【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版
セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法
セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド
新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版
新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全
【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説
新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ
新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法
【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版
【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集
アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法
インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順
【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版
【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法
SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法
MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説
BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法
BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略
BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順
【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版
【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ
【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説
営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選
FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド
【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方
14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順
アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ
シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ
これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順
【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集
【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP
【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説
営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ
御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP
【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順
【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集
営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法
営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順
27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場
【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順
営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準
新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル
営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント
クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順
営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説
営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順
営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順
最終更新日