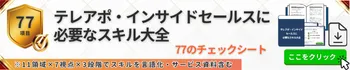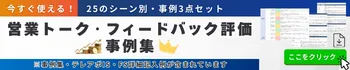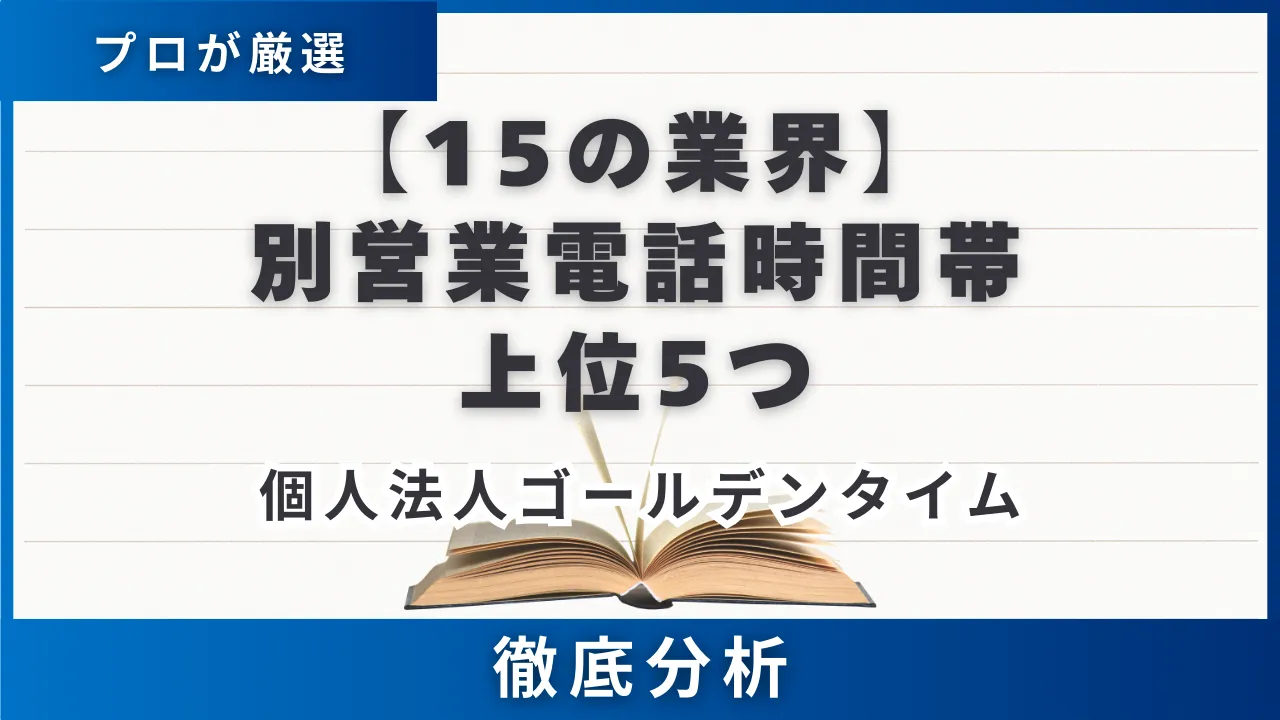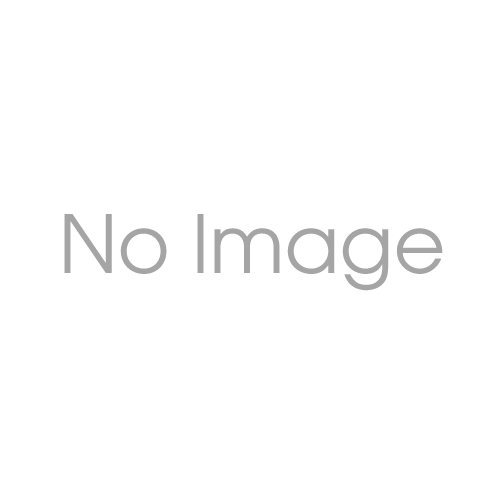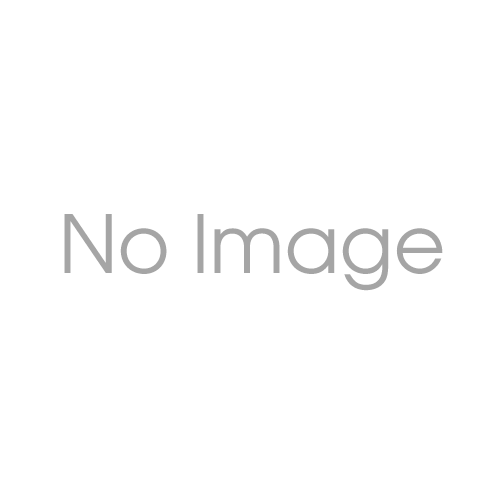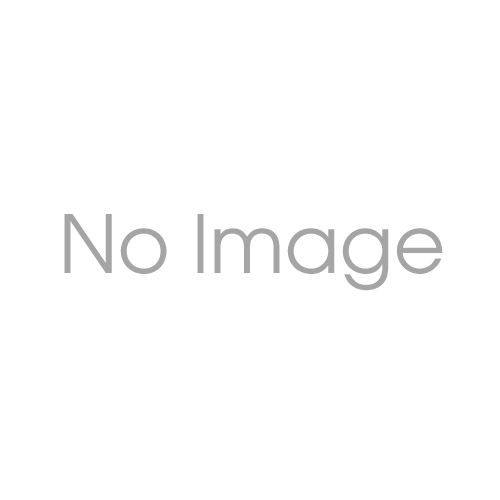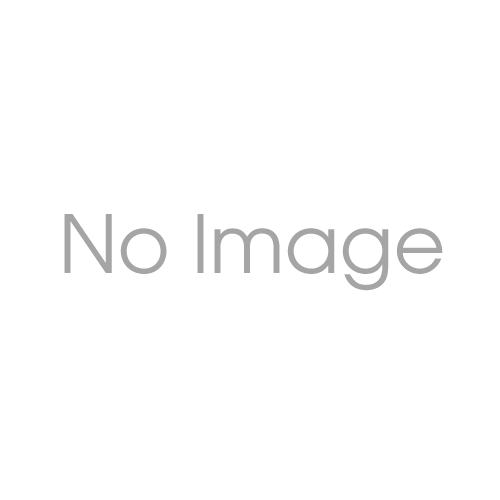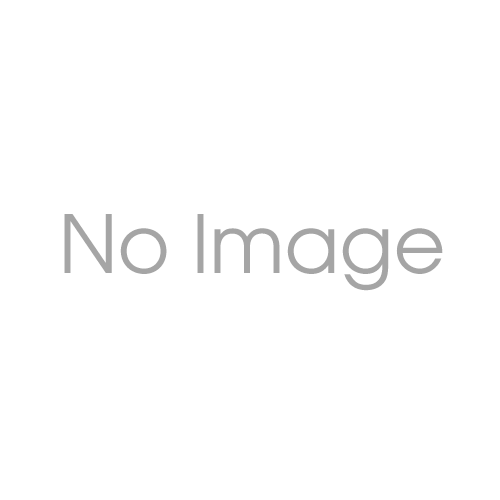プロが教える!TheModel型営業13の問題点・デメリットの打開策完全ガイド
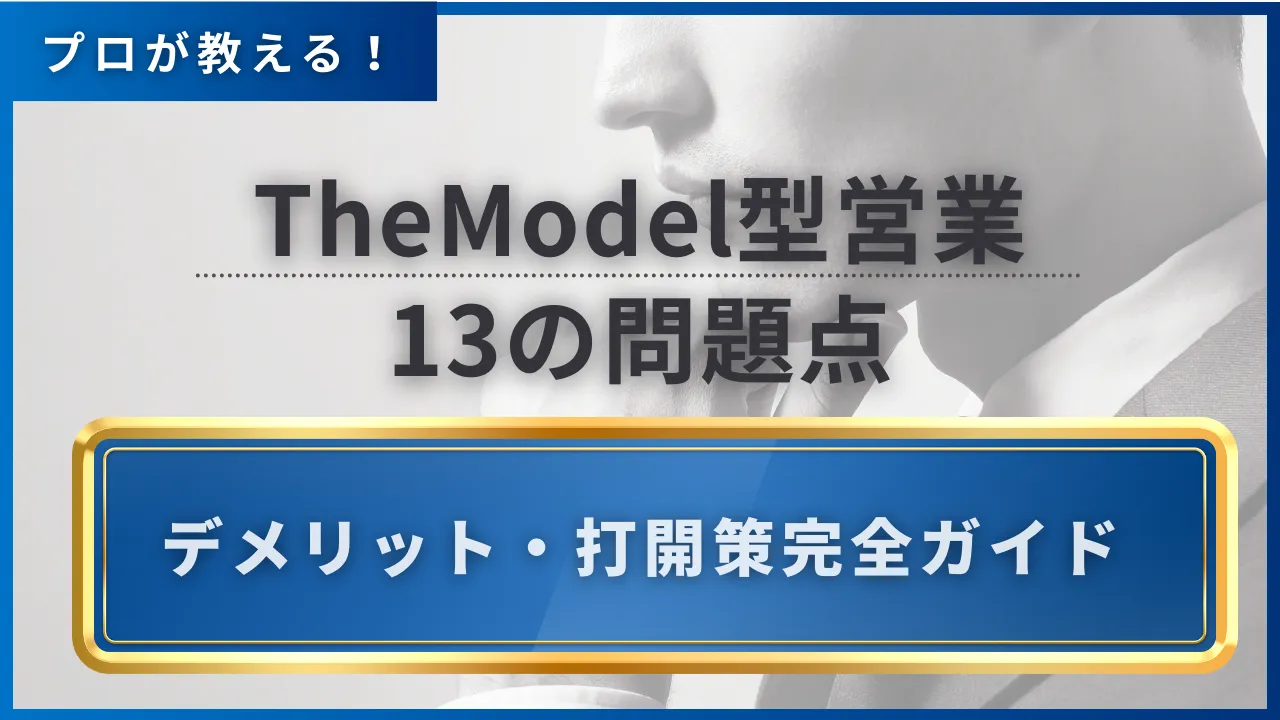
「The Model型営業って結局なにがいいの?」そんな疑問や不安を抱えていませんか?
成果は出やすい一方で、分業による“歪み”に悩む企業も少なくありません。
放置すれば顧客理解が浅くなり、責任の所在も曖昧に…。
本記事ではThe Model型営業の光と影を徹底解説し、実務で使える改善策まで紹介します。
・The Model型営業が注目されている3つの理由(SaaS/分業体制/DX推進)
・The Model型営業13の典型的な問題点(顧客理解不足/クロスセル機会損失/責任分散)
・The Model型営業の課題を乗り越える4つの手順(全体視点強化/CRM統合/CS視点KPI)
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
The Model型営業が近年注目されている3つの理由
SaaSの拡大で「継続収益モデル」に最適化できる

SaaSの広がりで、営業は「継続収益モデル」が注目されています。
一度売って終わりではなく、利用が続くほど収益が積み上がる仕組みが肝です。
だからこそ、新規契約よりも「継続率」と「アップセル」が収益を大きく左右します。
・「カスタマーサクセス」と連携して導入後の利用定着を支援する
・「利用ログ」を分析して課題を先回りし改善提案を行う
ポイントは、契約後にこそ営業が真価を発揮する場面があるということです。
このように、SaaS営業は顧客の成功を支えながら継続収益を最大化できます。
分業体制による「営業負担の偏り」をなくせる

営業を分業化すると、成果が安定しやすくなります。
新規開拓から受注、契約後のフォローまでを1人で担当すると、時間も負担も偏ることに繋がります。
役割を分ければ、それぞれが専門性を発揮でき、効率と成果の両方が向上します。
・「インサイドセールス」がリードを安定供給して営業の負荷を軽減する
・「フィールドセールス」が高確度の商談に集中して受注率を高める
ポイントは、一人が全部を抱え込まず、最適な役割分担を作ることです。
このように、分業体制は営業の生産性を底上げし、負担を均等化できます。
「DX推進」に即した柔軟な営業体制を実現できる
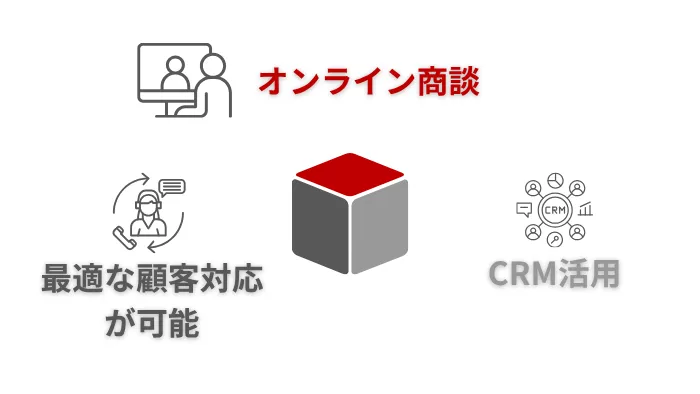
DXの進展により、営業は「柔軟な体制」で動くことが必須になっています。
従来型の訪問中心営業では、顧客の変化スピードに対応しきれないことに起因しています。
オンライン商談やCRM活用により、場所や時間に縛られず最適な顧客対応が可能になります。
・「オンライン商談ツール」を標準化して移動時間を削減する
・「CRM連携」で顧客データを一元管理し最適提案につなげる
ポイントは、DXを単なる効率化で終わらせず、顧客対応の質を高める武器に変えることです。
このように、DX推進を取り入れることで営業体制はしなやかに強化されます。
TheModel型営業13の問題点・よくある課題・デメリットの打開策
分業によって「顧客理解の深さ」が薄れる
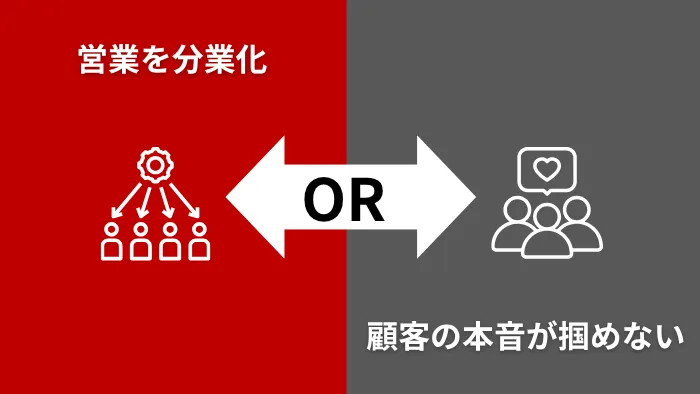
営業を分業化すると効率は上がりますが、顧客の本音をつかみにくくなる問題点があります。
インサイドセールスからフィールドセールスに情報を渡すとき、会話のニュアンスや背景事情が抜け落ちやすく、提案が浅くなることがあります。
その結果、顧客の課題に寄り添うよりも、商品説明に偏ってしまい、商談の信頼性が下がる危険性があります。
一方で、分業にはスピードや役割分担のメリットがあるため、情報の質を高める工夫を入れることで成果を守ることができます。
以下に、現場で今すぐ取り入れやすい具体例を整理しました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
情報の断絶 |
商談メモをCRMに詳細入力し、次担当へ即共有 |
|
温度感の欠落 |
商談直前にインサイド担当が短時間で口頭ブリーフ |
|
表面的提案 |
意思決定プロセスを図にまとめ、提案内容を対応付け |
このように、分業の効率を活かしながら顧客理解を深める工夫は、法人営業での信頼関係を長く維持する大きなポイントになります。
特に、契約更新や追加提案の成功率を支える基盤づくりに繋がります。
チーム間で「顧客情報の分断」が発生する
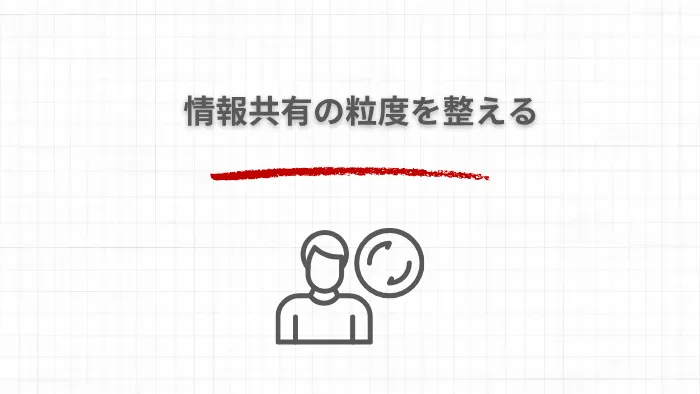
営業チームとマーケ、カスタマーサクセスの間で顧客情報が分断されると、商談の精度が下がる問題点があります。
初回接触の背景や検討プロセスが伝わらず、提案の質が不十分になりやすいのです。
この分断は、法人営業特有の「複数部門の連携」が必要な場面で特に影響が大きく、成約機会を逃す原因にもなります。
一方で、情報の分担管理は効率化のメリットもあるため、情報共有の粒度を整えることが大切になります。
以下に、分断を防ぐための具体的なポイントをまとめました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
引き継ぎ漏れ |
商談履歴・検討経緯をSFA/CRMに統一入力し、関係部署へ自動通知する |
|
部門間の温度差 |
商談直前に担当者同士で5分ブリーフィングを行い、顧客の温度感をすり合わせる |
このように、チームをまたぐ情報の粒度を揃える工夫は、法人営業における信頼獲得の基盤になります。
特に、大口案件や長期契約では、この一手間が商談の質を大きく左右します。
「リード数重視」で質の低い案件が増える場合がある
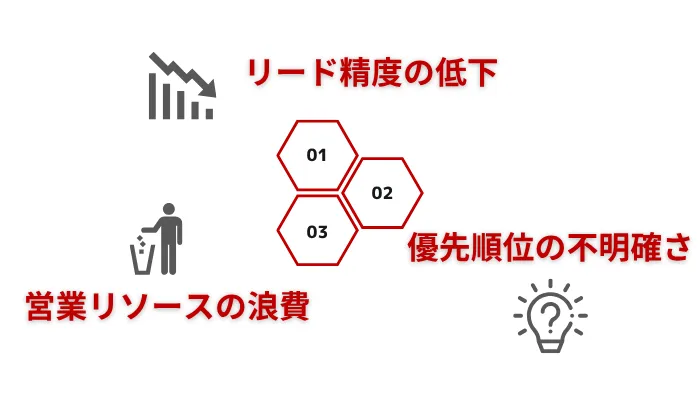
リード数ばかりを追いかけると、表面的な接点は増えても、実際の成約に結びつかない低質な案件が増えるという問題点があります。
たとえば展示会で集めた名刺をそのまま見込み顧客とみなすと、意思決定権を持たない担当者や購買意欲が薄い層まで商談化してしまいます。
結果として営業リソースが分散し、本当に優先すべき案件への投資が遅れ、チャンスを逃す危険が高まります。
一方で、リード数重視には接点拡大というメリットもあるため、「案件の粒度を揃える工夫」が欠かせません。
以下に、リードの質を確保するためのポイントを整理しました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
リード精度の低下 |
インサイドセールスでBANT条件に基づき一次スクリーニングを行う |
|
優先順位の不明確さ |
案件スコアリングを導入し、受注確度別にフォロー体制を分ける |
|
営業リソースの浪費 |
意思決定者との接触率をKPIに設定し、面談質を管理する |
このように、量だけでなく質を意識したリード運用は、営業効率を高めながら顧客信頼を築く基盤になります。
特に法人営業では「数の多さ」だけでなく「精度の高さ」も重要な視点となります。
「スコアリング不備」で優先顧客を見落とす場合がある

スコアリングの設計が不十分だと、本来注力すべき優先顧客を見落とすという問題点があります。
たとえば単純に「資料請求回数」や「メール開封数」だけで点数をつけると、意思決定に近い顧客よりも、情報収集目的の担当者が高得点になるケースが起きやすいです。
結果として営業が本当に価値のある商談にリソースを割けず、受注機会を逃す危険が高まります。
一方で、スコアリングには客観的に顧客を分類できるメリットがあるため、指標の精度を高める工夫が重要になります。
以下に、スコアリング精度を向上させるポイントを整理しました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
判断基準の偏り |
定量要素(行動履歴)と定性要素(役職・決裁権)を組み合わせて評価する |
|
点数の形骸化 |
商談成約率やパイプライン進捗に基づき、スコア基準を定期的に見直す |
|
営業現場との乖離 |
フィールドセールスからのフィードバックを反映し、運用ルールを改善する |
このように、現場の声とデータを組み合わせたスコアリング設計は、見込み度の高い顧客を確実に捉える基盤になります。
特に法人営業では、限られたリソースを正しい顧客に集中させるための実践的な仕組みとなります。
「組織文化の変革」が定着しにくい
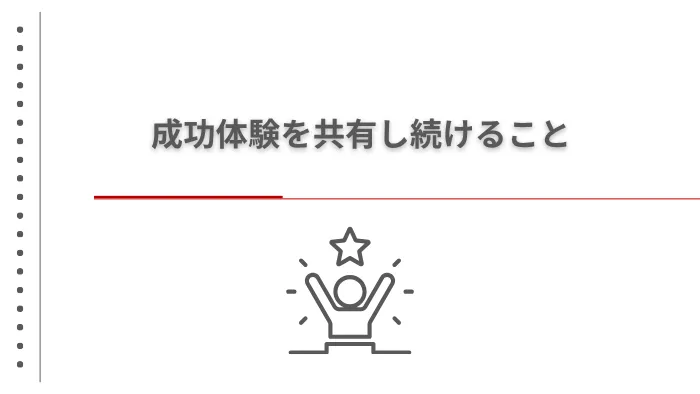
法人営業の現場では、新しい方針を打ち出しても「組織文化の変革」が定着しにくい問題点があります。
上層部が掲げる戦略と、現場の営業担当が日々追う数値目標がかみ合わず、結果的に行動が従来型に戻ってしまうことがよくあります。
このままでは改革の意図が形だけに終わり、提案の質や顧客との関係構築にバラつきが出てしまいます。
一方で、現場が「実際に成果につながった」と感じられる小さな事例を積み重ねていくメリットは大きく、変化を自然に受け入れやすくなります。
以下に、営業チームに文化を浸透させるためのポイントを整理しました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
方針が伝わらない |
週次会で案件成功事例を紹介し、行動と成果を結びつける |
|
現場が負担に感じる |
KPIを「次回アポ数」など小単位に分けて管理する |
|
変化が一過性で終わる |
ロールプレイやOJTを継続的に組み込み習慣化する |
このように、日常業務に小さな工夫を加えながら変革を根づかせる仕組みは、営業組織全体の信頼性を高めます。
特に、成功体験を共有し続けることが、文化を定着させる最も強い原動力になります。
部署ごとに「成果指標のズレ」が起きやすい
法人営業では、部署ごとに成果指標が異なると、全体最適よりも部分最適が優先される問題点があります。
例えば、マーケティングは「リード獲得数」、インサイドセールスは「商談化率」、フィールドセールスは「受注金額」を重視しがちです。
このズレが続くと、KPIの整合性が失われ、顧客体験の一貫性が崩れてしまいます。
一方で、部署別の指標管理にはスピード感や担当責任を明確化できるメリットもあります。
以下に、成果指標のズレを防ぐための具体的なポイントを整理しました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
部署間のKPI不一致 |
共通の「受注貢献度」を軸にKPIを再定義する |
|
数値重視による顧客軽視 |
定性指標(顧客満足度・商談フィードバック)を加える |
|
部分最適の優先 |
全社OKRで「案件獲得~継続」までを一気通貫で管理する |
このように、成果指標を整理し直すことで、組織の足並みが揃い、顧客にとっての価値を最大化できます。
特に、部門間の摩擦を減らし、営業活動全体をスムーズに進める大きな助けになります。
「リード品質のばらつき」に現場が振り回される
リードの質にばらつきがあると、営業現場は効率を大きく損なう問題点があります。
マーケティングから渡されるリードの情報精度が不揃いだと、初回接触の優先度判断に時間を取られ、商談化率が不安定になります。
特にBtoB営業では、ターゲット企業の決裁構造や購買プロセスが見えないリードが多いと、提案の方向性がぶれやすくなります。
一方で、高精度リードを的確に扱えれば受注までのリードタイム短縮につながるメリットも大きいため、精度差を埋める工夫が不可欠です。
以下に、現場で使える具体的な対処法を整理しました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
情報不足リード |
インサイドセールスが初期ヒアリングを徹底し、決裁者特定まで掘り下げる |
|
判別困難な温度感 |
MAツールのスコアリングを活用し、行動ログで優先度を数値化する |
|
商談化率の低下 |
ターゲット企業をABMリスト化し、マーケと営業で合意形成した基準に揃える |
このように、リード品質のばらつきを放置せず基準を整える工夫は、営業活動の再現性を高めます。
特に、営業の集中力を「確度の高い商談」に振り向けるために有効な取り組みになります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
効率の良いリード獲得法【BtoBマーケティング】
「属人的ノウハウ」が共有されずに埋もれる
法人営業では、経験豊富な担当者が持つ商談スキルや顧客攻略の勘所が、記録されずに本人の頭の中に留まってしまう問題点があります。
例えば「決裁者が動く一言」や「競合提案をかわす切り返し」などは極めて実践的ですが、属人化すると他のメンバーは同じ成果を再現できません。
一方で、仕組みを作って共有すれば、誰もが同じ地図を持って動けるようになり、営業チーム全体の底力が上がるメリットがあります。
以下に、ノウハウを埋もれさせないための具体的なポイントをまとめました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
商談の勘所が個人依存 |
勝ち筋を「営業プレイブック」に整理し全員で参照する |
|
顧客の決裁ルートが共有されない |
CRMに決裁プロセスや関係者マップを詳細に入力する |
|
若手が学ぶ機会を逃す |
成功事例を週次のナレッジ会議で発表し合う |
このように、属人的ノウハウを仕組みに乗せて共有する工夫は、営業力の再現性と強いチームづくりに直結します。
特に、引き継ぎや新規メンバーの立ち上がりを早める大きな助けになります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
BtoB法人営業で属人化を解消する方法|暗黙知を“型化”し組織力を高める実務解説
プロセスの複雑化で「営業サイクルの遅延」が起こる
営業プロセスが複雑になると、承認までの手順が増え、商談が前に進みにくくなる問題点があります。
法人営業では、決裁者が複数存在し、稟議が何度も差し戻されることで、提案の鮮度が落ちてしまう場面がよくあります。
この遅れは、顧客の購買意欲が高いうちに提案できないリスクを生み、競合に流れる原因にもなります。
一方で、流れを整理して余計な手戻りを減らすと、営業サイクル全体が短縮され、商談の成功率を高めるメリットがあります。
以下に、営業現場で実践できる具体的なポイントを整理しました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
稟議が長期化 |
事前に決裁フローを確認し、承認者リストを作成する |
|
社内調整が停滞 |
案件ごとに関係部署の担当者を早期に巻き込み、定例化する |
|
提案が差し戻し |
決裁基準を初回にヒアリングし、要件を反映した提案を準備する |
このように、複雑なプロセスを見える化して先回りする工夫は、営業のスピードと信頼性を同時に高めます。
特に、提案のタイミングを逃さないことが成約への近道になります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【成果を最大化する営業組織の構築方法】営業担当の生産性向上/ セールスイネーブルメント / 営業ラーニング
働き方のミスマッチで「人材の定着率」が低下する
営業組織で働き方の方向性が合わないと、現場のモチベーションが下がり、早期離職につながる問題点があります。
特に法人営業では、訪問重視かオンライン重視か、KPIを数量で測るか質で評価するかなど、スタイルの違いが不満を生みやすい状況です。
このギャップが埋まらないまま続くと、優秀な人材ほど他社に流れるリスクが高まります。
一方で、働き方の期待値をすり合わせ、制度や評価を整えることで、安心して長く活躍できるメリットが生まれます。
以下に、定着率を高めるための具体的なポイントを整理しました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
働き方の価値観のズレ |
面接時に営業スタイルや働き方の希望を具体的に確認する |
|
評価基準の不透明さ |
定量と定性のKPIを明示し、上司と定期的にレビューする |
|
キャリアの停滞感 |
ロールモデルを示し、成長イメージを描ける仕組みを作る |
このように、働き方のミスマッチを減らす工夫は、営業組織の安定と人材の長期活躍に直結します。
特に、組織の信頼感を高め、採用コスト削減にもつながる大切な取り組みとなります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
若手が定着しない企業の共通点とは?中小企業が陥る悪循環とは
「クロスセルの機会」を逃しやすい
既存顧客への提案は、どうしても「いま目の前の案件処理」に集中しがちで、クロスセルの機会を逃す問題点があります。
短期の受注だけを優先すると、顧客の全体像や長期的な課題を拾いきれず、本来なら一緒に提案できる関連サービスを見過ごしてしまいます。
その結果、受注が単発で終わり、顧客接点が浅くなる危険性が高まります。
一方で、クロスセルには「既存顧客の満足度を高めながら売上を伸ばせる」というメリットがあるため、顧客理解を深める工夫が欠かせません。
以下に、クロスセルの機会を捉えるための具体的なポイントを整理しました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
単発契約で終わる |
導入後の定例レビューで利用状況を確認し、追加課題を発見する |
|
ニーズが断片的 |
意思決定プロセスを可視化し、部門横断での提案余地を探す |
|
情報が不足 |
CSやサポートから成功事例を共有し、提案の切り口を増やす |
このように、クロスセルを意識した情報整理と連携は、顧客単価LTVの上昇や長期契約につながります。
「責任の押し付け合い」が生まれる
営業プロセスを分業化すると、担当間で境界が曖昧になりやすく、責任の押し付け合いが生まれる問題点があります。
たとえば、リード獲得後に進捗が止まった際、「マーケが悪いのか」「インサイドが不十分なのか」「フィールドが対応しないのか」と責任の所在が不明確になります。
この状態が続くと、顧客対応の遅れや社内の不信感を招き、商談機会を逃すリスクが高まります。
一方で、役割分担にはスピードや専門性を高めるメリットがあるため、境界を明確にする仕組みづくりが欠かせません。
以下に、責任の押し付け合いを防ぐためのポイントを整理しました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
責任の不明確さ |
各プロセスにKPIを設定し、担当範囲を数値で明示する |
|
対応の遅れ |
CRM上でタスクと期限を自動通知し、進捗を可視化する |
|
社内の不信感 |
定例の営業会議で失注理由を共有し、原因を全員で検証する |
このように、責任範囲を明確にしながら連携を深める工夫は、法人営業の組織力を強化します。
特に、スピード感のある対応とチーム全体の一体感に直結する実践的な仕組みとなります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【セールスフォース営業 大解剖】全員がアナリスト/データドリブン組織の創り方
「カスタマーサクセスの視点」が営業に還元されない
カスタマーサクセス部門が持つ「顧客利用データ」や「契約後の改善要望」が営業に還元されない問題点があります。
結果として、営業は新規提案の際に顧客の実使用状況を把握できず、ニーズから外れた提案になりがちです。
この断絶は、解約リスクを見逃すだけでなく、クロスセルやアップセルの機会を失う大きな損失につながります。
一方で、カスタマーサクセス情報を営業に統合できれば、提案の精度が高まり、信頼関係を深めるメリットが得られます。
以下に、情報連携のポイントを整理しました。
|
課題 |
対処法の例 |
|
契約後の利用データが営業に届かない |
定例でCS→営業へのフィードバック会を設置する |
|
解約予兆が見えない |
NPSや利用頻度をスコア化し、営業に共有する |
|
アップセル機会を逃す |
成功事例をCSが整理し、営業資料に反映する |
このように、CS視点を営業活動に取り込むことで、顧客の声を生かした提案が可能になります。
特に、解約防止や継続率向上に直結する重要な取り組みになります。
The Model型営業の問題点(課題)を乗り越える4つの手順
分業で弱まる「全体視点」を営業マネージャーが日次で補強する
分業体制になると、担当者は自分のタスクだけに集中しやすくなり、全体の流れを見失いやすいものです。
「全体視点」とは、案件が商談から受注、さらにフォローまでスムーズにつながっているかを確認する視点を指します。
ポイントは「毎日の短時間レビュー」で全員の動きをつなぐことです。
よくあるのは、数値だけを見て安心し、裏で顧客対応が滞っている事実に気づけないパターンです。
STEP
① 毎日5分で主要案件を一覧確認する
② 各担当に「昨日一番進んだこと」を一言で共有してもらう
③ 商談後のフォローや引き継ぎに抜けがないか目を通す
④ 気づいたことを即チャットで共有する
具体的には、「今日の一番の動きは?」と聞くだけで全体像が浮かび上がります。
小さな習慣を積み重ねることで、分業の弱点を自然に補うことができます。
バラバラに散る「顧客データ」をCRMで一本化して可視化する
営業現場では、顧客情報がメール、スプレッドシート、名刺管理などに散らばりがちです。
「一本化」とは、すべての顧客接点をCRMに集め、誰が見ても同じ情報を把握できる状態を指します。
ポイントは「入力を簡単にして、続けやすくすること」です。
よくあるのは、CRMを導入したのに入力が手間で放置され、結局スプレッドシートに逆戻りするケースです。
STEP
① 過去のリストや履歴を一度に取り込み初期整備する
② 商談メモは「次回アクション+顧客の一言」だけに絞る
③ メールやカレンダーを自動連携させて手入力を減らす
④ 毎朝のミーティングで「昨日更新したデータ」を1つだけ紹介する
具体的には、「次回訪問日」と「顧客が最後に言った要望」だけでも残すと、後から大きな武器になります。
情報がひとつにまとまれば、判断も行動も格段に早くなります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
CRMとは?基本機能から成功事例までHubSpotが解説します
早期離職を防ぐため「インサイドセールス研修」を仕組み化する
新人が成果を出せないまま早期離職してしまうのは、多くの営業組織の共通課題です。
「インサイドセールス研修」とは、架電やメールだけでなく、顧客理解やヒアリング技術を短期間で習得させる仕組みを指します。
ポイントは「座学だけで終わらせず、実際のトーク練習やフィードバックを繰り返す」ことです。
よくあるのは、マニュアルを配布するだけで、現場で使えるスキルが身につかないケースです。
STEP
① 基本トークスクリプトを使い、ロールプレイを週に1回以上実施する
② 架電後すぐに上司や先輩からフィードバックをもらう
③ 成果ログを共有し、改善点を翌日の練習に組み込む
具体的には、「週1回の全員ロールプレイ大会」を設けると、互いの学びが定着しやすくなります。
現場で使える力を日常の仕組みに組み込み、安心して成長できる土台を作ってみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【インサイドセールスを成功させる5つの事例と図解】
営業任せにせず「カスタマーサクセス視点」をKPIに組み込む
営業成果を売上だけで測ると、短期的な契約に偏りがちです。
「カスタマーサクセス視点」とは、契約後に顧客が成果を実感し、長期的に継続する状態を指します。
ポイントは「受注率」ではなく「利用率」や「更新率」をKPIに加えることです。
よくあるのは、営業が新規獲得に集中しすぎて、導入後の活用支援が抜け落ちるケースです。
STEP
① 受注後すぐに顧客活用のチェック項目を共有する
② 利用頻度や解約兆候をデータで把握する
③ カスタマーサクセスと営業が月次で情報を交換する
具体的には、「初回3か月の利用ログを必ず分析し、顧客と改善提案を一度行う」だけでも効果が見えます。
営業とCSが一体になる視点を、次の案件から意識してみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【丸わかり】カスタマーサクセスのKPIを完全理解できる動画
TheModel型営業・営業組織の改善・効率化でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「TheModel型営業・営業組織を工夫しているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
数字を追いかける日々の中で、仕組みづくりに時間を割けず、気づけば非効率な体制に縛られている。そんな状況が続けば、成果は頭打ちになり、組織全体のモチベーションにも影響してしまいます。
そこで有効なのが、現場を熟知したプロの知見を取り入れることです。弊社スタジアムの『営業代行サービス』は、戦略設計から実行までを一貫支援し、Web・IT・SaaS領域に特化した営業のプロが成果に直結する動きを実現します。特に、営業組織の立ち上げや新規開拓強化を考える企業にこそ最適です。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き
【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説
営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順
【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版
インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集
営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文
【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全
【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集
【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!
アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説
【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略
【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説
法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略
【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説
深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順
営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善
13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド
営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション
営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順
【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版
【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集
営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド
営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別
【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果
【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順
【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順
【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点
営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順
【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド
【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き
営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順
できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法
売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法
プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順
【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き
営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策
【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説
【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説
なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術
新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順
営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説
なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法
ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP
ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集
飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法
【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド
【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版
セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法
セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド
新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版
新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全
【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説
新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ
新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法
【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版
【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集
アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法
インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順
【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版
【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法
SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法
MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説
BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法
BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略
BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順
【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版
【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ
【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説
営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選
FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド
【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方
14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順
アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ
シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ
これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順
【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集
【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP
【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説
営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ
御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP
【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順
【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集
営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法
営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順
27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場
【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順
営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準
新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル
営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント
クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順
営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説
営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順
営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順
最終更新日