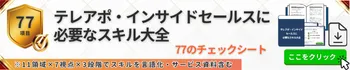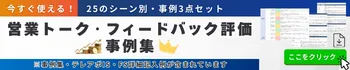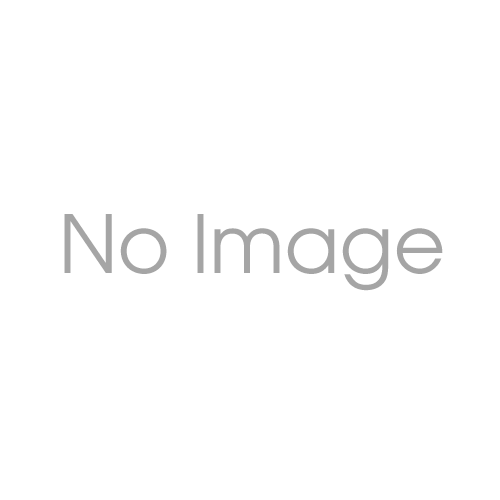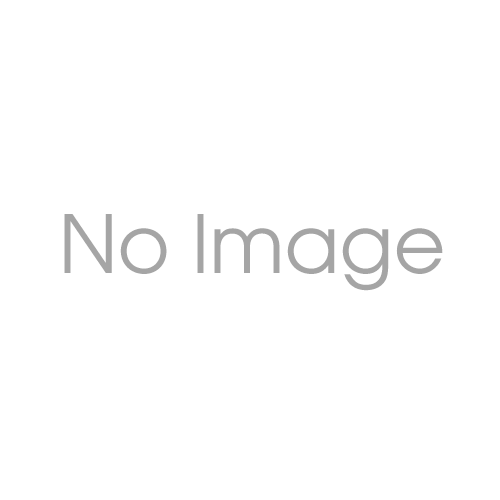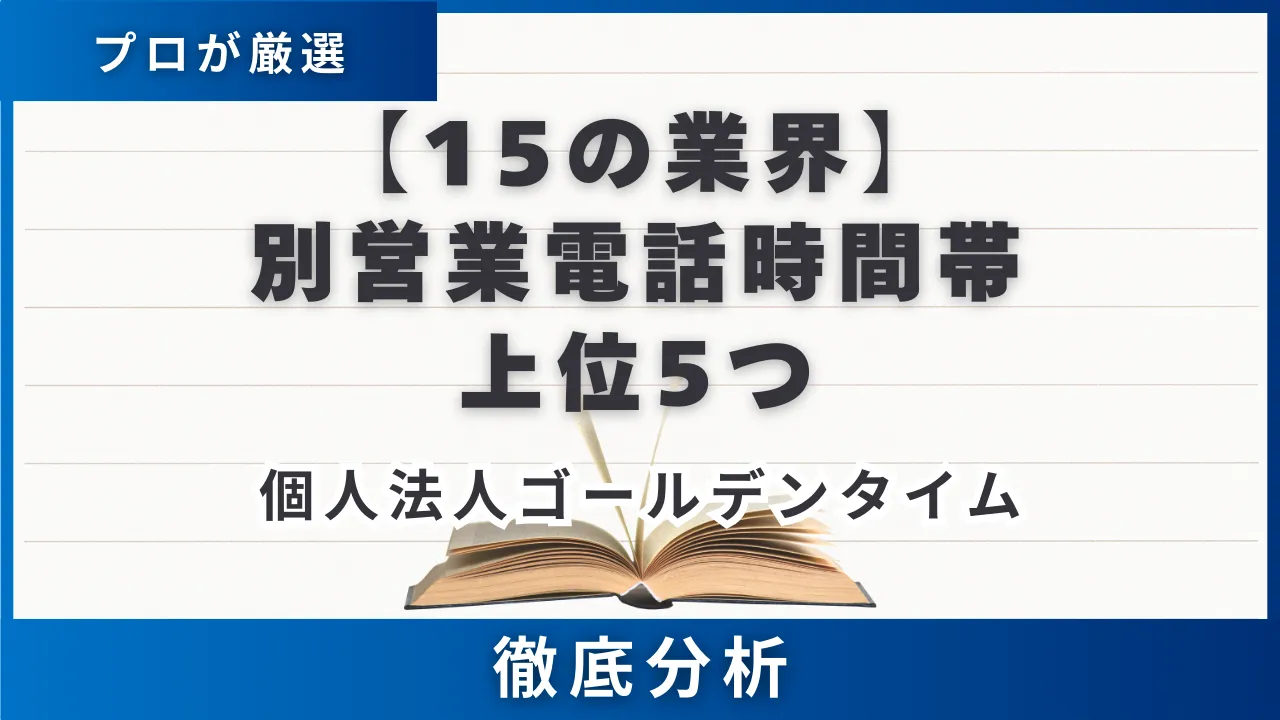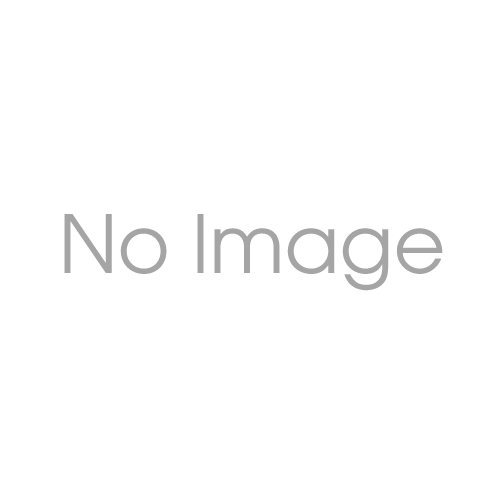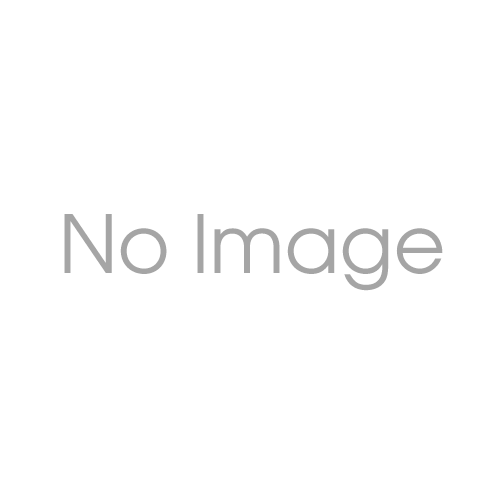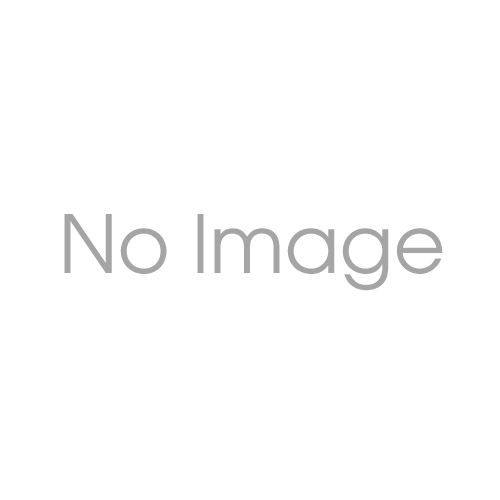【15種類】応酬話法の具体例と例文マニュアル
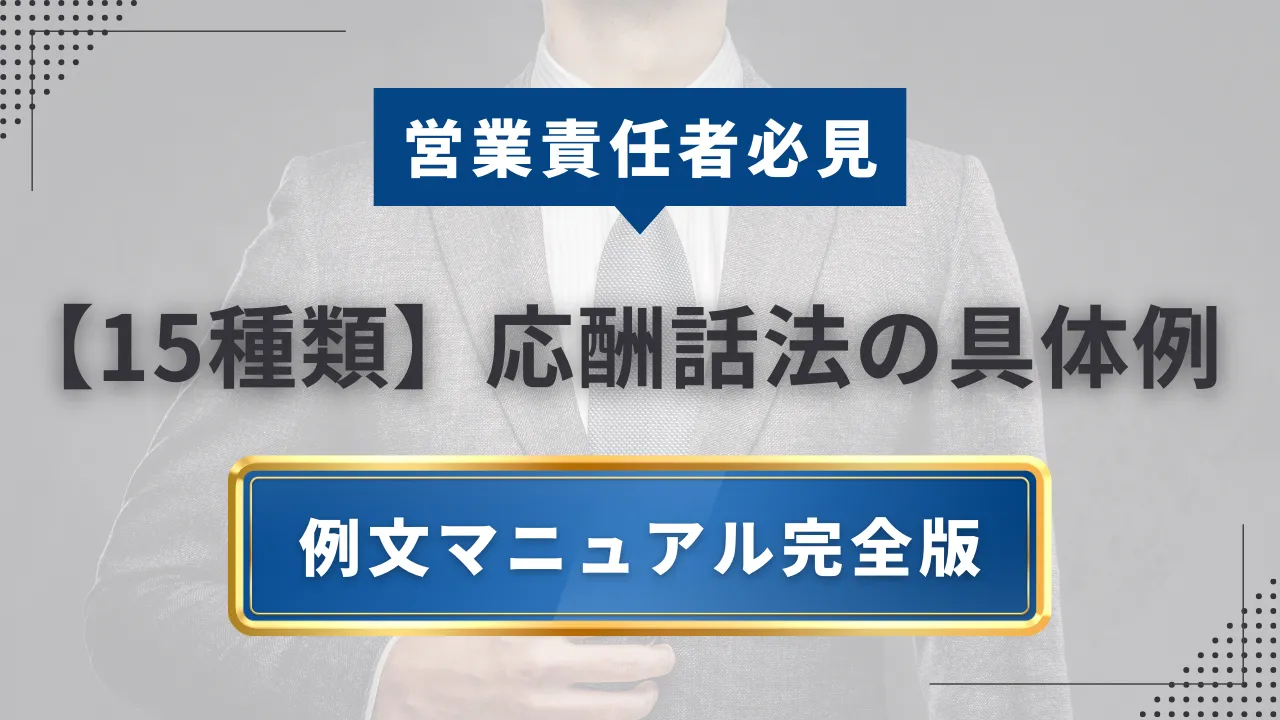
“応酬話法”とは?結局どれが成果(アポ獲得・商談化)につながりやすいのか?
本記事では、現場で本当に使える15の応酬話法と、そのトレーニング方法まで徹底解説。
営業成果を本気で上げたい方だけ、お読みください。
・営業で成果の出る!応酬話法15種類と例文マニュアル(肯定法・寄り添い法・Yes and)
・応酬話法を使いこなすために気をつけたい3つのこと(口ぐせ・棒読み・否定)
・現場で差がつく!効率的な応酬話法トレーニング方法7選(ロープレ・先輩同行・スクリプト化)
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
【15種類】応酬話法の具体例と例文マニュアル完全版
応酬話法とは、顧客からの否定的な反応や質問に対して、適切な切り返しを行い、商談をスムーズに進めるための話法です。
また「切り返し話法」や「切り返しトーク」とも呼んでいます。
具体的には、顧客の言葉を否定せずに一旦受け止め、そこから自社の提案や意見を伝えることで、顧客の抵抗感を和らげ、会話を継続させることが目的です。
「肯定法」でまず相手の意見を受け止める
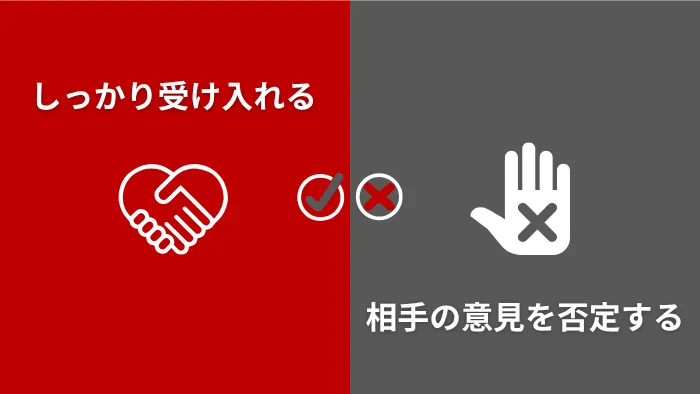
営業の第一歩として大切なのは、相手の意見をしっかりと受け止めることです。最初に相手が言ったことに共感を示すと、その後の会話がぐっとスムーズになります。相手が「これが課題だ」と感じている部分を理解していることを伝えるだけで、相手の心を開きやすくなります。
テンプレート例文
確かに、〇〇の問題は多くの企業で共通の課題ですよね。
↓(それ、よくありますね)
その点について、□□社様も以前同じような課題を抱えていましたが、導入後、確実に改善が見られました。
↓(改善したんですね)
もしよければ、その具体的な成果をお伝えしますので、少しお時間いただけますか?
↓(ぜひ聞きたいです)
ありがとうございます。それでは、□□社様の事例を基に、どのように解決したかをお話ししますね。
ここで大切なのは、相手の意見を否定せず、しっかり受け入れた上で次に進むこと。共感と具体例を交えることで、相手が「自分もこの解決策を試したい」と感じやすくなります。
「寄り添い法」でお客さんの立場にちゃんと共感する
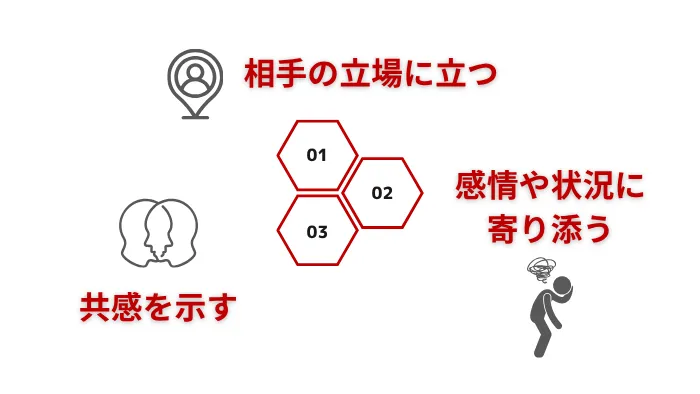
営業では、相手の気持ちや状況に寄り添うことが信頼を築く鍵です。
相手が感じている感情を、あえてそのまま言語化することで「この人は自分を理解してくれている」と感じてもらいやすくなります。
「寄り添い法」を使うと、相手は自分が理解されていると感じ、心を開きやすくなります。単に話を聞くのではなく、相手の立場に立って共感することで、次のステップに進みやすくなります。
テンプレート例文
おっしゃる通り、最近は〇〇の問題が多くの企業で重視されてきていて、そちらも大変なご負担だとお察しします。
↓(本当にその通りです)
私も同じような悩みを抱えている企業の担当者とよく話しますが、解決策を見つけることが非常に難しいという声をよく聞きます。
↓(わかります、課題は深刻です)
そんな中で、□□社様も同じような状況からスタートしましたが、弊社のサービスを活用してからは大きな改善が見られました。
↓(それは素晴らしいですね)
もしご興味あれば、その解決策について具体的にお話しさせていただければと思います。
このアプローチのポイントは、相手の立場に立ち、感情や状況に寄り添いながら共感を示すこと。そうすることで、相手は「この人は自分のことを理解してくれている」と感じ、次の提案を素直に受け入れやすくなります。
「Yes and法」で否定せずに話を前向きに広げる
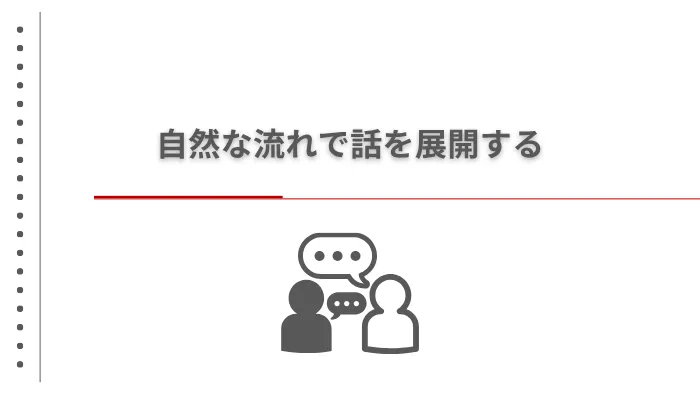
お客さまの意見を否定せず、肯定しながら話を広げる「Yes and法」は、関係性構築の初期段階で特に効果的です。
“そうですよね”と共感したうえで、“ちなみにこういう視点もあります”と別軸で提案することで、相手の意見を潰さずに自分の提案も自然に届けられます。
商談序盤の打ち手として活用することで、警戒心を解き、前向きな雰囲気を生み出すことができます。
テンプレート例文
〇〇の導入をご検討中とのこと、まずはお時間いただきありがとうございます。御社のように〇〇に課題を感じている企業さまには、△△の機能に注目いただくことが多いです。
↓(実は、すでに別のツールを入れていて…)
そうなんですね、すでに〇〇を導入されているのは先進的だと感じました。そのうえで、例えば⬜︎のような社内の情報連携やデータ統合の部分で、追加でお役立ちできるかもしれません。
↓(たしかに、情報の一元化はうまくいっていなくて)
ありがとうございます。実際、☆社では既存のツールと併用しながら、△△機能で月間◯時間の業務削減に成功されています。
もしご興味があれば、一度5分ほどで御社向けにカスタマイズしたご提案も可能ですが、いかがでしょうか?
このトークのポイントは、相手の既存の取り組みを尊重しつつ、自社提案を“対立軸”ではなく“補完軸”で提示すること。
お客さまのプライドを傷つけず、自然な流れで話を展開する“空気を読んだ広げ方”が、受注率の差を生みます。
「例え話法」で商品価値をイメージで伝える
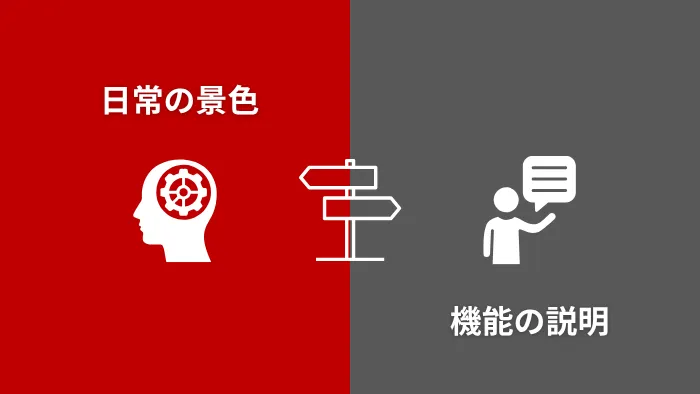
「それって結局、何がいいの?」という曖昧な疑問を、一発で「なるほど!」に変えるのが例え話法です。
機能を説明しても響かないときは、お客さまの“日常あるある”に落とし込むだけで、理解と興味のギアが一段上がります。
特にIT商材のように形がないものほど、「見える世界」に置き換えることが、最初の突破口になります。
テンプレート例文
よく“うちはまだ紙の運用ですが、それでも使えるんですか?”とご相談をいただきます。
↓(ウチみたいなアナログでも大丈夫なのかな)
ありがとうございます!〇〇は、“紙の書類を毎回FAXしていたのを、スマホで写真を撮るだけで自動で送れる”ようなイメージです。
↓(あ、それなら想像つきます)
実際、御社と同じように紙メインだった⬜︎業界のクライアントでは、導入初月で月△件分のFAX送信が不要になり、手間もコストも半分以下になりました。
↓(それならウチにも合いそう)
ちなみに、☆☆社様はその結果“1日30分かかっていた事務処理”がゼロになり、☆ヶ月で営業対応件数が120%に増えたというお声もいただいています。もし簡単に導入フローが見える資料、ご覧になりますか?
この話法の鍵は「機能の説明」を捨てること。
お客さまの頭の中に“見える映像”を描いてあげれば、導入の判断も一気に進みます。
「伝わる営業」は、専門用語より“日常の景色”で勝負が決まります。
「質問話法」で自分で答えを言わせる流れをつくる
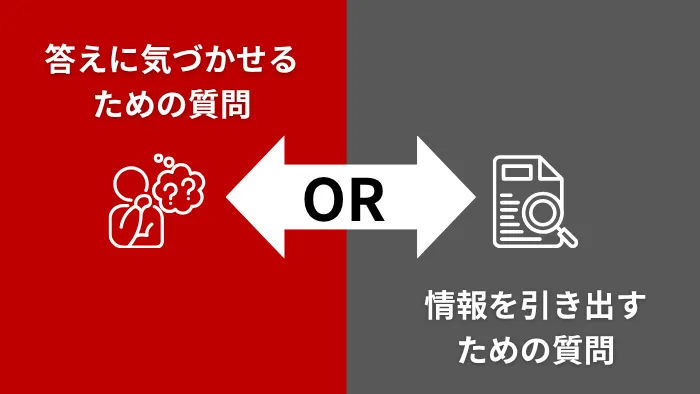
人は自分で言ったことに一番納得します。だからこそ、「質問話法」はただの情報収集ではなく、“気づかせて動かす”ための武器になります。
特に法人営業では、こちらが話しすぎると警戒されることもありますが、質問で考えさせることで、主導権を持ちながらも自然に相手の興味を引き出せます。
意図ある問いかけで「課題→必要性→次の一歩」までをお客さま自身の言葉で引き出せたら、成約率は一気に高まります。
テンプレート例文
今、御社では△△の業務、1日にどのくらい時間かかっていますか?
↓(だいたい2時間くらいですね)
ありがとうございます。仮に、その業務が月に☆時間減ったとしたら、その時間ってどんな活用ができますか?
↓(新規の案件対応とか、保留にしてた業務に回せますね)
なるほど、まさに☆☆社様も同じ状況でして、“月⬜︎時間の業務を短縮して、新しい案件獲得に動けた”という声をいただいています。
↓(うちも同じようにできるかもしれないですね)
はい、御社の業務内容を少し深掘りすれば、〇〇でどれだけ効果が出るか簡単にシミュレーションできます。ご都合よければ10分ほどで一度すり合わせしませんか?
この話法のコツは、“情報を引き出すための質問”ではなく、“答えに気づかせるための質問”をすること。
相手が自分で「必要だ」と言う流れをつくれれば、クロージングは驚くほどスムーズになります。
「否定法」で誤解やズレを冷静に正す

お客さまが〇〇の本質を誤って理解しているとき、真っ向から否定すると空気がピリつくことがあります。
そんな時は、まず共感を挟んでから「実は〜なんです」とやんわり正すことで、対話のリズムが崩れません。
「それ、よく言われるんですが…」という入りがあるだけで、相手の防御反応がスッと下がります。
テンプレート例文
「〇〇って△△向けですよね?」とよく聞かれるのですが、実は⬜︎業務でも使われることが増えています。
↓(へえ、そうなんですね)
たとえば☆☆社様では、最初は営業部門だけでお使いいただいていたのですが、意外と□□部門でも相性が良くて、導入から◯ヶ月で全社展開されました。
↓(うちも似たような部門あります)
御社でも◎◎のフローが紙ベースと伺っておりますので、〇〇を使えばその処理が一括管理できて、確認ミスや二重対応のリスクがかなり減るかと思います。
↓(たしかに、そこ困ってました)
もしご興味あれば、同じような流れで導入いただいた事例を2分ほどでご紹介できる資料がございます。お送りしても大丈夫でしょうか?
この「否定法」の本質は、正すより“視野を広げる”こと。誤解を切り捨てず、自然な会話の中で気づきを与えることで、信頼と関心の両方を引き寄せられます。
「ブーメラン法」でネガティブを強みに変える

ブーメラン法 顧客の主張を逆手にとってマイナスイメージをプラスに変えていくテクニックです。 相手がマイナスな発言をした場合に、「だからこそ~」と切り返し、興味をもたせたり、断る理由をなくす方法です。
「そうなんですよ、実はそこが最大のポイントでして」と返すだけで、一気に主導権を握れます。
「デメリット=欠点」ではなく、「その視点があるからこそ成果が出る」と切り返すのが“ブーメラン法”の核心です。
テンプレート例文
「〇〇ってちょっと高いですよね?」とよく言われるのですが、実はその分⬜︎機能に特化しておりまして、△△業務での成果が明確に出やすいんです。
↓(え、どんな成果が出るんですか?)
たとえば☆☆社様では、導入から◯週間で◎◎の手間が☆割削減できて、3ヶ月目には□□費用を△万円圧縮できたとご報告いただいています。
↓(それって費用対効果高いですね)
御社でも似たように◎◎にお困りと伺っておりますので、〇〇を活用いただくことで、その工数や属人化をまとめて解消できる可能性があります。
↓(うちにも当てはまりそうです)
ご関心あれば、過去の数値実績を1枚にまとめた資料がありますので、簡単にお送りしてもよろしいでしょうか?
このトークのポイントは、ネガティブを真っ向から跳ね返すのではなく、むしろ「そこに目を向けている御社だからこそ価値がある」と返すこと。信頼も意欲も自然に引き寄せられます。
「再定義話法で言い換える」
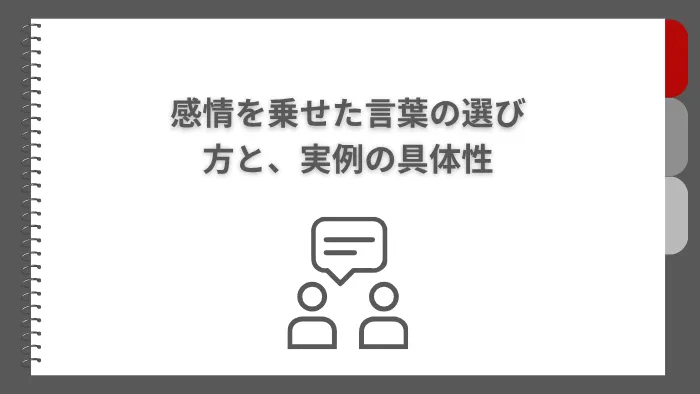
お客さまがネガティブに捉えている要素や“もったいない認識”に対して、視点を変えて言い換えることで、新しい価値を感じてもらえるのが「再定義話法」です。否定せず共感しながら再構築することで、「それならアリかも」と納得感を引き出すことができます。
テンプレート例文
実は、〇〇を“コスト”として見ている企業様が多いのですが、私たちはあえて“△△への先行投資”と捉え直す提案をしています。
↓(それってどういうことですか?)
ありがとうございます。たとえば〇〇の導入によって、今まで⬜︎にかかっていた時間が☆時間短縮でき、結果的に△△に集中できる時間が増えるケースが多いです。
↓(なるほど、それは確かに効率的ですね)
実際に、同じ業種の◯◯社様では、〇〇を使うことで営業の提案準備時間が⬜︎%削減され、月末の詰め対応が不要になったそうです。
↓(それ、うちにも当てはまるかも)
もしよろしければ、実際の業務フローに落とし込んだ資料がございますので、5分ほどでご説明差し上げます。いかがでしょうか?
この話法のポイントは、「お客さまの認識」を否定せず、前向きな意味に変換すること。価値の捉え直しができれば、判断軸そのものが変わり、導入の検討ラインが一段階進みます。感情を乗せた言葉の選び方と、実例の具体性が鍵です。
「比較話法で優位性を示す」
お客さまが他社サービスと比較検討しているタイミングでは、「数字」「実績」「使い勝手」などの具体的な差分を見せて優位性を体感してもらうことが重要です。抽象論ではなく、「比べた結果どう違うのか」を短文で伝えるのがコツです。
テンプレート例文
〇〇のご検討段階とのこと、ありがとうございます。よく比較対象に挙がるのが、□□社様のサービスなのですが、実は〇〇では△△の工程が不要になるため、導入スピードが◯週間以上早まることが多いです。
↓(他社より早く使えるってことですね)
はい、たとえば○○の初期設定に関しては、⬜︎項目が自動連携されるため、平均☆日で運用開始ができた実績があります。
↓(それは具体的でありがたい情報です)
実際に、□□社と比較して迷われていた◯◯社様も、「提案までのスピード感」で最終的に〇〇を選ばれました。
↓(そのスピード感は大事ですね)
もしよろしければ、比較検討時によく聞かれるQ&Aをまとめた資料がございますので、5分ほどで共有いたしますがいかがでしょうか?
この話法のポイントは、「比較することを前提として認めたうえで」、冷静かつ実利重視で差分を伝えること。決して他社を否定せず、“選ぶ理由”を丁寧に差し出すことで、前向きな判断の後押しになります。比較されることを恐れず、そこを突破口に変えるスタンスが効果的です。
「資料転換法」で話の主導権を取り戻す
「資料だけ見ておきますね」で終わる商談は、追っても温度が読めず、次の一手が打ちにくくなります。そんな時は、渡す資料を“行動につながるトリガー”に変える「資料転換法」が効果的です。
この手法は、口頭で伝わりづらい内容を資料を用いてわかりやすく伝える方法のことですが、この「わかりやすさ」を元に相手の興味を引き戻す、さらに興味づけを行う意識ができるとその効果はさらに高まります。
コツは、資料の中に“今一緒に確認すべき理由”をつくって、相手の視線を画面に引き戻すこと。「見ておきます」で終わらせず「今見て一緒に決める」流れに変えるのが主導権を握る一歩です。
テンプレート例文
今、◯分だけで要点がわかる資料をお渡ししています。
↓(資料だけ先に見てもいいですか?)
もちろんです!ただ、⬜︎ページ目に御社のような○○体制の事例がありまして、そこだけ☆分だけ一緒にご覧いただけると話が早いかと思いました。
↓(それなら少し見てみたいですね)
実際に〇〇社様はそこをきっかけに、翌週にはテスト導入まで進みました。現場の動きが具体的にイメージできたのが大きかったようです。
↓(うちも似てるかもしれません)
もしご都合よろしければ、今お繋ぎして、御社の〇〇業務に照らしながら一緒に確認できればと思うのですが、いかがでしょうか?
この話法の要は、資料の一部に“今見る価値”を埋め込むこと。相手の「あとで」モードを「今見よう」に変えることで、その場の熱を冷まさずに次のアクションに持ち込めます。資料は置き土産ではなく、主導権を取り戻す“共通の画面”に変えることが肝です。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業心理学】「資料送って」への正しい攻略法【アポ獲得率UP】
「黙殺法」で揺さぶりや無茶ぶりを受け流す
商談中に突然「それって安くできるの?」「他社はもっとやってるよ」といった揺さぶりや無茶ぶりを受ける場面は少なくありません。ここで正面から反応してしまうと、相手のペースに巻き込まれ、価格の話ばかりになるリスクがあります。そんな時に有効なのが「黙殺法」。意図的にその話題に強く反応せず、会話の主軸を“本題”に戻すことで、自然に主導権を握り直すことができます。
テンプレート例文
御社の○○業務に近い事例も含めて、本日はお時間をいただければと思っております。
↓(正直、それってもっと安くならないの?)
ありがとうございます!実は先日も似たようなご相談をいただいたんですが、⬜︎の部分で特にお役立ちできるポイントが見つかりまして、御社の場合も☆点だけ先に共有させていただければと思います。
↓(あれ?値段の話スルーされたな…でも聞いてみよう)
たとえば〇〇社様ではこの内容を基に◯ヶ月で△%の業務短縮につながっており、同様に御社でも具体的な活用イメージがつくかもしれません。
↓(たしかに、話聞いてから判断してもいいか)
もしご興味あれば、導入ステップと期待効果をまとめた資料があるので、○分だけ画面共有でご説明させていただいてもよろしいでしょうか?
このトークのポイントは、“挑発には乗らず、価値訴求に戻す”こと。感情を揺さぶる一言に反応しないことで、相手の意図を受け流しながら、商談の軸をぶらさずに進めることができます。反論せずに“次の話題で包み込む”ことで、冷静かつ主導権を持った提案が可能になります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
共感・沈黙・感情の扱い方…営業の必須スキルを徹底解説!
「聞き流し法」で雑な否定に巻き込まれない
初回訪問でありがちな「それはちょっと難しいですね…」という曖昧な否定。このときに正面から反論してしまうと、空気がピリついてその後の提案が通りづらくなります。
「聞き流し法」は、相手の否定を否定せず、受け止めず、あえて“スルー”して本題に戻すことで、会話の主導権を自然にこちら側に引き戻すテクニックです。
大事なのは「聞き入れない」のではなく、「受け流して、戻す」こと。主導権を握りながら空気も悪くしない、一番実践的な技です。
テンプレート例文
今日は、〇〇について、御社でも活用できそうな部分を絞ってご紹介できればと思っています。
↓ (いや、ウチはそういうのたぶん合わないと思います)
そうですよね、皆さん最初はそうおっしゃいます。実際に△△業界の他社さんも最初はピンと来ていなかったのですが、〇〇のここだけを使って一気に現場の工数が⬜︎%削減された事例もあります。
↓ (へぇ、どこを使ったんですか?)
たとえば、日報の収集と集計だけに絞って、週に☆時間かかっていた業務が、ほぼゼロになったパターンが多いです。御社も似た業務があるようでしたら、そこだけ試すことも可能です。
↓ (それならちょっと聞いてみたいですね)
ありがとうございます!じゃあ、一度○○だけに絞った事例と、実際の使い方を5分でご紹介しますね。
この「聞き流し法」は、反射的なNOに食い下がらずに、“話を戻す”“期待を思い出させる”技術です。感情を刺激せずに具体例と数字で主導権を取り戻すことで、営業の流れを崩さず提案を前に進められます。どんな商材でも、これは鉄板です。
「繰り返し法」で相手の本音を自然に引き出す
「それってどういうことですか?」と何度も聞き返すと、詰問に感じさせてしまうことがあります。「繰り返し法」は、相手の言葉をそのまま反復することで、無理なく自然に本音を引き出す営業トークの基本技です。
特に、ニーズがまだ言語化されていない初期段階では、相手も自分の課題を整理しながら話すため、繰り返しが“思考のきっかけ”になります。こちらが誘導せずとも、向こうから勝手に「深掘り」を始めてくれるのが最大の利点です。
テンプレート例文
今回は、御社の〇〇業務について、現場でどんな課題感があるのかを少しだけお聞かせいただければと思いまして。
↓(うちは今、情報共有がうまくいってないんですよね)
「情報共有がうまくいってない」、ということですね。
↓ (そうですね、口頭ベースになっちゃっていて、抜け漏れが多いんです)
「口頭ベースで抜け漏れが多い」と…。
↓ (はい、特に引き継ぎのところでミスが出ることがあって)
なるほど、「引き継ぎでミスが出る」。そこは現場の方も困っていらっしゃる感じですか?
↓ (そうなんですよ。結局、また最初から説明する手間が増えて…)
ありがとうございます。実は〇〇という機能が、そういった引き継ぎや情報共有に特化していて、⬜︎分で要点だけ整理して共有できる仕組みになってるんです。
このトークのポイントは、“問い詰めずに掘る”こと。相手の言葉を返すだけで、「もう少し話してみようかな」という空気を作るのが「繰り返し法」です。話すほどに相手自身が課題に気づき始めるため、こちらが説明する前に“導入理由”を口にしてくれるケースも多い、非常に使い勝手のいい技です。
▼編集部のおすすめ動画を見る
ユーザーヒアリングで 「隠れた本音」を引き出す方法を完全解説
「事例置き換え法」で他社の成功を自分ごと化させる
「他社ではうまくいった」という話だけでは、なかなか自分ごととして捉えてもらえません。
でも「御社の場合はこう変わるはずです」と言い切れる事例の伝え方なら、相手の表情が変わります。
事例置き換え法は、同じ業界・同じ課題・同じ規模の企業を引き合いに出し、そこに御社特有の業務構造や社内事情を重ね合わせて話すことで、話の解像度が一気に上がります。
「それ、まさにうちのことだね」と言われた瞬間、商談の空気が変わります。
テンプレート例文
実は以前、御社と同じ業界・同じ従業員規模の会社様に〇〇をご提案したことがありまして…
↓(それ、うちにも当てはまる気がします)
ありがとうございます!その企業様では、〇〇の導入前は△△業務に毎週⬜︎時間かかっていたんですが、導入後☆週間で担当者の残業がほぼゼロになりました。
↓(うちも残業多いので気になります)
御社のように部門ごとに管理体制が分かれていても、初期設定時に〇〇フローを整えることで、全社での運用定着まで◯ヶ月もかかりませんでした。
↓(他にもそういう事例ありますか?)
たとえば、□□業界の☆☆社様では、導入3ヶ月目で月次集計にかかる手間を1/3にでき、営業部門の入力率も⬜︎%改善しています。ご興味あれば、その事例資料もすぐに共有できますが、いかがでしょうか?
この応酬話法のカギは、「他社の話」ではなく「御社に置き換えた話」にして語ること。
相手の中でストーリーが“自社の未来像”として動き出した瞬間が、心が動くタイミングです。
応酬話法3つの目的
「反対意見」をチャンスに変えるために使う
反対意見は、関心があるからこそ出てくる大切なサインです。
だからこそ、うまく受け止めて対話を深めることが営業におけるポイントになります。
目的は、ただ説得することではなく、相手の「本音」を引き出しながら信頼をつくるためです。
現場で実際に活用されている具体例は以下の通りです。
- 「予算が厳しい」と言われたら「“成果の見える資料”を見せる」ようにする
- 「今はタイミングじゃない」と返されたら「“他社導入時期”を共有する」ようにする
- 「うちは必要ない」と言われたら「“業界平均データ”を提示する」ようにする
このように、反対意見はうまく使えば商談を前に進める力になります。
相手の言葉を否定せず、丁寧に深掘りすることで信頼が生まれます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業マン支援塾 第8回】お客様の“反対”はチャンス。成果を出す対応術
「課題の核心」を言葉にしてもらうために使う
顧客に課題を“自分の言葉”で語ってもらうことが、提案の精度を高めるポイントになります。
なぜなら、営業側の想像ではなく、顧客の本音に沿った解決策を提示するためです。
そのために応酬話法を使い、相手の気づきを引き出す対話を重ねることが大切です。
現場で実際に活用されている具体例は以下の通りです。
- 「漠然と困っている」と聞いたら「“日常業務の困りごと”を深掘りする」ようにする
- 「特に不満はない」と言われたら「“理想とのギャップ”を探る質問を投げる」ようにする
- 「いま満足している」と言われたら「“過去に困った経験”を聞き出す」ようにする
このように、相手の言葉で課題が語られると、提案に説得力が増していきます。
目的は、共通の理解をつくるための“会話の土台”を整えることです。
「価格交渉」を納得感ある流れにするために使う
価格交渉は、信頼をつくる絶好のタイミングです。
なぜなら、金額の話は「本音」と「本質」が出やすく、相手の優先順位を見極める“入り口”になるからです。
目的を明確にすることで、価格の話が対立ではなく、前進のきっかけになります。
現場で実際に使われている具体例は以下の通りです。
- 「コストを抑えたい」と言われたら→「導入の“目的”を具体化」する
- 「他社と比較している」と言われたら→「“決定基準”を丁寧に確認」する
- 「ちょっと高いね」と言われたら→「“成果とのバランス”を整理」する
このように、価格を“下げる”のではなく“納得に導く”ことがポイントになります。
相手の立場に寄り添いながら、本当に価値ある提案へと導くための場面に変わっていきます。
応酬話法を使いこなすために気をつけたい3つのこと
「口ぐせ」が相手の不信感を生むことに気づく
たった一言の“クセ”が、信頼の芽をつぶしてしまうことがあります。
「一応…」「たぶん…」と口にした瞬間、提案の価値は半分になると思ってください。
商談では、“何を言うか”よりも“どう聞こえるか”がすべてです。
言葉に曖昧さがにじむと、相手の頭には「この人、本当に大丈夫か?」という不安が残ります。
特に決裁者は、提案の内容より先に“人として信頼できるか”を見ています。
・「一応〜」という言葉が「責任を持っていない人」として伝わってしまう
・「なるほどですね」を繰り返すと「本質を理解していない人」と思われてしまう
営業は信頼の勝負です。
無意識の口ぐせこそ、最も危険なノイズになります。
▼編集部のおすすめ動画を見る
完全に勘違い営業マン!一生使ってはいけない口癖【トップセールス】
「反射的な否定」が会話を壊すと理解する
つい出る一言が、商談の流れを止めてしまうことがあります。
「でも」「いや」「それは違って」と反射的に否定してしまうと、相手の意見を潰したことになり、空気が一気に冷えます。
営業は“言い負かす場”ではなく、“納得してもらう場”です。
相手の話を途中でさえぎると、信頼も共感もすぐに失われます。
実際、否定から入った瞬間に、相手の顔つきが変わる場面を見たことがある人も多いはずです。
・「でも」を使うことで「この人は話を聞いていない」と思われてしまう
・「いや違いますよ」が「上から目線な人」として印象づいてしまう
まずは受け止めてから伝えるだけで、会話はスムーズになります。
会話の温度を下げるのは、内容より“反応のクセ”です。
「台本の棒読み」が一発でバレると知っておく
棒読みは、信頼を一瞬で壊します。
どれだけ内容が正しくても、“伝わらない声”には説得力が宿りません。
商談中、相手がフッと冷める瞬間があります。
それは、こちらが「セリフ」を話してしまったとき。
言葉に感情が乗っていないと、“聞かされてる感”が出て、会話が途端にズレ始めます。
たとえ正解を話していても、“自分ごと”として聞いてもらえないんです。
・「棒読みの返し」は、「準備してきた答え」にしか聞こえなくなる
・「声の温度」がないと、信頼ではなく“作為”が伝わってしまう
覚えるのはセリフじゃなく、“自分の言葉で話せる感覚”です。
口から出す瞬間に気持ちが入っていないと、営業は絶対に響きません。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【人前での話し方】書いてあることをそのまま読んでしまう人へ(棒読み改善)
応酬話法の効率的なトレーニング方法7選
「トークスクリプト」は語尾まで言葉を決めておく
結論をどこで“言い切るか”を決めておくだけで、言葉に芯が通ります。
「たぶん」「かもしれません」で終わる営業トークは、どれだけ話しても刺さりません。
逆に、語尾まで設計された一文は、相手の脳に“残る”んです。
現場では、思考しながら話す余裕なんてありません。
語尾まで決まっているからこそ、自分の言葉で“締める力”が出てきます。
とくに提案の一言、クロージングの一言に“決めの型”があると、判断が動きます。
・「一文の最後」に「相手の利益」を言い切って終える
・「提案トーク」は「語尾」まで“言葉を型化”して準備する
迷いがなくなるのは、話す前じゃなくて、“終わり方を決めている時”なんです。
「ロープレ」はリアルな商談を再現してやる
リアルさがないロープレは、ただの“発表会”で終わります。
現場と同じ緊張感・同じ空気を再現できてこそ、営業力は磨かれます。
たとえば、想定問答を読み上げるだけの練習では、「想定外」に対応できる力はつきません。
相手役が本気で断ってくる、想定外の角度から質問される、そういう“ズレ”のあるロープレが、実際の商談で効いてくるんです。
とくに、声のトーン、言葉の間、表情の動きなど、数字で測れない感覚を体で覚えるには、リアル再現が一番効果的です。
・「断り文句」や「沈黙」も含めて「現場の空気」を再現する
・「録音」して「自分の話し方」を客観的に見直す
大事なのは、“うまくやる”ことじゃなく、“本番のつもりでやる”ことです。
「ChatGPT(生成AI)」でお客さん役を自作して練習する
本番に近い“断られ方”で練習したいなら、ChatGPTに「手強いお客さん役」をやってもらうのがちょうどいいです。
ここでいう「お客さん役」とは、よくある断り文句や比較中のトーンをリアルに再現する仮想の相手のことです。
ポイントは、“簡単にOKしない顧客像”をAIに演じさせること。「検討中です」「他社も見てます」など、現場でよく刺さる返しを仕込むのがコツです。
ありがちなのは、AIに優しい顧客を演じさせてしまい、練習にならないパターンです。これでは反応力は磨かれません。
STEP
① ChatGPTに「◯◯業界の担当者として、即決しない顧客になってください」と依頼
② 「価格・タイミング・上長確認などで断ってきてください」と明確に指示
③ こちらが応酬すると、「今の返しは何点?理由も教えて」とフィードバックを求める
④ 改善案をもとに再挑戦、自然な対話になるまで繰り返す
具体的には、「物流会社の課長役で、他社と比較中という設定でお願いします」と入れるだけで、グッと実戦に近づきます。
気まずい空気を乗り越える応酬力こそ、現場で一番効く武器になります。今すぐAIに“断られて”みてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【ChatGPTとロールプレイング】1人で黙々と営業トークを磨く方法
「先輩同行」で返しの一言を盗む
返しの一言は、現場でしか磨けない営業の“勘”です。
実際に先輩が切り返す瞬間を横で見て、盗んで、真似することで、自分の中に引き出しが増えていきます。
教科書に載っていない言い回しや、絶妙なトーン、沈黙の使い方。
それらは、同行の数だけ拾える“実戦のヒント”です。
「こう言えば角が立たない」「この言い回しなら納得してもらえる」——そう思える一言が、商談の結果を変えることもあります。
・「値引き要求を受け流す言い回し」を拾って真似する
・「沈黙を活かした間の取り方」を観察して覚える
同行は、営業の言葉を“感覚ごと”学べる一番の近道です。
一言の重みを、自分の中に積み上げていく感覚を大切にしたいです。
「受注商談の動画」で勝ちパターンを探す
結果が出た商談の“空気感”や“流れ”を掴みたいときは、実際の受注商談の動画を観るのが一番早いです。
ここでいう「勝ちパターン」とは、受注につながった会話の“入り方・返し方・詰め方”など、再現性のある営業の型を指します。
ポイントは、「話し方」より「会話の運び方」と「間の使い方」に注目すること。特に、価格の話や競合との比較でどう切り返しているかがヒントになります。
よくあるのは、動画を“雰囲気で観て終わり”にしてしまうこと。具体的な型やフレーズを拾わなければ、学びは残りません。
STEP
① 受注商談の中から“同じ商品・同じ業種”の事例を選ぶ
② 動画を観ながら「どの瞬間に空気が動いたか」をメモ
③ キーフレーズや質問の順番を抜き出す
④ 自分の提案に当てはめて“口グセ化”してみる
具体的には、「価格の話になる前に“導入後の未来像”を入れて空気を変えてたな」といったポイントを抽出すると再現性が高まります。
まずは1本、“止めながら観る”ところから始めてみてください。答えは現場にしか落ちていません。
「録音チェック」で自分の間合いを修正する
録音は、営業の“癖”を可視化する鏡です。
自分では気づきにくい間の長さ、かぶせるタイミング、声のトーンまで、録音を聞くと手に取るようにわかります。
商談中は必死で覚えていない場面も、音声で聞き返すことで「あ、ここ早口だったな」「今の返し、ちょっと圧が強いかも」といった小さなズレに気づけます。
そのズレを1つずつ整えていくことが、“聞いてもらえる営業”への近道です。
・「間が早すぎる部分」を見つけて調整する
・「相手の話をかぶせた箇所」を振り返って修正する
録音を聞く習慣は、自分の話し方を“設計し直す”作業です。
間合いは感覚じゃなく、整えるものだと実感できます。
「失注の会話分析」で地雷ワードを洗い出す
「なんで刺さらなかったのか」を見つけると、次の商談は驚くほど変わります。
“失注の直前に何を言ったか”にこそ、改善のヒントが眠っています。
ここで言う「地雷ワード」とは、言った瞬間に相手の顔が曇るような一言のことです。
ポイントは、相手の「返事が薄くなる」「視線が逸れる」「うなずきが止まる」などの“反応の変化”を拾うこと。
ありがちなのが、無意識に言ってしまう「売り手目線の一言」で、場が一気に冷えてしまうパターンです。
STEP
① 商談の録音を聞き返し、「相手の反応が変わった瞬間」にマークをつける
② その直前の自分の発言を一つひとつ書き出す
③ 共通する言い回しや口癖をチェックする
④ 別の言い方で伝えられないか、代案を考える
たとえば、「他社と比べて〜」ではなく、「◯◯さんの今の課題に一番合うのが〜」と視点を変えるだけで伝わり方がまるで違います。
一度、自分の“引かれてしまう言葉”と、ちゃんと向き合ってみてください。
▼編集部のおすすめ動画を見る
営業上級編【断られてからが勝負!】断り文句をチャンスに変える切り返し術
応酬話法や営業のトークでお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「応酬話法や営業のトークを工夫しているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
お客様の「興味はあるけど、今はちょっと…」という一言に、うまく切り返せなかった自分にモヤモヤしたこと、きっとありますよね。
言葉を尽くして説明しても反応が鈍く、「話し方が悪かったのか」と自信をなくしてしまう…。
そんな場面が続くと、「自分には向いてないのでは」とさえ思えてくるものです。
でも安心してください。営業のトークは、才能ではなく“型”と“練習”で伸びるスキルです。
現場で磨かれた実践的な応酬話法を学べば、商談での迷いや不安が驚くほど減っていきます。
「Web・IT商材を扱っていて、提案の深掘りや断り文句の切り返しが苦手…」という方こそ、ぜひ一度、営業のプロに相談してみてください。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
【13の状況別・5つの方法】なぜ営業ロープレ練習が必要?・例文付き
【厳選13選】営業ロープレテンプレート・作成手順・やり方を徹底解説
営業ロープレお題設定で効果的な7つの方法・基本5つの手順
【11の業界別・活用術】営業ロープレチェックシート完全版
インサイドセールス・トークスクリプトに含めたい7つの項目・作り方・例文
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【マネージャー必見】営業ロープレで頭が真っ白になってしまった時・言葉が出てこない時メンバーに伝えたい11の技法
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
【15選】クロージングで有効な心理学の手法と9つの業界商材別例文集
営業ができる人のすごい裏側・解説|13の工夫と技術&5つの基本例文
【31選】トップ営業マンが厳選!心理学テクニック・刺さる例文大全
【業界別15選】BtoB法人営業テレアポのトークスクリプト例文集
【業界別13選・例文】 新規営業テレアポのトークスクリプトの作り方を9STEPで解説!
アポ取りのコツ17選【営業のプロが厳選】6STEPでやり方徹底解説
【13の極意】飛び込み営業ロープレのコツ・やり方・7つのメリット
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き】
最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
【シーン別13選】営業ロープレ評価シートテンプレート・5つの作成手順・徹底解説
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
新規開拓営業がうまくいかない11の理由と有効なアプローチ方法15選
営業ロープレの質を高めるフィードバックに含めたい11の要素・5つの手順
テレアポトークスクリプトの作り方・7つの手順・営業電話の精度を高める5つの技法
超実践的!営業トーク話し方のコツ・練習方法7つ・成果に繋げる5つの手順
【状況別13選】アポ取り・電話営業例文集
13の状況別・新規営業電話の例文集・かけ方・5つの技法
営業代行BPOとは?導入する際の10の判断基準・9つのメリット
【21選】法人営業の新規開拓手法・5ステップで完全攻略
【施策15選】新規開拓営業を成功させる17のコツと4つの手順
電話営業アポ取り・商談化のための19のコツ・例文付きで解説
法人営業のアプローチ手法・施策17選・6つの工夫
IT営業新規開拓が難しい理由と9の対処法・3つの戦略
【厳選13選】電話営業かけ方・マニュアル・改善するための5つの手順解説
深耕営業例文テンプレ15選・NG例5選・成果を出すための5つの手順
営業コストを削減するための14の考え方・対策・利益率改善
13の業界別・飛び込み営業電話例文集・完全攻略ガイド
営業代行の費用対効果を測る5つの指標・計測する7つの方法・シミュレーション
営業代行の利益率・アポ単価・ 利益率を高めるための5つの手順
【11シーン別・3フェーズ分類】営業後追い電話で成果を出すコツ・実践例文完全版
【11のシーン別】ChatGPTを活用した営業ロープレの実践法・プロンプト例文集
営業ロープレとは|11のコツと5つの効果・成果を出す手順と始め方完全ガイド
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【11のシーン別・7つの基本構成】フローチャート型営業トークスクリプト・成果を出す5つの手順
テレアポの取り方やり方・4フェーズ×5STEPで完全攻略・11の技法で成果を出す実践ガイド
【12の例文】営業電話かけ方の教科書・型化して成果を出す7つのコツ
なぜか営業成績がいい人の15の特徴・7つの課題・育成手法7選・見極め方3つ
【15のシーン別】訪問営業の挨拶文例集・成果を出す5つの手順・3つの目的効果・完全ガイド
営業「ご挨拶だけでも」が断られる7つの理由・11例文・ルート営業シーン別
【19の例文付き】インサイドセールス・フロントトーク作成9つの手順・信頼を勝ち取る3つの効果
【シーン別35選】オンライン営業アイスブレイク1分ネタ大全・成果を出す7つの手順
【67選・シーン別9種】営業初対面のアイスブレイク話題大全・成果を出す5つの手順
【19の状況別】テストクロージング例文集・成果を出す5つの手順・注意点
営業アイスブレイクいらない論争・11の見解と成果を出す5つの手順
【12のフェーズ別・5つの準備法】営業キラートーク例文集・成約率を高める実践ガイド
【25選×11フェーズ】営業話法一覧テクニック大全集・成果を出す実践例文付き
営業がずっと社内にいる15の理由と外出を促す9つの対策・成果を最大化する手順
できる営業マンの話し方15選・11のNGパターン例文と6つの練習法
売れる営業マンの話し方(共通点)・12シーン別例文集と質問力を磨く7つの方法
プル型営業とプッシュ型営業11の違い・手法7選・成果を出す5つの手順
【23選・フェーズ別】営業初心者やることリスト完全版・具体的手順解説付き
営業職の新人がほったらかしになる16の理由・育成を成功させる11の具体策
【21選】反響営業の成約率を高めるコツ・10の手順を徹底解説
【業界別21選】反響営業が盛んな業界一覧・やりにくい7パターン・業務内容5種類解説
なぜ反響営業が注目される?14のメリット・9のデメリット解消法・7業界の活用術
新しい営業スタイル22種類一覧・基本の7領域・4分類・成果を出す5つの手順
営業職が楽しすぎる本当の12の理由・楽すぎパターン9選・向いている人の特徴解説
なぜルート営業楽すぎ?11の理由・楽しすぎるパターン10選・成果を出す5つの方法
ルート営業はやめとけと言われる12の理由 向いている人3つの特徴・成果を出す5STEP
ルート営業で話すことがない13の理由・会話の質を高める7つの打開策と例文集
飛び込み営業・実は時代遅れではない理由14選と成果を出す5つの方法
【5つの目的・導入手順】SaaS営業組織セールスイネーブルメント完全ガイド
【16社の成功事例】セールスイネーブルメント成功法・7つのステップ・効率化ツール完全版
セールスイネーブルメント営業教育がうまくいかない理由と成功させる11の実践法
セールスイネーブルメントとは・導入する意味13のメリット・施策10選・完全ガイド
新規開拓営業・飛び込みで成果を出す24の打ち手・訪問前後15のコツ完全版
新規顧客開拓成功事例17選・プッシュ型×プル型の有効な手法大全
【33選】新規顧客を増やすには獲得するには・今やるべき施策大全・9つの視点で解説
新規開拓営業14の鉄則・成果を出す手法9選・BtoB/BtoC別3つのコツ
新規開拓営業うまくいかない12の理由・今すぐ実践できる15の対処法
【25の手法・12のコツ】新規開拓営業とは?11の手順やり方・成功法完全版
【17選】テレアポで成果を出す心理学テクニック・トークスクリプト例文集
アウトバウンドコールで成果を上げる15のコツ・営業効率を高める9つの手法
インバウンド営業とは?アウトバウンド9つの違い・手法10選・成果を出す5つの手順
【13の手法・8STEP】クロージング営業で成果を出すテクニック・タイミング・例文完全版
【11のシーン別・9つの手順】SPIN話法ヒアリングシート作り方・成約率を高める質問設計法
SPIN話法が古い時代遅れと言われる12の理由・成果を出すための7つの活用法
MEDDPICCとは?BANT営業との違い・8要素・使い分け例文7STEP完全解説
BANT情報とは?・営業フレームワークの8つの基本と活用法
BANT営業ヒアリングがうまくいかない理由と聞き方で成果を出す11のコツ・7STEP完全攻略
BANTCH情報営業とは?6つの構成要素・質問5つの効果・8つの手順
【11の質問・7STEP】営業SPIN話法とは?成約率を高めるフレームワーク完全版
【17のシーン別・11の業界別】テレアポ切り返しトーク集・7つのNG例・商談化率を高める6つのコツ
【シーン別18選】テレアポ営業マニュアル・トークスクリプト例文・6つの作成手順・徹底解説
営業の最初のトークのコツ・21の手法別例文・流れ・NGワード5選
FSV話法営業とは?19のシーン別例文・クロージング7つの流れ・成約率改善への完全ガイド
【13のシーン別】第三者話法・営業例文集・8つのデメリット・効果的な使い方
14のシーン別 テストクロージングとは?5タイプの質問法・仮定法・クロージングへの移行手順
アポ取り電話 最適な時間帯上位5つ・曜日5つ・避けるべき時間帯3つ・法人向けマナー9つ
シーン別15選・営業アポ取りメール例文・書き方7つの手順・成功率を高める3つのコツ
これからの営業に必要な29のスキル一覧・役職別3分類・向上させる5つの手順
【105選・年齢季節別】面白い話ネタ30秒短い・営業飲み会で使える例文集
【90選完全版】オチが面白い話爆笑短い営業雑談・年齢別季節別例文集・成功法9STEP
【37選】名古屋に強い営業代行会社一覧・8つの判断基準と選び方徹底解説
営業が強い会社組織の特徴15選・弱い組織5つの原因と改善7つのステップ
御用聞き営業が不要と言われる11のデメリット・脱却する5つの手順・成果を高める7STEP
【22のシーン別】営業トーク心理学テクニック・例文集・成約率を高める7つの手順
【17選・5つの手法】営業の話し方をゆっくりにするコツと信頼関係を築く例文集
営業の雑談はうざい?12の理由・いらない派の6つの意見・世間話ができない時の7つの対処法
営業成績グラフ張り出しで業績向上する?13のメリット・9つの懸念点・成果につながる7つの手順
27社比較営業リスト作成代行会社サービス一覧・9つの選び方判断基準・料金費用相場
【16の例文付き】営業の仕事目標振り返りで評価される書き方・5つの手順
営業丸投げ失敗する9パターン・営業代行丸投げが上手くいくための11の判断基準
新人営業育成の教科書・即戦力化する8つの方法・7つの手順・13のスキル
営業施策一覧47選具体例・商談化率を高める7つの手順と成功の3つのポイント
クロスセル営業とは?11のメリット6のデメリット・9の業界別具体例・成功させる7つの手順
営業成績を上げるには?15の技法・7つの手順・改善策を徹底解説
営業成績の見える化で追うべき5つの情報・15のメリット・成功させる7つの手順
営業数字に興味がない気にしない12の理由とトップ営業になるための7つの手順
最終更新日