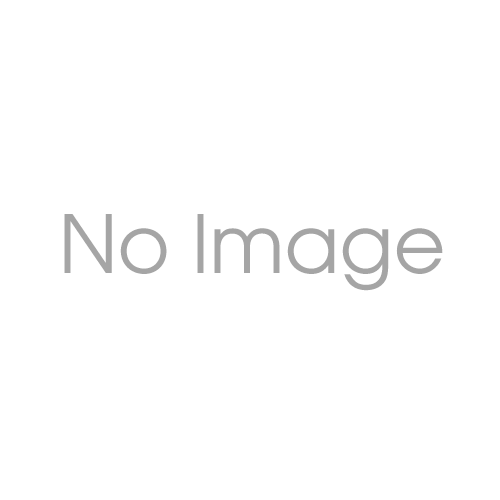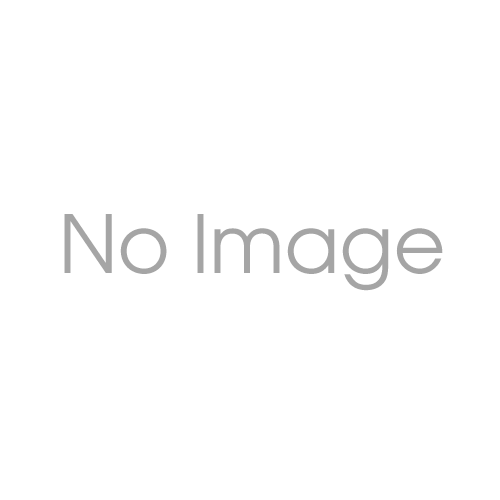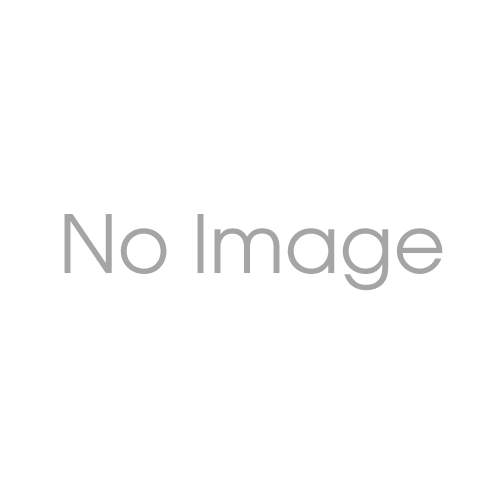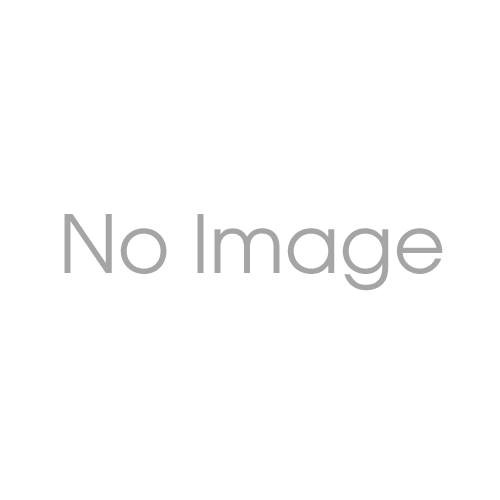営業ヒアリングのコツ!刺さる11例文&NG5つ【含めるべき7項目】
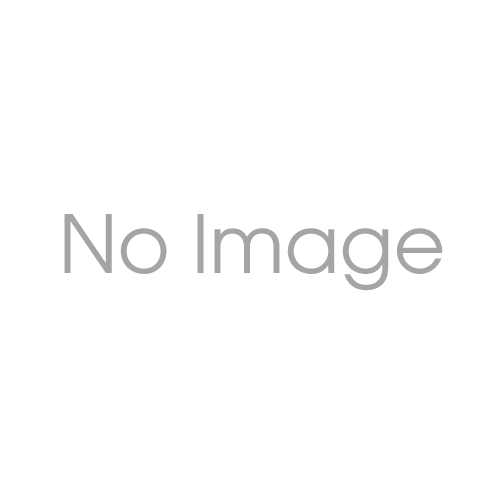
営業で「ヒアリングが苦手」 「沈黙が怖い」「何を聞けばいいか分からない」そんな不安のまま商談に臨んでいませんか?
本記事では、現場で即使えるヒアリングのコツからNG例、成果を出すフレームワークまで網羅してご紹介します。
・営業ヒアリング11のコツと刺さる例文(雑談・決裁者・予算の引き出し方)
・営業ヒアリングで避けるべき話題と5つのNG例文(焦らせる言葉・自慢・地雷ワード)
・営業のヒアリングに使えるフレームワーク6選(SPIN・BANT・MEDDIC)
現場の営業担当者だけでなく、営業責任者必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
営業ヒアリング5つの目的とは?
ニーズの把握をするため
相手の「本当の目的」をつかむために、営業ではニーズの把握が欠かせません。
これは、単なる商品の提案ではなく、「なぜその提案が相手にとって意味を持つのか」を明確にするためです。
なぜなら、法人営業の現場では、顕在ニーズだけでなく、言語化されていない「背景ニーズ」が意思決定を左右することが多いからです。
顧客自身が気づいていない「目的」と「本音」を引き出せれば、的を射た提案につながります。
現場で実際に活用されている具体例は以下の通りです。
- 「導入背景」を掘り下げて、潜在ニーズを引き出す
- 「既存業務の流れ」を聞いて、改善ポイントを探る
- 「決裁フロー」を確認して、提案タイミングを合わせる
このように、相手の立場や業務の背景まで深く理解することで、ただの機能説明ではなく「意味のある提案」に変えることができます。
相手の「なぜそれを求めるのか」に寄り添うことで、提案が自然と受け入れられるようになります。
顧客課題を理解するため
相手の「困っている理由」を知るために、営業では課題の理解が大切になります。
目的は、表面の要望に惑わされず、本質的な問題に向き合うためです。
なぜかというと、法人営業では「解決すべき課題」と「見えている課題」がズレていることが多いからです。
課題を誤ると、どれだけ優れた提案でも刺さらなくなります。
現場で実際に活用されている具体例は以下の通りです。
- 「業務フロー全体」を聞いて、ボトルネックを見つける
- 「過去の失敗例」を聞いて、再発リスクを避ける
- 「社内の温度感」を聞いて、合意形成を支援する
このように、相手の組織構造や過去の経緯まで踏み込むことで、課題の本質が見えてきます。
表面的なニーズに飛びつかず、一歩深く踏み込むことが提案の説得力を高めるポイントになります。
競争優位を確保するため
競争優位を確保するため、ヒアリングでは「他社が聞かないこと」を聞くのがポイントになります。
なぜなら、相手の本質的な課題に先回りして気づける営業だけが、検討の軸に入り込めるからです。
商品説明よりも、相手の事情や意図に深く寄り添うことで、「あなたに任せたい」と言われる関係が築きやすくなります。
現場で実際に活用されている具体例は以下の通りです。
- 「過去に断った“理由”を聞き出す」ようにする
- 「導入後の“社内反応”を探る」ようにする
- 「現場と決裁者の“温度差”を確認する」ようにする
こうした一歩踏み込んだ質問を重ねることで、提案の内容そのものが差別化されていきます。
競合と比べられない状態をつくるために、「聞く力」は最大の武器になります。
提案の準備のため
提案の準備のため、ヒアリングでは「何を聞くか」より「なぜそれを聞くのか」がポイントになります。
なぜなら、ヒアリングの質がそのまま提案の精度を決めるため、聞く目的が曖昧だと提案もズレやすくなるからです。
特に法人営業では、意思決定が複雑なぶん、背景や制約条件まで把握できているかが提案の説得力に直結します。
現場で実際に活用されている具体例は以下の通りです。
- 「社内決裁の“通し方”を確認する」ようにする
- 「過去に“見送られた理由”を掘る」ようにする
- 「“評価指標”が何かを明確にする」ようにする
事前に深く聞けていればいるほど、相手の視点で提案を組み立てやすくなります。
提案の準備のためには、「相手の判断軸」を言語化するヒアリングが欠かせません。
信頼関係を構築するため
信頼関係を構築するため、ヒアリングでは「売らずに聴く姿勢」を大切にするのがポイントになります。
なぜなら、相手は“売り込まれた瞬間”に警戒を強める一方で、「理解されている」と感じたときに心を開きやすくなるからです。
特に法人営業では、個人の感情よりも「安心して任せられるかどうか」が、検討の出発点になることが多いです。
現場で実際に活用されている具体例は以下の通りです。
- 「質問より“相づち”を丁寧に返す」ようにする
- 「相手の“社内背景”に共感する」ようにする
- 「話の“結論を急がず”に聴き切る」ようにする
焦らず寄り添うことで、「この人なら大丈夫そう」と思ってもらいやすくなります。
信頼を得るためには、売る前に“聴く”ことが何より大切な土台になります。
【刺さる11の例文】営業ヒアリングのコツ
「決裁者はどなたですか?」は言い方を変えて自然に聞く
商談で「決裁者」を確認する場面は避けて通れませんが、唐突に聞くと壁を感じさせてしまいます。相手の立場を尊重しつつ、スムーズに意思決定者の情報を引き出す言い回しが鍵です。相手に“探られている感”を与えないためには、あくまで業務の流れとして自然にヒアリングを重ねていくことが重要です。以下のテンプレートでは、共感から入りつつ、会話の流れの中で決裁者情報を引き出す実践的なトーク展開を例示しています。
テンプレート例文
御社と同じ業界の⬜︎⬜︎社様でも、最初にお話を伺ったご担当者様と並行して、早い段階で◇◇部門の方ともお話を進めさせていただいておりました。
↓(あ、それどういうことですか?)
ありがとうございます!今回の〇〇に関しても、御社の中で導入判断に関わる方が他にもいらっしゃるようでしたら、早めにその方の視点も踏まえたご提案ができればと考えております。
↓(なるほど、上長も絡むかもです)
そうなんですね、ちなみに過去に〇〇導入を進めた際は、最終的に△△部や◇◇部のお立場の方が意思決定に関わるケースが多くて。御社ではそのあたり、どなたが最終的にご確認されることが多いですか?
↓(部長ですね)
かしこまりました。今後のご提案内容も、部長様にも共有しやすいような形でご準備させていただきますね。タイミングを見て、同席いただくご調整なども一緒に進めましょうか?
このトークのポイントは、「他社事例 → 共感 → 確認 → 合意形成」の流れで自然に聞き出すこと。相手の立場を立てつつ、あくまで“成功確率を上げるための段取り”として伝えることで、信頼と情報の両方を得られます。
「最初の30秒」で信頼を勝ち取る雑談を用意しておく
商談の初動30秒は、信頼形成のゴールデンタイムです。いきなり本題に入るのではなく、相手が「この人とは安心して話せそうだ」と感じる雑談の一言があるかないかで、その後のヒアリングの深度が大きく変わります。雑談といっても、ダラダラした世間話ではなく、「相手の文脈に寄り添った一言」を準備しておくことが重要です。以下のテンプレートは、相手が思わず笑って返してしまうような“仕込みの一言”を通じて、緊張をほぐしながら空気を和らげるための具体例です。
テンプレート例文
本日はお忙しい中ありがとうございます。御社のHP、実は昨日じっくり拝見していて、特に⬜︎⬜︎の取り組み、あの切り口は本当に面白いですね。
↓(え、見てくださったんですか?)
はい、実は前職で◇◇業界を担当していて、当時あの課題にはかなり悩まされまして…。御社の取り組み、現場目線で本当に刺さりました。
↓(ありがとうございます。実は社内でも…)
やっぱりそうなんですね!〇〇領域って、現場の肌感をわかっていないと見落としがちですもんね。あ、ちなみに今日の商談資料にもその辺りを意識した事例を1つ入れてあります。
↓(なるほど、それ気になります)
ありがとうございます。では、本題に入る前にその事例だけ先にサクッとご紹介してもいいですか?
このトークのポイントは、「相手の事業背景+自分の体験」をかけ合わせた雑談を事前に仕込んでおくこと。“会話を始める理由”を作ることで、形式的なあいさつから抜け出し、一気に共感と信頼を得られます。
「予算ありますか?」ではなく「上限イメージってありますか?」と探る
「ご予算は?」と聞かれると、相手は一気に警戒します。
でも、「上限イメージってありますか?」と聞かれると、あくまで“配慮”として受け取られ、答えやすくなります。
ヒアリングでは“主導権を握りすぎない聞き方”が相手の本音を引き出すコツです。
特にSaaSやITツールなど幅のある価格帯を扱う商材では、価格を直接聞くよりも「範囲」で聞いたほうが確度の高い商談に繋がります。
テンプレート例文
〇〇のご支援をしている○○株式会社の△△と申します。もしお時間許せば、ヒアリングさせていただければと思っております。
↓(はい、お願いします)
ありがとうございます。ちなみに、ご検討中の中で「この金額を超えるのはちょっと…」という上限のイメージって何かお持ちだったりしますか?
↓(うーん、◯◯万円くらいまでなら…)
かしこまりました。実は、その◯◯万円前後で導入された企業さまも多くいらっしゃいまして、たとえば⬜︎⬜︎社さまはそのご予算内で◇◇まで実現されています。
↓(それなら可能性ありそうですね)
ありがとうございます。**御社のように複数拠点がある場合は、初期は◯◯拠点から小さく始めて、成果が出たら全社展開という進め方もできるんです。**よければ、そういった進め方も含めてご提案させていただければと思いますが、いかがでしょうか?
このトークのポイントは、「金額そのもの」ではなく「超えてほしくないライン」を丁寧に聞くこと。
そうすることで、相手の懐に入り込みやすくなり、無理のない商談設計が可能になります。
「今の課題って何ですか?」よりも「最近困ったことって何かありましたか?」と聞く
「今の課題は?」と聞かれても、構えてしまってすぐに言語化できる人は少ないものです。
一方、「最近困ったことってありましたか?」と聞けば、日常会話の延長で自然と本音を引き出せます。
“課題”という抽象ワードよりも、“困ったこと”という具体的な感情ベースの言葉を使うことで、記憶を辿ってもらいやすくなるのです。
営業ヒアリングでは「構えさせずに、具体的なエピソードを語ってもらう」ことが、真のニーズ把握につながります。
テンプレート例文
〇〇のご支援をしております○○株式会社の△△と申します。本日は少しお話を伺えればと思っております。
↓(お願いします)
ありがとうございます。ちなみに、最近、お仕事の中で「これは困ったな…」と感じたことって何かありましたか?
↓(そうですね…実は社内の◯◯で…)
なるほどです。そのお話、他社さまでもよく伺います。たとえば⬜︎⬜︎社さまではその悩みをきっかけに◇◇を導入されて、今は△△の時間を約◯◯%削減できている状況です。
↓(それ、かなり助かりますね)
**御社の業務フローも少しお聞きした上で、似たような改善案を一緒に考えられたらと思っております。**今、簡単に全体像をご共有してもよろしいですか?
このトークのポイントは、いきなり“課題”と聞かず、相手の「最近の実体験」から会話を始めること。
自然な導入から入ることで、相手の温度感や真のニーズが掴みやすくなり、その後の提案精度も格段に上がります。
顧客が分かったつもりにならないように「何をわかっていないか」5W2Hで探る
ヒアリングでは、顧客が語る内容の“前提”を疑ってみることがポイントです。
相手が「できている」と言っていても、実際には何が・いつ・どこで・誰が・どのように行っているのかを深掘ることで、見落とされていた課題やボトルネックが浮かび上がります。
5W2Hで具体性を詰めていくと、「思っていたより属人化していた」「そもそも目的が共有されていなかった」など、顧客自身が気づいていない本質的な課題が明確になることがあります。
テンプレート例文
〇〇の活用についてご検討中とのことですが、実際には「いつ・誰が・どこで・どのように」〇〇を運用されているか、少し詳しく教えていただけますか?
↓(あ、そこはちゃんと把握できてなかったかも)
ありがとうございます。ちなみに、そのフローが属人的になっていたり、部門間でやり方がバラバラだったりするケースが多くて、御社はいかがでしょうか?
↓(たしかに、部門ごとにやり方が違うかもしれません)
そうですよね。たとえば〇〇社様では「誰が・何を・どこまで対応するか」を見直すことで、対応のばらつきがなくなり、△△%の工数削減につながった例があります。
↓(その話、もう少し詳しく聞かせて)
もしご興味あれば、具体的に5W2Hで棚卸しした上で、御社内でどこが改善ポイントになるか一緒に整理できればと思いますが、いかがでしょうか?
このトークのポイントは、「できている前提」にメスを入れて、顧客自身の“見えていない曖昧さ”を一緒に可視化すること。
それによって「話を聞いてくれた営業」から「整理してくれるパートナー」に認識が変わります。
「現場の声」から引き出すと、ニーズが具体的に見えてくる
上層部の言葉だけでは、本当に困っている現場のニーズまでは見えづらいことがあります。
そこで、「実際に日々使う方」「作業の中で感じている違和感」「業務中に無意識にしている工夫」など、“現場の一次情報”にこそ注目することで、机上では出てこないリアルな課題が浮かび上がります。
数字よりも先に、現場の感情や不満、希望を言語化することで、提案の方向性がグッと現実に即したものになります。
テンプレート例文
〇〇について検討されていると伺いましたが、実際に日々〇〇を使っていらっしゃるご担当の方は、どのようなところで不便を感じていらっしゃいますか?
↓(現場はたしかに別のことを言っていたかも)
ありがとうございます。現場のお声を聞くと、「この部分が一番ストレス」「実は他のツールで代用している」などの声が上がることが多くて、御社ではいかがでしょうか?
↓(あ、それうちでも起きてます)
たとえば〇〇社様では、現場のヒアリングで「△△作業に毎日◇◇分かかっている」と分かり、そこを自動化したことで年間⬜︎⬜︎時間の削減につながったケースがあります。
↓(まさにそれ、うちでも似たような…)
もしよろしければ、御社でも現場の声を整理したうえで、一緒に改善ポイントを洗い出してみることも可能ですが、いかがでしょうか?
このトークのポイントは、「意思決定者の視点」だけでなく「現場の温度感」も合わせて聴くこと。
机上の提案ではなく、現実にフィットする打ち手に落とし込むために、現場の声を“起点”にすることが鍵です。
「導入後のイメージ」まで話を引き出せたら、決着は近い
導入後の未来像を描いてもらえると、お客さまの中で“変化の期待値”が具体的になります。
「自社に入ったらどうなるか」を自分ゴト化してもらうことで、検討段階から一気に導入前提のフェーズに進むことができます。
ヒアリングの中で「どこで・誰が・どんなふうに使うか」「どんな業務がどう楽になるか」まで具体的に言語化してもらえると、もう商談はかなり前に進んでいます。
テンプレート例文
まずは御社で〇〇をご活用いただくときの“使い方のイメージ”から一緒に描いていければと思っております。
↓(あ、じゃあ実際の使い方を考えておいた方がいいのかも)
ありがとうございます!たとえば御社の△△部門で〇〇をご利用いただくと、初月から⬜︎⬜︎の手間が大幅に削減されるケースが多いです。
↓(それって、誰が使う想定ですか?)
実際に操作されるのは◇◇の方々になることが多く、レクチャーは◯時間程度で完了するため、比較的スムーズに現場に定着しやすいです。
↓(他社でもそんなに早く使えるようになるんですね)
ちなみに同じ業界の〇〇社様では、導入3ヶ月で⧉⧉レポート作成時間が△△%短縮され、月次報告がワンクリックで完結するようになりました。
このトークのポイントは、「誰が・どこで・どう使うか」「それで何が変わるか」を“今ここで”一緒に考えること。
お客さまが自然に自社の運用に重ね合わせることで、検討から導入のスイッチが入ります。
「過去の失敗例」を出すと、相手の本音がポロッと出る
「成功の話」ばかりだと、相手の本音は隠れたままになりがちです。
過去に似た商談でうまくいかなかった事例や、導入後に現場でつまずいた事例をあえて共有することで、相手の警戒心がほどけ、心の中にあった“本当の懸念”が出やすくなります。
失敗談を出すと、「実は前にもこういうことで困ったことがあって…」と、相手側の地雷を先に見せてもらえるのが大きなメリットです。
テンプレート例文
実は以前、〇〇導入の際にある企業様で少し現場が混乱したケースがありまして…
↓(えっ、そういう話ってあまり聞かないけど…)
はい、そのときは、IT部門主導で進めた結果、現場の業務フローとのすり合わせが甘くて、実際に使い始めたときに混乱が起きてしまいました。
↓(あ、それうちでも似たようなことありました)
そうだったのですね。ちなみに御社では、〇〇導入時に現場の方の巻き込みって、どのように進めていらっしゃいますか?
↓(たぶんまたトップダウンで進めちゃうと思います)
ありがとうございます。実は、現場の△△さんに最初に〇〇の画面を一緒に触ってもらうだけで、定着率が大きく変わった事例があるので、そういった進め方もご提案できます。
このトークのポイントは、「失敗事例→共感→本音」の流れを意図的につくること。
成功トークでは出てこない“本当の障壁”を明らかにすることで、提案の解像度が一気に上がります。
「クローズドクエスチョン(限定質問)」でより具体的に引き出す
ヒアリングの序盤から「はい」「いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンをうまく使うことで、お客さまの中にある“まだ言語化されていない課題”を整理するきっかけになります。
オープンクエスチョンに比べて答えやすいため、相手の警戒心を下げつつ会話のリズムも作れます。
テンプレート例文
御社では現在〇〇に関して、すでに何かしらのツールをご導入されていますか?
↓(はい、導入してます)
ありがとうございます。ちなみに、それは△△のような用途でお使いですか?それとも⬜︎⬜︎に重きを置かれてますか?
↓(主に⬜︎⬜︎ですね)
なるほど、ではその⬜︎⬜︎の部分で、たとえば◇◇のような点に少しでもお困りのことはございますか?
↓(実はそこが…)
実際、他社様でも同じお悩みが多くて、当社の〇〇を使うとそのあたりが自然と仕組み化されます。もし5分ほどあれば、そこの流れだけ簡単にご紹介できますが、いかがでしょうか?
このように「はい/いいえ」で始まり、徐々に具体に絞っていく構造にすると、相手が“何に困っているのか”を自覚しやすくなります。
クローズドクエスチョンは、“気づき”を生むための最初の一手として非常に有効です。
「稟議の流れ」ではなく「社内で話を通すとしたら、誰からですか?」と聞く
稟議フローを聞くより、実際に「誰にどう話を通すか」を具体的に聞いた方が、決裁者やキーマンを浮き彫りにできます。
社内調整の実態は、表面上の稟議プロセスと異なることも多く、根回しの実情や“影響力を持つ人物”を知るうえで極めて有効です。
テンプレート例文
ありがとうございます!ちなみに、社内で〇〇のような新しい仕組みを導入する場合、最初にお話を通すのはどなたになりますか?
↓(それは□□部長ですね)
なるほど、□□部長が最初のポイントになるんですね。ちなみに、次に影響があるとすれば◇◇部でしょうか?
↓(そうですね、実際に使うのはそっちなので)
承知しました。実際に□□部長が前向きになられた場合、社内で承認を進めるうえでポイントになる方が他にいらっしゃれば教えてください。
↓(たぶん、あとは経営企画ですね)
ありがとうございます。関係者が見えてきたので、次回のご提案時にはそれぞれの部門での活用イメージも盛り込ませていただきます。
このトークのポイントは、「流れ」ではなく「誰」に話を通すかを聞くこと。稟議書に名前が出ない“実質的な影響者”を把握することで、後工程の障壁を事前に潰しておけるのが現場営業にとって大きな差となります。
「他にありますか」と聞くことで課題の網羅感を確認していく
ヒアリングの終盤で「他にありますか?」と聞くことは、漏れを防ぐだけでなく、相手に「全体を振り返ってもらう」きっかけになります。
さらに「他にはありません」で終わる場合も、逆に「それ以外はクリア」という確認にもなり、提案の焦点を定めやすくなります。
テンプレート例文
ありがとうございます。今まで伺った〇〇の対応や、△△の運用負荷以外に、現場で気になっていることや課題は他にありますか?
↓(今のところはそれくらいですね)
承知しました。では現時点では、〇〇と△△の改善が優先度高め、という認識で合っていますか?
↓(はい、そこが一番ボトルネックです)
ありがとうございます。ちなみに、たとえば⬜︎⬜︎のような観点では特にご不便などないですか?
↓(あ、そういえばそこの集計にも手間かかってました)
なるほどです。そこも含めて全体の整理をしたうえで、次回ご提案をまとめてお持ちしますね。
このトークのポイントは、「他にありますか?」をただの形式的な一言で終わらせず、“問い直し”によって相手の思考を深堀りさせること。聞き漏らしていた本質的な課題が出てくるきっかけにもなり、提案の精度を一段階高めることができます。
営業ヒアリングシートに盛り込むべき7つの項目
「今の業務フローと困りごと」は図にして残す
課題の“つながり”を見つけるカギは、図にすることです。
ヒアリングで出てくる困りごとは、断片だけ聞いていてもピンと来ないことが多いです。
でも、業務フローを図で描いてみると、「あ、ここが詰まってるんだな」と自然にわかる瞬間があります。
特に法人営業では、現場の手順や承認ルートが複雑で、聞き手の頭の中だけでは整理しきれません。
だからこそ、口頭でのヒアリング内容を図にまとめておくと、あとから見返したときにもズレがなくなります。
相手も図を見せられると、「そうそう、ここが手間なんですよ」と本音を話しやすくなります。
・「工程ごとの手書き図」で、非効率な動きをあぶり出す
・「担当者の流れ図」で、ボトルネックの人物や工程を明確にする
図にするだけで、課題の本質が“勝手に浮かび上がる”感覚を持てるようになります。
「予算感」は金額より“温度感”をメモする
金額よりも、「どこまで本気か」を見抜くほうが大事です。
数字だけを追うと、「予算はまだ決まってなくて…」で会話が止まりがちです。
でも、なぜ検討しているのか、誰が導入を決めるのか、いつまでに進めたいのか——
その温度感を聞き出せると、数字以上にリアルな“買う気”がわかります。
実際、社内調整で金額が後から動くことはよくある話。
だからこそ、温度感がつかめていないと、最終局面でズレた提案になってしまいます。
“温度”のない商談は、最後まで曖昧なまま終わってしまうこともあります。
・「導入希望時期」で、急いでいるかの真剣度を探る
・「決裁者の発言内容」で、社内の本気度を感じ取る
金額の裏にある“空気”を正しく読めると、提案の軸がブレません。
「決裁者と稟議の順番」は口頭の流れをそのまま書く
話の順番には、その会社の“社内の空気”が出ます。
だから、誰の名前が最初に出て、どこで一旦止まったのか。その流れをそのまま書くのがいちばん確かです。
たとえば、「課長がOK出せばあとは部長に回すだけなんです」と言われたら、それが現場の動きです。
あとから整理し直すと、現実とズレてしまうことがあるので、聞いた順にメモするのがコツです。
順番通りに書いてあると、上司に引き継ぐときもそのまま使えるし、誰にどの資料を見せるべきかも自然と見えてきます。
・「一次決裁者→相談役→最終決裁者」の順で、実際に出た名前を書いておく
・「稟議が動くきっかけになった一言」をそのまま書き留めておく
順番には理由があります。そこに営業の“次の一手”が隠れています。
「希望導入時期」は“納品逆算”で整理しておく
「いつまでに必要か?」が分かれば、「今なにを決めるべきか?」が自然と見えてきます。
導入希望日を聞いたら、そこから逆にスケジュールを組むのがいちばん現実的です。
たとえば「4月の展示会で使いたい」と言われたら、実は2月中に発注しておかないと間に合わない可能性が高いです。
多くの営業は“導入時期”をカレンダーの話だと思いがちですが、実際には「社内の事情」と直結しています。
逆算しておくと、提案に“今やる意味”を持たせることができ、先方の動きを前倒しにする力にもなります。
・「社内イベントや期初」を軸に、リードタイム込みで逆算しておく
・「導入後の定着ステップ」まで含めて、最終ゴールから逆に道筋をつけておく
納期ではなく、目的から逆に考えると、提案の芯がブレなくなります。
「検討中の他社」とその印象は正直にメモする
他社との比較軸を押さえられるだけで、提案の深度が一段階変わります。
「競合は〇〇で迷っているらしい」──この一言があるだけで、アプローチの角度も言葉のトーンも変えられるのが営業の現場です。
実際、他社サービスに対するお客様の評価には、今の課題や意思決定のクセが滲み出ます。
逆に言えば、その一言を聞き逃すと、ピントのズレた提案になるリスクが上がるということです。
・「比較対象の社名」と「印象」をセットで書き留めておく
・「期待値のギャップ」があるかどうかも会話から拾っておく
お客様自身が気づいていない本音は、こうした他社へのコメントの中にこそ現れます。
提案資料に差をつけたいなら、競合評価の“温度感”を必ず残しておくのがおすすめです。
「導入後の理想像」をお客様の言葉で書く
理想像がわかると、提案の“着地点”が明確になります。
営業としての役割は、単にモノを売ることではなく「その先にある成果を一緒に描くこと」。
そのためには、導入後のイメージを“こちらの言葉”でまとめず、“お客様の表現”で残すことが鍵になります。
・「〇ヶ月後にこうなっていたい」などの「未来の状態」を言葉通りに記録しておく
・「それができたら最高だな〜」といった「感情ベースの表現」もメモに含めておく
人は、感情を動かされたときに決断します。
だからこそ、“なぜそれを実現したいのか”をお客様の言葉で記録しておくことが、最終的なクロージングを助ける武器になります。
「KPI」や「成果指標」は数字+感情で残す
数値だけでは、意思決定の「熱量」が読み取れません。
たとえば「CVRを2%改善したい」というKPIだけを見ても、その背景にある温度感やプレッシャーまでは伝わらないですよね。
営業として大切なのは、数字の“裏側”にある「なぜその数字なのか」「どれほど本気なのか」を拾い上げること。
感情のトーンがわかるだけで、提案の優先度や説得の力点が変わります。
・「目標数値」とあわせて「焦り・期待・不満」といった「感情ワード」もメモセットでしておく
・「なぜそのKPIなのか」という「上位方針や背景」も可能な範囲で聞い出しておく
数字と感情のセットで残すことで、表面的なニーズではなく“本質的な期待”にアプローチできます。
それが、ただの提案を“当事者の伴走”に変える一歩になります。
営業ヒアリングで避けるべき話題と5つのNG例文
「うちは他社より優れてます」は言わない方がいい
「うちは他社より優れているんです」は、聞き手の警戒心を一気に高めます。
相手は「比較は自分でする」と感じて、逆に距離を取られてしまいやすいです。
自社を押し出すよりも、相手の課題にどれだけ具体的に寄り添えるかが大事です。
営業トークの例
顧客「他社と何が違うんですか?」
営業「弊社の方がサービスの質が上です」→NG
営業「御社の◯◯課題に、この仕組みがどう効いたか事例を共有してもいいですか?」→OK
“違い”を主張するより、“相手に近づく話し方”のほうが、自然に信頼が生まれます。
自慢話より、相手の目線に立った共通点が、受注の一歩目になります。
「で、いつ決まりますか?」は焦らせるだけ
「で、いつ決まりますか?」と聞かれると、多くの決裁者は圧を感じて身構えます。
この一言で「自分都合の営業だな」と思われ、関係性が一気に冷めてしまうこともあります。
大切なのは、相手の判断プロセスや社内事情に自然に寄り添うことです。
営業トークの例
顧客「社内で検討中です」
営業「で、いつ頃ご決定になりそうですか?」→NG
営業「承知しました。ちなみにご決定のプロセスって、どんな流れが多いですか?」→OK
決定日を急かすより、社内フローを聞く方が本音を引き出せます。
急がせる営業より、理解を示す営業のほうが、結果的に早く決まることが多いです。
「満足してないですよね?」は地雷ワード
「不満を前提」にした質問は、関係構築の芽を潰します。
この聞き方だと、相手は「誘導されてる」と感じてしまい、ガードが一気に上がります。
本音を引き出したいなら、まずは安心して話せる土壌を作ることが大切です。
営業トークの例
顧客「まあまあ満足してます」
営業「満足してないですよね?実は…」→NG
営業「ありがとうございます。ちなみに今よりもっと良くできるとしたら、どんな点でしょうか?」→OK
「不満を探す」のではなく「可能性を一緒に探す」スタンスが、結果的に本音と受注を引き寄せます。
会話は攻めるより、寄り添う方が深まります。
「その話、存じております」は相手の熱量を消す
話の腰を折るひと言で、相手の温度が一気に冷めてしまいます。
営業で大切なのは、内容よりも「話したい」という気持ちに寄り添うことです。
知っている情報でも、あえて初めて聞く姿勢で相手の熱量を受け止めることが信頼につながります。
営業トークの例
顧客「この前の展示会でね…」
営業「その話、知ってます。A社のことですよね」→NG
営業「そうなんですね!どんな話だったんですか?」→OK
相手が語る場を奪わず、むしろ「続きを話したくなる空気」をつくるほうが、関係が深まります。
知っていることでも「知らない顔」ができるのは、営業の重要スキルです。
「いきなり決裁者と会えますか?」は早すぎると警戒される
初対面で決裁者を求めると、相手の警戒心を強めてしまいます。
信頼も構築されていない段階で踏み込むと、「売り込み感」が強く伝わり、話が止まってしまうことがあります。
まずは目の前の担当者との信頼を積み重ねることが、次の扉を開く近道です。
営業トークの例
営業「ご決裁者の方と今度お会いできませんか?」→NG
営業「まずは◯◯様とすり合わせできたら嬉しいです。その上で、必要な方にご相談いただけると助かります」→OK
「早く進めたい」は営業の都合であって、相手の温度に合わせる配慮が信頼を生みます。
“今ここ”の関係に丁寧に向き合う姿勢が、最短で決裁者につながります。
営業のヒアリングに使えるフレームワーク6選
「SPIN話法」で雑談から本音を引き出せるようにする
SPIN話法とは、営業の会話で「現状→問題→示唆→解決」を順に掘り下げて、相手の本音やニーズを自然に引き出す会話技法のことです。
つまり、質問をただ重ねるのではなく、相手の話の“奥にある動機”まで寄り添いながら深掘りする手法といえます。
営業中に「雑談ばかりで核心に入れない…」と感じることはありませんか?
実は、導入の雑談で信頼関係を築いた後、SPIN話法で質問を切り替えると、本音をぐっと引き出しやすくなります。
たとえば、
「最近“離職率”が気になるとお聞きしてまして」
「現場の“情報共有”にお困りだとお聞きしたのですが」
のように、雑談の中に現状や悩みを丁寧に拾いながら質問を重ねると、相手も違和感なく本音を話してくれます。
ポイントは、会話を“質問で誘導”するのではなく“共感しながら掘り下げる”ことです。
信頼感を損なわずに深掘りするためにも、まずは現状の質問から、ひとつずつ丁寧に展開してみましょう。
以下の表を参考に、すぐに使えるSPIN質問の流れをストックしておくと便利です。
|
項目 |
例文 |
|
現状質問(Situation) |
「現在、営業体制は何名でご担当されていますか?」 |
|
問題質問(Problem) |
「その体制で、対応しきれない場面などありますか?」 |
|
示唆質問(Implication) |
「もし今の対応で機会損失があるとすれば、どのあたりでしょうか?」 |
|
解決質問(Need-Payoff) |
「たとえば、仕組みを変えることで成果が出るとしたら、どんな形が理想ですか?」 |
このように、雑談から自然にSPIN話法へと流れをつくることで、「表面的なニーズ」から「意思決定につながる本音」まで、会話の深度を高めることができます。
まずは“現状”の質問から実践してみてください。
「BANT情報」で“いつ・誰が・いくらで”を明確にする
BANT情報とは、営業において「予算・決裁者・ニーズ・導入時期」の4要素を確認し、商談の進行度を見極める基本フレームです。
つまり、「この案件、本当に買う気があるのか?」を見極めるための“判断軸”になる情報のことです。
「この人、良いこと言ってたけど、買うのは別の人だった…」といったズレを、営業現場で経験したことはありませんか?
実は、BANTの4つを最初の段階で確認しておくだけで、見込みの“濃さ”と“道のり”が一気にクリアになります。
たとえば、
「ご予算は“今年度の残り”で調整されています」
「“部長決裁”が必要で、今ちょうど社内稟議を上げてまして」
のように、相手の立場や決裁構造に自然に踏み込みながら聞き出すのがコツです。
ポイントは、単なるヒアリングではなく、「この4つを押さえれば、次のアクションが見える」という視点で会話を組み立てることです。
相手も営業だと気づいていても、構造的な会話にはちゃんと応じてくれるものです。
以下に、今すぐ使えるBANTの具体質問をまとめました。
|
項目 |
例文 |
|
Budget(予算) |
「ご予算感としては、どのくらいを想定されていますか?」 |
|
Authority(決裁者) |
「最終的にご判断されるのは、どちらのご担当者でしょうか?」 |
|
Need(ニーズ) |
「今、最もお困りの点はどの部分にありますか?」 |
|
Timeframe(導入時期) |
「導入を検討されるとすれば、どのタイミングを想定されていますか?」 |
このように、BANTはただのチェック項目ではなく、“受注までの地図”そのものです。
まずは雑談やヒアリングの中で、この4つの情報を自然に拾えるよう意識してみてください。
「MEDDIC」で“決裁者の本気度”を見極められるようにする
MEDDICとは、営業における商談の確度を高めるためのフレームワークのひとつです。
つまり、相手企業の「導入意志の強さ」や「決裁者の本音」に迫るための“道しるべ”のようなものです。
でも実際の現場では、「担当者とは盛り上がったのに案件が止まったまま…」ということはありませんか?
実は、決裁者の温度感を見抜けていないだけ、というケースが多くあります。
たとえば、
「意思決定基準を“社内稟議フロー”から確認しておく」
「導入の“痛みポイント”を定量で聞き出しておく」
など、事前にMEDDICの視点で情報整理しておくと、商談の濃度が一気に変わってきます。
ポイントは、「誰が・いつ・何を軸に判断するのか?」を徹底的に深掘りしておくことです。
商談が前に進まない時こそ、MEDDICを軸にした問いかけが、次の一手を見つけるヒントになります。
まずは、以下の例文を参考にして、会話の中で“本気度”を見極める感覚を掴んでみてください。
|
項目 |
例文 |
|
Metrics(定量効果) |
「今の業務で1件あたり何分かかっていますか?」 |
|
Economic Buyer(決裁者) |
「最終的なご判断はどなたがされるご予定ですか?」 |
|
Decision Criteria(評価基準) |
「導入を決める際に重視されるポイントは何ですか?」 |
|
Decision Process(意思決定プロセス) |
「社内ではどういった流れで稟議が通るイメージでしょうか?」 |
|
Identify Pain(課題の特定) |
「今、一番困っているのはどの業務ですか?」 |
|
Champion(社内推進者) |
「御社内で“この仕組みいいね”と広めてくれそうな方はいますか?」 |
MEDDICは“売るため”のフレームではなく、“買ってもらう理由”を一緒に見つける対話の型です。
ぜひ一つずつ会話に組み込みながら、商談の濃度を深めてみてください。
「3C分析」で競合と差別化ポイントを事前に整理しておく
3C分析とは、「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から市場を整理するフレームワークです。
つまり、営業の現場では“なぜ今この提案なのか?”を明確に伝えるための下準備として使える考え方です。
「競合と比べて、御社の違いってなんですか?」と聞かれて、言葉に詰まることはないでしょうか?
実は、差別化の材料が整理されていないまま話してしまうと、相手に響かないケースが多いのです。
たとえば、
「“競合は価格勝負”に対し、こちらは“継続率”を武器に話す」
「“大手企業対応”が競合なら、“中小特化の柔軟性”で対抗する」
など、比較軸を3Cで整理しておくだけで、伝えるべき“強み”が一気にクリアになります。
ポイントは、相手の業界や課題に合わせて、自社の「選ばれる理由」を見える形にしておくことです。
比較ではなく、“違いの価値化”ができるかが、提案の納得度を左右します。
以下に、実際の商談で使える3Cの例をまとめました。
|
項目 |
例文 |
|
Customer(顧客) |
「最近、契約が増えているのは“多店舗展開”の飲食チェーン様です」 |
|
Competitor(競合) |
「他社さんは“機能数”で訴求されていますが、当社は“操作の簡単さ”が選ばれる理由になっています」 |
|
Company(自社) |
「“導入後のサポート体制”に特化しているのが、弊社の一番の特徴です」 |
営業トークの下地にこの3Cがあるだけで、説得力も一段階深まります。
ぜひ、次の提案前に、自社ならではの違いを3つの視点で見つめ直してみてください。
その上で「5C分析」で“なぜ今なのか”の背景までつかむ
5C分析とは、顧客(Customer)・自社(Company)・競合(Competitor)・パートナー(Collaborator)・市場環境(Climate)という5つの視点から全体像を読み解くフレームワークです。
つまり、相手企業の「現状」と「打ち手の背景」に説得力を持たせるための“質問設計”に役立つ考え方とも言えます。
営業現場では、「今じゃなくてもいいのでは?」と決裁が先延ばしになることがよくあります。
では、なぜ相手は“今”動こうとしているのか? 何が変わったのか?という「背景」に踏み込むと、本音が引き出しやすくなります。
たとえば、
「競合の“価格改定”があって再検討が始まった」
「上期の“事業方針変更”でDX施策が急務になった」
のように、背景を言語化することで商談の“解像度”が一気に高まります。
ポイントは、「なぜ今なんですか?」ではなく、「最近、何か社内で変化などありましたか?」とやわらかく聞くこと。
タイミングの理由を押さえられると、提案の“刺さり方”がまるで変わってきます。
以下に実践的な質問例をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
|
項目 |
例文 |
|
顧客(Customer) |
「現場の方々から“業務負担が増えている”などのお声はありますか?」 |
|
自社(Company) |
「御社としての“注力分野”に最近変化はありましたか?」 |
|
競合(Competitor) |
「他社さんの動向で、社内に影響が出ていることなどはありますか?」 |
|
協業者(Collaborator) |
「取引先やパートナーとの関係性で、最近何か変化はありましたか?」 |
|
市場環境(Climate) |
「法改正や制度の影響などで、対応しなきゃいけないことが増えていたりしますか?」 |
こうした“変化の背景”に寄り添ったヒアリングができると、「今すぐ取り組むべき理由」に営業として自然と説得力を持たせられます。
「肯定法(バックトラッキング)」で話を聞き切る
肯定法(バックトラッキング)とは、相手の言葉を繰り返しながら共感を示し、話を深掘りしていく聞き方のことです。
つまり、“ちゃんと聞いてくれている”という安心感を与えながら、相手の本音を自然に引き出す技術とも言えます。
営業現場では、「ヒアリングが一方通行になってしまう…」という悩みがつきものです。
では、どうすれば相手にもっと話してもらえるのでしょうか?
実は、“話の腰を折らずに、オウム返ししながら相手のペースに合わせる”だけで、驚くほど会話が続きます。
たとえば、
「採用に課題を感じてまして」→「採用のところですね」
「店舗ごとに対応がバラついてて…」→「店舗単位での運用に差があるんですね」
のように、一言返すだけで“安心して話せる空気”を生み出すことができます。
ポイントは、相手の言葉を“要約せずにそのまま返す”こと。内容より“温度”を合わせる意識が大切です。
一方的な提案ではなく、対話を重ねる中で信頼が深まっていきます。
以下に、すぐに使える肯定法の返し方をまとめました。
|
項目 |
例文 |
|
不安に寄り添う |
「今の仕組みだとちょっと不安があって…」→「どうしても不安な部分って残りますよね」 |
|
現場の悩みを受け止め |
「現場から“忙しすぎる”と声が上がっていて」→「現場の方、かなり忙しいんですね」 |
|
方針に共感する |
「今年は攻めの営業を強化していく予定で」→「いまよりさらに拡大されていく方針なんですね」 |
|
感情をくみ取る |
「ちょっとモヤモヤしてまして…」→「気になるもののなかなか着手したり、情報整理したりするのが難しいことありますよね」 |
|
理由を探る |
「導入の判断が難しくて」→「すぐに判断するのは難しいテーマですよね」 |
“最後まで話を聞いてくれた営業さん”という印象は、数字以上に強い武器になります。
一言を返すだけの“聞く技術”、ぜひ今日の商談から試してみてください。
営業ヒアリングからクロージングまでの5つの流れ
「事前準備」で会社の動きと決算情報を頭に入れておく
商談の前に「相手の今」に目を通しておくだけで、会話の入り方も信頼の深まり方も変わってきます。
ここで言う「事前準備」とは、相手企業の決算内容やプレスリリースから、今どんな動きがあり、どこに注力しているかを把握することです。
ポイントは、「自社が入り込める変化」や「現場が困っていそうな兆し」を見逃さないこと。
よくあるのが、企業規模や売上だけを見てしまい、相手の課題感とズレた提案をしてしまうパターンです。
STEP
① 直近の決算資料をざっと読み、事業別の伸びと落ち込みをチェック
② プレスリリースで「新しい動き」や「提携・撤退」などの変化を確認
③ 社長メッセージや中期計画から、経営層の温度感を読み取る
④ 相手の変化に、自社の支援がどう絡めそうかを1行で言語化
たとえば、「〇〇事業の成長率が鈍化してましたが、現場でも影響出てますか?」と聞けるだけで、空気が変わります。
相手の“今”を知らずに行くのは、地図を持たずに山に入るようなものです。準備の5分が、商談の流れを大きく変えてくれます。
「アイスブレイク」で話しやすい空気を1分でつくる
商談の最初の1分で「話しやすい空気」がつくれると、その後の流れがぐっと楽になります。
「アイスブレイク」とは、雑談で笑わせることではなく、“相手の緊張をゆるめて、自然体に戻してあげるひと呼吸”のことです。
ポイントは、「相手が話しやすくなる話題」かつ「距離を詰めすぎないバランス感」です。
ありがちなのは、無理にウケを狙って空回りしたり、逆に天気の話だけで終わってしまうケースです。
STEP
① 相手の身につけているものや背景から話題を拾う(例:「そのボールペン、書きやすそうですね」)
② 相手が笑う必要はないので、共感+軽いツッコミ程度にとどめる
③ 話題が弾まなければすぐ切り上げ、次の話題にふわっと移る
④ 相手のリアクションを見て、テンションや話し方の“温度”を合わせていく
具体的には、「Zoomの背景、おしゃれですね。ご自宅ですか?」と聞くだけでも一瞬で空気がほぐれることがあります。
雑談の目的は“笑わせる”ことではなく、“安心して話せる状態”をつくること。ちょっとした観察力が、商談の立ち上がりを左右します。
「課題整理」で“相手が困っている本当の理由”を言語化する
商談が進まないとき、実は“本当の課題”が見えていないことがよくあります。
「課題整理」とは、相手の表現に振り回されず、“なにに困っていて、なにを避けたいのか”を一緒に深掘りしていく作業です。
大事なのは、言われたことをそのまま鵜呑みにせず、「なぜ?」をあと一歩踏み込んで聞けるかどうか。
よくあるのが、「コストを抑えたいんです」という言葉を“値引き要望”だと早とちりしてしまうケース。本当は「失敗して上司に怒られたくない」という不安だったりします。
STEP
① 相手の要望に対して「それって、何がきっかけで課題になったんですか?」ときっかけを聞く
② 出てきた背景に「なるほど、じゃあ理想はどういう状態なんですかね?」と未来像を描いてもらう
③ 話をまとめて「つまり、いちばん避けたいのは●●なんですね」と、整理して返す
具体的には、「たとえば、このまま何もしなかった場合って、どんなリスクがありますか?」と質問してみると、言葉の奥にある“本音”が出てきやすくなります。
表面じゃなく“奥の困りごと”を一緒に言葉にするだけで、相手との距離はぐっと縮まります。
「決裁フロー確認」で“話す相手”を間違えないようにする
せっかくいい話になっていたのに、社内で止まっていた――そんな経験があるなら、決裁ルートの確認があいまいだったのかもしれません。
「決裁フロー確認」とは、その提案が“誰のGOで動くか”を、最初のうちにしっかり聞いておくことです。
大事なのは、「稟議をどう通すか」ではなく、「誰のために通すのか」を把握すること。
よくあるのは、担当者と盛り上がったまま、決裁者がどこにいるか聞きそびれるパターン。あとから「実は部長の一言で全部ひっくり返りました」となるケースも珍しくありません。
STEP
① 商談の終盤で「ちなみにこの話、社内ではどなたが気にされそうですか?」とやんわり聞く
② 続けて「これまでって、どんな流れで社内OKもらってきました?」と過去の意思決定プロセスを聞く
③ 相手の話を受けて「その方って、どういうポイントを大事にされる方ですか?」と“決裁者の価値観”を探る
具体的には、「最終的に“どこで引っかかりそうか”一緒に想定しておきましょうか」と、相手の不安を先回りして整理するのがコツです。
あとで慌てないためにも、“最初に確認”が一番の近道になります。
「YesBut話法」で提案を締めくくる
商談の終盤で「いいんだけど…」という空気を感じたとき、そのまま押し切ると失注につながることがあります。
「YesBut話法」は、相手の懸念に寄り添いながらも、こちらの意図を自然に伝える言い方です。
大事なのは、最初に「共感のひと言」を置くこと。これだけで相手の警戒心がぐっと下がります。
よくあるのは、懸念を否定してすぐにメリットを語ってしまい、「話を聞いてないな」と思われてしまうケースです。
具体的には、
①「たしかにおっしゃる通りですね」で一度しっかり受け止める
②「ただ、〜という視点で見ると少し変わってきますよね」と軽く視点を変える
③「だからこそ、今回のご提案がフィットすると思ったんです」とそっと背中を押す
たとえば「初期費用がちょっと…」には、「確かに、最初のご負担は小さくないですよね。でも、その分◯ヶ月で回収できる設計にしてまして…」と返すと納得感が生まれます。
相手の“もやもや”を先回りして、そっと言葉で整えてあげる。そんな気配りが、最後の一押しになります。
営業のヒアリングでお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「法人営業でヒアリングを工夫しているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
ヒアリングの精度を上げようと努力しても、なかなかお客様の本音を引き出せなかったり、聞き出した情報をうまく商談に活かせなかったり……そんなジレンマを抱えている方は少なくありません。
営業は「聞く力」がすべて、と言われるほど重要ですが、実は“どう聞くか”だけでなく“誰が聞くか”も結果を左右します。
そこで、私たちスタジアムでは、営業ヒアリングに特化したプロ人材が、事前準備から実践・振り返りまでを徹底サポートしています。
特に、Web・IT領域で商談数や成約率の向上に悩む企業さまにこそ、私たちのノウハウがフィットします。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
【編集部が厳選】合わせて読みたい記事
トップ営業の切り返しトーク厳選15選&NG例7選【数字で成果を示す】
営業ロープレ台本例文集11のシーン別勝ちパターンを徹底解説【初心者〜管理者向け】
アイスブレイクが上手い人11の特徴と逆効果になる3つのシーン
営業のクロージングテクニック17のコツと成功の法則まとめ
飛び込み営業の天才が教える!成果を出す人11の特徴【例文5選&仕組み化】
【13の状況別】セールストークのコツ正解&NG例文集
営業トークのつかみを科学する。13のコツと商談化率を左右する3つの理由
飛び込み営業の挨拶で何を話すと有効か?55のチェック項目と例文集
営業マネジメント7つの役割とは?9つのマネージャーに必要な実践的スキル
17業界×9つのシーン別:営業トークスクリプトの例文集【完全保存版】
【17業界×13の技法】営業クロージングで成果の出た例文集
ファクトファインディングとは?5つの基本例文でやり方を解説【ヒアリングとの違いが肝】
営業の目標設定の教科書|4つの基本と具体例
営業「ロープレ」意味ない?!9つの理由と6つの対処法【目的の明確化が鍵】
営業効率化17のコツ。営業責任者必見!施策の効率を上げる7つのメリット
【21選】売れる新人営業を育てるための目標設定例・テンプレ付き
【72選】営業代行と相性が良い商材一覧・9つの特徴
2025年【31選】 B2Bに強い営業代行会社一覧7つの判断基準と料金を徹底解説
2025年【17社】業務委託で人気の営業代行会社一覧・7つの判断基準と利点を徹底解説
2025年成果報酬型のテレアポ代行会社17選と7つの判断基準
2025年最新成果報酬型の営業代行会社23選と7つの判断基準
IT商材に強い営業代行会社一覧26選と7つの判断基準
営業代行は「やめとけ」は本当?失敗理由10選と成功に導く選び方・5つの凄い利点
2025年最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
天才営業マン11の特徴「〇〇」で結果を出す最強の営業術
営業代行の費用相場/料金体系の選び方5つの手順【早見表付き/2025年最新】
2025年最新営業代行のメリットとは?コスト削減〜販路拡大まで9つの利点を解説
【25選】SaaS業界向け営業代行会社一覧7つの判断基準
東京に強い営業代行会社35選7つの判断基準と選び方
最終更新日