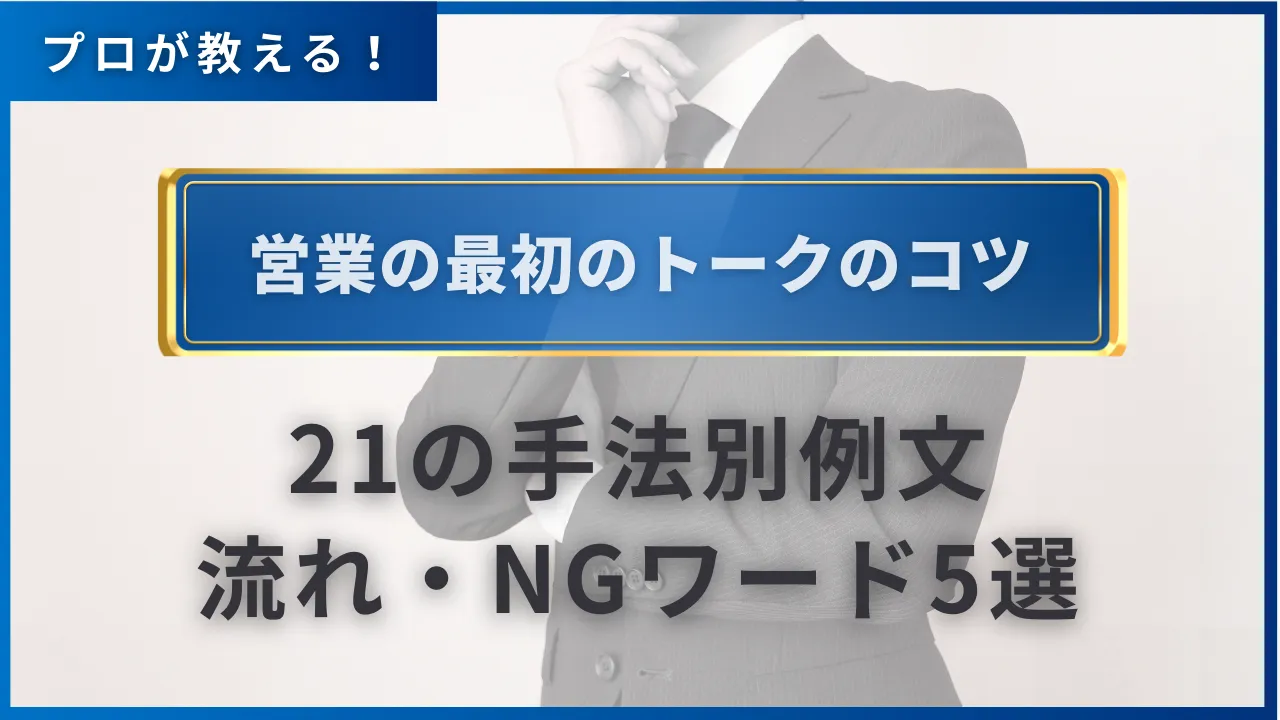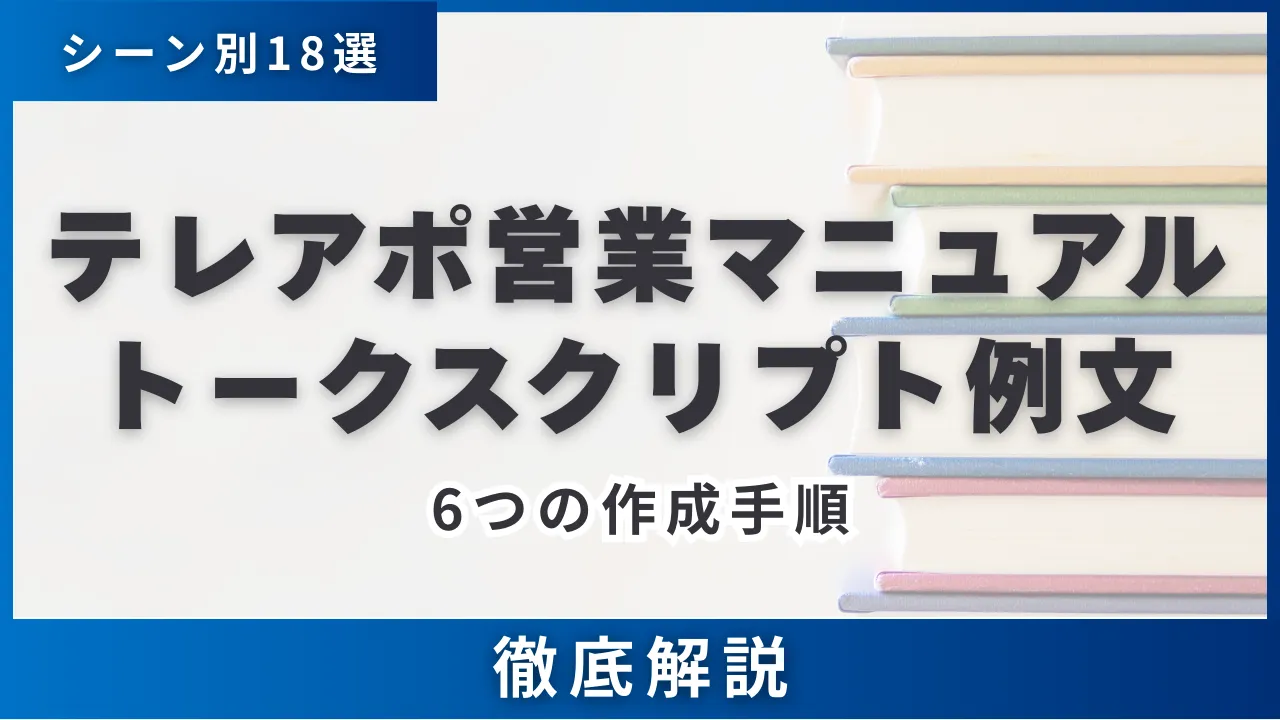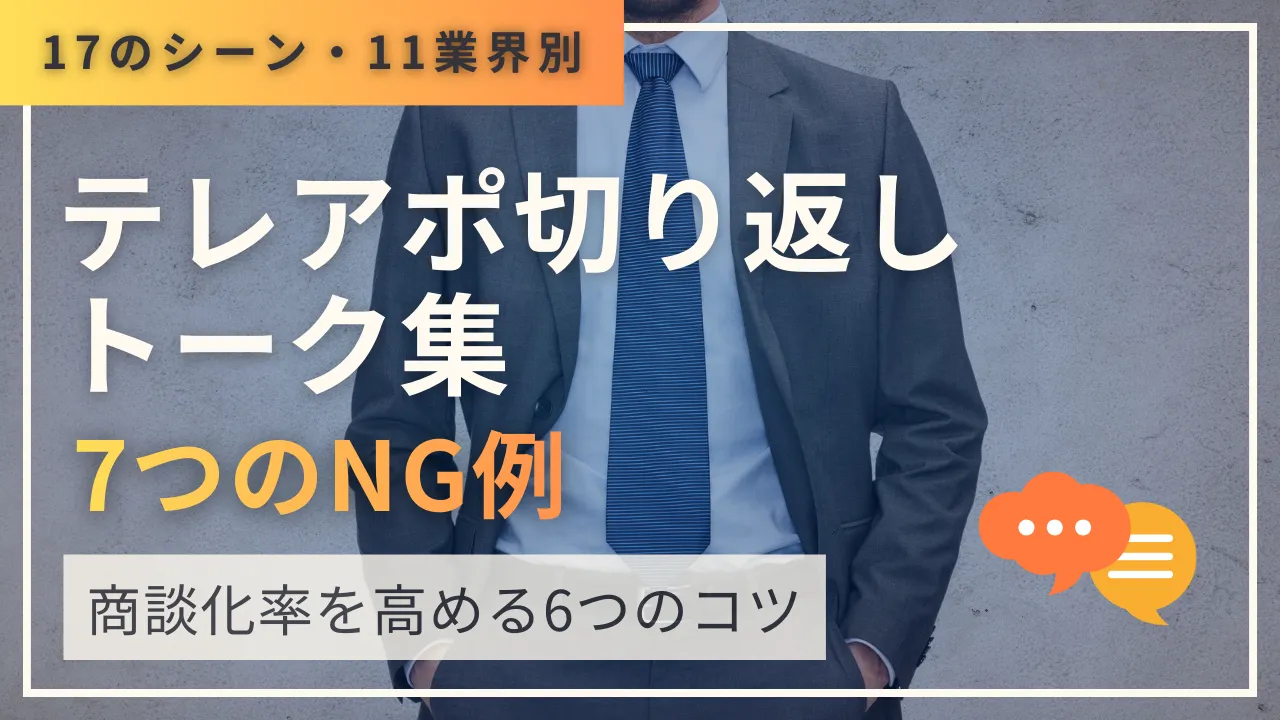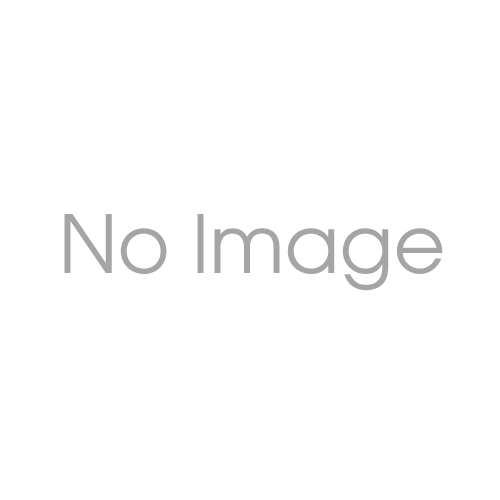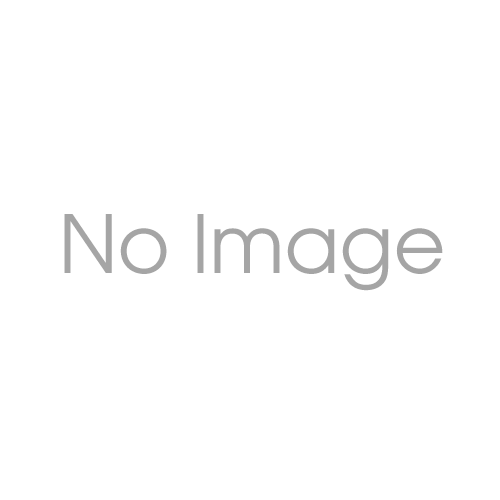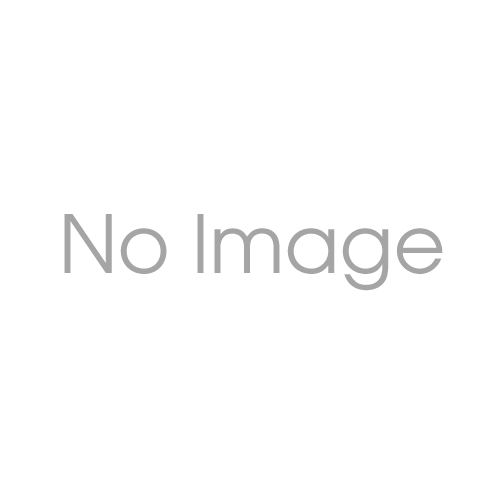SaaS営業きつい13の理由と5つの対処法【導入後の成果が鍵】
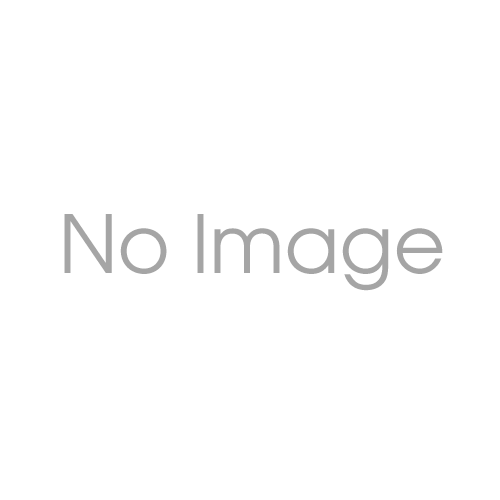
「SaaS営業って、なんでこんなにきついんだ…」
日々数字に追われ、商談化せず、部下のモチベーションも下がりっぱなし。
高いノルマ、成果が見えない毎日。
気がつけば、部下も自分も疲弊している――そんな現場、増えていませんか?
SaaS営業の特徴とは?(簡易まとめ)
SaaS営業は、関係を「育てていく」営業です。
SaaSとは、契約後も継続してもらうことで成果が出る「サブスク型の無形商材」です。
ポイントは、「導入後に成果が出る未来」を一緒に描けるかどうか。
よくあるのが、初回から売り込みすぎて相手が一歩引いてしまうパターンです。
例えば、「今どんな課題があって、何が変われば成功といえるか?」を先に引き出すと、その後の提案が刺さりやすくなります。
売るより先に、使い続けてもらう姿を一緒に想像してみてください。
本記事では、営業現場を知り尽くしたプロが「SaaS営業のキツさ」を徹底解剖。
マネージャーとして、チームを守り、成果を出すための具体策をお伝えします。
本記事を読むと分かること
・なぜ「SaaS営業はきつい」のか?リアルな13の理由
・成果を出すための「5つの具体的な対処法」
・SaaS営業に「向いている人・向いていない人」
上記についてよくわかります。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
- 「売上が伸びない」「営業組織の強化」「IT商材の営業」なら
- 「営業電話のモニタリング」「自動フィードバック」なら
SaaS営業きつい13のリアルな理由【導入後の成果が鍵】
「提案が抽象的」で相手に伝わらないのは、SaaS営業において誰もが一度は直面する課題です。
特に「競合が多すぎて」価格勝負になりがちな状況では、提案に具体性が欠けると一瞬で埋もれてしまいます。
さらに「分業体制」によって、提案内容と現場のズレが生まれやすく、納得感のある説明が難しくなるのも現実です。
伝わる提案を形にするには、導入後の声や成果を拾っておくことがポイントになります。
さらに詳しく見ていきましょう。
「提案が抽象的」で相手に伝わらない
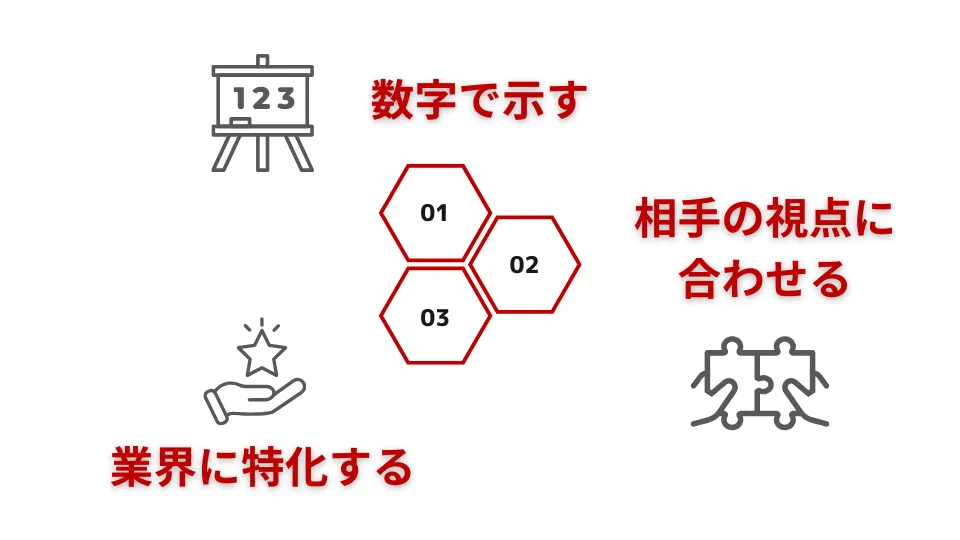
Saas営業で「提案が抽象的すぎる」と、決裁者の心に全く響きません。
なぜ営業は、せっかく提案しても「伝わらない」のでしょうか?
それは、「業務効率化」「工数削減」といった曖昧な言葉ばかりで、相手の現場に落ちるイメージが持てないからです。
以下の工夫で、提案の伝達力が一気に高まります。
- 「月30時間削減」「●円のコスト改善」など、数字で語ることで、決裁者の興味を引ける
- 「我々の機能は~」ではなく、「御社の○○部門で△△の課題に使えます」と相手視点に翻訳する
このように、抽象ワードを「数字・相手視点・業界特化」に置き換えるだけで、提案の刺さり方がまるで変わってきます。
「競合が多すぎて」価格勝負になりがち

SaaS営業では「どこも似たような機能ですよね?」と聞かれた瞬間に価格勝負へ突入しがちです。
それは、プロダクトの“定着率”や“運用支援力”といったSaaS特有の差別化ポイントが伝わっていないからかもしれません。
「なぜ他社より高くても成果が出せるのか」を、数字と支援体制で証明することが突破口になります。
実践的な対策例は以下の通りです。
- 「導入3ヶ月で利用率85%を維持」など、定着率データをプロダクト価値の証拠として活用
- 「SaaS商談でよくある競合比較表」を作成し、自社のオンボーディング支援やUI改善頻度を強調
- 料金表と一緒に「サクセスチームによる活用支援内容」を資料化し、価格以上の価値を可視化
価格だけで比較される前に、「成果が出る理由」をSaaSらしく丁寧に伝えることが差別化のポイントになります。
「導入までが長く」成果が見えづらい

SaaS営業では「導入までが長く、営業が前に進まない」と感じることがよくあります。
なぜなら、顧客社内での承認やIT部門との調整など、営業側が介入できないプロセスが多いためです。
営業が止まらないためには、初期段階で「道筋」を具体化し、顧客に“自分ごと”として動いてもらうことが重要です。
- 商談初期に「導入ステップと完了目安」を1枚の図解にまとめ、合意を先に取っておく
- 初月に実感できる成果(クイックウィン)を「●分設定でOK」など手軽に設計しておく
- 商談内容の議事録を見込み顧客との打ち合わせ後10分以内に毎回共有し導入障壁と次アクションを毎回明確に共有する
導入前の“止まり”を防ぎ、導入後の“期待外れ”を避けるには、「視える化や具体化」がポイントになります。
「カスタマイズNG」で顧客の要望に応えきれない
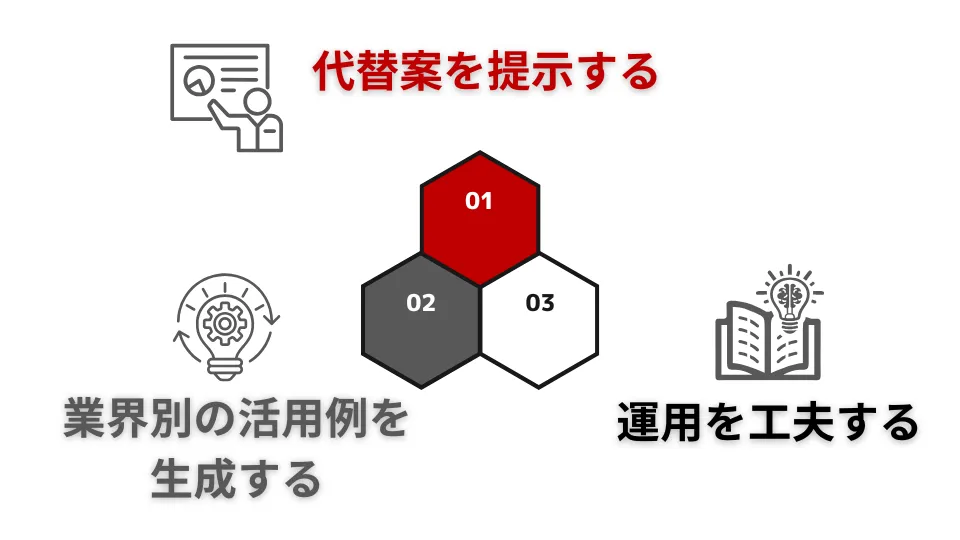
SaaS営業では「御社の業務に合わせて柔軟にできますか?」という質問が頻出します。
なぜなら、顧客はSaaSを“自社にフィットする前提”で選ぼうとするからです。
そこで「仕様上できません」と返すだけだと、「じゃあ他を探します」となりやすく、競合に流れてしまう可能性が高まります。
SaaS営業特有の対応例は以下の通りです
- 「API対応は今できませんが、Webhookを使った代替案があります」と技術的に“近い道”を提示する
- 「この機能は標準仕様ですが、利用権限の制御で実質的に非表示化できます」と運用側での工夫を提案する
このように「その場で代替パスを示せるか」がSaaS営業の成否を左右します。仕様に閉じるのでなく、“どう使うか”に視点を切り替える柔軟性が、商談を前に進める原動力になります。
「アップデート多すぎ」で製品理解が追いつかない
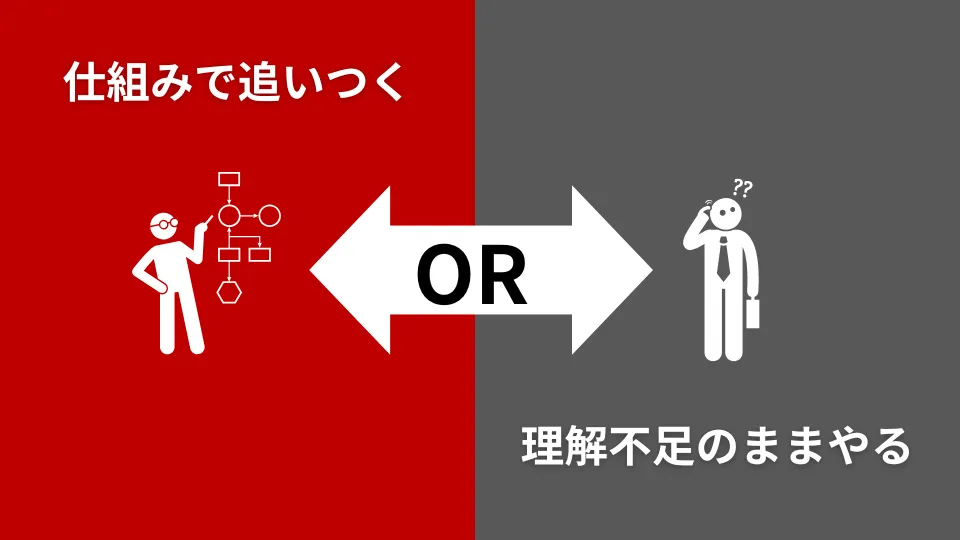
「この機能って何ですか?」と顧客に聞かれて詰まった経験、SaaS営業なら誰でもあるはずです。
機能追加が1週間単位で起きるSaaSでは、営業が理解できていないだけで“プロダクト不信”につながります。
特にAPI連携や料金体系の変更は、提案の根幹がズレてしまうリスクもあります。
では、どうすればSaaS営業がアップデートに置いていかれずに済むのか?
- ChatGPTに「最新の更新内容を、提案トーク用に要約して」と指示し5分で整理
- Notionで“営業向けの変更点まとめ”を作り、Geminiで「この業界向けの提案資料に変換して」と依頼
SaaS営業がプロダクト理解で遅れを取ると、全体の受注率に確実に影響します。
だからこそ「仕組みで追いつく」しかありません。
「KPI細かすぎ」で行動に縛られる

SaaS営業では、なぜこんなにKPIが細かく設定されがちなのでしょうか?
理由は、LTVを最大化するための“分業型営業”が主流になっており、成果を定量で管理しやすくする必要があるからです。でも実際には、数値に追われすぎて本質的な営業行動ができなくなるケースも少なくありません。
例えば、現場ではこんな課題が起きています。
- SDRが「1日50件のコール必達」で、ABM対象外のリードにも機械的に電話 → 無駄な工数がかさむ
- リードの温度感より「週◯件商談化」が優先され、適切な育成プロセスを踏めず失注率が上昇
- 商談ごとにHubSpot/Salesforceへ細かい入力が求められ、営業時間の2割がCRM作業に
こうした状況が続くと、営業が「売ること」より「KPIを埋めること」に意識を奪われてしまう可能性があります。SaaSモデル特有の“継続率・受注単価重視”の観点からも、KPIの精度と運用設計を見直すことが重要かもしれないです。
「分業体制」で全体像が見えにくい
SaaS営業で「このアポ、本当に意味あった?」と感じたこと、ありませんか?
分業が当たり前のSaaS営業では、SDRが獲得したリードがFSで失注すると、努力が水の泡に感じやすい構造があります。顧客の温度感や課題が、バトンの途中でこぼれ落ちてしまうからです。
とくにSaaSでは、単価が高くない分、量でカバーしがちなので、1件の重みが薄まりやすいのも現場のしんどさにつながります。
具体的な改善策は以下の通りです
- 録音した商談を文字起こしし、ChatGPTで課題・決裁構造・競合状況を要約→FSとCSへ即Slack連携
- HubSpotの「カスタムプロパティ」にSDRが聞き出した課題や利用中ツールを入力→商談全体で活用
- 月1回の「受注・失注ケースレビュー」をSDR・FS・CS合同で実施→共通言語を醸成
SaaS営業こそ、“バケツリレー営業”にならないための構造設計が不可欠です。点の情報を線にし、目的をつなげるとチーム全体の納得感が変わってきます。
「マーケやCSとの連携」で社内調整が面倒すぎる
SaaS営業では「マーケやCSとの連携」が商談の質と継続率に直結しますが、その調整が毎回ぐちゃぐちゃになりがちです。
なぜ営業は、連携のたびに疲弊するのでしょうか?──温度感の違いや目的のズレが原因です。
具体的にはこんなSaaS特有のズレがあります
- マーケから来た「ホットリード」が、実際は無料トライアルの登録だけで商談意欲ゼロ
- 営業が契約だけ済ませて放置→CSがツール導入の背景も分からず初回対応で迷子に
「熱い・冷たい」の感覚は人によってズレますが、SaaSではそれがチャーンリスクに直結します。
運用ルールを少し整えるだけで、営業が“調整役”から解放されるかもしれません。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【図解と事例で解説】マーケティング部門と営業部門が連携できない理由と解決策
「ITリテラシーの差」が商談を止める
SaaS営業では、ITリテラシーのギャップが商談の障害になります。
なぜなら、導入判断に関わる“技術的理解”がズレていると、話がかみ合わず、相手の不信感を招きやすいからです。
「SaaSなら当然わかるでしょ」という技術用語を、営業が噛み砕いて説明できるかが信頼の分かれ道になります。
- 「SCIM連携してますか?」に答えられず失注。→事前にSaaS導入時の“技術要件リスト”を把握しておく
- 「APIドキュメントありますか?」の質問に即答できず仕様提案の機会を逃す
- 「SaaS導入あるある技術質問テンプレ」を事前に生成しておくことが重要
こうした準備があると、“非エンジニア営業”でも安心して技術話に対応でき、商談のコントロールを失いません。
「解約リスク」が常に付きまとう
なぜSaaS営業では常に「解約リスク」に悩まされるのでしょうか?
理由は、契約後も継続利用されるかが収益に直結し、売っただけでは成果にならないからです。特に初月の活用定着が甘いと、数ヶ月後にサイレント離脱が起きやすくなります。
営業が実際に行っている具体的な対策は以下の通りです。
- 契約直後に「初月で達成すべき成果」をユーザーと明文化し、CSとSlackで共有→継続利用の期待値を揃える
- 「週次ログから離脱兆候がある企業」を抽出→フォロー優先順位を可視化しておく
- 営業とCSが月1で「解約予兆ミーティング」→責任の共有で放置を防ぎ、NDR改善に直結
このように営業とCSが連携し、初期活用の「成功設計」とログ分析を徹底することで、解約率を大きく抑えることができます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
解約阻止の話し方/N で年間1位を取り続けた営業秘技【後編】
「チャットやオンライン対応」で時間を奪われる
SaaS営業では、トライアル中の顧客対応が想像以上に時間を奪います。
「この機能どこ?」「バグかも?」のチャットに一日中つかまることもありますよね。
この“対応疲れ”を防ぐには、情報の整理とコミュニケーションルールの徹底が必須です。
- トライアルFAQを自動応答化。1日5件の機能確認チャットが実質ゼロに
- Notion AIでCSチャットを要約→「契約意欲あり」「他社比較中」など営業に必要なサインを抽出
- Geminiでプロダクト定例を自動文字起こし→営業用に要点だけSlack通知
SaaS営業の“売れる時間”を守るには、「対応しない仕組み」を持つのがポイントです。
「成果主義」でプレッシャーが常にかかる
SaaS営業では、毎日「見える化」された数値に追われがちです。
なぜSaaS営業は他業種よりプレッシャーが強いのでしょうか?
理由は、月間売上だけでなくMQL数やSQL転換率などの細かいKPIが細分化・公開されているからです。
以下のような工夫で、成果主義の重圧をチーム改善に変えられる可能性があります。
- MQL→SQL転換率を毎週Slackで共有し、改善点
- 商談録画を解析→トーク比率や沈黙時間を可視化し、1on1でフィードバック
このように、「結果を責める場」ではなく「プロセスを整える場」に変えることが、SaaS営業の継続力を高めるポイントかもしれません。
▼編集部のおすすめ動画を見る
成果が出ない…プレッシャーにどう打ち勝つのか!?【元リクルート営業が語る】
「成長スピード早すぎ」で自分が置いていかれる
SaaS営業は、週単位でプロダクトが進化するため、常に情報に追いつく負荷が大きいです。
では、どうすれば営業が新機能や仕様変更を即キャッチアップできるのでしょうか?
答えは「社内情報をAIで“営業目線”に再構築する仕組みづくり」です。
- NotionにアップされたリリースノートをChatGPTで要約し、「顧客に伝えるべき変更点」だけSlack通知
- 毎週のPdM説明会を録画→Veed.ioで字幕付き動画化→Nottaで要点抽出→5行以内で営業に配信
- ChatGPTに「このアップデート、競合と比べてどう強い?」と入力→即営業トークに落とし込める
SaaSの変化に置いていかれないポイントは、「AIをチームの情報係にする」ことかもしれません。
SaaS営業きつい場合の5つの対処法
「リードの質」が悪いなら、初回商談の同席率をKPIに入れる
初回商談で“手応えゼロ”…そんな営業、増えていませんか?
ヒアリングが浅いと、顧客の「本音」に届かず、課題設定すらズレます。
この“初動の空回り”を防ぐのに有効なのが、同席KPIの設定です。
たとえば初回からマネージャーが入れば、「検討フェーズ」や「キーマンの所在」を即座に見極められます。
営業1人だと拾えない“匂い”を、経験値の高い視点で補えるからです。
- 「初回同席率50%」をKPIに→“商談設計ミス”が激減する
- 「失注理由の可視化」→次のリード精査に即つながる
リードの質にモヤモヤするなら、まず“最初の5分”にこだわってみてください。
そこに同席者がいるかどうかで、商談の“骨格”が変わってきます。
「決裁者不在」の商談は、ヒアリング段階で稟議フローを聞き出す
「いい話ですね、でも私は決裁できません」──その一言、何度経験しましたか?
決裁者不在のまま提案を詰めても、最後に“稟議の壁”で止まるのが営業の現実です。
だからこそ、ヒアリング段階で稟議フローを押さえることが肝になります。
担当者が主導に見えても、裏には「稟議書」「回覧フロー」「部門承認」が潜んでいます。
その全体像を早期に把握できれば、提案の形も、巻き込む順番も変えられます。
- 「稟議決裁までのプロセス確認」で“提案の打ち手”が増える
- 「誰がどこで止めるか」を先読み→“逆算型アプローチ”が可能に
決裁者がいないなら、“仕組みそのもの”にアプローチする。
ヒアリングの段階でそれが見えれば、営業の打率は確実に変わります。
「検討します」で終わるなら、仮説ベースのROI試算を事前に用意する
「持ち帰って検討します」──その言葉、営業の手応えを一瞬で冷やしますよね。
多くの場合、これは“納得の根拠”が足りていないサインです。
だからこそ、商談前にROI試算の仮説を準備しておくことがカギになります。
数字の裏付けがあるだけで、話の重みは一気に変わります。
ROIの仮説があるだけで、顧客の“社内説明負荷”も下げられるんです。
- 「年間コスト削減額の仮説提示」→“検討”を“検証”に変える
- 「投資対効果のざっくり試算」→“決裁者への材料”として刺さる
精緻な計算じゃなくていいんです。
相手の業界や業務に合わせた“仮説ベース”のROIが、営業の説得力を底上げします。
「数字が追いつかない」なら、更新月前に提案を仕込む
月末に慌てて電話しても、数字は伸びません。
なぜか?決裁のタイミングは、もう少し前に“決まっている”からです。
だから、「更新月」の1~2ヶ月前に提案を仕込むことが、営業の勝負を変えます。
更新前は予算も意思決定も動きやすく、“見直し理由”が生まれやすい。
このタイミングで入ると、案件の主導権を取りやすくなります。
- 「更新30〜60日前」に接点→“再検討の余地”を引き出せる
- 「契約条件・利用実態の振り返り」→提案の“材料”が増える
追い込まれる前に、仕掛ける側にまわる。
そのための“逆算スケジュール”が、営業数字の下支えになります。
「ネガティブ反応」が多いなら、業界特化の導入事例を刺さる順に並べておく
「うちはちょっと合わないかも」──そんなネガティブ反応、営業中に出ると一気に空気が冷えますよね。
この壁を超える鍵は、“共通点”の提示です。とくに業界特化の事例は、想像以上に効きます。
事前に業界・業種別の導入実績を「刺さる順」で用意しておくだけで、流れはガラッと変わります。
「同じ業界×同じ課題」を見せることで、“うちにもハマるかも”という認知が生まれます。
相手が疑っているのではなく、ただイメージが湧いていないだけかもしれません。
- 「業界別の導入実績」→“想像の壁”を越えるきっかけになる
- 「課題別の成功例」→“営業トーク”よりもイメージしやすい
伝える順番で、伝わり方は変わります。
事例の“並べ方”がポイントです。
SaaS営業職に向いている人3つの特徴
「数字」を見て行動を変えられる人
営業で、数字を見て何を変えるか考えていますか?
SaaSでは、商談数・受注率・ARRがすべて連動して動きます。だから、数字の変化に気づき、すぐ動ける人が強いです。
ただダッシュボードを見るだけでは意味がありません。数字をもとに手を打てるかが分かれ道です。
- HubSpotで提案フェーズの離脱が多い→提案資料を2枚減らし、ヒアリング項目を3つに増やした
- 商談数を週15→20に増やした週、受注数が1.6倍に→翌週から週20を基準に変更
数字は“行動のヒント”です。見て終わる人と、動く人で結果が変わります。
「聞く力」と「提案力」を兼ね備えている人
営業で「話すより聞く」が大事って本当?
――結論から言えば、“聞く力”がある営業ほど、提案の質と信頼が圧倒的に高まります。
なぜなら、顧客の言葉の裏にある「真のニーズ」をくみ取り、それに沿った提案ができるからです。SaaS営業では特に、課題に“どう応えるか”が評価の分かれ目です。
具体例は以下の通りです。
- 発話割合を確認し、「顧客7:営業3」以下の比率に整えたチームは受注率が◯%向上
- 「手間が多い」と言う顧客に、手順短縮ではなく「自動処理での離脱防止策」を提案→即決に
このように、「聞いて、くみ取り、再提案する力」が、成果を生むSaaS営業の本質です。
▼編集部のおすすめ動画を見る
聴けば聴くほど提案力アップ!ヒントは会話の中に【質問型営業】
「トレンド変化」にワクワクできる人
SaaS営業では、変化を先回りして話せる人が一歩リードします。
なぜなら、顧客の関心は「今どんなツールが成果を出しているか」に集中しているからです。新機能や最新活用法を即トークに盛り込める営業は、提案の説得力が格段に上がります。
具体的には以下のような行動です。
- 新機能「Slack通知設定」の翌日、「それ、A社で通知遅延がゼロになったらしいですよ」と実例で切り出す
- 毎朝「SaaS 営業 × 自動化の事例」を調べ、要約を営業チームにSlack共有→提案に即反映
“変化を楽しむ癖”があるだけで、SaaS営業の信頼と差別化は加速します。
SaaS営業に向いていない人3つの特徴
「感覚営業」で乗り切ろうとする人
SaaS営業では「ノリ」で売れる時代は終わりました。
なぜSaaS営業に感覚頼りは危険なのか?理由は“導入判断が論理と再現性で下される”からです。
- 「この機能すごいんですよ!」と熱弁 → 顧客は「で、何が変わるの?」と冷静。KPI改善の根拠がなければ響きません
- トークで乗り切ろうとして資料なし商談 → セキュリティ・API連携の質問に詰まり失注 →
- 過去の感覚で「このパターンでいける」と思い込み → 新たな競合の機能比較で完敗 → 競合比較表を毎週自動更新する仕組みに変えて改善
SaaS営業は、「感覚より構造」「熱意より定量」。ここを外すと勝てません。
「一人でやりたい」タイプの人
SaaS営業で「一人でやる」は、成果が出にくい最大の落とし穴かもしれません。
なぜなら、SaaSは仮説検証と改善のスピードが成果を左右する営業だからです。
孤立した動きでは、ナレッジも改善サイクルも遅れ、数字に直結してきます。
具体例は以下の通りです。
- Slackに商談内容を共有せず、同じミスが繰り返される → 次の担当者が同じ顧客に失注提案
- 上司のフィードバックを無視 → GongやZoom録画で確認したら初回商談のヒアリングが浅すぎた
- インサイドと連携せず、全部一人でリスト・メール・商談 → ChatGPTでメール生成すれば接触数2倍にできた
SaaS営業は「再現性と連携」が命です。
チームで動く人ほど、少ない努力で最大の成果を出せるようになります。
「数字の振り返り」が苦手な人
SaaS営業で「数字の振り返りができない」と、継続率も成約率も下がるリスクがあります。
なぜなら、SaaSはLTV・CACなど指標ごとの改善が成果に直結するモデルだからです。
「営業でどの数字をどう振り返ればいい?」という疑問には、KPIを行動に紐づけて分析することが効果的です。
SaaSでは「どこで止まってるか」を数字で振り返るだけで、営業改善の精度が一気に上がります。
SaaS営業3つやりがい
自分の提案で売上が動く実感がある
SaaS営業では、「何を売るか」より「どう使ってもらうか」で商談が決まります。
なぜ営業で“活用提案”が成果を分けるのか?──答えは、顧客は「機能」より「成果」にお金を払うからです。
具体的な現場例は以下の通りです。
- 勤怠SaaSで「CSV出力→自動API連携」に切り替え、月30時間の手入力削減を提案し導入決定
このように、SaaS営業は“売る”より“使わせる”提案で、数字が動く瞬間に立ち会えます。
顧客の課題を解決できる充実感がある
SaaS営業では、課題の本質を見抜いて改善まで導けるのが一番のやりがいです。
なぜSaaS営業はそこまで深く顧客に入り込めるのでしょうか?
理由は「導入して終わり」ではなく、「継続的な支援」が求められるモデルだからです。
顧客の業務改善に継続的に関わることで、実感できる手応えが圧倒的に違います。
- 「日報入力が遅い」→Slack連携のワークフローを提案し、入力率が月5割→9割に改善
- 契約後、定着支援のためにオンボーディング動画を内製し提供→初月利用率が70%超
SaaS営業は「成果が見える」からこそ、顧客に感謝され、自分の仕事に誇りが持てます。
SaaS営業5つの種類方向性
「インサイドセールス」は初回接点のプロになる仕事
SaaS営業では、初回接点で「使うイメージ」を持たせると商談化しやすくなります。
なぜなら、SaaSは形がないぶん「自分ごと化」されないと検討すら進まないからです。
では、どうすれば初回の営業で相手に導入後の姿を想像させられるのでしょうか?
以下の工夫で、ファーストコールの質が劇的に変わります。
- スクリプト冒頭で「◯◯ツール、周囲で使ってる企業ありますか?」→関心度を引き出す
初回接点は「情報提供」ではなく「具体イメージの喚起」がポイントになります。
「フィールドセールス」はクロージング力で勝負する仕事
営業で「あと一歩届かない」原因は、決裁者の感情面を見落としているケースが多いです。
不安を事前に拾い、相手の“決断の壁”を先に崩しておくことが大切です。
例えば、「今期で一番リスクを感じている部分は?」と率直に聞き、不安を言語化してもらう。
このように、感情に寄り添い、準備で差をつけると、クロージングの精度が一気に変わってきます。
「カスタマーサクセス」は継続利用と信頼構築に全振りする仕事
SaaS営業で「継続率が伸びない」と悩むなら、CS(カスタマーサクセス)の仕組みを見直すことが突破口になります。
なぜなら、プロダクトが良くても、活用されなければ解約につながってしまうからです。
以下のような具体策が即効性を持ちます。
- 月次の打ち合わせでは「成果指標ベース」で話す
例「1ヶ月で作業時間を20%削減できた」といったKPI改善の可視化が信頼につながる - 問い合わせ対応の自動化で“顧客対応の遅れ”を防ぐ
例「パスワード再発行」などのよくある問い合わせはワークフローを整備して自動化し即時応答→月に20時間以上の負担減
このように、CSは「顧客が成功体験を感じるプロセス」をデザインすることが肝です。
「マネージャー」でチームを動かせるようになる
個人で成果を出せても、チームを動かす力はまた別のスキルです。
ここでいう「マネージャーで動かす」とは、「指示ではなく、仕組みと共感でチームを前進させる状態」のことです。
ポイントは、「数字」よりも先に「納得感」をつくることと、「属人化しない再現性ある動き方」を定義すること。
よくあるのが、トッププレイヤーの感覚で詰めすぎて、メンバーが“なぜ動くか”を見失ってしまうケースです。
例えば、「今週の行動は◯◯が目的で、こうすれば成果が出る確率が上がる」と“意味づけ”を一緒に言語化するだけで、現場の動きが一気に変わってきます。
数字を出すのはチームであり、マネージャーの仕事は“その動き方を設計すること”だと捉えてみてください。
「マーケ」へ移って売れる仕組みを作れる
営業の現場にいると、「この顧客の声、マーケにもっと活かせないのか?」と感じる瞬間が多いはずです。
なぜなら、顧客の“本音”は営業の会話にしか出てこないからです。
その声をマーケティングに繋げるには、以下のようなやり方も良いでしょう。
営業で得られた知見をマーケ組織に共有し、現場での声を事例記事等に含める。
メールマガジンに営業メンバーの実践的な知見を記載するなど、BtoBマーケターとして売れる仕組みを考えるのも一つの方法として大いにありです。
SaaS営業きつい状況でも成果を出す!4つの手順
「初回商談」はKPIを深掘って突破口をつくる
最初の商談では、いきなり提案に走らず「KPIの背景」にじっくり耳を傾けてみてください。
ここでいうKPIとは、営業・CS・マーケティングなど部門ごとに追っている主要指標のことです。
ポイントは「その数字がなぜ重要か」「どんなプレッシャーがあるか」に踏み込むこと。
よくあるのが、表面的に「月間リード数を増やしたいんですね」と流してしまうケース。
これでは相手の本当の課題や、稟議に通す理由づけを見逃してしまうことがあります。
具体的には、「◯件達成すると、どんな社内評価になるのか?」「過去に未達だった要因は何だったのか?」など、相手の立場で考えて質問してみてください。
すると、導入のインパクトが「KPI貢献」として裏付けられ、提案が一気に通りやすくなります。
相手の数字の“意味”を一緒に整理するつもりで、聞きに行ってみてください。
「決裁者アポ」は稟議ルートを先回りして設計する
商談をスムーズに進めたいなら、決裁者に会う前から稟議の流れをイメージしておくことが大切です。
稟議ルートを先回りして設計するとは、「誰がどこで止めるか」を予測し、事前に潰しておくことです。
ポイントは、「決裁者を最初に動かす」のではなく、「稟議に必要な人たちの納得材料」を先にそろえること。
よくあるのは、いきなり部長にアポを取り「話はいいね。でもまず担当課長通して」と戻されるパターンです。
具体的には、担当者との会話で「このご提案、課長や経理の方もご覧になりますか?」と軽く確認しておき、事前に稟議資料も用意します。
「決裁の流れって、どんな順番になってますか?」と率直に聞いておくのも、実は信頼を得る一手です。
社内調整のストレスを軽くしてあげることで、「この人、頼れる」と感じてもらえるかもしれません。
「検討中フェーズ」では競合比較と意思決定軸を具体化させる
このタイミングでは、相手の頭の中にある「迷い」を一つずつ言語化させていくことが重要です。
「検討中」とはつまり、複数の選択肢を比較している状態。ここで優先順位をはっきりさせることが鍵になります。
ポイントは、「何と迷っているか」「その理由は何か」「どういう判断基準があるか」を丁寧に引き出すことです。
よくあるのは、「とりあえず比較検討中なんで…」という言葉をそのまま受け取り、深掘りしないまま放置してしまうパターンです。
具体的には、「他社様と比較されている点は、どの部分が大きいですか?」「最終的にご判断されるとしたら、どんな基準になりそうですか?」と聞いていくことで、相手の中にある“判断の軸”が見えてきます。
今はまだ決められないという温度感でも、一緒に整理する姿勢を見せると信頼につながります。
「受注クロージング」はIS・CSとの役割を分解して営業主導に戻す
受注直前でモタつかないためには、クロージング工程をもう一度営業主導に引き戻すことがカギになります。ここでいう役割の分解とは、「誰が、いつ、どの判断を支えるか」を事前に線引きしておくことです。
ポイントは、「意思決定者との面談」と「懸念払拭の最後の一押し」は必ず営業が握ること。
よくあるのは、CSやISに任せすぎて、気づいたら熱量が下がっていたというパターンです。
例えば、「トライアル振り返りの場面では、営業が主導で資料をまとめ、CSは利用データの補足に徹する」など役割を明確に分けておくと、会話の流れが締まります。
最後の面談は、営業が“決めにいく場”として設計しておくのがポイントです。少し勇気を出して、主導権を握り直してみてください。
最終更新日