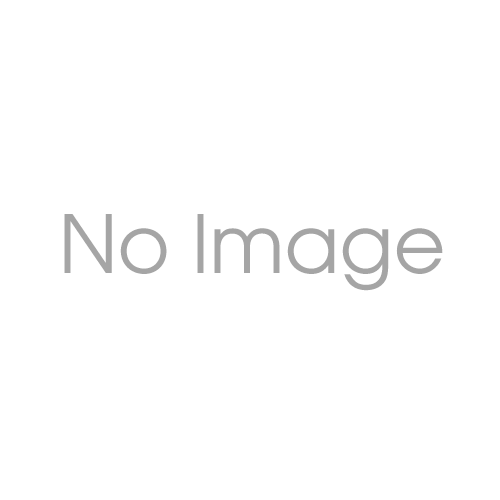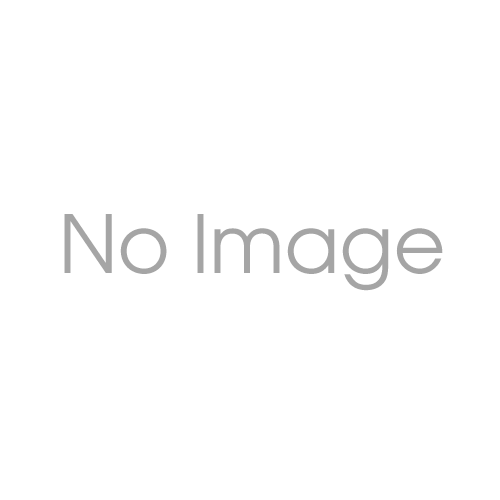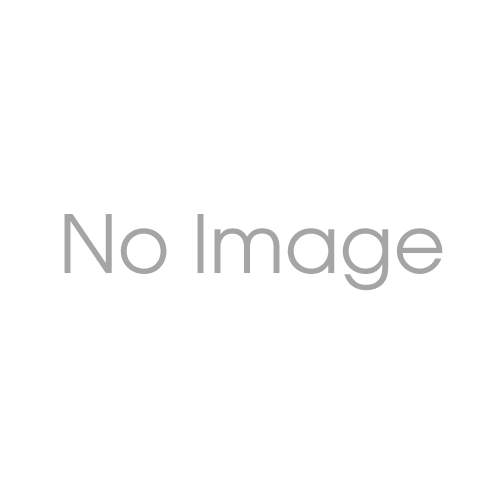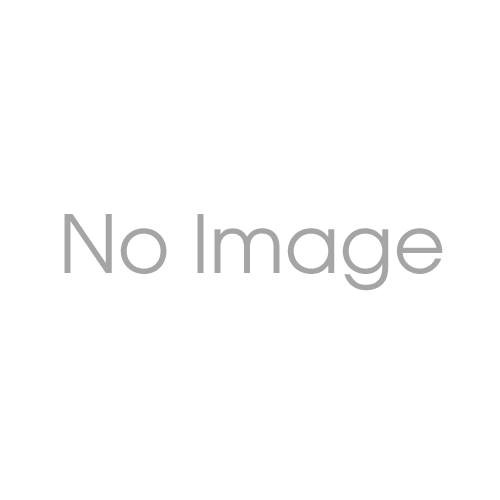飛び込み営業「迷惑」回避!迷惑なものにしてしまう9つの理由/成功率の高い時間帯
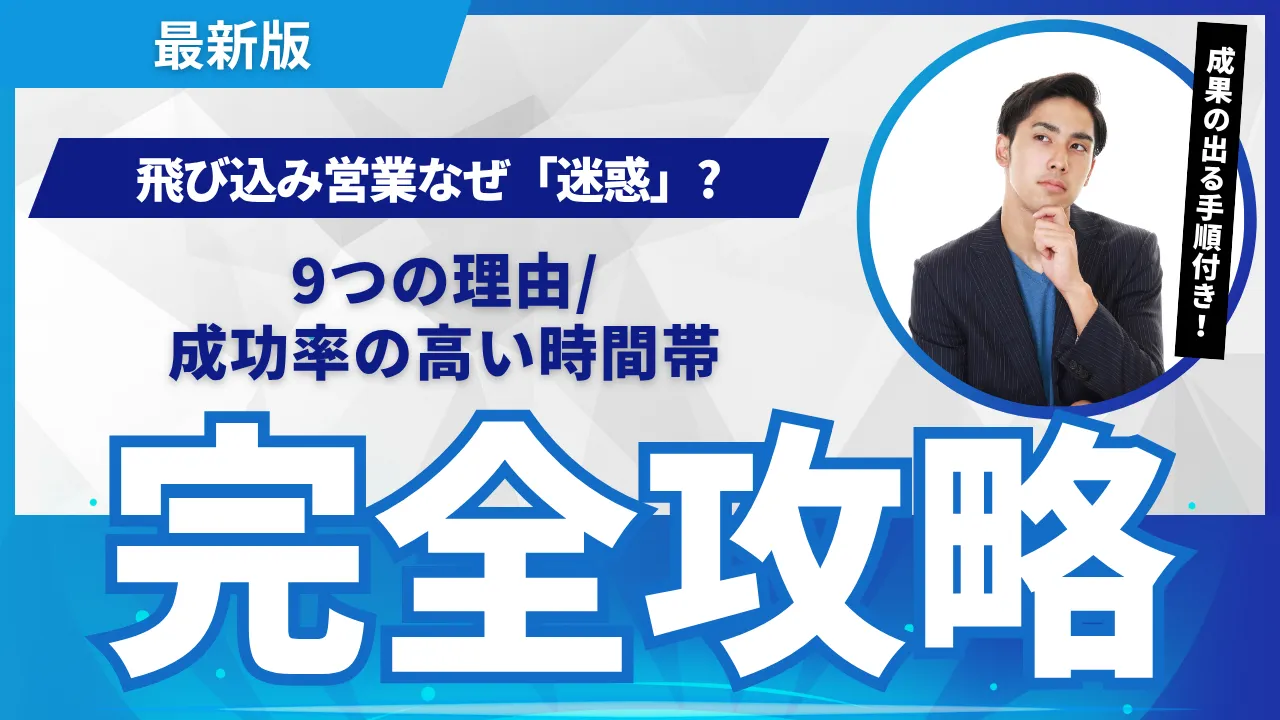
「飛び込み営業って、やっぱり迷惑なのだろうか…」
訪問営業、その中でもアポイントを設定せずに訪問を行う”飛び込み営業”には、知っておかないといけないマナーや礼儀があります。
逆に、相手にとっても歓迎される営業作法を身につければ、飛び込み営業は営業マンにとっても見込み顧客にとっても有用なコミュニケーションになります。
一番大切なことは相手にとって迷惑にならないかを最優先して考え、営業をすることです。
本記事では、迷惑にしてしまう理由と、営業成果を最大化する方法を解説します。
タイミング・配慮・事前準備、この3つの視点が劇的に成果を左右します。
・なぜ飛び込み営業は迷惑と思われるのか?(アポなし訪問・担当者不在・売り込み感)
・訪問成果を高める最適な時間帯とは?(午前10時~11時・午後2時~4時)
・迷惑にならない飛び込み営業の工夫と手順(事前通知・訪問設計)
現場の営業マンだけでなく、営業マネージャー必見の内容です。
「もっと詳しく教えて欲しい」「これ、うちにも当てはまるかも」と思った方は、ぜひ営業のプロ集団「スタジアム」に無料で相談してみましょう!
飛び込み営業を迷惑なものにしてしまう9つの理由
”飛び込み営業”では多くの営業マンが経験することかもしれませんが、顧客からの反応は必ずしもポジティブなものであるとは限りません。他の営業手法でも、8割はお断りの会話であるというのが一般的ですが、顧客と直接対話するこの営業手法では、飛び込み営業特有の『気をつけないといけないこと』を知らないままに営業することは、自分にとっても顧客にとっても失礼になるかもしれません。
そこで今回は、顧客目線・営業目線両方で、『迷惑』な営業にならないための事前知識をお伝えしていきます。
「アポなし訪問」は相手の業務を中断させてしまう
アポなし訪問とは、事前連絡や約束をせずに突然相手先を訪問することです。
つまり、相手のスケジュールを無視して、突発的に時間を奪ってしまう行動になってします。
だからこそ、「どうすれば迷惑にならないか」を徹底的に考えることが重要です。
まずは事前に「相手の会社の稼働時間帯や業務内容」を調べ、訪問が負担にならないタイミングを見極めることが大切です。
そして訪問時には「短時間で終わること」と「相手に何の得があるのか」を明確に伝えることを意識します。
例えば以下のような工夫が効果的です。
- 「午前中の静かな時間帯」を狙って訪問する
- 「●●の業務効率に役立つかもしれない情報」として要点を一言で伝える
- 「手渡し用の1枚資料」を用意し、会話は最小限で完結するようにする
アポなしでも印象を損なわず、次につながる接点をつくることは可能です。
だからこそ、“準備と配慮”が、飛び込み営業の価値を大きく変えるかもしれません。
営業は“入り口”での印象が9割です。
訪問前に「相手のワークフローにどう入るか」を設計できると、信頼残高は確実に変わってきます。
「担当者不在」のリスクが高い
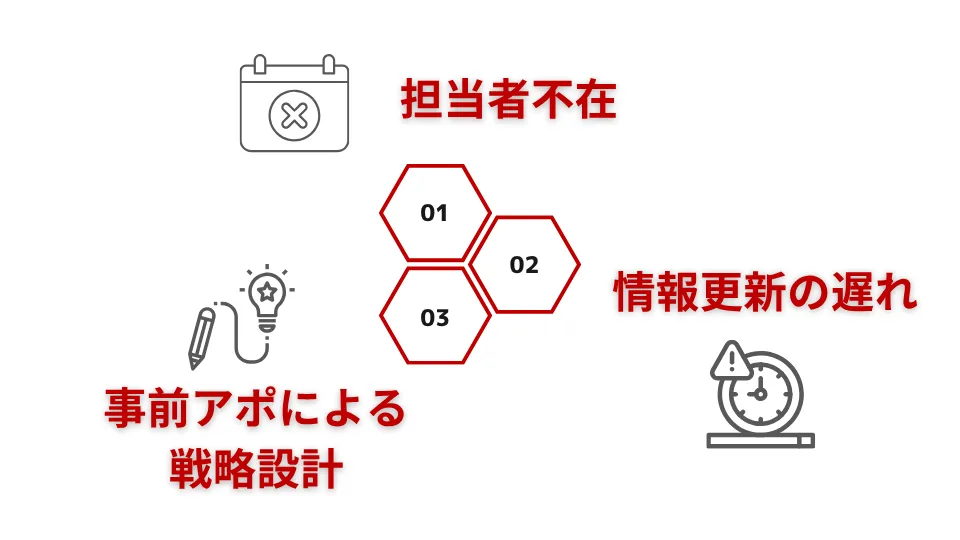
営業で「せっかく現地に行ったのに、誰にも会えなかった…」という経験、ありませんか?
今の法人営業は、フリーアドレスやハイブリッドワークの普及で、訪問しても“担当者が物理的にいない”ケースが当たり前になっています。
営業としては、その“空振り”が積み重なることで、時間だけでなく信頼やモチベーションも少しずつ減ってしまうかもしれません。
それだけに、訪問前の「一手間」が、実は大きな差を生み出すように感じます。
弊社でも、「訪問前の在席確認」と「顧客情報の更新」を徹底することで、空振り訪問を大きく減らしてきました。
代表電話での在席確認に加えて、SNSやWebサイトでの情報収集も積極的に活用しています。
たとえば、次のような具体策があります。
- 代表電話で「本日〇〇様はご在席ですか?」と丁寧に確認する
- 企業のSNSで「出社日」や「稼働状況」を事前にチェックする
- 名刺管理ツールで異動・退職などの最新情報を常に更新する
こうした工夫を重ねることで、訪問が“実を結ぶ”確率を自然と高めることができます。
だからこそ、「無駄を減らす事前の準備」が、これからの営業には欠かせないです。
「警戒心」が先に立ち、会話が成立しづらくなる
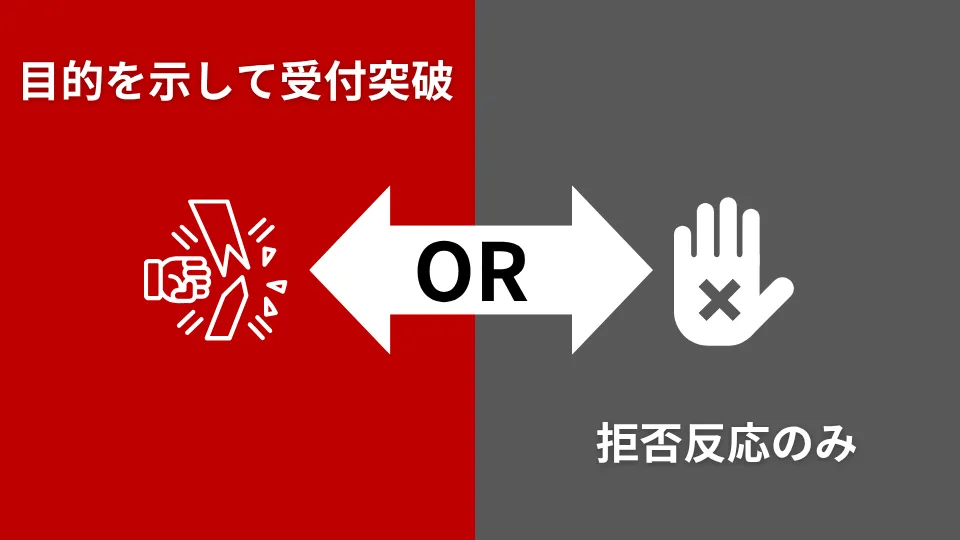
営業で「入口で止められて、商談どころじゃなかった…」と感じたことはありませんか?
今は飛び込み=“想定外のリスク”として扱われやすく、受付突破すら営業力の一部になっています。
特にBtoB企業では、未接触の訪問者をCRMで即チェックし、社内ルールでブロックされることもあります。
では、どうすれば最初の“拒否反応”を和らげられるのでしょうか?
現場で今すぐ試せる打ち手はこちらです。
- 「既知の存在」としてアプローチできるように準備する
訪問前に、可能な範囲で対象企業との接点を作る努力をしましょう。
例えば、自社で発行しているニュースレターを事前に送付したり、企業のSNS投稿にコメントを残したりするなど、直接訪問する前に何らかの形で「接点があった」という痕跡を残すことで、受付での警戒心を和らげ、「既知のリード」として認識されやすくなります。
- 最初の15秒は「相手の関心事」でアイスブレイク
企業ウェブサイトやプレスリリースで、その企業の最近の動向を調べ、「御社、〇〇のリリース拝見しました」といった形でアイスブレイクに使います。
これは「あなたの会社をちゃんと調べています」という姿勢を示すことになり、相手は警戒しつつも話を聞く姿勢になりやすくなります。
このように、最初の15秒で「誰?なんの目的?」の壁を超えられるかが、商談の入口を決めます。
飛び込みでも、準備ひとつで“情報武装型セールス”に変わる可能性があります。
「売り込み感」が強すぎて拒否したくなる
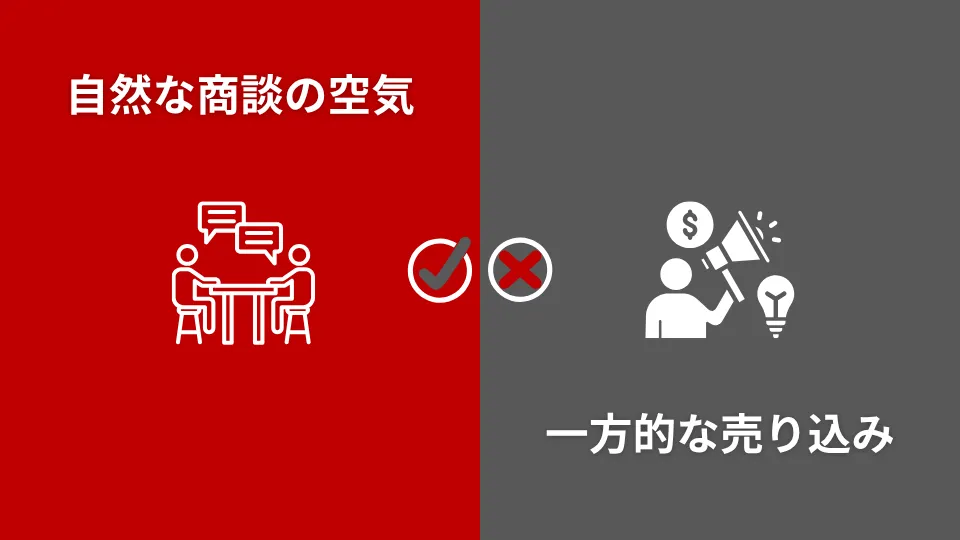
営業で「いきなり売り込まないで」と反発された経験はありませんか?
相手の話を聞く前から商品説明を始めてしまうと、「売りたいだけなんだな」と思われてしまうことがあります。
その印象は、知らず知らずのうちに相手の心のシャッターを下ろしてしまう原因になるかもしれません。
私たち自身も、 営業先でも同じように、“会話のペース”を乱されると、違和感を持たれてしまうことがあるように感じます。
そこで重要なのは、「売ること」ではなく「知ってもらうこと」から始めることです。
たとえば、初回訪問ではヒアリングを優先し、相手の状況や考え方を丁寧に聞き出すことを意識しています。
具体的には以下のような工夫を取り入れています。
- 相手の「温度感」に合わせて話し方のトーンを調整する
- 「ヒアリング→共感→提案」の順で会話の構造を設計する
- 商材の話に入る前に「なぜお会いしたか」を情報提供ベースで伝える
このように、売り込みではなく“信頼の会話”を起点にすることで、相手の反応は大きく変わります。
話した瞬間から「売ってこない安心感」をつくれるかが、営業の入り口かもしれません。
「タイミングの悪さ」で印象が一気に悪くなる

営業で「今その話されても困るんだけど」とピシャリ断られた経験はありませんか?
飛び込み営業では、内容よりも“訪問のタイミング”で印象が決まってしまうことがあります。
月初・週初・朝礼明けなどは特に応対ストレスが高く、好印象に持ち込むのが難しくなります。
どうすれば訪問タイミングの精度を上げ、相手に受け入れられやすくなるのでしょうか?実務で使える具体的な工夫は以下の通りです。
- 過去の商談履歴から「行動パターン」を特定する
顧客管理システム(Salesforceなど)で、過去の商談履歴や活動ログを詳細に確認しましょう。
「この会社の担当者は、火曜の15時以降は比較的手が空いていることが多い」「月末は特に忙しい傾向がある」といった行動パターンや、対応されやすい時間帯を割り出します。これにより、闇雲な訪問を避け、効率的なアプローチが可能になります。
- 「接触済みタイミング」を把握し、自然な再訪問を設計する
名刺管理システム(Zoho CRMなど)のログから、過去に接触したタイミングやその時の相手の状況を把握しましょう。
例えば、「以前は忙しそうだったが、そろそろ落ち着いた頃か」といった仮説を立て、それに合わせて「先日は大変お忙しいところ失礼いたしました。この度、改めてご挨拶に伺いました」と、相手の状況を考慮した自然なリベンジ訪問を設計します。
飛び込みの勝率は、商材より“訪問の文脈”で決まることがあります。
雑談でも「今ちょうど話したかった」が引き出せたら、それはもう価値ある商談の入口です。
「情報提供の価値」がないと即座に拒否される
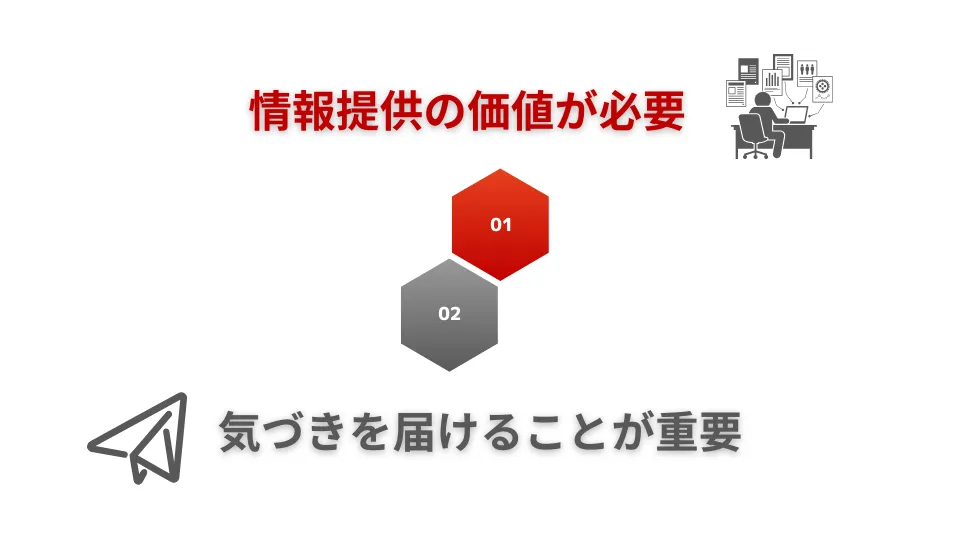
営業で「どこも同じ提案ばかりで響かない」と言われた経験はありませんか?
“商品軸”で話すと押し売りに見え、“顧客軸”で話すと一気に信頼が生まれます。
相手の業界事情やタイムリーな課題に即した情報を持ち込むことで、初回訪問でも会話が前に進みやすくなります。
- 「売る」ではなく「課題解決のヒント」を提供する意識する
訪問の目的を「商品を売る」ことから、「相手の業界における共通の課題解決のヒントを提供する」ことにシフトさせましょう。
これにより、相手は売り込みとしてではなく、有益な情報交換の機会として捉えてくれやすくなります。
- 同業他社の成功事例を具体的な数字で提示する
顧客管理システムで同業他社の成功事例を抽出し、具体的な改善効果(例:「物流費の見直しで月間200万円削減された事例をご紹介したくて伺いました」)を提示しましょう。
これは、相手にとって「自分たちにもメリットがあるかもしれない」という具体的なイメージを与え、興味を引き出す強力なフックとなります。
“情報を渡す営業”ではなく、“気づきを届ける営業”が、次の商談の入り口をつくります。
「名刺だけ渡して終わる」パターンも多く迷惑に感じやすい
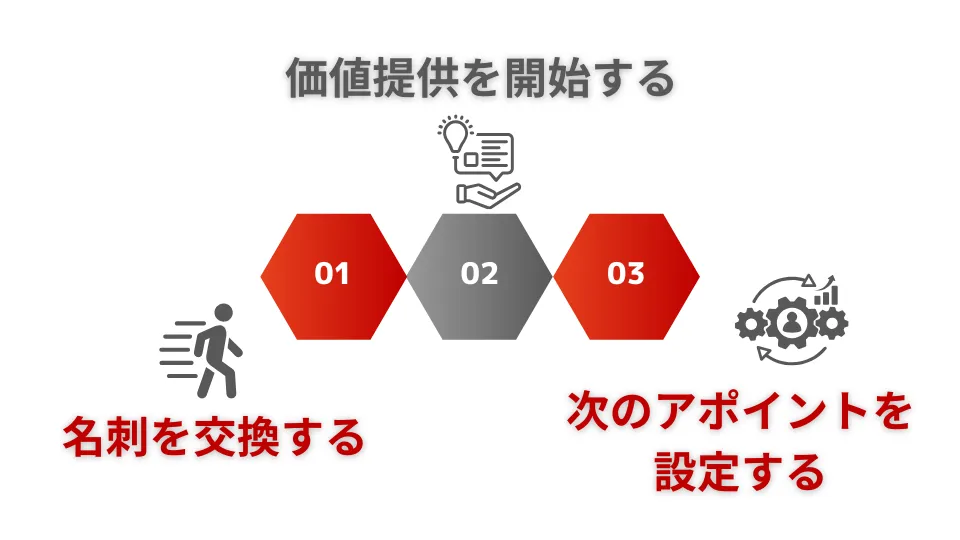
営業で「とりあえず名刺だけ置かせてください」が逆効果になっていませんか?
初対面の訪問先で、名刺だけをそっと置いて立ち去る営業スタイルが、意外と相手に負担を感じさせてしまうことがあります。
「売り込み感が強い」「時間だけ取られた」と思われる原因は、名刺という“手段”が目的化してしまっているからかもしれません。
誰しも忙しい中で突然現れた人に、名刺だけを渡されても、その営業の“顔”や“想い”が何も伝わらなければ、印象はすぐに薄れてしまいます。
だからこそ、私たちは「名刺+α」の価値を添える工夫を大切にしています。
例えば次のようなアプローチがあります。
・「相手の業界に合わせたミニ資料」をA5サイズで渡す
・「事例動画へ誘導するQRコード」を名刺に添える
・「〇〇の件でお伺いしました」と一言添えて渡す
名刺交換は、あくまで会話のきっかけにすぎません。そこに“相手のための情報”をさりげなく添えることで、印象は確実に変わってきます。
このように、“名刺交換”を“価値提供の入口”に変えられる営業は、次のアポイントにつなげる確率がぐっと高まります。
「トークの切り出し方」が不自然で違和感がある
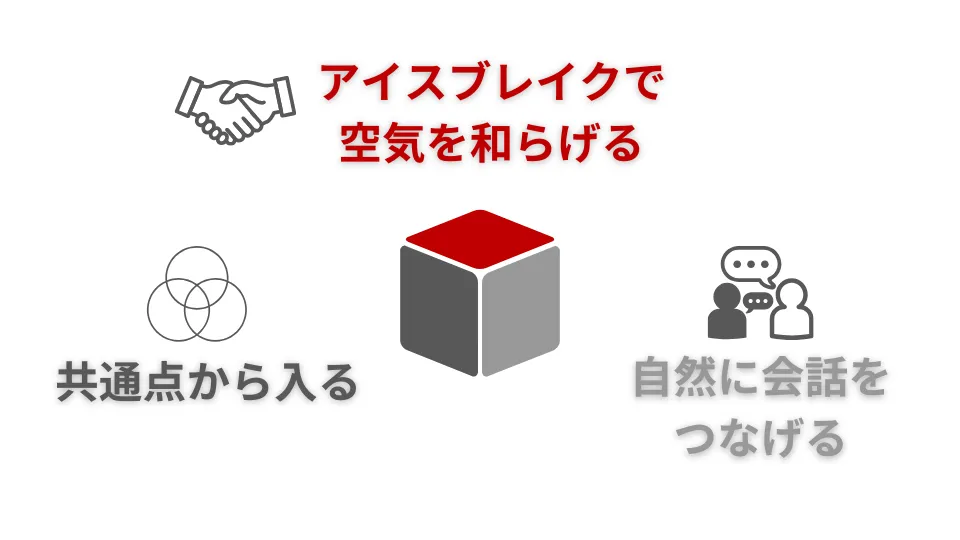
飛び込み営業で「最初のひと言がうまく決まらなかった…」と感じることはないでしょうか?
定型文のような始まり方だと、「また営業か」と相手の警戒心が一気に高まってしまいます。
私たちも現場で何度も体感してきましたが、第一声の工夫だけで空気がまるで変わります。
特に“相手の今”に目を向けた話題は、自然に心の距離を縮めてくれます。
そこで私たちは、以下のようなアプローチを実践しています。
- 「業界のトレンド」に触れて会話を始める
- 「御社のプレスリリース」に言及し、訪問理由を伝える
- 「近隣の話題のカフェ」の話から自然に切り出す
このように視覚情報や地域情報、企業の最新ニュースなど、相手にとって身近な話題を入口にすることで、「ちゃんと見てくれている」という安心感が生まれます。
最初の5秒で壁がなくなると、その後の話もスムーズにつながります。
小さな気づきの積み重ねが、大きな成果へとつながっていくかもしれません。
最初の数秒で“営業っぽさ”を消せると、商談のハードルは一気に下がります。
「訪問ルール無視」が企業の反感を買いやすい
「今そのタイミングじゃないんだよね」と、冷たい空気に変わった瞬間が忘れられない方もいるかもしれません。
突然の訪問が“邪魔”と受け取られてしまうのは、営業のせいというより、訪問の“理由とタイミング”に根拠がないからかもしれません。
私たちも、何度もその壁にぶつかってきました。
けれど、訪問前にちょっとした手間をかけるだけで、相手の反応がまったく変わってくることを実感しています。
たとえば、こんな工夫を取り入れています。
- 「近隣企業にヒアリング」して営業対応の傾向を探る
- 「過去の訪問記録」を確認し、不快な時間帯を避ける
- 「SNSや採用情報」から社内の繁忙期を読み取る
こうした事前準備をすることで、“今、訪ねるべきかどうか”の判断に自信が持てます。
「ちゃんと考えて来てくれたんだな」と相手が感じてくれれば、たとえ飛び込みでも、会話の糸口がぐっとつかみやすくなります。
一歩踏み込む前に、一度立ち止まって“訪問の根拠”を確かめることが、信頼の入り口になるのかもしれません。
飛び込み営業に適した成功率の高い時間帯とは?【知識まとめ】
「法人営業」は午前10時〜11時と午後2時〜4時が最も反応が得られる傾向はある
「訪問先の集中力と業務の余裕が重なる時間帯」に営業をかけると、反応率が高まりやすいと言われています。
つまり、相手の頭と時間が“空いている時間”を狙うことが、商談の入口をつくるコツになります。
「この時間って、営業しても迷惑なんじゃないか?」と悩んだ経験はありませんか?
実は、午前10時〜11時、午後2時〜4時は、法人の担当者が比較的予定が空きやすく、気持ちにも余裕がある時間帯とされているんです。
営業での具体例
・午前9時台に訪問し、朝礼や会議中で門前払いされる
・午後1時台に行くも、ランチ明けで相手が不在だったり眠そうだったりする
・午後5時以降に訪問し、事務処理に追われ「今、無理」と断られてしまう
だからこそ、「相手の一日の流れ」に合わせて訪問時間を調整することが、会話のきっかけをつかむポイントになります。
カレンダーを見るとき、自分の都合だけでなく“相手の過ごし方”を一度イメージしてみると、結果が少し変わるかもしれません。
法人向け営業においては、アポイントあり・なしに分けて、適切な時間が違う事も多い
法人営業では、「予定が組まれている時間」と「隙間時間」が顧客対応の分かれ目です。
つまり、アポあり営業は“打ち合わせ枠”、アポなし営業は“合間の余白”を狙うと、反応が得やすくなります。
「訪問はこの時間でいいのか?」と迷ったことはありませんか?
実は、アポイントの有無によって、相手の時間の使い方は大きく異なるケースが多いんです。
営業での具体例
・アポありで朝イチ9時に設定したが、部長が前会議から戻らず10分押しになる
・アポなしで午前11時に訪問し、資料整理中の課長にスムーズに対応してもらえる
・アポありで午後4時の面談が、ちょうど一日の整理時間に重なり好印象で終わる
だからこそ、「この時間はアポ向きか?飛び込み向きか?」を意識することで、無駄足が減り、商談率も自然と上がってきます。
相手の一日を想像しながら、時間帯と営業手法をセットで考えてみるのがコツかもしれません。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【知らないと損】商談時間をコントロールして契約を ...
「個人営業」は平日夕方と土日午前に訪問数を集中させると効率が上がる
個人営業では、「在宅率」と「心理的な余裕」が成果に直結する傾向があります。
つまり、人が“家にいて話を聞ける”時間帯を狙うと、会話のきっかけが生まれやすくなります。
「いつ訪問すれば会ってもらえるんだろう?」と悩んだことはありませんか?
実は、平日夕方(17時〜19時)と土曜・日曜の午前中(9時〜11時)は、家庭内に人がいる確率が高く、反応が得られやすい時間帯なんです。
営業での具体例
・平日昼に訪問しても在宅率が低く、空振りが続いてしまう
・土曜の朝に訪問したところ、ご夫婦で在宅中でその場で話を聞いてもらえる
・平日18時に訪問し、仕事から帰宅した本人とタイミング良く話せる
だからこそ、訪問数を集中させる時間を決めるだけで、出会える確率が大きく変わってきます。
まずは“誰かが家にいる”時間を基準に、訪問ルートを組み直してみると成果に直結しやすいかもしれません。
個人向け営業においては、9時~10時もしくは17時以降の在宅率が高い
個人向け営業では、相手が在宅かどうかで成果が大きく左右されます。
つまり、空振りが続く原因の多くは「訪問のタイミング」にあるのです。
「なぜ、何件回っても誰にも会えないのか?」と感じたことはありませんか?
実は、9時〜10時や17時以降は、在宅率が高まりやすく、訪問効率が上がる時間帯だとデータでも示されています。
営業での具体例
・午前9時台に訪問し、在宅中の高齢者に保険の相談を進めることができる
・夕方18時頃に訪問し、帰宅した共働き家庭に住宅設備の提案を行う
・平日夜に訪問し、在宅している単身者にネット回線の切り替え提案を進める
だからこそ、在宅率の高い時間を狙って訪問するだけで、無駄な移動や不在訪問を減らせます。
訪問リストを作る前に「いつ訪ねるか」も少し意識してみると、結果が変わるかもしれません。
営業(飛び込み営業)の時間を定める法律はない
飛び込み営業には「訪問時間の制限を定めた法律」は実は存在しません。
つまり、深夜や早朝に訪問しても法的には違反ではないのです。
「法律で決まっていないなら、何時でも訪問していいのか?」と疑問に思う方も多いかもしれません。
実は、法ではなく“常識”や“地域のマナー”が営業活動の成否を左右する場面がほとんどです。
営業での具体例
・朝8時に訪問して相手の機嫌を損ね、その後の再訪が困難になる
・20時にインターホンを押したことで、管理会社にクレームが入る
・時間帯への配慮が評価され、翌週の商談アポが取れる
だからこそ、「法律がない」ことよりも「相手の生活リズムへの想像力」が大切になります。
訪問の許容ラインは“地域性”と“常識”に支えられている、という視点を持っておくと安心です。
特定商取引法では迷惑な営業は禁じられている
特定商取引法では、しつこい勧誘や不快に感じさせる訪問を「迷惑勧誘」として禁止しています。
つまり、相手の意思を無視した営業は、法的にアウトになる可能性があるのです。
「どこまでが“迷惑”とされる営業なのか?」と感じたことはありませんか?
実は、断られたのに何度も訪問したり、相手の都合を無視して長居する行為が“迷惑”と判断されやすいです。
営業での具体例
・一度断られた家に2日連続で訪問してトラブルになる
・明らかに忙しそうな相手に長時間説明を続けてしまい印象を悪くする
・断られた直後に「なぜダメですか?」と詰め寄って信頼を失う
だからこそ、営業の自由には「相手の感情を尊重する責任」がついてきます。
訪問時は「断られたらすぐ引く」だけでも、信頼の土台をつくる第一歩になります。
決裁権者と会える確率が高い時間を営業日報から割り出すのが効果的
商談の成果は「誰に会えるか」で大きく変わります。
つまり、決裁権者に直接会える時間帯を狙うことで、提案の進行スピードが一気に加速します。
「決裁者って、いったい何時に会社にいるの?」と悩んだことはありませんか?
実は、自社の営業日報を分析すると、面談できた時間帯に一定の傾向が見えてきます。
営業での具体例
・日報から“月曜10時台”の商談成立が多く、重点訪問時間に設定する
・“水曜15時以降”の訪問で役員と面談できる確率が高いことに気づく
・午前は不在が多いと分かり、午後一番に訪問計画を集中させる
だからこそ、感覚や勘ではなく、自社データを使って時間戦略を立てることが大切です。
営業日報を「記録」ではなく「武器」に変えると、動き方が変わり、成果にもつながっていきます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【決裁権なし担当者から最短で契約を取るトーク術】 – 決裁権者に辿り着く営業戦略
【状況別】飛び込み営業をする時!迷惑にならないための6つのポイント
「事前通知ツール」で一言連絡を入れて心理的ハードルを下げる
営業で「飛び込み=迷惑だと思われていないか?」と不安に感じたことはありませんか?
実は、訪問前に一言“予告”を入れるだけで、心理的バリアが驚くほど下がります。
LINE WORKSやSFA連携ツールを使って、さりげなく一報を入れる工夫が鍵になります。
現場で実践できる工夫は以下の通りです。
- 短いメッセージで「近くにいる」ことを伝える
顧客管理ツール(Zoho CRMなど)のテンプレート機能を活用し、「この度、近くを通っておりますので、もし差し支えなければ5分だけご挨拶できませんでしょうか?」といった短いメッセージを送る運用を整えましょう。この際、返信がない場合は訪問を控える判断基準を設けることが重要です。これにより、相手の都合を優先する姿勢が伝わります。
- 名刺交換済み相手には「過去の接点」を強調する
名刺管理ツール(Sansanなど)で名刺交換済みの相手に連絡する際は、「以前、〇〇の展示会でご挨拶させていただいた〇〇です」といったように、過去の接点を明確に記載しましょう。これにより、全くの初対面ではないという安心感を相手に与え、営業色を薄めて自然な連絡を行うことができます。
突然の訪問を“予告付き訪問”に変えるだけで、営業の受け入れ態勢はぐっと変わってきます。
相手のリズムを尊重する姿勢が、次の商談の扉を開いてくれます。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【自動商談ツールが生むセールス新手法】逃さない その ...
「ノンアポ訪問」をやめ、インサイドセールスと連携する
営業で「飛び込んでも温度感ゼロ、手応えがない…」と感じたことはありませんか?
非効率なノンアポ訪問は、今の時代にそぐわないどころか、チャンス損失につながることもあります。
そこで重要になるのが、インサイドセールスとの連携による“リードの事前精査”です。
成果につながる実践例を以下にまとめました。
- Salesforceで「資料DLから30日以内かつ直近に問い合わせあり」のリードに絞り、飛び込み対象を週次でリスト化する
- SATORIとSales Cloudを連携させ、閲覧ページ数や滞在時間から“行動熱度”をスコア化し、アタックタイミングを見極める
無作為な訪問をやめ、“確度の高い温度感”に営業リソースを集中させることが成果を分けます。
打席数よりも、打率を上げる視点に切り替えていきましょう。
▼編集部のおすすめ動画を見る
インサイドセールスとは?導入のメリットや具体的な方法を解説!
「訪問前に」生成AIで顧客営業時間を精査し、スプしにまとめておく
営業で「何度訪問しても不在、そもそも受付がやっていない…」と感じたことはありませんか?
無駄足を避けるには、事前に“訪問可能な時間”をデータで可視化しておくことが鍵になります。
生成AIを活用すれば、顧客ごとの受付時間や対応部署の傾向を数分で抽出できます。
すぐ使える実践例は以下の通りです。
- ChatGPTに「○○業界×企業受付時間×来訪可能な曜日と時間帯」を聞き、Excelに自動整理させる
- Geminiで飛び込み成功ログを分析し、「火曜午後×経営企画部」などの狙い目条件を抽出する
効率のいい営業ルートは、訪問前の“スクリーニング精度”で決まってきます。
生成AIを味方につけて、ムダのない営業動線を描いていきましょう。
「断られた後のフォロー方法」で商談機会を取り戻す
営業で「失注=終了」と考えてしまっていませんか?
本当の勝負は“断られた直後”から始まります。
理由を聞き出し、ナーチャリングの土台をつくることで、失注が再商談の入口に変わります。
実際の現場で使えるフォロー設計は以下の通りです。
- 失注理由を「型化」して確実に取得する
顧客管理システム(Zoho CRMなど)に、「ご予算のタイミングでしょうか?」「内容が合わなかったでしょうか?」「現状維持で十分だったでしょうか?」といった、失注理由を確認するためのテンプレートを登録しましょう。
これにより、感情的にならず、顧客から具体的な理由を確実に引き出す運用を徹底させます。得られた理由は、後の改善策や再アプローチの貴重なヒントとなります。
- 「再接触タスク」を自動で立ち上げる仕組みを作る
Salesforceなどで、失注から30日後や90日後など、適切なタイミングで「再接触タスク」が自動で立ち上がるように設定します。
タスクの内容は、「〇〇様、そろそろ状況変わりましたか?と軽くタッチしてみる」「新たな事例ができたので情報提供」など、再アプローチのきっかけを具体的に示しましょう。
これにより、忘れずに顧客との接点を持ち続けられます。
“ただの断られ”を終点にせず、丁寧に設計されたフォローアップが、商談の機会をもう一度つくってくれます。
断られてからの一手が、営業の力を問われる瞬間です。
▼編集部のおすすめ動画を見る
【営業トークのコツ】断られたお客様からYesをもらう
「迷惑がられない導線」を設計し、営業プロセス全体を改善する
営業で「なんで訪問したの?」「今はちょっと…」と冷たくあしらわれたことはありませんか?
その原因の多くは、“導線設計の甘さ”にあります。
事前に関心度や接点履歴を可視化し、相手にとって違和感のないアプローチを仕込むことで、迷惑と思われない導線がつくれます。
現場で使える工夫は以下の通りです。
- 自社サイトの行動履歴から「関心度の高い企業」に絞って訪問する。
- 顧客が資料請求や問い合わせをした履歴を特定し、それを明確な訪問理由として伝える。
- 社内の人脈を事前に確認し、名刺交換済みの相手には「〇〇からのご紹介で」と関係性を明確にして訪問する。
飛び込みも“導線を仕立ててから動く”だけで、相手の反応は大きく変わってきます。
訪問前の一手間が、迷惑から歓迎に変わる境界線です。
▼編集部のおすすめ動画を見る
Webマーケティング初心者向け 無形商材の販売導線設計
飛び込み営業でお困りのことがあればスタジアムに無料で聞いてみよう!
「飛び込み営業をがんばっているのに成果が出ない」――そんな悩みを抱えていませんか?
名刺を配るだけの“訪問数勝負”に疲れ、テレアポリストの反応も薄い。
決裁者に辿り着けず、空振りが続いてモチベーションも下がっている。
数字を追うたびに、「このやり方で合ってるのか…?」と不安が募る。
そんな時こそ、戦略設計から見直すタイミングです。
ターゲット設定、導線設計、初回商談の切り口まで、成果が出る型は必ずあります。
スタジアムでは、現場で実績を積んだ営業のプロが、貴社の課題にフィットした打ち手を一緒に考えます。
新規開拓に苦戦しているマネージャーの方へ。今だけ、初回相談は無料です。
営業組織の立ち上げや新規開拓営業の強化、営業リソース追加に向けたひとつの手段として、まずは一度、些細な悩みを無料で相談してみませんか?
※具体的にサービス導入を検討していない方もお気軽に。
“現場を熟知した営業のプロ”に軽く壁打ちするだけでも、ヒントはきっと見つかるはずです。
今すぐ、IT・Web領域の営業のプロ集団「スタジアム」に無料で直接聞いてみましょう!
最終更新日